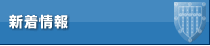広報・プレスリリース情報(2013年(平成25年))
水中に入れても膨張も形崩れもしない高強度の医用材料、ハイドロゲルを世界で初めて開発
近年、再生医療への関心が高まる中、医用材料としてのハイドロゲルに注目が集まっています。
日常生活で目にするハイドロゲルは豆腐・寒天・煮こごり等の食べ物が主ですが、コンタクトレンズやオムツなど、医療や衛生分野で用いられているものも多くあります。
ハイドロゲルは、高い含水率(~ 90%)を有し、生体軟組織に類似した組成を持つことから、生体に優しい医用材料の有力な候補として挙げられています。
しかしながら、生体内では、ハイドロゲルは体内の水分を吸収し、膨張してしまうために、元の形状を維持できないばかりか、その力学特性も大きく損なわれてしまうという問題がありました。
今回、東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 酒井・鄭研究室(鄭雄一教授:医学系研究科兼担)の酒井崇匡助教らは、生体環境下で収縮する特殊な高分子を、任意の割合でハイドロゲルに導入することで、水分を吸収して膨張しようとするハイドロゲルの変形を制御することに世界で初めて成功しました。
このハイドロゲルは、特殊な高分子を含む二種類の水溶液を混ぜるだけで誰でも簡単に作製することができ、生体内においても膨張することなく水分を吸収する前の初期の形状を維持し、かつ高い強度を有することから、人工軟骨や人工椎間板としての応用や、再生医療/組織工学における細胞(iPS細胞やSTAP細胞など)の足場素材として利用されると期待されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 381KB]
リリース文書[PDF: 381KB]
(2014/2/27)
微弱な電流で身体のバランス障害を改善
人間の耳には、3つの半円状の管である三半規管(さんはんきかん)と耳の中の平衡砂を収めた耳石器(じせきき)で構成される前庭(ぜんてい)という身体のバランスを保つ器官があります。
この前庭の機能が障害されるとめまいやバランス障害を生じます。
特に両耳の前庭が障害されると、歩行時などに強いふらつきを感じる、まっすぐ歩けない、物が揺れて見える、などの症状が出現しますが、これらに対する有効な治療はこれまでにありませんでした。
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 准教授 岩﨑真一、同科教授 山岨(やまそば)達也、同大学院教育学研究科 教授 山本義春らの研究グループは、耳の後ろに貼った電極から、刺激を感じない程の微弱な電流を流すことで、両側前庭障害患者のバランス機能の改善が可能なことを明らかにしました。
この刺激は、痛みや不快感などの副作用を伴わず、携帯型の簡便な刺激装置で行えることから、前庭機能障害患者のみならず、高齢者のバランス障害の改善や転倒予防の新たな治療となることが期待されます。
本研究の成果は、米国の神経科学雑誌「Neurology(電子版)」に掲載されました(日本時間2月15日)。
印刷版は3月14日号に掲載されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 92KB]
リリース文書[PDF: 92KB]
(2014/2/17)
ビタミンKの肝臓での作用不足は出血と寿命短縮に至る
~ビタミンKの肝臓内外への多面的な作用解明に道筋~
ビタミンKは緑黄色野菜や納豆に多く含まれ、臨床的には新生児の頭蓋内出血の予防や、加齢や医薬品等に使われるステロイドによる骨粗鬆症の治療に用いられています。
また、疫学研究によりビタミンK不足が動脈硬化や認知症、悪性腫瘍の危険性を上げる可能性も報告されています。
ビタミンKは主としてγグルタミルカルボキシラーゼという酵素の作用を助け、タンパク質の修飾にかかわるメカニズムが示されており、肝臓での血液凝固因子の活性化に必要です。
ビタミンKとγグルタミルカルボキシラーゼの作用を受ける分子は血液凝固因子以外にも10種類以上知られ、全身に分布しており、ビタミンKは上記の疾患やさまざまな生理作用にかかわる多様な働きが推測されています。
しかし、ビタミンKの作用は不明な点が多いほか、γグルタミルカルボキシラーゼを全身で欠損するマウスは激しい出血傾向により生存できないため、多面的なビタミンKの作用を動物モデルにて解明することは困難でした。
このたび、東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター抗加齢医学講座特任教授の井上聡、老年病科特任講師(研究当時)の東浩太郎、埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 講師の池田和博らは、大阪大学、神戸薬科大学との共同研究により、γグルタミルカルボキシラーゼを肝臓のみで欠損するマウスの作製に成功し、そのマウスが出血傾向を示すことを示しました。
また、この遺伝子改変マウスは寿命が短縮するものの、オスよりもメス(妊娠していない)の方が長生きであるという興味深い結果を得ました。
本研究の技術を用いることにより、肝臓をはじめ、特定の臓器のみでビタミンKの作用を欠損したマウスを作製することが可能となり、今後、全身における多彩なビタミンKの作用が解明されると期待されます。
本研究成果は、日本時間2月11日にPLOS ONEオンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 172KB]
リリース文書[PDF: 172KB]
(2014/2/11)
脳症の臨床症状と新しい治療法を明らかに
~ 2011年の大腸菌O-111食中毒を事例に~
O-157やO-111に代表される腸管出血性大腸菌の感染者は大腸炎を発症します。
大腸炎患者の一部は溶血性尿毒症症候群を、さらにその一部は脳症を併発します。
現代の医療では、溶血性尿毒症症候群までは透析などの集中治療により救命可能ですが、脳症には有効な治療が乏しいため、死亡例の大多数は脳症が死因です。
このため、脳症の治療法開発は急務です。
東京大学大学院医学系研究科の水口雅教授、亀田メディカルセンター小児科の高梨潤一博士、富山大学医学部附属病院小児科の種市尋宙博士らは、2011年4~5月にある焼肉チェーン店で生肉を食べた人々がO-111食中毒を発症した事例を分析することにより、腸管出血性大腸菌O-111による脳症の臨床症状の特徴とその新しい治療法の効果を明らかにしました。
本事例では、富山県を中心に86名が大腸炎に罹りました。
うち34名が溶血性尿毒症症候群、21名が脳症を併発し、5名が死亡しました。
本事例では、溶血性尿毒症症候群や脳症を合併する重症患者の割合が、過去の事例に比して特に高いことが分かりました。
死亡した5名は大腸炎から脳症発症までの時間が短く、脳浮腫が急激に進行して死に至りました。
死亡した患者の中にステロイド治療を受けた者はいませんでした。
これに対し、脳症を発症して生存した16名中、15名は後遺症無く回復しました。
回復した者のうち11名がステロイド治療(メチルプレドニゾロン・パルス療法)を受けており、脳症に対するステロイド治療の有効性が示唆されました。
なお、本研究は厚生労働科学研究費の支援を受けて行われました。
本研究成果は、『Neurology(1月17日オンライン版)』に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 190KB]
リリース文書[PDF: 190KB]
(2014/1/20)
統合失調症患者の神経細胞でレトロトランスポゾン配列が増大
~統合失調症の病態理解への大きな一歩~
統合失調症はおよそ100人に1人が発症し、幻聴、妄想などの陽性症状、意欲低下などの陰性症状、認知機能障害などが出現し、社会生活が障害される精神疾患です。
統合失調症の発症メカニズムには、遺伝因子および環境因子の相互作用による脳発達の障害が関係していると考えられていますが、その詳細なメカニズムはわかっていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科(分子精神医学講座 岩本和也特任准教授、文東美紀特任助教)および理化学研究所 脳科学総合研究センター(精神疾患動態研究チーム 加藤忠史チームリーダー)の研究グループは、慶應義塾大学、新潟大学、奈良県立医科大学と共同で、脳の発達中に、神経細胞のゲノムの中で、LINE-1(ラインワン)と呼ばれる転移因子(レトロトランスポゾン)が増えることが、統合失調症の病態に関わることを明らかにしました。
本研究の成果は、統合失調症の病態の理解に大きな手がかりを与えるとともに、統合失調症の治療法、診断法や発症予防法の開発に寄与すると期待されます。
なお、本研究の成果は、米国の科学雑誌ニューロン(電子版)に掲載されます(日本時間1月3日 午前2時 発表)。
本研究は、文部科学省科学研究費新学術領域研究「マイクロエンドフェノタイプによる精神病態の解明」、科学技術振興機構さきがけ(エピジェネティクスの制御と生命機構)・CREST(エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出)、および文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 128KB]
リリース文書[PDF: 128KB]
(2014/1/3)
関節リウマチの発症の鍵となるT細胞を発見
~免疫反応を抑制するT細胞が関節の炎症と骨破壊を促進するT細胞へ変身~
関節リウマチは、自己の免疫系が自分自身の細胞を攻撃することによって起きる自己免疫疾患の中でも発症頻度が高く、関節の炎症と骨の破壊が主な症状です。
このような自己免疫疾患は、免疫の司令塔であるT細胞のうち、自己に対する免疫応答を抑制するT細胞と促進するT細胞のバランスが破綻すると発症すると考えられています。
しかし、関節リウマチの発症原因は不明な点が多く、また自己免疫疾患を促進するT細胞の発生メカニズムもこれまでよく分かってないため、根本的な治療法の確立が難しい状況にありました。
東京大学大学院医学系研究科の高柳広教授と小松紀子客員研究員らの研究グループは、マウスを使った実験により自己免疫疾患の発症の鍵となるT細胞(exFoxp3Th17細胞)を新たに発見し、この細胞が免疫を抑制するT細胞からの分化転換により発生することを見いだしました。
関節リウマチモデルマウスへの細胞移入実験やトランスクリプトーム解析などの手法により、今回発見した新たなT細胞はこれまで知られていたT細胞よりも関節の炎症や骨破壊を強力に引き起こすとともに、他に類を見ない遺伝子群を発現することを明らかにしました。
本研究により新たに発見されたT細胞は、関節リウマチだけでなく多発性硬化症や全身性エリテマトーデスなどのさまざまな自己免疫疾患の治療標的となる可能性を持っており、新しい治療薬や診断マーカーの確立に繋がることが期待されます。
本研究は独立行政法人 科学技術振興機構(JST)課題達成型基礎研究「高柳オステオネットワークプロジェクト」との共同研究として行われ、2013年12月22日 (米国東部時間)発行の米国科学誌Nature Medicineにオンライン掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 790KB]
リリース文書[PDF: 790KB]
(2013/12/24掲載)
自閉症の新たな治療につながる可能性
~世界初 オキシトシン点鼻剤による対人コミュニケーション障害の改善を実証~
自閉症スペクトラム障害は、表情や声色を活用して相手の気持ちを汲み取ることが難しいといった対人コミュニケーションの障害を主な症状とし、一般人口の100人に1人以上で認められる代表的な発達障害です。
この障害の原因は完全には解明されておらず、その治療法も確立されていません。
結果として、知能の高い方でもこの障害のために社会生活に困難をきたしている現状にあります。
東京大学大学院医学系研究科精神医学分野 准教授 山末英典は、同研究科統合生理学分野 特任助教(当時)渡部喬光らと共同で、ホルモンの1種であるオキシトシンをスプレーによって鼻から吸入することで、自閉症スペクトラム障害において元来低下していた内側前頭前野と呼ばれる脳の部位の活動が活性化され、それと共に対人コミュニケーションの障害が改善されることを世界で初めて示しました。
今後はこの研究成果をもとに、オキシトシンの点鼻スプレー製剤を活用して、未確立だった自閉症スペクトラム障害における対人コミュニケーションの障害の治療法開発に取り組んでいきます。
これらの成果は、日本時間12月19日午前6時にJAMA psychiatry(米国医師会雑誌(精神医学))にて発表されます。
本研究は、科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「精神・神経疾患の分子病態理解に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」研究領域(研究総括:樋口 輝彦)における研究課題「社会行動関連分子機構の解明に基づく自閉症の根本的治療法創出」(研究代表者:加藤 進昌)および文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」の一環として行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 225KB]
リリース文書[PDF: 225KB]
(2013/12/19掲載)
脳腫瘍である神経膠腫の悪性化・再発時に起きるゲノム変化を解明
神経膠腫(グリオーマ)は、代表的な脳腫瘍のひとつです。
診療経過中に悪性に転化することが知られており、多くの患者さんにおいて、この悪性への転化が死亡の原因になっています。
しかしながら、この悪性転化の機構については、未だ良く分かっておらず、そのため再発時の治療法選択がしばしば困難です。
そこで今回、東京大学医学部附属病院 斉藤延人教授、武笠晃丈特任講師(病院)[助教]、東京大学先端科学技術研究センター 油谷浩幸教授、及び大学院生の相原功輝らは、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校のグループなどと共同で、低悪性度の神経膠腫(グリオーマ)が診療経過中に悪性に転化し再発する過程に生じる遺伝子変異を、全遺伝子解析を行って詳細に解析しました。
これにより、再発に際しては新たな遺伝子変異が出現し、なかでも抗がん剤の一種であるアルキル化剤による治療が解析した23症例中10例で行われていましたが、その症例の半数程度で特定の塩基変異(シトシン/グアニンがチミン/アデニンに置換する変異)が高頻度に生じることを観察しました。
本成果は、特に低悪性度の腫瘍に対しての抗がん剤治療法の最適化について、検討を促す契機となるものです。
なお、本研究は次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムの一環として行われたものであり、また、医学研究における国際共同研究であることが特筆すべき点です。
本成果は、米国の論文誌「Science」への掲載に先駆け、オンライン版の「Science Express」に米国東部時間12月12日に掲載されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 164KB]
リリース文書[PDF: 164KB]
(2013/12/13掲載)
環境化学物質への母胎曝露が仔ラットの記憶学習機能に影響
ダイオキシンは、環境・食品中に広く存在している残留性有機汚染物質の一種です。
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 健康環境医工学部門の遠山千春教授のグループは2012年に、発達期に微量のダイオキシンの曝露を受けたマウスでは前頭前皮質の機能異常が生じる可能性を明らかにしました。
前頭前皮質は、さまざまな情報を統合する役割を持つ重要な脳部位であり、その影響について検証を進める必要があります。
しかし前頭前皮質の研究はヒトやサルを用いて行われることが多く、毒性試験で用いられるマウスやラットを用いて調べることは難しいとされてきました。
今回研究グループは、ラットの記憶学習機能を評価できる新たな検出解析方法を用いて、前頭前皮質の使われていることが知られている極めて高度な学習機能に対するダイオキシンの影響をラットにおいて調べました。
その結果、微量のダイオキシンを投与された母ラットから生まれた仔ラットでは、餌の場所を覚えるような比較的簡単な記憶課題ではダイオキシンの影響が認められない一方、町の地図を覚えるような複雑な記憶学習課題を与えたところ、過去の経験をもとにして知識を体系化するという高次の脳機能が阻害されていることを明らかにしました。
今回の結果は、そのままヒトには適用できませんが、母体・母乳から体内に取り込んだ微量の化学物質が、子どもの高次脳機能の発達に影響を及ぼす可能性を示唆しており、今後より詳しく検討していく必要があります。
この成果は「Archives of Toxicology」 2013年12月2日オンライン版に掲載されました。
なお、本研究の成果は文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、厚生労働科学研究費補助金、文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 278KB]
リリース文書[PDF: 278KB]
(2013/12/4掲載)
熱帯熱マラリア原虫に対する5-アミノレブリン酸と鉄の相乗的な増殖阻害メカニズムを解明
マラリアは、3大感染症の一つであり、年間の罹患者が数億人、死亡者が100万人を超えるといわれる重大な感染症です。
ALAを投与するとマラリア原虫に感染した細胞にポルフィリンが蓄積され、そのポルフィリンを手がかりに光照射でマラリア原虫を殺せることはすでに知られていますが、血液に光照射を行うことは現実的ではなく実用化の障壁となっていたため、光照射を伴わないALA薬剤の開発が望まれていました。
東京大学大学院医学系研究科の北 潔教授、東京工業大学大学院生命理工学研究科の小倉 俊一郎准教授とSBIファーマ株式会社は、ALAと2価の鉄の併用により、光照射することなく熱帯熱マラリア原虫の生育を阻害できることを2011年に学会で発表しました。
その後MRC National Institute for Medical Researchも研究に加わり、マラリア原虫の各オルガネラにおけるポルフィリン類の分析結果から、今回ALAと2価の鉄の併用が特定のオルガネラへのポルフィリンの蓄積と活性酸素の発生を引き起こし、それらがマラリア原虫の成長阻害を誘導するという作用メカニズムの一端を明らかにしました。
本成果は、多くの人たちを苦しめているマラリアを治療するための新規の医薬品の開発につながるものと期待されます。
ALA、2価鉄ともにすでに安全性が確保され、食品や医薬品として利用されている化合物であり、早期に臨床開発に移れる可能性があり、既存の抗マラリア薬と比べて副作用が小さく予防的にも服用可能な画期的な抗マラリア薬となることが期待されます。
本成果は12月2日発刊のThe Journal of Biochemistryに掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 267KB]
リリース文書[PDF: 267KB]
(2013/12/3掲載)
臨床研究不正防止のために、すべての研究者が活用できる世界初の症例データレポジトリを運用開始
東京大学医学部附属病院 大学病院医療情報ネットワーク研究センターは、平成25年11月28日、世界で初めて、大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)サービスにおいて、臨床研究不正防止のために、すべての研究者が活用できる症例データレポジトリ(ICDR=Individual Case Data Repository)の運用を開始し、第1例目として、「ピタバスタチンの耐糖能異常者に対する糖尿病発症予防試験(J-PREDICT=Japan Prevention Trial of Diabetes by Pitavastatin in Patients with Impaired Glucose Tolerance)」(責任研究者:医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 門脇孝教授)の匿名化された全症例データが症例データレポジトリに登録されました。
このシステムは、研究者が自身の実施した臨床研究症例の匿名化したオリジナルのデータセットを研究者自身の同意のもとにUMINサーバに保管し、UMINがその内容を第三者(当該の研究者以外のすべての研究者)に担保するものです。
症例データレポジトリへの症例のオリジナルのデータセット登録が一般的になることにより、1)臨床研究データの散逸防止と長期保存(匿名化された症例データをバックアップやセキュリティ体制の整ったUMIN症例データレポジトリに保管することによる)、2)臨床研究データの質の担保(例えば、相互チェック・査察のための正本の提供等)、3)論文で公表された以外の新たな知見を得るための統計解析のリソースとしての様々な用途での活用が可能となります。
海外には、米国医薬食品局(FDA=Food and Drug Administration)が製薬会社の治験用に構築した症例データレポジトリや米国NIH(National Institutes of Health)が研究費を出している臨床研究に対して症例データレポジトリを構築した例はありますが、すべての研究者が活用できる症例データレポジトリの提供は、我々が把握しているかぎり、世界初です。
既に臨床試験登録は関係者の努力によって普及しつつあり、臨床研究の不正防止に一定の役割を果たしていますが、今後は症例データレポジトリが一般化することによって、臨床試験の不正予防対策が大きく進むことが期待されます。
しかしながら、症例データレポジトリによって、臨床研究不正は根絶できるわけではなく、この他に相互チェック・査察の仕組み等の対策が今後別途必要であることに充分留意する必要があります。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 131KB]
リリース文書[PDF: 131KB]
(2013/11/28掲載)
アルツハイマー病の超早期診断技術の確立を目指す
~東大病院など全国41施設で臨床研究を実施~
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と東京大学、バイオテクノロジー開発技術研究組合は、アルツハイマー病超早期診断技術の確立を目指す全国規模での臨床研究(J-ADNI2)を、東京大学医学部附属病院(東大病院)など全国41の臨床施設で実施します。
J-ADNI2は、NEDOのプロジェクトである「脳画像・臨床・ITの融合によるアルツハイマー病超早期診断と先制医療の実現」の一環として行うもので、予定されている41施設における臨床研究を通じ、日本の認知症患者(約460万人)の6割を占めるアルツハイマー病の診断技術の確立や、治療法の開発に必要なデータを収集します。
※詳細は こちら(NEDOホームページ内) をご覧下さい。
(2013/11/27掲載)
発達期のシナプス結合を選別するメカニズムを解明
~生後間もなくの神経細胞の「活動タイミング」が脳の発達の決め手に~
生後発達期に脳の神経回路が形成される過程において、必要なシナプス結合の強化と、不必要なシナプス結合の除去(シナプス刈り込み)が起こり、神経回路の大規模な再編成が行われます。
必要な結合の強化や不必要な結合の除去は、神経細胞の活動に依存するとされており、これまでの研究で神経細胞の活動に依存して機能するさまざまな分子がシナプス刈り込みに関わる因子として同定されていました。
しかし、脳内における神経細胞のどのような活動がシナプス結合の選別に重要なのかは全く知られていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の狩野 方伸教授、喜多村 和郎准教授らのグループは、ラットおよびマウスを用いた実験から、発達期の小脳において必要なシナプス結合の強化とシナプス刈り込みに関わる神経細胞の活動パターンを同定し、シナプス結合が選別されるルールを明らかにしました。
多数の弱いシナプス入力(情報を伝える側の神経細胞が発する電位・電流変化)が協働して受け手側の神経細胞に発火を引き起こし、その発火に最も寄与した入力側の神経細胞とのシナプス結合のみが強化されることが分かりました。
本研究成果は、2013年11月14日に科学雑誌「Nature Communications」のオンライン版で公開されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 332KB]
リリース文書[PDF: 332KB]
(2013/11/15掲載)
アディポネクチン受容体を活性化して健康長寿を実現する内服薬の種を発見
~アディポネクチン受容体を活性化する内服薬が、運動と同様の効果をもたらし、メタボリックシンドロームや糖尿病の治療薬となることが期待~
現代社会では、過食や運動不足による肥満が土台となるメタボリックシンドローム・糖尿病・心血管疾患・癌の患者数が急激に増大しています。
これまでの多くの研究から糖尿病などには食事療法や運動療法が有効であると明らかとなっています。
加えて、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 門脇孝教授、同 山内敏正講師らの研究室はこれまでに、脂肪細胞から分泌されるホルモンであるアディポネクチンが、抗糖尿病、抗メタボリックシンドローム作用を有するのみならず、元気で長生きを助ける善玉のホルモンであることを明らかにしてきました。
実際、肥満によって、血液中のアディポネクチンの量の低下は、メタボリックシンドロームや糖尿病の原因になるのみならず、心血管疾患や癌のリスクを高め、短命になることが知られています。
そのため、アディポネクチンと同じような効果を持つ物質、またアディポネクチンの作用を細胞内に伝えるアディポネクチン受容体を活性化するような化合物の発見が期待されてきましたが、これまでそのような化合物は見つかっていませんでした。
この度、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 門脇孝教授、同 山内敏正講師らの研究グループは、アディポネクチンの代わりにアディポネクチン受容体を活性化することができる大学発となる内服薬(低分子化合物)の種を、マウスを用いた実験により発見することに成功しました。
この内服薬の種は、糖・脂質代謝を改善させるのみならず、生活習慣病により短くなった寿命を回復させることも明らかになりました(日本時間10月31日午前3時に、Nature オンライン版にて発表)。
内科的疾患や運動器疾患等によって運動ができない場合でも、アディポネクチン受容体を活性化することが、メタボリックシンドロームや糖尿病の効果的な治療法となり、健康長寿の実現につながると期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 96.0KB]
リリース文書[PDF: 96.0KB]
(2013/10/31掲載)
マウスにおいてメタボリックシンドロームにおける新たな免疫細胞の役割を解明
~脂肪組織の慢性炎症を標的とする新しい治療の可能性を示唆~
近年、食生活の変化や運動不足に伴い肥満が増加しており、心筋梗塞や脳卒中の危険因子としてメタボリックシンドロームが注目されています。
メタボリックシンドロームでは、脂肪組織に慢性炎症がおき、全身に悪影響を与えると考えられていますが、そのメカニズムはまだよくわかっていません。
東京大学医学部附属病院 循環器内科 システム疾患生命科学による先端医療技術開発 特任准教授 西村智(研究当時。現 自治医科大学分子病態治療研究センター 教授)、東京大学医学部附属病院 循環器内科講師 真鍋一郎、東京大学 名誉教授 永井良三(現 自治医科大学 学長)は、2009年にマウスにおいてCD8陽性T細胞が脂肪組織の炎症を引き起こすことを明らかにしていました。
今回研究グループは、マウスにおいて脂肪組織に存在する制御性B細胞が、脂肪組織の炎症を抑えることを世界に先駆けて発見しました。
また、この制御性B細胞は肥満するとマウスのみならずヒトでも減少することも分かりました。
その結果、炎症を進行させる細胞の働きの方が炎症を抑える細胞の働きよりも強くなり、炎症が進んでしまう可能性があります。
また、制御性B細胞が作るインターロイキン10が炎症の抑制に重要であることも見いだしました。
本研究の成果により、脂肪組織の制御性B細胞はメタボリックシンドロームの新たな診断・治療法開発の標的になることが期待されます。
なお、本成果は、イノベーションシステム整備事業先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム(文部科学省)「システム疾患生命科学による先端医療技術開発」、最先端研究開発支援プログラム(内閣府/日本学術振興会)「未解決のがんと心臓病を撲滅する最適医療開発」の支援を受けて行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 100KB]
リリース文書[PDF: 100KB]
(2013/10/25掲載)
正常組織ならびにがん組織におけるリンパ管の形成を阻害する因子の発見
リンパ管は、体全体で血管から漏れ出た組織液を汲み上げて血管に戻すことで浮腫(病的なむくみ)を防ぐ役割をしている。
一方で、リンパ管はがん細胞が原発巣(もともとがんが発生した場所)からリンパ節へと転移し、さらにリンパ節を介してさまざまな臓器へ転移するための主要な経路ともなっている。
そのため、リンパ管の形成を調節する因子の発見は浮腫やがん転移などのリンパ管が関与する疾患の理解を深める上で重要である。
これまでさまざまなリンパ管を形成する誘導因子が明らかにされてきたのに対して、抑制因子はほとんど見出されていなかった。
今回、東京大学大学院医学系研究科の吉松康裕、渡部徹郎、宮園浩平らは、骨形成因子(BMP)ファミリーに属する因子BMP-9が、正常なマウスにおけるリンパ管形成のみならずがんを患ったマウスにおけるリンパ管の新生を抑制することを見出した。
具体的にはBMP-9がALK-1と呼ばれる受容体を介して、Prox1という転写因子の発現を低下させることでリンパ管を構成する内皮細胞の増殖を低下させるという詳細なメカニズムを初めて明らかにした。
なお、本成果はさまざまな種類の培養細胞や遺伝子改変マウスを用いて明らかにしたものである。
本研究の成果により、リンパ節に転移したがんを標的とした新たながん治療法の開発につながることが期待されるだけではなく、リンパ浮腫に悩む多くの患者を救う可能性が開かれた点で意義深い。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 367KB]
リリース文書[PDF: 367KB]
(2013/10/16掲載)
脳の発達における出生の新たな役割を解明
金沢大学 脳・肝インターフェースメディシン研究センターの河﨑 洋志 教授(2012年12月末まで、東京大学医学部附属病院 神経内科/大学院医学系研究科 神経機能解明ユニット 特任准教授)および日本学術振興会特別研究員(2012年3月末まで、東京大学医学部附属病院 神経内科 特任研究員)の戸田 智久 研究員らの研究グループは、出生は単に赤ちゃんを産み出すだけではなく、実は赤ちゃんの脳発達を制御するという出生の新たな役割を発見しました。
今回の成果は、出生異常による脳の発達障害の病態解明にもつながることが期待されます。
本研究成果は、2013年10月14日正午(米国東部夏時間)発行の米国科学誌「Developmental Cell」のオンライン版に掲載されました。
本成果の一部は、文部科学省 科学研究費補助金、日本学術振興会 科学研究費補助金、グローバルCOEプログラムの支援を受けて行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 392KB]
リリース文書[PDF: 392KB]
(2013/10/15掲載)
筋萎縮性側索硬化症の新たな原因遺伝子を発見・根本治療への手がかりを得る
~大規模な国際共同研究により実現~
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動神経細胞が進行性に脱落していくことにより、発症してから3-5 年で全身の筋肉が動かなくなる難病です。
家族性ALSの一部を除いてはその原因が不明であり、現在に至るまで根本的な治療法は見つかっていません。
このたび、東京大学医学部附属病院 神経内科教授 辻省次らの研究チームは、日本、カナダ,フィンランド,米国、豪州の研究者による国際共同研究により、ALS の新たな原因遺伝子としてERBB4 遺伝子を発見しました。
ERBB4 遺伝子の変異が原因で発症するALS(ALS19 と命名されました)は稀ですが、人種を越えて存在すること、孤発性ALSにも存在することを見出しました。
さらに、ERBB4遺伝子によって作られる蛋白質はある種の神経栄養因子の受容体であり、その受容体の機能が低下していることが発症の原因になっていることを明らかにしました。
本研究の結果は、これらの神経栄養因子により受容体を活性化することが、ALS の根本的な治療につながる可能性を示唆します。
この成果は、従来の方法では疾患の原因となる遺伝子の発見が困難であった小規模な家系に、DNA の塩基配列を高速かつ大量に解析可能な次世代シーケンサーを用いて、全ゲノム解析を行うことで達成されたものです。
本研究の成果は、American Journal of Human Genetics に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 98.0KB]
リリース文書[PDF: 98.0KB]
(2013/10/11掲載)
マウスにおける筋萎縮性側索硬化症の遺伝子治療実験に成功
~孤発性筋萎縮性側索硬化症の根本治療へ向けた大きなステップ~
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は主に中高年に発症する、進行性の筋力低下や筋萎縮を特徴とし、数年の内に呼吸筋麻痺により死に至る神経難病で、有効な治療法はありません。
これまで、国際医療福祉大学臨床医学研究センター 郭 伸特任教授(東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 臨床医工学部門 客員研究員)らの研究グループは、ADAR2という酵素がALSの大多数を占める遺伝性のない孤発性ALSの運動ニューロン死に関与していることを突き止めていました。
今回、郭特任教授と東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 臨床医工学部門 山下雄也特任研究員らの研究グループは、自治医科大学 村松慎一特命教授らと共同で、脳や脊髄のニューロンのみにADAR2遺伝子を発現させるアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを開発し、このベクターを孤発性ALSの病態を示すモデルマウスの血管に投与したところ、その運動ニューロンの変性と脱落、および症状の進行を食い止めることに世界に先駆けて成功しました。
また、発症前のみならず発症後に投与した場合でもADAR2遺伝子を運動ニューロンに発現させることで死に至る一連の過程を止め、明らかな副作用を生ずることなく、運動ニューロン死による症状の進行が抑えられました。
従来、静脈注射により脳や脊髄に遺伝子を導入することは困難とされていましたが、ニューロンのみで遺伝子を発現するAAVベクターを用いることで、一度の静脈注射で効果的な量のADAR2遺伝子の発現を長期間持続させることができました。
モデルマウスでの結果ではありますが、孤発性ALS患者でも類似の分子メカニズムが働いていると想定され、今回用いたヒト型ADAR2に治療効果が得られたことからも、同様の方法での遺伝子治療の有効性が期待できます。
また、AAVベクター自体の安全性は高いことが知られており、今回の改良型AAVベクターの安全性を確認し、薬剤の効果が最も得られる用量などが明らかになれば、ALSの治療に道を拓くものと期待されます。
以上の成果は、「EMBO Molecular Medicine」(9月24日オンライン版)に掲載されました。なお、本研究は科学技術振興機構・戦略的研究推進事業(CREST)研究と厚生労働省・疾病障害者対策研究の支援を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 269KB]
リリース文書[PDF: 269KB]
(2013/09/26掲載)
自閉症スペクトラム障害の血液中マーカーの開発につながる成果
~血液中の代謝産物の網羅的な解析によって同定~
自閉症スペクトラム障害は、表情や声色を活用して相手の気持ちを汲み取ることが難しいといった対人コミュニケーションの障害を主な症状とし、一般人口の100人に1人以上で認められる代表的な発達障害ですが、この障害の診断や重症度を客観的に評価する方法は乏しいのが現状です。
東京大学大学院医学系研究科精神医学分野 准教授 山末英典、同研究科 こころの発達医学分野 助教 桑原斉、同研究科 精神医学分野 教授 笠井清登らは、客観的な評価方法を開発するため、網羅的に血液中の代謝産物を調べるメタボローム解析を行いました。
その結果、自閉症スペクトラム障害を持つ群ではアルギニンなど4つの代謝産物の血液中濃度が、健常対照群に比べて偏りがあることがわかりました。
この結果は、別の自閉症スペクトラム障害群と健常対照群においても確認されました。
また、この4つの代謝産物の血液中の濃度を利用することで、自閉症スペクトラム障害の方か健常対照の方かを約80.0%という高い確率で判別できました。
この結果から、こうした代謝産物濃度が血中マーカーとして役立つ可能性が示されました。
これらの成果は、日本時間9月19日午前6時にPLOS ONE誌(電子版)にて発表されます。
本研究は、文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」の一環として、また、科学技術振興機構「戦略的創造研究推進事業 CREST」の支援を受けて行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 192KB]
リリース文書[PDF: 192KB]
(2013/09/19掲載)
転写共役因子/SHP2がんタンパク質複合体の細胞質—核移行が担う細胞密度調節機構
正常細胞は互いに接触し合う密度に達すると増殖を停止します。
この現象は接触阻止(contact inhibition)と呼ばれ、がん細胞では失われることが知られています。
近年、細胞密度の変化に応じて、細胞の増殖を制限して器官や組織の成長を制御するHippo情報伝達経路が大きな注目を集めています。
一方で、細胞にはその増殖や発がんに重要なRAS-MAPK情報伝達経路やWnt情報伝達経路もありますが、それらとHippo経路との関連性、例えば、共通の分子によって情報の受け渡しがなされているのかなどが不明でした。
東京大学医学系研究科 病因・病理学専攻 微生物学分野の畠山 昌則 教授、堤 良平 助教(発表当時。現在、オンタリオ癌研究所 ポストドクター)らの研究グループは、SHP2という細胞内でタンパク質のチロシン脱リン酸化を担う酵素(チロシンホスファーゼ)がHippo情報伝達経路の標的である転写共役因子YAPならびにTAZと結合することを発見しました。この結合を介してYAP/TAZ がSHP2の運び屋(carrier)として機能する結果、Hippo経路活性化の有無に応じてSHP2 の細胞内局在が変動することが明らかとなりました。
SHP2は細胞内でRAS-MAPK経路とWnt経路の制御にも関与していることから、本研究の成果は、RAS-MAPK経路、Wnt経路ならびにHippo経路がSHP2を介して細胞密度に連動した増殖の調節を行なっていることを示すものです。
SHP2 の機能獲得型変異は、Noonan (ヌーナン) 症候群やLeopard (レパード) 症候群と呼ばれる発達障害を伴う発がんしやすい先天性奇形や小児白血病や固形がんなど様々ながんの発症に関わることが知られており、がんタンパク質としての役割が明確に示されているホスファターゼです。
本研究は、SHP2異常が関与するがんや先天奇形の理解を深めるとともに、SHP2 の人為的な制御によるこれら難病の治療への道を拓く研究成果です。
本研究の内容は米国科学誌「Developmental Cell 誌」9月30日号に掲載されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 391KB]
リリース文書[PDF: 391KB]
(2013/09/13掲載)
統合失調症の進行を反映する脳内マーカーの開発につながる成果
~脳内の生化学物質の濃度を統合失調症の3 つの異なる段階で比較して同定~
統合失調症は、一般人口の100人に1人に近い頻度で認められ、思春期や青年期早期に出現して慢性的に進行し、日常生活や社会生活を深刻に制限します。
この病気の進行を防ぐことができれば、世界中の当事者や家族、さらには社会全体に多大な利益をもたらします。
その第一歩として、この病気が進行するしくみの解明やこの病気の生化学的な脳内マーカーを開発することが重要です。
東京大学大学院医学系研究科精神医学分野 准教授 山末英典、同研究科 博士課程 夏堀龍暢、同研究科 教授 笠井清登らは、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーという方法を用いて、統合失調症にかかる危険が高い状態にある群、発症後まもない時期にある群、慢性化している群の、脳内化学物質の濃度を調べました。
その結果、慢性化している群についてのみ、内側前頭前野とよばれる脳部位のグルタミン酸−グルタミン総和とN-アセチルアスパラギン酸という物質の濃度低下が認められるという新たな知見を示しました。
この結果は、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピーの所見が統合失調症の進行を反映する新たな脳内マーカーとして役に立つ可能性を示しています。
これらの成果は、日本時間 9月10日にSchizophrenia Bulletin誌(電子版)にて発表されます。
なお、本研究は、文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」の一環として、また科学研究費補助金 若手研究(A)(22689034)の支援を受けて行われました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 228KB]
リリース文書[PDF: 228KB]
(2013/09/10掲載)
ドコモと東大病院による社会連携講座「健康空間情報学」の第二期共同研究を開始
~医療現場への適用に向けて研究を継続~
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、ドコモ)と東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)は、2009年9月から4年間にわたり、社会連携講座「健康空間情報学」(以下、健康空間情報学講座)を東大病院22世紀医療センター内に設置して、携帯電話等のモバイル情報機器を活用した医療情報環境の構築に関する共同研究を行ってまいりました。
本研究で得られた成果を発展させるとともに社会へ導入していくことを目的として、2013年9月1日から2016年8月31日までの3年間、健康空間情報学講座を継続し、第二期の共同研究を開始いたします。
第一期(2009年9月~2013年8月)の研究においては、主に5つのテーマで医療支援システムを共同開発し、その有効性について検証してまいりました。
「2型糖尿病患者の自己管理支援システム」は、健康機器で測定した健康データや食事内容・運動内容等をクラウドサーバに送信すると、自動で健康指導アドバイスがフィードバックされ、異常値が測定された場合は医師に通知されるシステムです。
本システムを利用した臨床試験を実施した結果、患者の生活習慣の行動変容を通じて、糖尿病診断の重要な基準である「HbA1c」の値が有意に減少するというデータが得られ、糖尿病患者の継続的な療養指導、セルフケアに有効であることを確認いたしました。
また、「クラウド型モバイル12誘導心電図システム」は、救急車内で記録した心電図をモバイル端末からクラウドサーバへアップロードすることで、循環器専門医師が遠隔で心電図を診断し、専用治療設備のある病院へスムーズに搬送することができるシステムです。
本システムの利用により、心筋梗塞患者の処置までに要する時間について従来の30%の短縮効果が得られたことを確認し、患者の救命率および予後の向上に貢献できるものと考えております。
このような成果を踏まえ、第二期(2013年9月~2016年8月)の研究では、各システムのさらなる効果検証を進めるとともに、実際の医療現場に導入するための仕組みの構築に向けて取り組んでまいります。
ドコモと東大病院は、健康空間情報学講座を通じて、先端的なICT(情報通信技術)、モバイル情報機器、臨床医学の融合を実現し、時間的・地理的なハードルを越える医療を具現化する医療環境の実現を目指します。
そのために質の高い臨床試験を実施し、開発したシステムの有効性を臨床的エビデンスとして確立してまいります。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 568KB]
リリース文書[PDF: 568KB]
(2013/08/28掲載)
記憶を整理する大脳シナプスの運動を発見
~抑制伝達物質GABAが関与~
私たちがものを覚える時、大脳では神経細胞のシナプスと呼ばれる部位で神経間の結合(シナプス結合)の強さが変わっている。
大脳の興奮性のシナプスは神経細胞の樹状突起のスパインという棘構造にでき、スパインの形態的な変化がシナプス結合の強弱に関与していることが分かっている。
一方でシナプス結合が弱まる場合のスパインの変化については、理解が不十分であった。
東京大学大学院医学系研究科 附属疾患生命工学センター 構造生理学部門の河西 春郎教授、葉山 達也博士課程4年、野口 潤助教らは、2色のレーザーで興奮性伝達物質グルタミン酸と抑制性伝達物質ギャバ(GABA)のそれぞれを放出することにより、大脳のスパインの収縮や除去を誘発することに初めて成功した。
この結果、単一スパインの頭部増大を誘発すると、その効果は単一スパインに限局するのに対して、単一スパインの収縮・除去を誘発すると周囲のスパインにも広がること、収縮・除去を誘発する刺激と頭部増大を誘発する刺激とが競合して、増大刺激が勝ったスパイン、ひいてはシナプスのみが残ることがわかった。
このGABAの作用は神経突起内のカルシウム濃度上昇の抑制による。
また、この増大や収縮の競合はコフィリンという蛋白のリン酸化の競合による。
従来よりGABAは活動電位の発生を抑制すると考えられているが、今回それに加えてGABAにはシナプス周囲のカルシウム上昇の抑制により細胞運動に至る細かな調整があることが明らかとなった。
脳機能は興奮性伝達物質グルタミン酸と抑制性伝達物質GABAの綱引きで決まり、GABAは脳のさまざまな様々の機能の発達、その臨界期、睡眠、自閉症や統合失調症などの精神疾患に深く関係している。
今回の研究は、これらの精神現象や疾患の理解に新しい展望をもたらすものと期待される。
なお、本研究は、文部科学省 脳科学研究戦略推進プログラムの一環として行われ、かつ、科学研究費補助金などの助成を受けて行われました。
本研究成果は、Nature Neuroscience 8月25日オンライン版に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 296KB]
リリース文書[PDF: 296KB]
(2013/08/26掲載)
世界初のNTDs創薬研究向け統合型データベース「iNTRODB」が第11回産学官連携功労者表彰において厚生労働大臣賞を受賞
~Access to Healthの改善に向け、世界のNTDs(顧みられない熱帯感染症)研究加速化に貢献~
8月19日、内閣府による第11回産学官連携功労者表彰において、国立大学法人東京工業大学(所在地:東京、学長:三島 良直)と国立大学法人東京大学(所在地:東京、総長:濱田 純一)、アステラス製薬株式会社(本社:東京、社長:畑中 好彦)の3機関が共同開発した世界初の顧みられない熱帯感染症(NTDs)創薬研究向け統合型データベース『iNTRODB(イントロ・ディービー):Integrated Neglected TROpical disease DataBase』が厚生労働大臣賞を受賞しました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 359KB]
リリース文書[PDF: 359KB]
(2013/08/19掲載)
肺線維化をもたらす線維芽細胞が病変部位に集積するメカニズムの一端を解明
JST課題達成型基礎研究の一環として、東京大学医学系研究科の津久井 達哉日本学術振興会 特別研究員、上羽 悟史 講師、松島 綱治 教授らの研究グループは、肺線維症をもたらす活性化線維芽細胞が病変部位に集積するメカニズムの一端を明らかにしました。
肺線維症は、ガス交換を行う上皮組織が慢性炎症により、I型コラーゲンなどに置き換わり硬くなることで呼吸困難をきたす致死的疾患です。
詳しいメカニズムはいまだに解明されておらず、多くの場合で薬剤による治療が困難であり、発症機序に基づく新たな診断マーカーおよび治療法の開発が望まれています。
線維化をもたらす原因として、活性化した線維芽細胞が線維化部位に集積し、I型コラーゲンを大量に産生することが明らかになっています。
本研究グループは、I型コラーゲンを大量に産生する線維芽細胞の量的・質的変動の解明が肺線維症の予防・治療法の確立に不可欠と考え、マウス肺線維症モデルを解析しました。
その結果、線維化の病態形成過程では活性化した線維芽細胞は、増殖と細胞死の動的平衡状態にあり、従来の考えとは異なり数的には増加せず、移動により線維化部位へ集積することが分かりました。
さらに、活性化線維芽細胞ではオステオポンチンをはじめとする細胞外高分子や、細胞周期、細胞移動に関わる分子の遺伝子発現が高まっていることも分かりました。
線維芽細胞の活性化と、動的平衡状態、細胞移動に関わる分子制御を明らかにすることで、肺線維症の新たな診断・予防・治療法の開発につながることが期待されます。
本研究は、東海大学の稲垣 豊 教授、京都大学の戸村 道夫 准教授、金沢大学の橋本 真一 特任教授らの協力を得て行いました。
本研究成果は、2013年7月22日(米国東部時間)に米国科学誌「The American Journal of Pathology」のオンライン速報版で公開されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 675KB]
リリース文書[PDF: 675KB]
(2013/07/22掲載)
筋肉運動の持続力を生み出すミトコンドリア遺伝子の発見
~ミトコンドリア呼吸鎖のスーパー複合体を作る因子が酸素呼吸の効率を上げる~
酸素を使って脂肪や糖質を燃やす有酸素運動においては、筋肉中の細胞内小器官であるミトコンドリアが必要です。
ミトコンドリアで効率的に呼吸反応(呼吸鎖)が行われることにより、筋肉を動かすためのエネルギーが生み出されます。
呼吸反応を促進させる酵素群には、5 つの複合体が存在し、より効率的な呼吸反応のためには、これらのうちの3 つの複合体がさらに巨大なスーパー複合体をつくることが知られていましたが、その仕組みについてはこれまでほとんど明らかになっていませんでした。
今回、東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター抗加齢医学講座特任教授の井上聡、埼玉医科大学ゲノム医学研究センター講師の池田和博らは、ミトコンドリア呼吸鎖のスーパー複合体形成に必要なCOX7RPタンパク質を世界に先駆けて発見しました。
COX7RPを欠損させたマウスは持続的な運動ができなくなるのに対して、COX7RPを過剰に発現させたマウスでは運動持続力がのびるマラソンランナー型になることがわかりました。
COX7RPは筋肉の運動持続能に必要なエネルギー産生とともに体温維持にも重要であり、内分泌や代謝の異常による病気の新たな治療のターゲットになることが期待されます。
本研究は文部科学省の科学研究費補助金「新学術領域研究」およびセルイノベーション事業の支援を得て行われました。
この研究成果は日本時間7月16日午後6時に英国科学雑誌(Nature Communications)に発表しました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 356KB]
リリース文書[PDF: 356KB]
(2013/07/18掲載)
脳内の外界情報データベースが作られる仕組みを解明
~従来の定説を覆す発見~
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻統合生理学分野の宮下保司教授、平林敏行特任講師らは、霊長類大脳皮質の階層的な領野構造に作り上げられる外界の情報データベース「外界の内部表現」(内部表象)の新しい計算原理を発見しました。
私たちは、脳の外界情報データベース「外界の内部表現」を通じて世界を認識しています。
物体の視覚特徴の表象様式は大脳皮質の内部表現の中でも最もよく調べられています。
しかし、個々のニューロンの活動計測に基づいた従来の見解では、ある脳領野における視覚特徴の神経表象は、その領野において生成され、支配的な神経表象になると考えられてきました。
これに対して、低次領野において神経表象の「前駆コード」が少数生成され、それが高次領野において「増殖」する、という「前駆コード生成→増殖仮説」も立てられます。
本研究では、マカクザル下部側頭葉の隣接した領野であるTE野と36野のそれぞれにおいて複数のニューロンから同時に活動を記録し、図形間対連合の神経表象を生成する神経回路を明らかにすることにより、後者の仮説が正しいことを初めて実証しました。
本研究により、私たちの脳が世界を表象する原理についての理解が深まるのみならず、階層的な構造をもつ人工データベースの効率的設計や、神経表象に関わる疾患に対する治療法にも繋がると期待されます。
本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)研究領域「脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御技術の創出」の一環として行われ、研究成果は米国科学雑誌「Science」7月12日号に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 697KB]
リリース文書[PDF: 697KB]
(2013/07/12掲載)
腎臓癌における遺伝子異常の全体図を解明
~腎臓癌に関する最大規模のゲノム解析を実施~
淡明細胞型腎細胞癌は腎臓に発生する癌のうちおよそ80%を占める代表的な腎臓癌です。
現在のところ、手術による切除以外には完全な治癒を期待できる治療法がありません。
癌が進行し転移を生じた場合には免疫療法や分子標的薬による治療が行われますが、その効果は限定的であり、より有効かつ身体への負担が少ない、新たな治療法の開発が求められています。
そのためには、遺伝子変異をはじめとして、癌細胞で後天的に生じているゲノム異常・分子病態を詳細に理解する必要があります。
京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学講座 教授 小川誠司および東京大学大学院医学系研究科(医学部附属病院 泌尿器科)教授 本間之夫を中心とする共同研究チームは、100 例以上の症例を対象として、これまでで最大規模の統合的な淡明細胞型腎細胞癌のゲノム解析を行い、淡明細胞型腎細胞癌で生じているゲノム異常・分子異常の全体図の解明に成功しました。
ゲノム解析には、東京大学医科学研究所附属 ヒトゲノム解析センター 教授 宮野悟 の協力により、次世代シークエンサーによる塩基配列情報の収集と、スーパーコンピュータによる高速度のデータ解析を行いました。
本研究の成果は、米国科学雑誌「Nature Genetics」電子版にて2013年6月24日(米国東部夏時間)に公開されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 1.0MB]
リリース文書[PDF: 1.0MB]
(2013/06/26掲載)
グリア細胞が脳傷害から神経を守るカルシウム機構の解明
脳内において神経細胞を取り囲むように存在するグリア細胞は、その数が神経細胞を凌ぎます。
通常、グリア細胞は神経細胞の信号伝達をサポートすると考えられています。
しかし、てんかんや脳梗塞などの脳疾患、あるいは脳挫傷などの外傷により脳がダメージを受けると、グリア細胞は「通常型」から「病態型」へと姿を変えて神経細胞を保護する機能を獲得します。
このような変化が起こるメカニズムには不明な点が多く残されていますが、このたび東京大学医学系研究科細胞分子薬理学分野の飯野正光教授らは、そのメカニズムの一端を明らかにしました。
グリア細胞内のカルシウム濃度の変化が、通常型から病態型への変化と神経細胞を保護する作用を獲得するために重要であることが分かりました。
本研究では、損傷した脳組織周辺のグリア細胞において細胞内カルシウム濃度が上昇することに着目し、グリア細胞内のカルシウム濃度の変化とグリア細胞の通常型から病態型への変化との関係を調べました。
その結果、カルシウム濃度の変化が、ある種のタンパク質の合成を加速させることで病態型への変化を制御していることがわかりました。
本研究は、グリア細胞内のカルシウム濃度の変化が、脳損傷の治癒過程に貢献することを初めて示しただけではなく、脳疾患の新規治療法の開発につながる可能性を秘めた重要な知見です。
本研究成果は、「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS;米国科学アカデミー紀要)」(2013年6月24日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 473KB]
リリース文書[PDF: 473KB]
(2013/06/25掲載)
ナノDDSで難治膵臓がんの標的治療に成功:効果を遺伝子改変マウス(自然発症膵がんマウス)で実証
がんの新しい治療法の開発においては、動物モデルから実際の患者さんに至るトランスレーションにおける効果の見極めが極めて重要となります。
現在まで、新規薬剤の効能の試験においては、皮下移植腫瘍が広く用いられていますが、このようなモデルは、的確にヒトのがんの状態を再現していないということが指摘されています。
がん細胞の同所移植腫瘍(例えば、膵がん細胞を膵臓に移植して形成された固形がん)も評価系として使用されていますが、実際のヒトのがんの状態を反映するモデルとは必ずしも言えないのが現状です。
このような背景において、近年、遺伝子改変の手法を用いてヒトと同様に自然にがんを発症するマウスが創出され、利用できるようになってきました。
このマウスでの効果判定がヒトでの有効性を確認する時の決め手となりつつあります。
近年、ドラッグデリバリーシステム(DDS)を利用したがん標的治療は、抗がん剤などの薬剤をがん組織に選択的に送達することによって、副作用を示すことなく優れた治療効果をもたらす画期的ながん治療法として注目されています。
DDSの固形がんへの集積メカニズムは、腫瘍における血管壁の透過性亢進と未発達なリンパ系の構築に基づくEnhanced Permeability and Retention(EPR)効果により説明されていますが、これまで自然発症固形がんにおいてEPR効果に基づくDDSの有効性を実証した例はありませんでした。
そこで本研究では、難治がんとして知られる膵がんを自然発生する遺伝子改変マウスを用いて、精密設計高分子材料の自己組織化により形成されるナノキャリア(高分子ミセル)の有効性を検証しました。
その結果、白金抗がん剤を内包した高分子ミセルは、自然発生膵がんに効果的に集積し、優れた治療効果をもたらすことが明らかになりました。
特に、治療実験において、白金抗がん剤内包ミセルは、フリーの白金抗がん剤では抑制効果が見られなかった肝臓や小腸への転移やがん性腹水を完全に抑制し、マウスの生存期間を大幅に延長させることが明らかになりました(フリーの白金抗がん剤治療での70日後のマウス生存率は20%以下でしたが、抗がん剤内包ミセルによる治療では全匹生存)。さらに、白金抗がん剤内包ミセルの膵がんに対する治療効果は、血中の腫瘍マーカー(CA19-9)の減少からも確認されています。
現在、この白金錯体抗がん剤内包ミセルは実際に膵がんの患者さんを対象とする臨床試験が行われています。
延命効果が約3ヶ月の従来の標準薬物治療に比較して、ミセル投与群では1年を超えて生存する例が出てきており、今回の結果はこの臨床での効果を科学的に立証するものとして、非常に大きな意義を有しています。
膵がんは、有効な診断・治療法が確立されておらず、5年生存率が最も低いことから“難治がんのなかの難治がん”として知られていますが、本研究成果は膵がんに対する画期的な治療法の実現に繋がるものと期待されます。
本研究成果は、Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America(PNAS) (米国科学アカデミー紀要)6月24日オンライン版に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 347KB]
リリース文書[PDF: 347KB]
(2013/06/24掲載)
若くして痛風を発症する遺伝子要因を特定
~痛風ハイリスク群の早期発見と発症予防に期待~
血液中の尿酸値が高くなると、痛風とよばれる激しい関節痛の発作を引き起こすほか、高血圧や脳卒中などの危険因子となることが知られています。
痛風は、以前は中年以降の男性に多い病気であると考えられていましたが、最近では20~30 代で発症する患者も見られています。
この度、防衛医科大学校の松尾洋孝講師、中山昌喜医官、東京薬科大学の市田公美教授、および東京大学医学部附属病院の高田龍平講師らの研究グループは、痛風患者の発症年齢と尿酸を運ぶ輸送体の遺伝子解析から、若くして痛風を引き起こす主な要因がABCG2という尿酸輸送体の特定の遺伝子変異と強く関連していることを発見しました。
すなわち、尿酸輸送体ABCG2に遺伝子変異が認められる場合にはそうでない場合に比べて、痛風の平均発症年齢が最大で6.5歳若いことが分かりました。
そして、20代以下では痛風発症のリスクを最大22.2倍も高めました。
20代以下で発症した痛風患者の約9割(88.2%)がこの遺伝子変異を持っていました。
この成果は、2013年6月18日18時(日本時間)にネイチャー・パブリッシング・グループのオンライン総合科学雑誌「Scientific Reports」に掲載されました。
ABCG2の遺伝子変異は比較的簡便な検査で検出可能であり、最近増えつつある若い年代での痛風患者の遺伝的リスクを評価するための有用な手段となります。
これにより、痛風を発症するリスクの高い人を早期に見つけて、新たな視点から予防することが可能になります。
若い時から健康管理をすることにより、痛風の発症が抑えられるばかりでなく高血圧や脳卒中の予防にもつながることから、生活の質(Quality of Life, QOL)を維持し長期的な医療費の削減にもつながることが期待されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 424KB]
リリース文書[PDF: 424KB]
(2013/06/20掲載)
神経の活動が前初期遺伝子Arcを介してシナプス刈り込みを促進する
統合失調症や自閉症の病態の根底には、神経回路の発達異常があると考えられています。
生後間もない脳には過剰な神経結合(シナプス)が存在しますが、発達の過程で不要なシナプスは淘汰されて、機能的な神経回路が完成します。
この過程は「シナプス刈り込み」と呼ばれ、機能的な神経回路が出来上がるために不可欠とされています。
シナプス刈り込みに神経の活動が必須であることは示されてましたが、詳細な分子メカニズムは不明でありました。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の三國貴康特任研究員と狩野方伸教授らは、発達期の小脳において、シナプス刈り込みに前初期遺伝子Arcが必要なことを明らかにしました。
研究グループはまず、マウスの小脳のプルキンエ細胞の神経活動を上昇させると、登上線維シナプスの刈り込みが促進されることを示しました。
そのうえで、プルキンエ細胞内へのカルシウム流入とそれに引き続くArc遺伝子の発現誘導がシナプス刈り込みを促進していることを明らかにしました。
さらに、誘導されたArc分子が、プルキンエ細胞の細胞体にある過剰なシナプスを除去することにより、シナプス刈り込みを完成させることを明らかにしました。
脆弱X症候群や結節系硬化症といった発達障害をきたす幾つかの症候群の疾患モデルマウスの脳では、Arcの発現異常があることが最近相次いで報告されています。
本研究の成果は、これらの精神疾患の病態を「シナプス刈り込み」の視点から解明するための新たなアプローチを提供するものであります。
本研究成果は、2013年6月19日に科学雑誌「Neuron」のオンライン版で公開されます。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、また科学研究費補助金などの助成を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 403KB]
リリース文書[PDF: 403KB]
(2013/06/20掲載)
うつ症状を呈する精神疾患の鑑別診断を補助する検査の有用性を確認
~簡便な神経画像計測、光トポグラフィー検査を用いた多施設共同研究~
精神医療において精神疾患は、問診により得られる情報に基づいて診断や治療されることが主流であり、客観的な「バイオマーカー(生物学的指標)」に基づいて進められていないことが問題とされてきました。
精神疾患の鑑別診断や治療評価の際に患者や医師の助けとなるバイオマーカーを確立することは、精神疾患の診断や治療を評価できる検査の開発につながり、ひいては個別治療の質の向上をもたらすだろうと考えられています。
群馬大学大学院 医学系研究科 神経精神医学 教授 福田正人、東京大学大学院 医学系研究科精神医学分野 助教 滝沢龍、教授 笠井清登らのグループは、うつ症状を伴う精神疾患(大うつ病性障害、双極性障害、統合失調症)の鑑別を診断する指標として、光トポグラフィーにより得られる脳機能指標の有用性を検討しました。
本研究は、群馬大学・東京大学・国立精神神経医療研究センター(NCNP)など日本全国の7 施設が参加する多施設共同研究として行われ、うつ症状のある患者さん673 名と健常者1,007 名が課題を実施している間の脳機能を、光トポグラフィーを用いて測定しました。
その結果、脳機能指標を用いた鑑別診断では、大うつ病性障害と臨床診断された患者さんのうち74.6%、双極性障害もしくは統合失調症と臨床診断された患者さんのうち85.5%を正確に鑑別できました。
さらに、同じ脳機能指標を用いて全く独立に光トポグラフィーを用いた測定を行ったところ、残りの6 施設においても同等の結果が得られました。
本研究は、光トポグラフィー由来の脳機能指標により、うつ症状を伴う精神疾患の鑑別診断を高い判別率で行えることを示した初めての大規模研究です。
加えて、本研究での鑑別診断は、精神医療分野で唯一の先進医療として、厚生労働省に承認されている「光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助」と同様の方法で行われており、大規模かつ多施設研究によって、精神疾患の鑑別診断補助における光トポグラフィー検査の一定の有用性を再検証したものです。
本成果は、NeuroImage 電子版にて6 月10 日(米国西海岸夏時間)に発表されました。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、また文部科学省新学術領域研究などの助成を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 152KB]
リリース文書[PDF: 152KB]
(2013/06/17掲載)
膵臓手術で発生する「膵液の漏れ」を可視化する蛍光イメージング法を開発
膵臓手術に際して、致死的な合併症につながる可能性のある「膵液漏」を予防し、安全に術後管理を行う方法を確立することは、消化器外科に残された最大の課題です。
この課題を解決するためには、無色透明である膵液を可視化して、膵液漏出の有無や漏出箇所を手術中に正確に検出する技術の開発が必要です。
東京大学医学部附属病院と医学系研究科の研究グループでは、膵液中の蛋白分解酵素(キモトリプシン)と反応して、速やかに緑色の蛍光を発するプローブを作成することに世界で初めて成功しました。
このプローブを、患者さんの膵臓の断端(手術でがんを切除した際の切り口)を転写した濾紙に噴霧し、濾紙に青色光を照射しながら黄色のフィルターを通して観察して、緑色に発光している部位があるかどうかを調べることで、膵液漏出の有無や漏出箇所を手術中に同定することができました。
さらに、手術後にドレーン(体液を体外に排出する管、用語解説3)から流出する体液中の蛋白分解酵素活性を測定することにより、膵液漏が重症化するリスクを評価することができました。
このプローブを患者さんの体内に直接噴霧することはまだできませんが、上記の技術を応用することにより、手術中に膵液の漏出部位を閉鎖して膵液漏を予防することや膵液漏の重症度に応じて適切な術後管理を行うことが可能になると期待されます。
この研究成果は、British Journal of Surgeryオンライン版にて、6月13日(英国時間)に発表されました。
なお、このプローブの開発は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業・研究加速課題(光機能性プローブによるin vivo微小がん検出プロジェクト)として行いました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 156KB]
リリース文書[PDF: 156KB]
(2013/06/14掲載)
原因不明の神経難病、多系統萎縮症に関与する重要な遺伝的因子を発見・治療法実現へ道を拓く
多系統萎縮症は神経難病の一つですが、これまで、病気の発症機構が全く不明であり、有効な根本的治療法が存在しませんでした。
このたび、東京大学医学部附属病院 神経内科 教授 辻省次らの研究チームは、日本、ヨーロッパ、北米の国際多施設共同研究による遺伝子解析を行い、家族性・孤発性に共通して病気を発症しやすくする遺伝子(COQ2 遺伝子)が存在することを初めて発見しました(The New England Journal of Medicine 米国東部時間6月12日午後5時(日本時間13日午前6時)発表)。
COQ2 はコエンザイムQ10 の生合成に必須な酵素のDNA 塩基配列を記述する遺伝子です。
本研究により、多系統萎縮症の発症には、COQ2 遺伝子の働きが低下することが関連すると考えれ、実現可能性の高い治療法の開発が期待できます。
これまで、孤発性の疾患の発症機構を解明することは非常に困難でしたが、本研究では従来と比較して、大量かつ高速にDNA の塩基配列を解読できる次世代シーケンサーを用いた大規模ゲノム解析を行うことにより、多系統萎縮症の発症に関与する遺伝子を発見することができました。
また、この研究は、国内の大規模多施設研究体制、さらには、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリアや米国での大規模多施設研究体制による協力態勢のもと可能となったものです。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 100KB]
リリース文書[PDF: 100KB]
(2013/06/13掲載)
新開発 冠動脈狭窄症の血液検査法
~質量分析技術を用いた新しいバイオマーカー開発~
動脈硬化などにより狭くなった冠動脈をカテーテルで治療した後に、その治療部位が完治したかどうか確認する手段は心臓カテーテル検査が標準となっていますが、この検査は身体への負担が大きく、費用も高額です。そのため、心臓カテーテル検査に代わる簡易な検査法が求められていました。
このたび、東京大学医学部附属病院 循環器内科・ユビキタス予防医学講座 特任准教授鈴木亨、東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学教室 前教授永井良三、教授小室一成は、株式会社 島津製作所 基盤技術研究所 主任研究員 藤本宏隆と共同で、質量分析計を用いて新しい血液検査法を開発しました。
これにより、冠動脈カテーテル治療後の再狭窄の診断において、心臓カテーテル検査を受ける必要があるかどうかを簡単に検出することができるようになり、身体への負担を軽減できる新しい検査方法となることが期待されます。
本研究開発の成果は、クリニカル・ケミストリー(Clinical Chemistry)電子版にて5 月13 日(米国東部夏時間)に発表されました。
今後、当院ではこの診断法の実用化を目指します。
なお、本成果は、厚生労働科学研究費、科学研究費(文部科学省)、最先端研究開発支援(FIRST)プログラム(日本学術振興会)、イノベーションシステム整備事業(先端融合領域イノベーション創出拠点形成)プログラム(文部科学省)の支援を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 264KB]
リリース文書[PDF: 264KB]
(2013/05/17掲載)
前立腺がんに対するウイルス療法の臨床研究を開始
~遺伝子組換えヘルペスウイルスを用いた前立腺がん治療は世界初~
東京大学医学部附属病院は、泌尿器科・男性科 講師 福原浩を総括責任者として、再燃前立腺がん患者を対象にしたウイルス療法の臨床研究を開始します。
これは、がん細胞だけで増殖するようにウイルス遺伝子を組み換えた人工的なウイルスを使ってがん細胞を破壊する、新しいがん治療法です。
用いるのは東京大学医科学研究所 教授 藤堂具紀らが開発した第三世代のがん治療用単純ヘルペスウイルスⅠ型のG47Δ(デルタ)で、現在、悪性脳腫瘍を対象にした臨床研究が本学で進行中です。
今回は、ホルモン療法が効かなくなってきた、手術を受けていない前立腺がんの患者が対象です。
遺伝子組換え単純ヘルペスウイルスⅠ型を前立腺の中へ投与するのは世界で初めての試みであり、安全性を調べるのが今回の臨床研究の目的です。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 225KB]
リリース文書[PDF: 225KB]
(2013/05/17掲載)
造血多能性細胞の増殖を制御する新しい分子メカニズムの発見
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター分子病態医科学部門の中島克彦助教と宮崎徹教授のグループは、遺伝子改変マウスを用いた研究から、造血多能性細胞の増殖を制御する新しい分子メカニズムを明らかにした。
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ4(PAD4)によるクロマチン修飾は、様々な遺伝子を制御することが示唆されていたが、その生理機能はほとんど不明であった。
今回の研究成果により、PAD4は他の制御因子と複合体を形成し、がん遺伝子c-mycの上流に結合しクロマチンを修飾することでその発現を制御することを明らかにした。
また、遺伝子改変マウスを用いた解析から、PAD4は骨髄の造血多能性細胞の増殖を調節していることが明らかとなった。
今回の研究成果は、PAD4ががん抑制因子として機能することを示唆しており、白血病等の造血系疾患に対するPAD4を標的とした診断や治療の可能性が考えられる。
本研究の成果は『Nature Communications』(5月14日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 187KB]
リリース文書[PDF: 187KB]
(2013/05/15掲載)
低分子化合物(TD-198946)で処理した軟骨再生シート
~変形性関節症の治療を目的として~
変形性膝関節症は膝関節軟骨が摩耗する病気で、一度軟骨が磨り減ると元の状態に戻すことができないとされており、これまでの治療法は対処療法がほとんどです。
軟骨組織再生についてはすでに多くの研究開発が進んでおりますが、今回、東京大学大学院工学系研究科(医学系研究科兼担)の鄭雄一教授らは、細胞シートを培養する温度応答性細胞培養器材(株式会社セルシード製)を用いて、軟骨分化誘導能をもつ分子化合物(TD-198946)で処理した軟骨細胞シートを作製し、膝関節軟骨欠損動物モデルに移植し、より効率よく硝子様軟骨組織を再生させました。
細胞シート工学の技術と軟骨分化誘導能をもつ化合物を組み合わせることによって、軟骨組織再生を効率よく行うことができると考えています。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 248KB]
リリース文書[PDF: 248KB]
(2013/05/15掲載)
再燃前立腺がんの新たな治療標的を発見
~アンドロゲン応答性の新規長鎖非コードRNA が前立腺がんの増殖を担う~
前立腺がんは最も発症頻度の高いがんのひとつで、その発症者、死亡者の急激な増加は、超高齢社会を迎えた日本においても大きな社会問題となっています。
前立腺がんの発生と進展においては、男性ホルモンであるアンドロゲンの作用が鍵を握っており、アンドロゲンの作用を抑制するホルモン療法が広く普及しています。
しかし、ホルモン療法に対する耐性ができてしまい治療効果が出なくなって再燃することが多く、問題になっています。
この場合のホルモンの作用メカニズムの詳細については、これまで明らかになっていませんでした。
今回、東京大学医学部附属病院22 世紀医療センター抗加齢医学講座の井上聡特任教授、老年病科の高山賢一特任臨床医らは、文部科学省の革新的細胞解析研究プログラム(セルイノベーション)と次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムの支援を得て、次世代シーケンサーを活用し、新規の長鎖非コードRNA分子(遺伝子ではないゲノム領域から作られるタンパク質の情報を有さないRNA)であるCTBP1-AS がアンドロゲンの刺激を受けてがん遺伝子のように働くことを世界に先駆けて発見しました。
さらに、CTBP1-AS は前立腺がんの増殖、進展に大きな役割を果たしていること、ならびにそのエピゲノム作用を介する分子メカニズムを解明しました。
特に、ホルモン療法が奏功しない難治性前立腺がんの新たな治療の標的となりうることを明らかにしました。
この研究成果は日本時間5月3日午後11時に欧州科学雑誌(The EMBO Journal)に発表しました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 343KB]
リリース文書[PDF: 343KB]
(2013/05/08掲載)
滅菌可能な骨誘導性微小人工骨の開発に成功
骨形成性薬剤を徐々に放出するテトラポッド型リン酸カルシウム微小人工骨による骨再生
高齢化社会を迎えた現代において、種々の疾患によって生じた骨欠損の治療は健康寿命の延伸につながる重要な課題の一つです。
健常部位から採取した骨組織の移植による骨再建と比較して、人工骨を用いた再建は健常骨の採取に伴う侵襲を減らすことができるものの、人工骨自体は骨形成を誘導する能力に乏しいことが問題でした。
そのため、骨欠損部周囲に存在する患者自身の細胞に働きかけることで積極的に骨形成を促進する人工骨、つまり骨誘導性人工骨の開発が期待されています。
東京大学大学院医学系研究科感覚・運動機能医学講座口腔外科学(主任:高戸毅教授)医学博士課程の前田祐二郎氏、東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の大庭伸介特任准教授、鄭雄一教授らは、骨形成性薬剤をテトラポッド型リン酸カルシウム微小人工骨に搭載することで、滅菌可能な骨誘導性微小人工骨を開発しました。本人工骨を骨欠損部に充填すると、細胞を移植しなくとも、骨形成性薬剤が徐々に放出されることにより海綿骨・皮質骨両方の骨修復が誘導され、その薬効は滅菌処理によって失われません。
本研究は、骨形成性薬剤の使用による作製・滅菌・保存の簡便さと骨誘導性を併せ持つ微小人工骨を用いることで、生体の自然治癒能力を効率的に引き出しながら、細胞移植を行わずに骨再生を誘導する方法を提案するものであり、新たな骨再生医療戦略の開発への寄与が期待されます。
本研究の成果は『Biomaterials』(2013年4月23日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 288KB]
リリース文書[PDF: 288KB]
(2013/05/02掲載)
シナプスの演算ルールを可視化することに成功!
ナノレベルの記憶形成機構解明
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻神経生化学分野の尾藤晴彦教授と藤井哉特任助教らは、シナプス可塑性が起こる過程を顕微鏡で観察し、シナプス酵素が行う情報処理を明らかにしました。
これまで、外界の情報は神経入力となってシナプスの様々な酵素を活性化して可塑性を引き起こし、記憶につながると考えられていました。しかし、シナプスの酵素がどのように神経入力を読み解くのか、またこれをシナプスがどのような演算ルールとして活用するのかは全く分かっていませんでした。それは従来の方法では1フェムトリッター以下の容量のシナプスを分離して生化学的な分析することができないためでした。
本研究グループは、複数の酵素の活性化を直接顕微鏡で動画として記録する方法(dFOMA法)を開発しました。この方法を用いて、シナプスの酵素が神経入力の情報を読み解く様子を、世界で初めてリアルタイムで観察することに成功しました。また、これまで単に遺伝子の実態として捉えられてきた酵素について、実はそれぞれ固有の情報処理を行う素子であるという新しい機能を明らかにしました。
今回の結果は、記憶の分子メカニズムという複雑なシステムを理解する上で重要な知見であり、将来的にはアルツハイマー病など高次脳機能障害の解明に役立つことが期待されます。また、今回開発したdFOMA法は広く生物学一般への応用が可能であり、様々な生命現象の原理を、まるで動画を見るように理解することができるようになることが期待されます。
本研究の成果は『Cell Reports』(4月18日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 713KB]
リリース文書[PDF: 713KB]
(2013/04/19掲載)
鞭毛モーターの司令塔を発見
~鞭毛を動かす分子モーターの活性を制御する中心装置の存在を初めて明らかに~
鞭毛は波打ち運動によって液体の流れを生み出す細胞小器官で、人間を含む多くの生物の細胞運動や発生に重要な役割を担っています。例えば人間の精子は、鞭毛を波打たせて泳ぎます。また、肺の気道では、吸い込んだホコリや病原体を外へ出すために、沢山の繊毛(鞭毛の一種)が粘液の流れを作っています。この様に体内で重要な役割を担っている鞭毛は、数千個のダイニンと呼ばれるモーター分子によって動かされています。鞭毛では多種多様なダイニン分子が働いていますが、異なる種類のダイニンがどのように協働しているのか分かっていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の小田賢幸助教と吉川雅英教授らのグループは、超低温電子顕微鏡などを用いて、鞭毛の外側のダイニンと内側のダイニンを繋ぐ役割をしているタンパク質ODA-IC2を同定しました。さらに超高速度カメラ等による多角的解析から、このODA-IC2を遺伝子操作によって乱すと外側にあるダイニンは制御から外れて暴走し、内側にあるダイニンは逆に働きが低下することが分かりました。これらの結果は、ODA-IC2が鞭毛の動きを制御する上で「司令塔」として働いており、そこに手を加えるとダイニン全体に影響が及ぶ急所であることを示しています。今回得られた知見は、鞭毛運動の制御機構についての理解を深めるだけでなく、鞭毛が関わる不妊、呼吸器疾患、水頭症等の研究に貢献することが期待されます。
本研究は内閣府・最先端・次世代研究開発支援プログラム、及び科学研究費補助金の助成を受けて行われました。本研究の成果は『Current Biology』(2013年4月22日号)に掲載されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 199KB]
リリース文書[PDF: 199KB]
(2013/04/15掲載)
歯周靭帯(歯根膜)の成熟と機能を特徴づける分子を発見
~歯の萌出とともに発現し細胞接着を増強する分子テノモジュリン~
歯周靭帯(歯根膜)は顎骨内に歯を牽引固定する重要な組織であり、咬合力への抵抗性、接触感覚などの重要な機能を担っています。一方で、口腔衛生状態の低下によって歯周炎に罹患すると破壊されてしまい、失われた歯周靭帯を再生させることは非常に困難で、今のところ歯周靭帯を含め、歯周組織を完全に再生させる有効な療法はありません。現在、歯周組織を再生する研究は多岐に展開していますが、機能的な再生を評価する指標が乏しく、再生組織が腱・靭帯としての性格を有することを評価できませんでした。
東京大学医学部附属病院集中治療部の小宮山雄介博士、東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の大庭伸介特任准教授・鄭雄一教授らのグループは、ドイツ ルートヴィッヒ・マクシミリアン大学のDenitsa Docheva 講師、京都大学再生医科学研究所の宿南知佐准教授・開裕司教授との共同研究で、テノモジュリン(Tenomodulin、以下Tnmd)という分子が、歯周靭帯の発生と機能に関わることを新たに見出しました。Tnmd は成熟腱・靭帯組織のマーカー分子であるのみならず、機能的にも腱・靭帯組織を特徴づける分子であると考えられます。本成果が、歯周靭帯をはじめとする腱・靭帯組織の再生医療において、機能的な組織の再生療法を開発する際の足がかりとなることが期待されます。
※詳細は下記ページをご覧下さい
東京大学工学部ホームページ プレスリリース
(2013/04/11掲載)
肥満から起こる様々な自己免疫病の決定的な原因の発見
~AIMによる様々な現代病に対する治療の可能性~
現代社会において、糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病が肥満に伴い発症するが、同様に、肥満は種々の自己免疫疾患の引き金になることも知られている。しかし、なぜ肥満が多彩な自己免疫疾患を導くのか、そのメカニズムは明らかでなかった。
東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター分子病態医科学部門の新井郷子講師と宮崎徹教授のグループは、そうした肥満に伴う自己免疫疾患の発症機序を明らかにし、その中心的役割を果たすのが、発表者自身が発見した、脂肪を融解する血液中のタンパク質AIM (Apoptosis Inhibitor of Macrophage)であることを見出した。これまで発表者らは、血液中のAIMの量をコントロールすることによって、肥満の進行のみならず、糖尿病や動脈硬化を抑制できる可能性を示してきた。
本研究によって、AIMの制御により、肥満に伴う自己免疫疾患も抑制し得ることが明らかになった。したがって、AIMは、糖尿病、動脈硬化、自己免疫疾患など、肥満に伴う幅広い疾患の統一的な治療のターゲットになると考えられる。
本研究の内容は、Cell Reports(4月4日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 192KB]
リリース文書[PDF: 192KB]
(2013/04/05掲載)
多くの「匂い」情報を識別できる仕組み
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科 教授 山岨達也、菊田周は、テキサス大学医学部ヒューストン校 助教 永山晋との共同研究において、マウスの脳内で「匂い」識別に関わる基本構造単位である細胞群を可視化することに初めて成功しました。さらに、基本構造単位内における細胞が空間的にどのように配置しているかによって神経活動が多様化していることを見つけました。
マウスの嗅球は、鼻に吸い込まれた「匂い」を最初に処理する脳の領域であり、私達がどのようにして多くの「匂い」情報を識別しているのかを知るうえで手がかりとなる領域です。しかし、嗅球の細胞が吸い込まれた「匂い」をどのように連携して処理し、「匂い」識別のしくみに関わっているのかはよく分かっていません。
本研究グループは、同じ「匂い」受容体から情報を受け取る細胞群を選択的に可視化し、その神経活動を直接計測、比較することに成功しました。その結果、細胞の深さ方向や横のひろがりといった空間配置によって、神経活動に違いが生じることを突き止めました。これは、同じ受容体から情報を受け取る細胞群は、「同じ受容体からの刺激に同じように反応する」とするこれまでの定説を覆し、「同じ受容体からの刺激に多様に反応する」巧妙な情報処理様式が嗅球の基本構造単位内に存在することを示しています。これにより、私たち哺乳類は限られた「匂い」受容体でより多くの「匂い」情報を識別できると考えられます。
この発見は、私たちの脳内で行われる「匂い」情報処理機構の理解を深めるだけではなく、中枢性嗅覚障害の病態生理解明の糸口となることが期待されます。
本研究成果は、2013年3月20日(米国東部時間)に米国科学誌「ニューロン」のオンライン速報版で公開されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 208KB]
リリース文書[PDF: 208KB]
(2013/03/29掲載)
熱性けいれん重積後の急性脳症を発症しやすい遺伝的素因の解明
東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 発達医科学分野の水口雅教授、齋藤真木子助教らの研究グループは、アデノシンA2A受容体遺伝子の多型がけいれん重積型(二相性)急性脳症の遺伝的背景であることを明らかにしました。この型の急性脳症は日本人小児にしばしば生じ、熱性けいれん重積に続いて意識障害をきたし、後遺症として知的障害、運動麻痺やてんかんなどを残します。現状では発症早期の診断・治療が確立していません。
アデノシンは体内の信号物質(神経修飾物質)で、複数の受容体に結合して作用を発揮します。脳の中にはA1受容体とA2A受容体があり、A1には神経細胞の興奮を抑制、A2Aには促進する作用があります。
本研究により、急性脳症の発症にA2A作用の亢進、つまりアデノシンを介した細胞内情報の変化が関わっていることが明らかになったので、今後、急性脳症の新しい薬物治療を開発する際の標的分子が明確になりました。
本研究の内容は、Neurology(3月27日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 207KB]
リリース文書[PDF: 207KB]
(2013/03/28掲載)
福島原発事故後の避難による高齢者死亡リスクの分析
東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学分野の渋谷健司教授、野村周平大学院生らは、東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門の上昌広特任教授ら、南相馬市立総合病院と共同で、福島第一原子力発電所の23km圏に位置する福島県南相馬市内5つの老人介護施設の協力のもと、事故後の避難による高齢者の死亡リスクの推定と、避難プロセスにおける死亡率上昇要因の分析を試みた。
研究グループは、5つの老人介護施設について、避難を経験していない震災前過去5年間と避難期間を含む約1年間の高齢者死亡率の比較を、数理モデルを用いた回帰分析と各施設長および介護士らへのインタビューという二つの手法を用いて実施した。避難回数・距離・数値化しづらいケアの状況等を考慮した、施設ごとの死亡リスクが議論されたのは今回が初めてである。
結果として、避難後の死亡率は避難前に比べて、全体で2.7倍に増加したことがわかった。ただし、避難後の死亡率の変化には、施設によってばらつきがある。避難プロセスや施設のケア状況に関する分析により、長距離の移動による身体的負担以上に避難前の栄養管理や避難先の施設のケア・食事介護への配慮が重要であること、初回の避難による死亡リスクは二回目以降の避難よりも高いことなどが示唆された。
今回の成果により、事故直後の避難は必ずしも最善の選択ではなかった可能性が見えてきた。高齢者の避難は生死に関わる問題であり、今後の災害時には避難のリスクについても検討する必要があることが強く示唆された。
本研究の内容は、PLOS ONE (3月27日オンライン版)に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 192KB]
リリース文書[PDF: 192KB]
(2013/03/27掲載)
内科学専攻 代謝・栄養病態学分野 門脇 孝 教授(医学部附属病院長)が日本学士院賞を受賞
この度、内科学専攻代謝・栄養病態学分野 門脇 孝 教授(医学部附属病院長)が平成25年度の日本学士院賞を受賞しました。
今回の受賞は、「2型糖尿病・メタボリックシンドロームの分子基盤に関する研究」に対するものです。
※ 受賞理由の詳細については、下記より日本学士院のホームページをご覧ください。
※日本学士院ホームページ (日本学士院賞授賞の決定について)
(2013/03/13掲載)
世界一の日本の健康寿命の危機
米国ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME)と東京大学などによる共同プロジェクトである「2010年の世界の疾病負担研究(Global Burden of Diseases 2010、GBD 2010)」では、世界21地域での分析に加えて、今回新たに、世界187か国における死亡と障害の原因を性・年齢階級別に詳細に分析し、データビジュアル化オンラインツールを公表した。
これにより、今回の研究では、現在の日本人の健康寿命を取り巻く状況が複雑で、死亡と障害の主な原因は脳卒中と腰痛であること、最大の危険因子が栄養の偏った食事であること、また、若年層での自殺の増加を明らかにした。
本研究成果により、これまで20年の間世界第一位を誇ってきた日本人の健康寿命は、偏った食習慣や心の健康の問題、喫煙、高齢化の課題に取り組まなければ、トップの座を維持できない可能性があること、また日本人は世界で最も長寿だが、長く生きた分だけ病気や障害に苦しむ年数も増大していることを明らかにした。
本研究の内容は、ランセット誌3月5日オンライン版に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 218KB]
リリース文書[PDF: 218KB]
(2013/03/05掲載)
アフリカ睡眠病治療薬の候補化合物と標的タンパク質との複合体構造の解明
アフリカ睡眠病は、中枢神経系を侵され最後は昏睡状態になって死に至る致死性の感染症です。しかし、「顧みられない熱帯病」と呼ばれているように先進諸国の関心が薄く、アフリカの貧困層を中心に蔓延しています。ツェツェバエが媒介する寄生性原虫アフリカトリパノソーマの感染によって起こり、年間約30,000人もの人々が死亡していると報告されていますが、正確な数字は把握されていません。現在使われている治療薬は、強い毒性や副作用があるので、より安全で治療効果の高い薬の開発が求められています。
アフリカトリパノソーマがヒトなどの哺乳類血液内で生息している時、アフリカトリパノソーマの生存に必要なエネルギーを産み出すためにシアン耐性酸化酵素(TAO)が重要な役割を担っています。TAOは哺乳類にないタンパク質なので格好の薬剤標的になり、その働きを阻害する化合物を開発すれば睡眠病治療薬へつながります。
1995年、東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 生物医化学分野の北潔教授らは、日本で糸状菌から発見された抗生物質、アスコフラノンがTAOを強く阻害することを見出しました。アスコフラノンをリード化合物にしてドラッグデザインすればもっと優れた睡眠病治療薬に導くことができるはずです。しかし、ドラッグデザインに不可欠なTAOの立体構造が全く不明でした。そこで京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 応用生物学部門 構造生物工学研究室の原田繁春教授と共同研究を開始しました。
今回、同研究グループは、TAOやTAOにアスコフラノン誘導体が結合した構造を日本が誇るSPring-8やPFの放射光施設を用いたX線解析で決定し、両者の間に働いている相互作用を明らかにしました。その結果、さらに優れた睡眠病治療薬のドラッグデザインを加速できるようになりました。
本研究の内容は、米国科学誌「米国科学アカデミー紀要;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)」3月4日オンライン版に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 619KB]
リリース文書[PDF: 619KB]
(2013/03/05掲載)
脳脊髄神経系にメッセンジャーRNA(mRNA)送達を可能とする高分子ミセルの開発
脳や脊髄などの中枢神経系疾患は、根治的治療が困難な難治疾患の代表例です。メッセンジャーRNA(mRNA)は神経細胞で効率よく目的とするタンパクを産生させる機能を持ち、新しい核酸医薬として治療への応用が期待されるものですが、mRNAは極めて不安定で生体内では急速に分解されてしまうこと、また自然免疫機構を刺激して、生体内で強い炎症反応を引き起こすことから、これまでmRNAの治療への応用例はほとんどありませんでした。
本研究は、このmRNAによる新しい中枢神経系疾患への治療実現に向けて、東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻/東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター臨床医工学部門の片岡一則教授・位髙啓史特任准教授の研究グループにより、高分子ミセル型ドラッグデリバリーシステム(DDS)を用いた、mRNAの中枢神経系への安全な送達・機能発現に世界で初めて成功したものです。
本研究では、mRNAを内包させた高分子ミセルを脳脊髄組織へ投与することにより、5日間に渡る持続的なタンパク発現を得ました。このmRNAによる長期持続性機能発現における高分子ミセルの働きとして、mRNAを安定に保持することに加え、自然免疫機構に認識されることを防ぎ、炎症反応の発生を抑えることを明らかとしました。本システムによる安全・実用的なmRNA送達の実現により、アルツハイマー病、脊髄損傷といった難治性の中枢神経疾患・外傷に対して、画期的な新規治療法の開発に繋がることが期待されます。
なお、上記の研究成果は、最先端研究開発支援プログラム「ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション」(中心研究者:片岡一則教授 URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/nanobiof/)により得られたものです。本プロジェクトは、平成21年度にスタートし、平成25年度末までに、がん・神経系疾患を始めとする難治性疾患の診断・治療に向けた画期的技術の確立を目指しています。具体的には以下の4つのサブテーマがあり、それぞれの分野において、医工薬・産独学の融合研究が進められています。
I. ナノ診断システムの創成
II. ナノ薬剤送達システム(ナノDDS)の創成
III. ナノ低侵襲治療システムの創成
IV. ナノ再建システムの創成
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 248KB]
リリース文書[PDF: 248KB]
(2013/03/04掲載)
脳内のマリファナ類似物質が‘慣れ’をコントロール
刺激や環境に対する‘慣れ(馴化)’は最も単純な学習であり、統合失調症や自閉症などの様々な精神疾患において障害されることが報告されている。
今回、東京大学大学院医学系研究科の菅谷佑樹助教と狩野方伸教授らは、内因性カンナビノイドと呼ばれる脳内の大麻様物質の一種である2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)が匂いや空間に対する馴化を制御するメカニズムを明らかにした。
2-AGの合成が低下するように遺伝子改変されたマウスは匂いや空間に早く馴化し、神経細胞間の情報伝達が増強されやすくなっていた。
さらに、遺伝子改変マウスの馴化と神経細胞間の情報伝達の関係を調べたところ、2-AGが海馬歯状回の興奮性を低下させシナプス伝達の変化を抑えることで馴化を遅延させるというメカニズムが明らかになった。
内因性カンナビノイドは統合失調症や自閉症、依存症との関連が示唆されている。
最も単純な学習である‘慣れ’に関してマウスで見出された本研究の成果は、これらの精神疾患の学習・適応能力の理解につながる可能性があると考えられる。
本研究は文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、また科学研究費補助金の助成を受けて行われた。
この研究成果は「The Journal of Neuroscience」2013年2月20日号に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 348KB]
リリース文書[PDF: 348KB]
(2013/02/21掲載)
脳内で不安を抑える分子モーターKIF13A
レントゲンや内視鏡などによって診断を下せるガンなどの身体的疾患に比べて、不安障害やうつなどといった精神的疾患の原因はまだ十分にわかっていません。
精神疾患の原因解明のためには「安心」「不安」などといった我々の感情に結びつく高次の脳機能がどのような分子の働きでコントロールされているかを知る必要があります。
今回、東京大学大学院医学系研究科細胞生物学・解剖学講座/分子構造・動態学講座の廣川信隆特任教授らの研究グループは、分子モータータンパク質KIF13Aが脳内でセロトニン受容体を輸送することで不安を抑制することを明らかにしました。
KIF13Aが働かないマウスの脳内ではセロトニン受容体が神経細胞表面まで輸送されません。このマウスでは不安が高まり、エサを探さずに暗いところに隠れようとする「心配性」の異常行動が観察されました。
不安の感じ方には個体差がありますが、KIF13Aの働きが弱いと不安を感じやすい性格になるのかもしれません。
また、セロトニン受容体は精神安定剤や抗うつ剤の重要な標的として知られていますが、KIF13Aもまた創薬標的分子となるかもしれません。
この研究成果は「Cell Reports」2013年2月7日オンライン版に掲載されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 170KB]
リリース文書[PDF: 170KB]
(2013/02/12掲載)
神経細胞の突起の“伸び”と“つながりやすさ”は別々に制御される
~細胞骨格制御蛋白質DCLKの新しい機能を発見~
神経細胞は、樹状突起と軸索という二種類の突起をつくり、長く伸びた二種類の突起の間で接着が起こり「シナプス」と呼ばれる構造を形成します。
シナプス間の情報のやりとりにより機能的な神経回路が発達期に形成されます。
突起の伸長とシナプスの形成の両者は共に回路の形成を促進しますが、突起が十分伸びた後でシナプスが形成される必要があり、両者のバランスをきちんと調節することが必要です。
東京大学大学院医学系研究科神経細胞生物学分野 岡部繁男教授らの研究グループでは、脳の発達障害に関連する分子であるDCLKが突起の先端に局在して突起形成を促進することを見出しました。
一方でDCLK分子はシナプス内にも入り込み、突起先端でシナプスの形成が過剰に起こることを抑制することも見出しました。
DCLKはN末端に微小管結合ドメイン、C末端に蛋白質のリン酸化を行うドメインを持つキメラ分子ですが、N末端ドメインが突起を伸ばし、C末端ドメインがシナプス形成を阻害することで相反する作用が生じることもわかりました。
今回の研究により、神経突起の伸長とシナプス形成という神経回路形成に重要な二つの現象のバランスが、一個の分子の二つのドメインで制御されていることを初めて示しました。
本研究成果は、2013年2月5日に科学雑誌「Nature Communications」のオンライン版(http://www.nature.com/ncomms/index.html)で公開されました。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、科学研究費補助金などの助成を受けて行われました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 253KB]
リリース文書[PDF: 253KB]
(2013/02/06掲載)
変形性膝関節症の原因となる細胞外分子Notch の発見
変形性膝関節症は膝関節の軟骨が摩耗する病気で、高齢者の生活の質(QOL)を低下させ、健康寿命を短縮させる、いわゆるロコモティブシンドロームの代表的疾患です。しかしながらその根本的治療法は不明のままです。
これまでに、変形性膝関節症の原因分子がいくつか報告されてきましたが、その殆どが細胞の中の分子(細胞内分子)で、治療物質が届きにくく治療の標的には難しい状態でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科 整形外科学 大学院生の保坂陽子、同研究科/医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 准教授の川口浩らは細胞の表面に存在するNotchという受容体タンパクが変形性膝関節症に大きく関与していることを、マウスの実験によって発見しました。
細胞表面分子や細胞外分子は細胞内の分子に比べて治療の対象になりやすいという利点があります。実際に、Notch の阻害剤である低分子化合物DAPT を膝関節内に注射投与したところ、軟骨細胞に働いて変形性膝関節症を予防することを見出しました。
本成果は、米国科学アカデミー紀要(Proc. Natl. Acad. Sci. USA:略称PNAS)電子版にて米国東部標準時間1 月14 日午後3 時に発表されました。
DAPT に代表されるNotch の阻害剤は、変形性膝関節症の根本的治療法の確立に繋がる可能性があります。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 1.08MB]
リリース文書[PDF: 1.08MB]
(2013/01/16掲載)
記憶を思い出す源となる神経回路を解明
JST課題達成型基礎研究の一環として、東京大学 大学院医学系研究科の宮下 保司 教授、平林 敏行 助教らは、サルを被験動物とした実験により、記憶を思い出す時の信号の生成と伝播を担う神経回路を発見しました。
大脳の側頭葉は、物体についての記憶を司る脳の領域であり、物事を覚え込んだり、思い出したりする時に活動する神経細胞が多く存在することが知られています。
しかし、これらの神経細胞が、どのような神経回路を形成し、連携することによって記憶を思い出す信号を生成しているのかは分かっていませんでした。
本研究グループは、1つの図形(例えば鉛筆)を手がかりにして、事前に対として記憶している別の図形(消しゴム)を連想する作業を遂行中のサルの側頭葉で、複数の神経細胞群の活動を同時に記録しました。
その結果、手がかり図形(鉛筆)に応答しその情報を保持するニューロン(手がかり図形保持ニューロン)から、別の図形(消しゴム)を思い出す時に活動するニューロン(対図形想起ニューロン)へと特異的に神経信号が伝達し、それがさらに他の対図形想起ニューロンへと伝播していくことによって、記憶想起信号が生成され、増幅されることが分かりました。これにより、私たち霊長類が物体についての記憶を思い出す際に用いられる側頭葉の神経回路とその動作が初めて明らかになりました。
今回用いた複数の神経細胞群の活動を同時に記録し、解析する手法により、記憶想起信号の起源となる局所神経回路の解明が進むとともに、あるタイプの記憶障害に関与する神経回路についての研究の進展や、連想型データベースの高速化・効率化などへのさまざまな応用が期待されます。
本研究成果は、2013年1月9日(米国東部時間)に米国科学誌「Neuron」のオンライン速報版で公開されました。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 759KB]
リリース文書[PDF: 759KB]
(2013/01/10掲載)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報