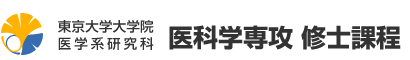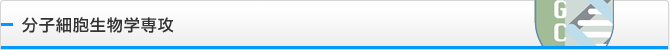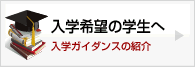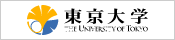東大医学部は大学院化に伴い、解剖学講座と生化学・分子生物学講座が合体し、この専攻を作りました。一見、必然性の無い結合に見えますが、現代の生命科学の最も基礎的な分野を統合しています。
東大医学部は大学院化に伴い、解剖学講座と生化学・分子生物学講座が合体し、この専攻を作りました。一見、必然性の無い結合に見えますが、現代の生命科学の最も基礎的な分野を統合しています。
というのは、生命科学では、化学(尿素合成などの有機化学)、遺伝学(ご存じメンデルから)、細胞生物学(フックによる細胞の発見から)の三つの起源を持ち、これらが発展し、融合して一つの大きな研究領域を作り出しました。それが、分子細胞生物化学であり、分子生物学と同義です。
専攻には大きく細胞生物学(旧解剖学)と生化学・分子生物学(旧生化学、栄養学)の講座に分かれ、また、それぞれが7つの研究分野に分かれています。細胞生物学は主として形態学的アプローチに重点をおき、また、生化学・分子生物学は分子の単離と解析的アプローチを中心としますが、遺伝子工学、発生工学などの実験手技は相当重なっておりますし、教室間の研究交流も進めています。個々の研究内容は研究室のホームページを参照してください。