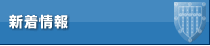広報・プレスリリース最新情報
血液を使ったがん遺伝子パネル検査の成功確率の予測モデル
~ より副作用の少ない治療をより多くの患者さんに届けるために ~
東京大学大学院医学系研究科の鹿毛秀宣教授と、同大学医学部附属病院の生島弘彬助教らによる研究グループは、日本全国の膵がん患者さんの臨床情報・がん遺伝子情報を用い、がん遺伝子パネル検査を受けた2,220名の膵がん患者さんの臨床情報から、膵がんのがん細胞から血中に漏れ出てくるがん遺伝子を血液検査で検出できる確率を個別に推定する機械学習モデルを開発し、Webアプリケーションとして実装・公開しました(URL:https://pancreasliquidcgp.streamlit.app/)。本モデルを活用することで、より効果的に遺伝子パネル検査を実施できるようになり、より副作用の少ない個人個人に最適な膵がん治療を患者さんに提供できる機会が増えることが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2026/2/13)
薬になりにくい―天然物創薬の限界を突破する合成法確立
~ 赤痢アメーバ症はじめさまざまな疾患治療薬への展開に期待 ~
名古屋大学大学院生命農学研究科の恒松 雄太 准教授らは、国立健康危機管理研究機構、静岡県立大学、東京大学、名古屋工業大学との共同研究により、微生物を利用した新しい創薬手法「ケム・バイオハイブリッド合成」を確立し、赤痢アメーバ症に対する有望な治療薬候補の創出に成功しました。
赤痢アメーバ症は、発展途上国を中心に多くの患者が報告されている原虫感染症であり、重症化すると命に関わることもあります。有効な治療薬はいくつか知られているものの、副作用や薬剤耐性といった課題が指摘されてきました。本研究グループは、赤痢アメーバに対して非常に高い活性を示す天然物「オバリシン」に着目しました。しかし、この化合物は体内で速やかに分解されてしまうため、薬として使うことが難しいという問題がありました。そこで研究グループは、微生物のオバリシン生合成機構を解明したうえで設計し直し、化学的に改変しやすい非天然型の天然物を微生物に大量に作らせるという新しいアプローチを採用しました。
さらに、得られた化合物に対して必要な部分だけを化学的に修飾することで、「よく効き、分解されにくく、安全性の高い」化合物の開発を進めました。その結果、YOK24およびNS-181という2種の化合物が、ハムスターへの皮下注射および経口投与の両方で高い治療効果を示し、病変を消失させることを確認しました。
本研究は、これまで「効くが薬にならない」とされてきた天然物を、治療薬として実際に使える形へと作り替える新しい創薬の考え方を示すものです。今回確立した手法は、赤痢アメーバ症にとどまらず、さまざまな感染症や難治性疾患に対する新薬開発へと応用できることが期待されます。
本研究成果は、2026年2月3日付米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2026/2/13)
選ばれた接続を強く育てる脳の仕組みを解明
~ 小脳神経回路形成におけるmGluR1シグナルの意外な二役 ~
北海道大学大学院医学研究院の山崎美和子准教授、帝京大学先端総合研究機構の狩野方伸特任教授(東京大学大学院医学系研究科名誉教授)らを中心とする、北海道大学、帝京大学、東京大学、広島大学の研究グループは、運動学習や認知機能・社会性を担う小脳の神経回路形成過程において、重要な神経接続を強化する仕組みを明らかにしました。
生まれた直後のマウスのプルキンエ細胞は、5本以上の登上線維とシナプスを形成していますが、その後の1週間で1本の線維が選ばれて「勝者」となり、これ以外の線維(敗者)は最終的に除去されます。これまでの研究では、この「勝者」が強化され、樹状突起の広い範囲へ支配を拡大する仕組みについてよく分かっていませんでした。
本研究では、マウスを用いた実験により、プルキンエ細胞に豊富に発現する1型代謝型グルタミン酸受容体(mGluR1)―プロテインキナーゼCγ(PKCγ)に至る伝達経路が、「勝者」のシナプス機能と構造を強化し、樹状突起へと配線を広げるために必須であることを解明しました。これまでに、このシグナル伝達経路は、不要な神経結合(敗者)を除去するために必須であることが分かっていましたが、本研究により、必要な結合を強く育て上げ、勝者と敗者の格差を増強する役割も併せ持つことが初めて明らかになりました。
なお、本研究成果は2026年1月23日(金)公開のProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America誌にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2026/1/29)
国際バイオバンク横断解析でゲノムと環境の相互作用を解明
~ 相互作用のメカニズム解明・個別化医療・創薬に貢献 ~
東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学の難波真一助教、岡田随象教授(兼:大阪大学ワクチン開発拠点先端モダリティ・DDS研究センター教授、大阪大学大学院医学系研究科遺伝統計学 教授(研究当時)、理化学研究所生命医科学研究センター チームディレクター)、東京大学医科学研究所 附属ヒトゲノム解析センター シークエンス技術開発分野の松田浩一特任教授(兼:同大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻クリニカルシークエンス分野 教授)、愛知県がんセンター研究所がん予防研究分野の小柳友理子主任研究員、松尾恵太郎分野長、国立がん研究センターがん対策研究所の山地太樹室長、岩崎基部長、澤田典絵部長らによる研究グループは、日本人集団および欧米人集団440,210人を用いて、ゲノム全体に存在する数百万箇所の遺伝子多型に対して遺伝子–環境交互作用(G×E)を網羅的に調べました。その結果、ヒト疾患形質の個人差に関連する94個のG×E効果を同定し、多様な集団からなる539,794人を用いてG×E効果の再現性および集団間での共通性を評価しました。
個々のG×E効果を調べることで、従来のゲノムワイド関連解析(GWAS)では見逃されてきた遺伝的効果が明らかになりました。また、疾患による食生活の変化がG×E効果をもたらすという予期しない例がみられ、G×E効果は注意深く解釈する必要があることがわかりました。ゲノム全体のG×E効果はヒト疾患形質の個人差の一部を形作っており、G×Eを考慮することでヒト疾患形質の予測精度が改善しました。さらに、G×E効果は遺伝的効果の変動に潜む生物学的メカニズムを捉えていました。最後に、代謝物(メタボローム)に対するG×E解析を実施し、脂質代謝において遺伝的効果の正負が男女で異なる例を複数同定しました。
本成果は、ゲノムと環境の相互作用がヒトの個人差の形成に関わることを示すものであり、疾患の分子メカニズム理解やゲノム個別化医療・創薬につながると期待されます。
本研究は2026年1月28日午前11時(米国東部標準時)に国際科学誌Natureに掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2026/1/29)
血管新生を促す「超大型細胞外小胞」の分泌機構を解明
~ PI3K—Rab18-GDPシグナルによる新たな細胞間情報伝達機構 ~
東京大学大学院医学系研究科の田中庸介講師らの研究グループは、血管新生因子ソニックヘッジホッグ(SHH)を高濃度に含む直径600 nm超の超大型細胞外小胞(XLEVs)が、PI3K—Rab18-GDPシグナル経路によって選択的に形成・分泌される分子機構を解明しました。SHHを含むXLEVsは血管内皮細胞に強い血管新生の促進作用を示し、従来知られていなかった細胞間情報伝達様式として、再生医療や血管再生治療への応用が期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2026/1/28)
高校生はコロナ禍で抑うつになりにくくなっていた?
~ 心の変化を“地形図”で可視化、集団傾向を数理的に解析 ~
名古屋大学大学院理学研究科の岩見真吾 教授・立松大機 日本学術振興会特別研究員DC1(受入機関:名古屋大学)の研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の小池進介 教授(兼:東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者)らとの共同研究により、東京ティーンコホートの参加者84人の高校生を対象に毎月行われた抑うつに関するWEBアンケートのうち、コロナ禍前およびコロナ禍中のデータを、エネルギー地形解析を用いて解析しました。その結果、先行研究と同様、本コホートの高校生集団全体としてコロナ禍において抑うつになりにくい傾向があったことを示しました。また、層別化解析により、抑うつスコアが「低く安定なグループ」と「高く不安定なグループ」の存在を見出しました。エネルギー地形図上でシミュレーションを行った結果、コロナ禍中において、安定グループでは抑うつ状態への遷移が起こりにくく、他方、不安定グループでは健康な状態に戻りやすくなり、結果として全体の抑うつスコア平均が減少することを確認しました。さらに、アンケート調査参加者が約2年ごとに受けた頭部MRI検査の解析からは、中前頭回の尾側と側頭極の皮質厚の成長過程がグループ間で異なり、この脳構造の成長過程の違いが抑うつの感受性に関与している可能性も示唆しました。
本研究では、気分や意欲、不安など相互に関連するアンケートデータに内在する相関構造や状態遷移に着目し、物理学・神経科学・生態学などで用いられてきたエネルギー地形解析を精神医学領域に応用することで、心的状態の変化を直感的に読み解く新たな可能性を示しました。さらに、抑うつが感染症対策によってどのような影響を受けたのかを明らかにしました。これまでの心理学、精神医学のアプローチでは見えなかった心的状態について、WEBアンケートによる毎月のデータ取得および数理解析によって、新たな視点を付与することができました。将来的には、パンデミックや大災害のような大規模な社会変化が生じた際に、精神状態への影響を早期に予測し、支援を要する人々を適切に選別できることが期待されます。
本研究成果は、2026年1月23日午前4時(日本時間)付で国際学術雑誌『PLOS Medicine』に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2026/1/25)
思春期に孤独感が持続すると精神症・抑うつ・不安・幸福度低下につながることを確認
~ 孤独感が改善すれば影響が軽減される可能性 ~
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所行動医学研究部 成田瑞 室長、キングス・カレッジ・ロンドンGemma Knowles講師、東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター 西田淳志センター長、東京大学大学院医学系研究科 笠井清登 教授(同大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)らの国際的な研究グループは、思春期において孤独感が持続すると、精神症(幻覚や妄想のような体験)、抑うつ、不安、幸福度の低下といったメンタルヘルス不調につながることを確認しました。一方で、孤独感が途中で改善した場合には、これらのメンタルヘルス不調との関連が軽減されることも示されました。
本研究では、厳密なデータ解析手法を用いて、思春期における孤独感の「時間的な変化」と、その後のメンタルヘルスとの関連を検証しました。人とのつながりが大きく変化する思春期において、本研究の知見は、孤独感への早期の気づきや支援の重要性を示すものと考えられます。
本研究成果は、国際学術誌『Journal of Child Psychology and Psychiatry』に日本時間2026年1月22日18時(英国時間:1月22日9時)にオンライン掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2026/1/22)
肺拡散能が慢性血栓塞栓性肺高血圧症の治療効果と予後に関連
~ 治療反応性と予後を予測する新たな指標 ~
東京大学医学部附属病院の皆月隼特任助教と波多野将准教授(研究当時)らによる研究グループは、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)において、肺の拡散能(DLco)が治療効果および予後を規定する重要な指標であることを明らかにしました。本研究成果は、英国時間1月7日(日本時間1月8日)に国際呼吸器学分野の主要学術誌Thorax誌に掲載されました。
本成果は、患者ごとの病態に応じた治療戦略の立案や、治療後のフォローアップ強化の判断に役立つことが期待されます。また、今後は微小血管障害そのものを標的とした新たな治療法の開発や、CTEPH研究のさらなる発展につながることが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2026/1/8)
“治療抵抗性”とされてきたBRCA野生型卵巣がんに 有効な治療標的を発見
~ PLK1/WEE1阻害によりDNA修復の弱点を狙い撃ち ~
東京大学医学部附属病院の織田克利教授、国田朱子特任講師、同大学院医学系研究科のQian Xi(シー チェン)大学院生(研究当時)らによる研究グループは、BRCA1/2野生型高異型度漿液性卵巣がん(以下BRCA野生型卵巣がん)に対して、PLK1またはWEE1阻害が有効であることを明らかにしました。
本研究では細胞周期のG2/M期チェックポイントを担う酵素であるPLK1やWEE1を阻害すると、BRCA野生型卵巣がん(HRP:相同組換え修復正常)では主要な二本鎖DNA修復機構である相同組換え修復(HR)が抑制され、DNA損傷が蓄積して細胞死が誘導されることを明らかにしました。一方、BRCA変異型卵巣がん(HRD:相同組換え修復欠損)では、非相同末端結合(NHEJ)という別の修復経路が強く働くため、PLK1/WEE1阻害に耐性を示しました。
さらに、患者由来腫瘍(PDX)モデルにおいても、PLK1とWEE1の両阻害薬がHRP腫瘍に選択的に抗腫瘍効果を示しました。本研究はこれまで「薬剤抵抗性の指標」とされてきたHRPを、治療感受性を示すバイオマーカーとして活用できる可能性を示しました。本成果は、BRCA野生型卵巣がんに対する新たな治療戦略として期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/12/25)
がん組織のみを用いたがん遺伝子パネル検査の結果から遺伝性腫瘍に関わる生殖細胞系列バリアントを高精度に予測する機械学習モデル・ノモグラムを開発、Webアプリとして公開
~ 日本人大規模データベース(C-CAT)を活用し、国際ガイドラインを上回る精度を実現 ~
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所 細胞情報学分野 池上政周主任研究員、高阪真路分野長、間野博行特別研究員らは、国立がん研究センター中央病院 遺伝子診療部門 平田真部門長、東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎外科 張劉喆助教、小林寛講師、東京都立駒込病院 遺伝子診療科 山口達郎部長、骨軟部腫瘍科 平井利英医長、九州がんセンター臨床研究センター腫瘍遺伝学研究室 織田信弥室長と協力し、がん遺伝子パネル検査のデータを用いて、遺伝性腫瘍症候群の原因となる「生殖細胞系列バリアント(生まれつきの遺伝子の変化)」を高精度に予測する数理モデルおよびAIモデルを開発し、2025年11月にWebアプリケーションとして公開しました(https://www.felis-portal.com/U3Nomogram)。
標準治療が終了したがん患者さんに、がん細胞がもつ遺伝子バリアントに対応する有効性の高い治療法がないかを探索するため、がん遺伝子パネル検査が年間25,000例に対して実施されています。その約8割で実施されている「がん組織のみ」を用いたがん遺伝子パネル検査(Tumor-onlyパネル)では、見つかった遺伝子バリアントが「がんの原因となった生まれつきのバリアント」なのか、それとも「がん細胞の中で後天的に生じたバリアント(体細胞バリアント)」なのかを区別できない場合があり、真に遺伝学的検査や遺伝カウンセリングを必要とする患者さんを事前に判断することが難しいという課題があります。本研究では、国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に登録された日本人の大規模ながん遺伝子パネル検査のデータを解析し、腫瘍の純度とバリアントのアレル頻度を組み合わせた新しい指標を導入することで、日本人の患者さんに最適化された生殖細胞系列バリアントの予測モデル「U3-Nomogram」を構築しました。このモデルは、既存の欧州臨床腫瘍学会(ESMO)の規準(以下、「ESMO規準」)よりも正確に遺伝性腫瘍の可能性を判定できることが確認されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/12/18)
生殖補助医療データを用いて孵化補助の有効性を評価
~ 年齢や胚の状態に応じた実施判断の重要性を示す ~
孵化補助(Assisted Hatching:AH)は、胚の外側にある透明帯の一部を薄くしたり穴を開けたりして、胚が外へ出やすくなるようにする技術です。加齢や体外培養、凍結融解の過程で透明帯が硬くなると考えられており、妊娠成績の改善を目的に長年多くの施設で行われ、2022年には保険診療の対象にもなりました。しかし、AHの有効性や適応については明確な結論がなく、施設や医師により判断が分かれていました。
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座の原田美由紀教授と、同大学医学部附属病院女性外科の草本朱里助教らによる研究グループは、日本におけるAHの実施状況、有効性の評価、そして治療成績に影響を与える因子の抽出を行い、AHの実施判断と適応について検討しました。その結果、すべての患者に対して一律にAHを行うことは推奨できず、患者や胚の状態によって効果が異なることが明らかになりました。
本研究は、今後のAHの適応を検討する上で重要なデータとなります。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/12/11)
RNA転写のずれ(スリッページ)が筋ジストロフィーの原因であるジストロフィンタンパク質欠損を補う新たな仕組みを解明
この度、東京大学医学部附属病院脳神経内科の成瀬紘也助教、大学院医学系研究科神経内科学の戸田達史名誉教授(現・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院長)らの研究グループは、「転写スリッページ」と呼ばれるRNAの書き写し時の“ずれ”によって、変異により失われるはずの全長ジストロフィンが一部産生され、病気の重症度が変わる新しい仕組みを明らかにしました。
一般に、DMD遺伝子の変化によってジストロフィンタンパク質がほとんど作られない場合は重症のデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)に、一部残る場合には比較的症状が軽いベッカー型筋ジストロフィー(BMD)になると考えられています。本研究で解析した患者さんは、本来であればDMDを来すと予想される「読み枠のずれ(フレームシフト)」を伴う変化を持ちながら、全長ジストロフィンが約15%残存しており、症状もBMDに近い経過を示していました。
患者さんの筋肉からRNAを詳しく解析した結果、DMD遺伝子の特定部位に同じ塩基(アデニン)が並ぶ配列が生じており、この部分で転写スリッページが起こることで読み枠のずれが部分的に補正され、全長ジストロフィンが実際に産生されていることが確認されました。 この成果は、DNA配列だけを見ればDMDと判断されるような変化であっても、RNAの段階で起こる転写スリッページにより読み枠のずれが補正され、その結果症状が軽くなる場合があることを示すものです。ジストロフィン異常症の診断・病型評価において、遺伝子解析に加えてRNAレベルの解析を行う意義を裏付ける結果といえます。
本研究成果は、2025年11月19日(米国時間)に米国科学誌「Annals of Neurology」にてオンライン版に先行掲載されました。
※詳細は東大病院HPをご覧ください。
(2025/11/28)
重症心不全患者の予後予測が可能に!?
~ 心臓プロテオーム解析による心不全予後予測タンパク質の同定 ~
東京大学大学院医学系研究科先端循環器医科学講座の野村征太郎特任准教授、同研究科システムズ薬理学の大出晃士講師、日本医科大学統御機構診断病理学の堂本裕加子准教授(2020年3月まで:東京大学大学院医学系研究科人体病理学)らによる研究グループは、重症心不全患者の心臓をプロテオーム解析し、左室補助人工心臓(LVAD)を装着した後に心臓機能が回復するかどうかを予測する因子を明らかにしました。さらにLVAD装着後に生じる心臓の状態変化に関わる因子を見出しました。
具体的には、LVAD装着後に心臓機能が回復する心不全患者さんの心臓では、ミトコンドリアタンパク質(中でもIDH2タンパク質)の量が多く、細胞外基質タンパク質(中でもPOSTNタンパク質)の量が少ない、という特徴があることがわかりました。さらに、IDH2およびPOSTNの量をLVAD装着時に調べることによって、その患者さんの心臓機能が回復するかどうかを事前に予測できることがわかりました。またLVAD装着後には、ミトコンドリアタンパク質は減少し、解糖系タンパク質は増加することがわかり、LVAD装着に伴って心臓の代謝がミトコンドリア代謝から解糖系にシフトすることが示唆されました。
本研究の成果により、LVADを装着する重症心不全患者において、心機能が回復する可能性を事前に予測できると期待され、プレシジョン・メディシンの発展に寄与する可能性が示されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/11/25)
人工透析下の腎臓がんの前がん病変および発症機構を解明
国立研究開発法人国立がん研究センター(東京都中央区、理事長:間野 博行)研究所(所長:間野博行)細胞情報学分野の田中 庸介研究員、高橋 潤任意研修生、間野 博行特別研究員らは東京大学医学部附属病院泌尿器科・男性科(久米 春喜教授)との協力体制のもと、人工透析(血液透析)患者さんに特有に発症する腎臓がんの分子メカニズムを明らかにしました。一般に、慢性腎臓病が進行して末期腎不全に至ると人工透析療法が必要となりますが、長期の透析により腎臓には多発性の嚢胞(後天性嚢胞腎:ACKD)が形成され、その後の腎臓がん発症リスクが一般人口の15倍に上昇することが知られています。
本研究では、空間的マルチオミックス解析により、後天性嚢胞腎およびそこから発生する腎臓がんが、腎臓の構成要素である近位尿細管細胞を起源としていることを明らかにしました。特に、長期透析により腎臓の多くの組織が傷害・萎縮していく一方で、一部の近位尿細管が周囲微小環境から分泌されるHGF(hepatocyte growth factor:肝細胞増殖因子)によってMETチロシンキナーゼを活性化し、さらに遺伝子変異の蓄積を伴いながらクローン性に増殖することで嚢胞化し、最終的に腎臓がんへと進展する過程を解明しました。また、発症した透析特有の腎臓がんは、一般的な腎臓がんと比べて遺伝子異常などの分子プロファイルが大きく異なることが分かり、透析腎特有の発がん経路が示唆されました。本研究で明らかになった発がん機構を基盤として、今後は透析患者さんにおける腎臓がん発症リスクの層別化や、新しい診断・治療戦略の開発が期待され、長期透析患者さんの予後改善に向けた新たな一歩となることが見込まれます。本研究成果は、米国時間2025年11月20日(日本時間11月21日)付で、国際学術誌「Cancer Discovery」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/11/21)
長期的な暑熱適応の効果を見込んでも気候変動と超高齢社会により21世紀半ばに向けて熱中症死亡者数が増加する
国立環境研究所および東京大学からなる研究チーム(以下「当研究チーム」という。)は、今後、数十年にわたる長期的な暑熱適応の効果を考慮して、熱中症死亡者数を予測することが可能な手法を開発し、気候変動および人口動態も考慮した上で、47都道府県の将来予測に取り組みました。
その結果、熱中症死亡数は、暑熱適応を考慮したとしても、基準期間(1995年から2014年)と比べて21世紀半ば(2031年から2050年)に1.6倍に増加することを明らかにしました。気候変動や超高齢社会の進行により、熱中症死亡数は21世紀半ばに向けて増加すると予測され、さらなる熱中症対策の必要性が示唆されました。
本研究の成果は、2025年10月15日付けでエルゼビア社から刊行された国際学術誌『Environmental Research』に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/11/17)
医療の区分化における難病当事者の抱える困難
~ 22q11.2欠失症候群にともなう重複障害の医療人類学的分析 ~
東京大学医学部附属病院の笠井清登教授(東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)、熊倉陽介助教、東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎教授、慶應義塾大学文学部の北中淳子教授、ミシガン大学医学部内科学部門・人類学部のスコット・ストニングトン准教授の国際共同研究グループは、先天性心疾患、知的障害、精神症状などが重なる難病「22q11.2欠失症候群」をもつ子どもと家族の心理社会的困難を質的に分析しました。
その結果、臓器ごとに縦割りで提供される医療サービスと、重複障害をもつ当事者のニーズとの間に見えにくいミスマッチが生じることを明らかにし、新たに「医療の区分化(medical compartmentalization)」という概念を提唱しました。従来は、疾患や障害ごとのサービスを積み重ねれば包括的支援になると考えられてきましたが、実際にはどの制度にも適切に当てはまらず、心理社会的困難を招くことが示されました。
本研究は、複雑な障害に対応するために医療サービスの構造や医療者教育の変革が必要であることを示し、難病支援にとどまらず、誰一人取り残さないインクルーシブな医療の実現に向けたユニバーサルデザインの重要性を訴えています。
本研究成果は、2025 年11月13日(英国時間)に国際医学雑誌『The Lancet』のオンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/11/14)
脳全体の活動リズムを3次元で可視化
~ マウス脳のさまざまな領域の朝・昼・夜の活動パターンを明らかに ~
東京大学大学院医学系研究科の上田 泰己 教授(久留米大学 特別招聘教授 兼任)、山下 勝成 特別研究学生(大阪大学大学院医学系研究科 博士課程)、木下 福章 特任研究員、久留米大学 分子生命科学研究所 山田 陸裕 准教授らの研究グループは、マウス脳のさまざまな領域の神経活動が1日の中でリズムを示すことを明らかにしました。
本研究では、組織透明化技術「CUBIC」を用いて、時系列的に採取したマウス脳全体の神経活動を観察することで、脳の約8割の領域で一日周期の活動リズムが見られることを世界で初めて明らかにしました。従来の研究が限られた脳領域にとどまっていたのに対し、本研究では、高精度な時系列解析により脳全体を網羅的に評価し、その結果を全脳データベースとしてWeb上に公開しました。この成果は、脳の活動を時間軸から理解するための新たな基盤となり、今後、睡眠・記憶・薬効などの時間依存的な脳機能研究の発展や医療応用への貢献が期待されます。
本研究成果は、2025年11月13日(米国東部時間)に米国学術誌「Science」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/11/14)
肺がん診療における超高感度リキッドバイオプシーの有用性を確認
~ 英国TRACERx試験の解析結果から ~
英国UCLがん研究所およびフランシス・クリック研究所のJames Black研究員、Charles Swanton教授と、東京大学医学部附属病院呼吸器外科の唐﨑隆弘 助教らによる研究グループは、肺がんの術後再発リスク予測における高感度リキッドバイオプシーの有用性を明らかにしました。
研究チームは、英国で実施されているTRACERx臨床試験に参加した431人の非小細胞肺がん患者から得られたデータを解析しました。本研究では、現在多くの臨床試験で利用されている「第一世代」と呼ばれるアッセイではなく、さらに微量の血液中の腫瘍由来のDNA(循環腫瘍DNA:ctDNA)まで検出することが可能な「第二世代」と呼ばれる最新のアッセイを利用しました。その結果、第一世代では検出困難な微量のctDNAが検出された場合でも、肺がんが再発するリスクが高いことが確認されました。また、術後のctDNAの検出量や増え方と、肺がんの再発するタイミングや部位についての関連性を明らかにしました。
これらの研究成果によって、肺がんの手術後、再発リスクに応じて、これまで以上に適切な治療を提供し、より多くの肺がん患者さんの治療成績が改善することが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/11/10)
肝切除後の重篤な合併症「胆汁漏」を効果的に防ぐ合成ハイドロゲルシーリング剤を開発
~ 瞬時に固まり止血、時間とともに組織へ強固に接着 ~
東京大学大学院工学系研究科の石川 昇平 助教、酒井 崇匡 教授らの研究グループは、医学部附属病院血管外科の保科 克行 病院教授、大学院医学系研究科の松原 和英 大学院生(研究当時)らと共同で、肝切除後に生じる重篤な合併症「胆汁漏」を効果的に防止する新しい合成ハイドロゲルシーリング剤を開発しました。胆汁漏は、手術関連死につながることもある深刻な合併症です。既存の生体材料由来のシーリング剤や合成接着剤では十分な防止効果が得られず、新しい材料の開発が求められていました。本研究グループが開発したシーリング剤では、ポリエチレングリコール(PEG)を基材とし、独自の「時間差二段階反応」を採用しています。第一段階で瞬時にゲル化し出血や胆汁漏出を物理的に遮断した後、遅れて進行する第二段階の反応によりゲルと生体組織表面とを化学的に結合させることで、強固で長時間安定した接着を実現しました。ラット肝切除モデルを用いた実験では、本ハイドロゲルが1分以内に止血を達成し、既存のシーリング剤では防げなかった胆汁漏を効率的に防止することに成功しました。さらに、生体内での安全性評価でも術後炎症や肝障害はほとんど認められませんでした。これらの成果は、今後の臨床試験を経て、肝切除や移植手術などにおける胆汁漏防止剤として実用化される可能性を示しています。
本研究成果は、2025年11月3日(西ヨーロッパ時間)に「Advanced Healthcare Materials」のオンライン版で公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/11/4)
細胞の“運び屋”に新たなルール
~ 脳の働きや病気の理解につながるタンパク質輸送の仕組み ~
東京大学大学院医学系研究科教授吉川雅英博士、同東京大学特別研究員蒋緒光博士、同東京大学名誉教授/順天堂大学大学院医学研究科特任教授廣川信隆博士、群馬大学大学院医学系研究科助教一ノ瀬聡太郎博士らによる研究グループは、細胞の“運び屋”として働くモータータンパク質キネシン‐2が、どのように荷物を認識して運ぶのか、その仕組みを世界で初めて明らかにしました。
研究グループは、クライオ電子顕微鏡やライブセルイメージングなどの最先端技術を組み合わせることで、キネシン‐2の尾部に存在する新しいフック状の“部品”(HACドメイン)を発見し、その立体構造を原子レベルで解明しました。この部品はアダプターや荷物との結合の足場として働き、正確な輸送を可能にしていることがわかりました。
今回の成果は、モータータンパク質全体に共通する基本原理の理解につながるとともに、神経発達障害や繊毛病など細胞内輸送の不具合が関わる病気の分子基盤解明や治療法開発に役立つことが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/10/27)
がん免疫療法の治療効果の鍵を握るT細胞増殖を予測する遺伝子群を発
~ 腫瘍内でのT細胞応答の理解と新たな治療法開発へ重要な知見 ~
がん免疫療法を実施する際、T細胞が腫瘍内で急速に増殖する強力な免疫応答が起こるかどうかが成功の鍵を握ることが知られていましたが、その免疫応答がどのように制御されているかはわかっていませんでした。
東京理科大学 生命医科学研究所 炎症・免疫難病制御部門の上羽 悟史准教授、松島 綱治教授、東京大学大学院医学系研究科の石川 俊平教授らの国際共同研究グループは、T細胞が腫瘍内で増殖、または停滞を決定する遺伝子群を同定することに成功しました。
研究チームは、腫瘍内でのCD8+ T細胞の応答を継続的に追跡する革新的な手法を開発し、T細胞の増殖を予測する特定の遺伝子群「増殖シグネチャー」を発見しました。この遺伝子群の活性化を評価することで、マウスモデルとヒト患者データの両方において免疫治療後の腫瘍内でのT細胞増殖を高精度に予測できることを実証しました。
この発見は、免疫療法の効果をリアルタイムで追跡できる可能性を示唆しています。将来的にはこの「増殖シグネチャー」を標的として、T細胞増殖を促進する新しい治療法の開発が可能になると期待されます。
本研究を主導した上羽准教授は「免疫療法の成功と失敗をリアルタイムで動的に理解する新たな扉が開かれました。増殖シグネチャーは治療応答の予測因子としてだけでなく、免疫システムが衰退し始めた際に再活性化する新しい治療法設計の指針としても活用できると期待しています。今回得られた知見をベースにさらに研究を発展させることで、真に個別化された免疫療法の実現に近づくことができるでしょう」とコメントしています。
本研究成果は、2025年10月20日に国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/10/21)
心理的苦痛とメンタルヘルス医療の利用の10年の動向を解明
~ パンデミック前後で日本人のメンタルヘルスが二極化? ~
東京大学大学院医学系研究科の佐々木那津講師と、西大輔教授らによる研究グループは、全国の大規模データを解析し、日本人のメンタルヘルスと医療の利用について過去10年の変化を明らかにしました。
本研究では厚生労働省「国民生活基礎調査」の、延べ約176万人データを用いて、日本人成人の心理的苦痛およびメンタルヘルス医療の利用の変化を明らかにしました。その結果、パンデミックを境に、中等度の心理的苦痛は減少する一方、重度の心理的苦痛が同期間に上昇していることが明らかになりました。特に若年女性や中年男性で重度の心理的苦痛の増加がみられました。メンタルヘルス医療の利用は、この10年で増加していることが示されました。日本の代表的な大規模データを用いてパンデミック前後でのメンタルヘルスの変化を明らかにした初めての研究であり、この研究成果は今後のメンタルヘルス政策に役立てられることが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/10/21)
アルツハイマー病治療薬実用化1年
~ 全国専門医調査で明らかになった医療現場の課題と今後の検討点 ~
アルツハイマー病に対する疾患修飾薬としてレカネマブ、ドナネマブといった新薬(抗アミロイド抗体薬)が登場し、2023年12月からレカネマブは国内で臨床実用されています。抗アミロイド抗体薬の安全・適正な使用のためには多くの事前検査を行なった上で、投与にあたって各種要件を満たした施設・医師によって投与されることが重要です。しかしそのような条件を満たす施設・医師、また治療枠の数は必ずしも十分ではないため、各医療機関で必要な患者さんへ検査や治療が十分に提供できない可能性、また地域ごとの格差がある可能性なども懸念されていました。
今回、東京大学大学院医学系研究科認知症共生社会創成治療学・岩坪威特任教授、筑波大学附属病院・新井哲明教授らのグループは、厚生労働省の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「認知症医療の進展に伴う社会的課題への対応のための研究」(代表:新井哲明)」の一環として、抗アミロイド抗体薬を処方可能な認知症関連の専門医を対象に2024年12月~2025年1月にウェブアンケート調査を実施し、新薬診療の最初の1年間の実態(使用状況、副作用の出現状況など)、また治療上の課題などについて調査を行いました。本研究によって今後のアルツハイマー病新薬治療のより安全・適正・持続可能な提供への施策のための基礎的資料となることが期待できます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/10/21)
森林・泥炭地火災から発生する煙霧による健康リスク:火災の近隣地域では?
~ 森林・泥炭火災煙霧の発生地域と風下地域における影響の違い ~
東京大学大学院医学系研究科のPHUNG Vera Ling Hui(プン ヴェラリンフイ)助教と、北海道大学大学院医学研究院 上田 佳代 教授、同大学北極域研究センター 川崎 昌博 研究員、鹿児島大学大学院理工学研究科 大橋 勝文 教授、京都大学大学院農学研究科 内藤 大輔 助教らによる研究グループは、インドネシア・中央カリマンタン州のパランカラヤ大学との共同研究から、同地域で森林・泥炭地火災から発生する煙霧が呼吸器疾患を増やすことを示しました。また、発生源に近い地域では、煙霧による健康リスクが大きくなる可能性を示しました。
東南アジアで発生する煙霧は、地域の大気汚染物質だけでなく、周辺地域で発生する火災由来の煙が原因となります。本研究では、粒子径が10μm以下の粒子状物質(PM10)と衛星画像による火災(ホットスポット)を用いることにより、煙霧の種類を火災由来、非火災由来に分けた分析を行いました。火災の近隣地域では、火災由来の煙霧の健康影響が大きいことが明らかになりました。本研究は、インドネシアを含む東南アジア地域において、火災の発生地域や煙霧の種類・継続期間を考慮した曝露評価を行った点で新規性があり、これまでの研究にはない知見を提供しました。この成果は気候変動に伴い増える可能性のある日本を含む世界各地の森林火災による煙霧発生時の公衆衛生対策の強化や優先順位付けにも貢献することが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/10/20)
地域・時期に応じた「熱中症警戒アラート」発表基準
~ 熱中症死者数の半減に向けて ~
東京大学大学院医学系研究科のPhung Vera Ling Hui(プン ヴェラリンフイ)助教、橋爪真弘教授らの研究チームは、国立環境研究所、長崎大学などと共同で、政府が掲げる「2030年までに熱中症による死亡を半減する」という目標に向け、効果的な熱中症警戒アラートの発表基準について検討しました。
日本では2021年に熱中症警戒アラートが全国で導入され、暑さ指数(WBGT)が33以上と予測される場合に発表されています。しかし、南北に広がる日本では、地域によって気候が大きく異なり、全国一律の基準で十分に対応できているのか検証することが課題となっていました。
本研究では、全国47都道府県の熱中症死亡データを分析し、都道府県ごとにWBGTと熱中症死亡数との関連を検討しました。その結果、地域や時期に応じて基準を設定することで、より熱中症死亡を防げる可能性が示されました。本成果は、Environment & Healthに掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/10/16)
思春期女子のメンタルヘルス悪化と拡大する性差
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 行動医学研究部 成田瑞 室長、キングス・カレッジ・ロンドン Gemma Knowles 講師、東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター 西田淳志 センター長・山﨑修道 副参事研究員、東京大学大学院医学系研究科 笠井清登 教授(東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)らの研究グループは、近年、思春期女子のメンタルヘルスが悪化し、男子との差(メンタルヘルス・ジェンダーギャップ)が拡大している現状を指摘しました。特に日本においては、2024年に20歳未満の女子の自殺者数が男子を初めて上回った深刻な統計を踏まえて、社会的対応の必要性を強く訴えます。
本研究成果は、国際医学雑誌『Nature Human Behaviour』に日本時間2025年9月30日18時(英国時間:9月30日10時)にオンライン掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/10/1)
高齢化と気候変動が救急医療体制に及ぼす将来的影響を日本で初めて統合的に予測・評価
~ 長崎大学・東京大学・国立環境研究所の共同研究により、日本全国を対象に2099年までの救急搬送需要を推計 ~
長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科のマダニヤズ・リナ准教授を中心とする研究チームは、東京大学および国立環境研究所との共同研究により、日本における高齢化と気候変動が救急医療体制に及ぼす影響を日本で初めて統合的に予測・評価しました。
本研究では、日本全国の65歳以上の高齢者を対象に、救急搬送件数の将来の動向と季節性の変化を、人口動態および気候変動の影響を考慮して2099年まで予測を行いました。予測にあたっては、消防庁、気象庁、総務省統計局などの公的データに加え、複数の将来人口および気候シナリオを用いて、都道府県別・季節別に評価しました。気候シナリオについては、産業革命前と比べて今世紀中に気温が約2~5℃上昇する4つの将来気候シナリオ(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5)を用いました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/9/12)
線維芽細胞が心不全を引き起こす?
~ 非心筋細胞の意外な役割と新たな治療標的の発見 ~
岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)循環器内科学の湯浅慎介教授、東京大学大学院医学系研究科先端循環器医科学講座の小室仁日本学術振興会特別研究員、慶應義塾大学医学部内科学教室(循環器)の家田真樹教授および国際医療福祉大学の小室一成教授らは、 心不全の進行に“心臓の線維芽細胞”が深く関与する新たな仕組みを明らかにしました。
研究チームは、心不全モデルマウスを用いた解析により、これまで「構造を支持しているだけの細胞」と考えられていた線維芽細胞が、c-MYCというタンパク質を介してCXCL1という分子を分泌し、心筋細胞のCXCR2という受容体を介して心不全を増悪させることを発見しました。さらに、このc-MYC-CXCL1-CXCR2経路の働きをブロックすることで心不全の悪化を防げることも示され、心不全の新たな原因解明とともに、非心筋細胞を標的とする新しい治療法の可能性が示唆されました。本研究成果は基礎研究段階ですが、ヒト心不全患者でも同様のメカニズムが確認されており、今後の臨床応用が期待されます。
本成果は、2025年9月10日、国際学術誌「Nature Cardiovascular Research」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/9/11)
脆弱X症候群のマーモセットモデル開発に成功
~ 疾患メカニズム解明と創薬に貢献 ~
東京大学大学院医学系研究科の饗場篤教授と、ハーベスまりあ大学院生(研究当時)らによる研究グループは、FMR1遺伝子に変異を導入したマーモセットが脆弱X症候群の非ヒト霊長類モデルとして有用であることを明らかにしました。
脆弱X症候群は、精神遅滞や発達障害を伴う遺伝性疾患です。X染色体上のFMR1遺伝子に変異が起こり、その働きが失われることが発症の原因と考えられています。これまで脆弱X症候群のモデル動物として、Fmr1遺伝子を欠損したマウスやラットが広く使用されてきましたが、げっ歯類でヒトの症状を理解することには限界がありました。そこで本研究は、ヒトに近い行動様式を示す霊長類のコモンマーモセットで新たな脆弱X症候群のモデルを開発しました。FMR1遺伝子に変異を導入したマーモセットは患者と類似した表現型を示す有用なモデル動物であることが明らかとなりました。この脆弱X症候群の非ヒト霊長類モデルは疾患のメカニズムの解明や有効な治療法の開発に貢献することが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/9/5)
「子ども睡眠健診」プロジェクト・2026年度継続決定!
プロジェクト参加校(小・中・高)の第五次(2026年度)募集を開始
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学教室の上田泰己教授(久留米大学分子生命科学研究所教授)と岸哲史講師の共同研究チームは、全国の学校の子ども(小中高生)を対象として、ウエアラブルデバイスを用いた睡眠測定を実施し、日本の子どもの睡眠実態の把握と、子ども・保護者に対して睡眠衛生に関する理解を増進する「子ども睡眠健診」プロジェクトを推進しています。このたび、9月3日「秋の睡眠の日」に合わせて、2026年度もプロジェクトを継続することを決定し、参加校の第五次募集(2026年度募集)を開始します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/9/3)
全ゲノムシークエンス解析により乾癬の新規関連遺伝子を発見
~ 見逃されてきた希少変異と構造変異の関与を解明 ~
東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学の曽根原究人助教(研究当時、現:ウェルカム・サンガー研究所 Postdoctoral Fellow)、岡田随象教授(兼:大阪大学大学院医学系研究科 遺伝統計学 教授、理化学研究所生命医科学研究センター チームディレクター)、東京大学医科学研究所 附属ヒトゲノム解析センター シークエンス技術開発分野の松田浩一特任教授(兼:同大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻クリニカルシークエンス分野 教授)、東京科学大学大学院医歯学総合研究科免疫学分野の佐藤荘教授、名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学分野の森田明理教授らによる研究グループは、日本人乾癬患者と対照者の計5,383名の全ゲノムシークエンス解析により、これまで未解明だった希少変異および構造変異の疾患への関与を網羅的に解析しました。構造変異の解析では、IFNLR1遺伝子座の3.3kb欠失が乾癬発症リスクを有意に低下させることを発見しました。希少変異の解析では、CERCAM遺伝子を新たな乾癬関連遺伝子として発見しました。Cercam遺伝子欠損マウスを用いた実験では、乾癬モデルで皮膚炎症の増悪が観察されました。
本成果は、従来のゲノムワイド関連解析(GWAS)では見逃されてきた希少変異と構造変異が乾癬の発症に関与することを示すものであり、疾患の分子メカニズム理解や新規治療標的探索につながると期待されます。
本研究は2025年8月22日午前11時(米国東部夏時間)に国際科学誌Cell Genomicsに掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/8/29)
神経回路の発達:シナプス伝達は“勝者”の選別には不要だが配線の“精緻化”には不可欠
~ 発達障害や運動失調症などの理解・治療標的探索に新しい視点を提供 ~
帝京大学先端総合研究機構の狩野方伸特任教授(東京大学大学院医学系研究科 名誉教授)、東京大学大学院医学系研究科のKao Tzu-Huei研究員(研究当時)、帝京大学先端総合研究機構研究員の奥野優人研究員、東京大学大学院医学系研究科の上阪直史講師(研究当時、現東京科学大学医歯学総合研究科教授)らの研究グループは、小脳において、運動制御だけでなく社会性や認知機能を担うプルキンエ細胞にシナプス入力する登上線維が、発達の初期段階でどのように「勝ち残り」、その後どうやって不要な線維を取り除いて大人の神経回路を完成させるのかを明らかにしました。
生まれた直後のマウスのプルキンエ細胞は、5本以上の登上線維からシナプス結合を受けています。従来は、これらの複数の登上線維のうち、プルキンエ細胞に対して「強いシグナル(シナプス伝達)を送ることができる線維が“勝者”として勝ち残り、弱いシグナルしか送れない線維は“敗者”として排除される」と考えられてきました。この仮説を検証するため、本研究では一部の登上線維から神経伝達物質(グルタミン酸)の放出を遺伝学的に阻害して、プルキンエ細胞にシグナルを送ることができないようにした際、発達期の小脳の神経回路形成がどのように影響されるかを調べました。
その結果、シナプス伝達がなくても初期段階の“勝者”のselection(選抜)は起こり得ることを示しました。一方で、選抜された登上線維がプルキンエ細胞の樹状突起とシナプス結合する領域を拡大し、他の線維を排除して最終的な配線を仕上げるrefinement (精緻化)にはシナプス伝達が必須であり、これを阻害すると未熟な配線が長期にわたり残存することが確認されました。
この結果は、発達期の神経回路形成は、(1)シナプス伝達を必要としない「選抜」フェーズと、(2)シナプス伝達に依存する「精緻化」フェーズという二段階で進むことを示唆します。これは、発達障害や運動失調症など、神経回路の微細な異常が関わる疾患の理解・治療標的探索に新しい視点を提供します。すなわち、まずシナプス伝達とは関係なく勝ち残る神経線維が選ばれ、その後にシナプス伝達に依存するメカニズムによって配線を磨き上げるという「分業制」の存在を、実験的に裏づけた点に本研究の最大の意義があります。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/8/26)
運動タイミング学習中に小脳が大脳皮質運動野へ報酬に基づく誤差信号を伝達することを解明
東京大学大学院医学系研究科細胞分子生理学分野の赤穗吏映特任研究員と松崎政紀教授(兼:理化学研究所脳神経科学研究センター脳機能動態学連携研究チーム チームディレクター、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 教授)らによる研究グループは、報酬に基づく誤差情報が小脳から大脳皮質運動野へ伝えられ、学習中の運動タイミング修正に寄与することを明らかにしました。
本研究では、マウスにタイミングを計りながらレバーを引く運動課題を訓練させ、課題実行中の小脳から視床を介して高次運動野へ伝達される神経活動を光計測しました。学習段階では、十分待てずにレバーを引いて無報酬だった試行の直後の試行のタイミング合図音開始直後に、これらの神経活動が高い一過性活動を示すとともに、待ち時間が長くなり成功率が上昇しました。一方、学習後期ではこのような失敗試行後の高い活動は消失し、代わって運動開始に向けた急峻な活動上昇が見られました。本研究結果は、報酬誤差駆動型学習の神経基盤の理解および、リハビリテーションや神経疾患の治療への応用が期待されます。
本研究成果は、米国のSpringer Nature社(シュプリンガー・ネイチャー)が発行する学術雑誌『Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)』のオンライン版に 2025年8月18日 (英国夏時間) に公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/8/25)
子どもの食事を“測る”評価ツール
~ 8日間食事記録との比較により、BDHQ15yの妥当性を全国規模で初検証 ~
東京大学大学院医学系研究科栄養疫学・行動栄養学(社会連携講座)の大久保公美特任教授、田島諒子特任助教、社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏東京大学名誉教授らの研究グループは、小中高生の習慣的な栄養素・食品摂取量を簡便かつ定量的に評価するために開発された「簡易型食事歴法質問票: brief-type diet history questionnaire for Japanese children and adolescents (BDHQ15y)」の妥当性を全国規模で初めて検証しました。8日間の詳細な食事記録と比較した結果、BDHQ15yは主要な栄養素や食品群の摂取量を概ね正確に把握できることが示されました。一方、個人単位の詳細な評価には限界があることから、主に集団での活用が推奨されます。本研究は、これまで十分に検証されてこなかった幅広い年齢層での正確さを明らかにした点で新規性があります。今後は、学童・思春期の栄養状態の把握や食育・健康施策の評価に広く活用されるとともに、個別評価の精度向上に向けた改良も進められる見込みです。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/8/21)
日本人集団初の免疫細胞シングルセルアトラスの創生
~ 多層オミクス情報をシングルセル空間へ投影するフレームワークを開発 ~
大阪大学大学院医学系研究科の枝廣龍哉助教(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム 客員研究員)、佐藤豪さん(当時:博士課程、現在:東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 助教/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム 客員研究員)、熊ノ郷淳教授(呼吸器・免疫内科学)、岡田随象教授(遺伝統計学/東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授/理化学研究所生命医科学研究センターシステム遺伝学チーム チームディレクター)らの研究グループは、日本人集団235名(新型コロナウイルス感染症:COVID-19患者88名、健常者147名)のPBMC 150万細胞超を対象にシングルセルトランスクリプトーム解析(scRNA-seq)を実施し、生殖細胞系列変異と体細胞変異を含むヒトゲノムデータ・血漿プロテオームデータ・腸内微生物叢シークエンスデータの多層オミクス情報を有する免疫細胞シングルセルアトラス「OASIS」を構築しました。
このOASISを用いて、各種オミクス情報をシングルセル空間に単一細胞解像度で投影する解析を網羅的に実施しました。その結果、生殖細胞系列変異(一塩基多型:SNP、HLA多型、ポリジェニックリスクスコア:PRS)、体細胞変異(モザイク染色体異常: mCA、Y染色体喪失: LOY、ミトコンドリア・ヘテロプラスミー)、腸内微生物叢菌量は、細胞種・細胞状態に応じて免疫細胞プロファイルを動的に制御していることが明らかとなりました。
また、その解析の一環で、日本人集団における初のシングルセルeQTLリソースを構築することに成功しました。
さらに、体細胞変異は、COVID-19患者において細胞種特異的に集約される傾向を示し、同一個体内においても変異細胞と正常細胞とで異なる免疫プロファイルを示すことが確認できました。また、これらの体細胞変異がCOVID-19重症化の一因となる分子メカニズムも解明しました。
本研究は、多層的オミクス情報をシングルセル空間に投影する新たな解析フレームワークを提示したものであり、今後の疾患病態解明やゲノム創薬発展に向けた重要な基盤となることが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/7/30)
マウスの運動学習時の脳活動と行動を同時記録した大規模データセットを公開
~ 行動変容生物学を加速する国際標準形式のオープンデータ ~
福井大学学術研究院工学系部門の中江健准教授、東京大学大学院医学系研究科の近藤将史助教、松崎政紀教授らを含む複数機関からなる研究グループは、マウスの運動学習過程における脳活動と行動の変化を包括的に記録した大規模データセットを構築し、国際標準形式で公開しました。本データセットは、マウスが水報酬を得るためにレバーを引く課題を15日間学習する過程で、大脳皮質全体のカルシウム活動と、3台の高速カメラによる身体・顔面・眼球運動を同時記録したものです。さらに、課題遂行中の環境パラメータ(温度、湿度、CO2濃度等)も記録しています。データは国際標準規格であるNeurodata Without Borders(NWB)形式で整備され、約8テラバイトの生データと解析済みデータがオープンアクセス可能です。これにより、世界中の研究者が共通のツールを用いてデータを解析できるようになり、行動と脳活動の関係解明から行動変容生物学を推進し、AIを用いた脳機能研究の発展が期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/7/30)
抗原に結合して初めて光る蛍光プローブの新規設計
~ チオールと蛍光団の可逆的付加反応を抗原検出に応用する ~
東京大学大学院医学系研究科の中館眞美子大学院生(研究当時)、小嶋良輔准教授、同大学大学院薬学系研究科の清家直樹大学院生、橘椋助教、浦野泰照教授(同大学大学院医学系研究科兼担)らによる研究グループは、がん表面抗原などの標的抗原に結合するだけで大きな蛍光増強を示す蛍光プローブの新たな設計法を開発しました。本研究では、チオールとの可逆反応によって蛍光のON/OFFが切り替わる蛍光団SiPと、部位特異的にシステインを導入した抗原認識タンパク質DARPinを組み合わせて用いました。SiPとDARPinを適切な形で複合体にすることで、抗原非存在下ではDARPin中のシステイン側鎖のチオールとSiPが付加反応して、蛍光をOFFにすることができる一方で、DARPinが標的抗原に結合すると、チオールとSiPの付加反応の平衡が解離方向に移動し、蛍光をONすることができることを見出しました。本研究は全く新しい化学的メカニズムに基づいて、”activatable”に抗原を蛍光検出することを可能にするものです。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/7/24)
マウスモデルで細胞老化のメカニズムに迫る老化細胞が周囲の細胞に与える影響
曽我部裕子研究員(CiRA未来生命科学開拓部門、京都大学大学院医学研究科)、山田泰広教授(東京大学大学院医学系研究科)、山本拓也教授(CiRA未来生命科学開拓部門、京都大学ASHBi、理化学研究所AIP)らの研究グループは、細胞老化が誘導された細胞(以下、老化細胞)が体内で周囲の細胞に与える影響について、その詳細なメカニズムを明らかにしました。
これまで、培養細胞を用いた研究では、老化細胞が分泌する物質(SASP:senescence-associated secretory phenotype)が周囲の正常細胞の細胞老化を誘導することが示唆されていました。しかし、体内の組織において、わずかな数の老化細胞がどのようにして全身の個体老化に寄与するのか、その詳細は明らかになっていませんでした。
本研究では、特定のシグナル伝達経路を人為的に活性化し、生体内で老化細胞を可視化・追跡できる新たなマウスモデルを開発しました。このモデルを用いて、細胞老化が個体の加齢現象と密接に関連していることを明らかにしました。さらに、細胞老化の様態は組織の種類や誘発因子によって異なること、同じ種類の細胞であっても多様な反応を示すことを発見しました。特に肝臓においては、マクロファージが分泌する炎症性サイトカイン(IL-1B)が周囲の細胞の細胞老化を促進すること示し、細胞老化の伝播メカニズムの一端を解明しました。
本研究で開発したマウスモデルは、生体内における細胞老化の動態を個体レベルで解析・操作できる強力なツールであり、細胞老化の基本原理の理解と、老化関連疾患に対する新たな治療戦略の基盤となることが期待されます。
この研究成果は2025年7月11日18:00(日本時間)に「Nature Aging」で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/7/18)
「手ばかり」はどれくらい正確?
~ 食品の量を手で測る方法を科学的に検証 ~
東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野の篠崎奈々助教、村上健太郎教授、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、日本人成人1,081人から得られた12,148食分の食事データを用いて、手ばかりの有用性を明らかにしました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/7/18)
卵巣機能を予測する人工知能モデルを開発
~ 妊孕性向上を目指した、プレコンセプションケア、不妊治療の最適化へ ~
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座の原田美由紀教授、東京大学医学部附属病院女性外科の小池洋助教(研究当時、現:東京大学大学院医学系研究科研究倫理支援室)ならびに、サイオステクノロジー株式会社の野田勝彦、吉田要らによる研究グループは、卵巣機能を予測する人工知能(AI)モデルを開発しました。
近年、不妊症の増加が顕著となっており、その大きな要因の一つとして卵巣機能の低下が考えられています。しかし現在のところ、適切な対策を講じるための卵巣機能を簡便かつ正確に評価する手段が限られており、これが大きな課題となっています。
本研究で開発した卵巣機能予測モデルは、年齢や月経周期などの聞き取り内容と、1回の少量採血でわかる測定項目を入力すると、「卵子の数と質」を予測することができます。卵子の数に関しては従来法を上回る高精度な予測が可能であり、これまで確立された予測手法が存在しなかった卵子の質についても、一定の予測精度を達成しています。このモデルの活用により、将来的な妊娠を見据えた早期の健康管理(プレコンセプションケア)が可能となり、また、不妊治療の場面では、個々人の状態に応じた最適な治療方針の立案(個別化医療)に貢献することが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/7/18)
骨粗鬆症治療薬における変形性関節症発生リスクの比較研究
~ ロモソズマブは変形性関節症発生リスク低減 ~
ロモソズマブは、スクレロスチンに対するヒト型モノクローナル抗体製剤であり、骨形成促進と骨吸収抑制の二重作用を有します。日本では、2019年に骨粗鬆症治療薬として保険収載され、臨床で処方されています。一方、テリパラチドは副甲状腺ホルモン製剤であり骨形成促進作用を有し、2010年より骨粗鬆症治療薬として保険収載されています。これらの薬剤が変形性関節症の発生リスクに与える影響については、基礎研究では検討がなされているものの、臨床におけるエビデンスは限られているため、検証が求められています。
そこで、東京大学大学院医学系研究科の羽多野雅貴(医学博士課程)、齋藤琢准教授、田中栄教授、康永秀生教授らの研究グループは、日本人の骨粗鬆症患者を対象に、新薬ロモソズマブの投与を新規に開始した群と従来薬テリパラチドの投与を新規に開始した群の間で、変形性関節症(膝関節、股関節、手指の関節を含む)の発生リスクを比較する研究を実施しました。その結果、ロモソズマブ投与群は、テリパラチド投与群と比較して変形性関節症のリスクが低いことを明らかにしました。この研究成果は、ロモソズマブ投与が骨粗鬆症の患者さんにおいて変形性関節症リスクを低減する可能性を示すものであり、骨粗鬆症治療薬の選択における有用なエビデンスとなることが期待されます。
本研究は、日本時間2025年7月11日に学術誌 Annals of the Rheumatic Diseases オンライン版 Published Ahead of Print に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/7/14)
日常診療のX線画像から骨の密度を推定
~ AIで骨粗鬆症を早期発見、高齢社会の健康寿命延伸・医療負担軽減へ ~
東京大学大学院医学系研究科の茂呂徹特任教授と田中栄教授らの研究グループは、骨がもろくなる骨粗鬆症を早期に発見するため、腰のX線画像を用いて、腰と足のつけ根の骨の密度を人工知能(AI)で同時に調べる「AI骨粗鬆症診断補助システム」を開発しました。このシステムは、国内外で特許を取得した独自の技術に基づいており、これまでの検査機器とは異なる新しいアプローチです。
骨粗鬆症は、骨折するまで自分では気づきにくく、検査機器の普及率も低いため、多くの人が治療を受けられていないのが現状です。さらに、骨折は要介護や寝たきりの大きな原因となるだけでなく、寿命にも関わることがあるため、早期発見と予防的な治療の重要性が高まっています。
本成果により、骨折する前に病気を見つけて治療を始めることができれば、高齢者の健康寿命の延伸に大きく貢献することが期待されます。また、広く普及しているX線撮影装置を活用できるため、国内外のさまざまな医療現場での実装が見込まれます。なお、本成果は、国際医学雑誌「Journal of Orthopaedic Research」(オンライン版:日本時間7月9日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/7/9)
食塩摂取量が多い食事とは?食べる状況と食品の特徴を解明
東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野の篠崎奈々助教、村上健太郎教授、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、日本人成人2,757人から得られた延べ6万食以上の食事データを用いて、食塩摂取量が多い食事の状況と食品の種類を明らかにしました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/30)
熱中症で死なせないために
エアコンを使いこなせない人を取り残さないように
熱中症は、エアコン(冷房)を使用すれば予防できます。しかし、エアコンを適切に使いこなせず、熱中症を引き起こして死亡する方が少なくありません。家族、コミュニティ、近隣での支えあいや目配りを行うことで、熱中症で亡くなる方を減らすことにつながるよう願い、この度、研究分析結果(中間報告)を発表します。
東京大学大学院医学系研究科の橋本英樹教授、東京都監察医務院の林紀乃院長、浦邉朱鞠監察医の共同研究では、2013-2023年の間に東京都23区において熱中症で亡くなった方々(1,447症例)の分析を行っています。熱中症を防ぐうえでエアコンの適切な使用が必要であるということは、ニュース・メディアでも取り上げられていますが、実際どのような事例があるか、どのような対応ができるのか、発表します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/20)
子宮腺筋症の黄体ホルモン療法の効果予測
~ 病態に応じた個別化治療による子宮腺筋症女性のQOL向上へ ~
東京大学大学院医学系研究科の平塚大輝(医学博士課程)、廣田泰教授、同大学医学部附属病院女性診療科・産科の松尾光徳助教らによる研究グループは、子宮腺筋症患者の子宮内黄体ホルモン放出システムによる治療効果と関連するMRI画像の特徴を解析し、子宮腺筋症の病変の位置や広がり方によって治療効果が異なり、病変が子宮筋層の内側にある場合と比較して、外側にある場合や筋層全層に及んだ場合に治療効果が得られにくいことを明らかにしました。これは、子宮腺筋症の病変の位置や広がり方を評価することによって、黄体ホルモン療法の効果を予測できることを示唆しています。
子宮腺筋症は生殖年齢女性の20~30%に見られ、月経痛、過多月経などの月経随伴症状や不妊症・不育症・妊娠合併症をきたし女性のQOLを著しく損なう良性疾患です。本成果により子宮腺筋症の位置や広がりの評価に基づいて適切な治療法選択ができるようになり、子宮腺筋症女性のQOL向上に繋がるものと期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/6/14)
「睡眠学習」が生じる条件を理論的に予測
~ 特定の神経活動量と学習則がシナプス結合を強化 ~
JST戦略的創造研究推進事業ERATOにおいて、東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田 泰己 教授(理化学研究所 生命機能科学研究センター 合成生物学研究チーム チームリーダー兼任(当時)、久留米大学 特別招聘教授 兼任)、大出 晃士 講師、大阪大学 大学院医学系研究科 博士課程 木下 福章さん(当時)と久留米大学 分子生命科学研究所 山田 陸裕 准教授らは、睡眠時の大脳皮質における神経シナプス結合の強さがシナプス学習則と睡眠時の神経活動量に依存して変化することを示し、「睡眠学習」が生じ得る条件を理論的に予測できることを明らかにしました。
大脳皮質では、多数の神経細胞がシナプスと呼ばれる接合部を介して情報をやり取りしています。各シナプスのつながりの強さは神経細胞の活動状況に応じて変化し、これが学習や記憶の基盤になると考えられています。これらの活動のパターンとシナプスのつながりの変化の関係にはいくつかの決まりがあり、「シナプス学習則」と呼ばれています。睡眠は学習や記憶にとって重要であることが知られていますが、睡眠時にシナプス結合がどのように変化するのかについては解明されていない部分が多く残されていました。
そこで本研究グループは、多くの種類の神経細胞がつながった神経ネットワークの活動をコンピューターシミュレーションにより再現し、覚醒状態や睡眠状態で観察される神経活動が生じている時のシナプス結合の変化を調べました。その結果、特定の神経活動量とシナプス学習則が組み合わさることで、睡眠時に大脳皮質のシナプス結合が強まることが分かりました。これにより、睡眠中でもシナプス結合の強化が起こる条件が明らかとなり、「睡眠学習」が生じ得る条件を予測することが可能になりました。
今後、この予測を基に、睡眠と学習・記憶の関連性についてより深い理解が進むことが期待されます。また、神経精神疾患のような睡眠障害を伴う脳疾患のメカニズム解明にもつながる可能性があります。
本研究成果は、2025年6月12日(現地時間)に米国学術誌「PLOS Biology」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/13)
新たな希少がん分類を策定
~ 実臨床に即した分類の活用により希少がん対策の推進を期待
日本のがん発生の約2割が希少がんに該当する実態も確認 ~
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の力武諒子助教、東尚弘教授は、国立がん研究センター希少がんセンターと共同して、がんが発生する臓器と組織型で希少がんを分類する、新しい希少がん分類「New Classification of Rare Cancers(NCRC)」を策定しました。 また、この希少がん分類で、日本のがん罹患を網羅する全国がん登録データを解析したところ、2016年から2019年に日本で診断されたがんの約2割が希少がんであることが明らかになりました。また、これまで用いられてきた欧州の希少がん分類では含まれなかった希少がんも特定されました。
希少がんは、厚生労働省の希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書(2015年8月)において、「概ね罹患率人口10万人当たり6例未満、数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい」がん種と定義され、分類は欧州で開発されたRARECARE分類を参考とすることになっています。しかし、RARECARE分類は、病気の性質や日本での発生頻度とのずれがあることや最新の分類ではないことなどから、日本の実臨床に即した希少がん分類の開発が必要とされていました。
新たに策定した希少がん分類は、年間発生数が人口10万人あたり6例未満であることを基準に、がんが発生することが少ない臓器31部位のがんと、がんの発生が多い臓器であるが発生が少ない特定の組織型のがん364種を希少がんに分類しました。
どのがんが希少がんかを明確にすることは、希少がんの実態把握や政策の推進に不可欠であり、本希少がん分類の活用により、日本の希少がん対策が進むことが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/10)
膵癌のリスク層別化を実現する新たな視点~脂肪膵とIPMN併存癌~
~ MRIを活用した観察研究 ~
東京大学医学部附属病院 消化器内科の大山博生 助教、浜田毅 助教、藤城光弘 教授らによる研究グループは、脂肪膵を有する患者がIPMN由来癌ではなくIPMN併存癌を発症するリスクが高いことを明らかにしました。
IPMNは膵癌の高リスク群であり、IPMN由来癌とIPMN併存癌が同程度の頻度で発生することが知られています。一方で近年、脂肪膵が膵癌のリスク因子であることが認識されてきています。本研究では330ものIPMN症例について、MRI画像(T1強調画像)を用いて脂肪膵の程度を定量的に測定することで、IPMNの長期経過観察開始当初から脂肪膵を認める場合にIPMN併存癌に罹患しやすく、高度な脂肪膵の患者ほどIPMN併存癌に罹患するリスクが高くなることを世界で初めて報告しました。先行研究と比較して、IPMN由来癌とIPMN併存癌の発生機序の違いに迫る点、脂肪膵と通常型膵癌の発生との因果関係を明確にした点で新規性があり、この研究成果は今後膵癌のリスク層別化や早期発見に役立つことが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/6/4)
吸入麻酔薬はなぜ効くのか?作用メカニズムの一端を解明
~ 標的分子の1つとして1型リアノジン受容体を特定 ~
JST 戦略的創造研究推進事業 ERATOにおいて、東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田 泰己 教授(久留米大学 特別招聘教授 兼任)、金谷 啓之 医学博士課程大学院生、桑島 謙 特任研究員(研究当時、現 同大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 助教)、大出 晃士 講師らの研究グループは、カルシウム放出チャネルである1型リアノジン受容体(RyR1)が、吸入麻酔薬の標的分子として全身麻酔の導入に関与していることを見いだしました。
吸入麻酔薬の麻酔作用は約180年前に発見されて以来、外科手術の全身麻酔などに用いられてきましたが、どのようにして麻酔作用を発揮するのかは、いまだ完全に解明されていません。これまでの研究から、吸入麻酔薬が複数のたんぱく質に作用して麻酔効果を発揮することが分かっていましたが、未知の標的分子の存在も示唆されていました。
一方、通常と異なるRyR1を持つ(RyR1の変異)患者は、吸入麻酔薬によってまれに引き起こされることがある悪性高熱症の発症リスクが高いことが知られていましたが、吸入麻酔薬とRyR1との直接的な分子間相互作用は明確に示されておらず、麻酔作用との関連も分かっていませんでした。
本研究グループはまず、イソフルランをはじめとする吸入麻酔薬がRyR1を活性化して小胞体からのカルシウム放出を促すことを確認しました。次に、イソフルランによる活性化に重要なRyR1のアミノ酸残基を特定することに成功し、イソフルランの結合部位を推定しました。また、イソフルランに反応しないRyR1変異体を発現する遺伝子改変マウス(ノックインマウス)を作製してイソフルランを投与したところ、正常なマウスに比べ、部分的に麻酔への感受性が低下することが確認できました。
さらに、化合物スクリーニングによってイソフルランの推定結合部位に作用する新しい化合物を特定することに成功し、その化合物が実際にマウス個体で鎮静作用に近い効果があることを見いだしました。これらの結果は、RyR1がイソフルランの標的分子の1つとして麻酔作用に関与することを示唆しています。
本成果は、全身麻酔に用いられる吸入麻酔薬の分子メカニズムの一端を明らかにするものです。これまでの研究では、哺乳類においてRyR1と麻酔作用の関連は示されておらず、新しい知見となります。麻酔薬が作用する仕組みをより詳細に理解することで、より優れた麻酔薬や投与方法の開発につながる可能性が期待されます。
本研究は、筑波大学 医学医療系の広川 貴次 教授、順天堂大学 医学部の大久保 洋平 准教授、村山 尚 准教授、日本大学 医学部の飯野 正光 上席研究員らと共同で行われました。
本研究成果は、2025年6月3日午後2時(米国東部夏時間)に米国科学誌「PLOS Biology」オンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/4)
慢性子宮内膜炎の新たな治療の可能性を発見!
~ 魚に含まれるEPAが妊娠を助ける鍵に ~
不妊や流産を繰り返す原因の一つとされる「慢性子宮内膜炎」。この病気の背景に、脂質代謝の異常が深く関わっていることを、日本医科大学 松田繁 助教、桑原慶充 准教授、東京科学大学 大石由美子 教授、東京大学 村上誠 教授、千葉大学 眞鍋一郎 教授らの共同研究グループが明らかにしました。さらに、魚油に多く含まれるω(オメガ)3系脂肪酸「エイコサペンタエン酸(EPA)」を食事として補うことで、この病気の改善や流産の防止が期待できることも示されました。この研究は、慢性子宮内膜炎に対する新しい治療法を提案するだけでなく、妊娠を考える女性が日常的に取り組める「プレコンセプションケア(妊娠準備のための健康管理)」の重要性を示すものです。研究成果は2025年6月に「Frontiers in Immunology」誌に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/30)
山本一彦名誉教授が瑞宝中綬章を受章
山本先生は、リウマチ学および臨床免疫学の分野において、ヒトを対象とした研究を長年にわたり推進されてきました。独自の手法による自己抗体の認識エピトープの同定、抗原特異的T細胞による免疫応答の証明に加え、既知の制御性T細胞とは異なる、IL-10産生を特徴とする新たな制御性T細胞サブセットを明らかにされ、自己免疫疾患における免疫応答および免疫制御機構の解明に多大な貢献をなされました。
さらに、ヒトゲノム情報に基づいて疾患感受性遺伝子を評価する手法を確立され、関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患に関連する多数の感受性遺伝子を同定されました。これにより、遺伝的素因の解明にとどまらず、これらの遺伝子が病態形成や治療戦略において果たす重要な役割を明確にされました。中でも、関節リウマチの感受性遺伝子としてPADI4を同定されたことは、抗シトルリン化蛋白抗体という最も特異性の高い自己抗体の標的抗原形成に深く関与する発見であり、特筆すべき成果です。また、ヒト体内の複雑な免疫系の解明を目指して、機能ゲノム学という新たな解析体系を構築され、多くの疾患に関与する免疫経路を明らかにされたことは、今後のヒト免疫学の発展に大きく寄与する業績として高く評価されています。
平成9年から平成29年まで東京大学医学系研究科アレルギー・リウマチ内科教授を務められた後、理化学研究所生命医科学研究センター長として5年間にわたり卓越したリーダーシップを発揮されました。学会活動においても、日本リウマチ学会およびアジア太平洋リウマチ学会連合の理事長を歴任されるなど、国際的にもご活躍されました。
これらの優れた業績に対し、日本リウマチ学会賞、日本チバガイギーリウマチ賞、エルウィン・フォン・ベルツ賞(アレルギー疾患および自己免疫疾患の研究に対して)、日本医師会医学賞、高峰記念第一三共賞、日本免疫学会ヒト免疫研究賞、Carol Nachman Award、欧州リウマチ学会賞、紫綬褒章など、数多くの栄誉ある賞が贈られています。
さらに、これらの一連の研究の中で、山本先生が大学院生の頃よりご指導された多くの後進が、現在では国内有力大学の教授として活躍しており、日本のみならず世界におけるリウマチ学および免疫学の発展に大きく貢献しておられます。
このたびのご受章を心よりお慶び申し上げますとともに、今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
(医学部附属病院 藤尾圭志)
(2025/5/20)
辻省次名誉教授が瑞宝中綬章を受章
令和7年春の叙勲において、本学名誉教授ならびに国際医療福祉大学特任教授の辻省次先生が、長年にわたる学術および医療への顕著なご貢献により、瑞宝中綬章をご受章されました。
先生は、神経内科学およびゲノム医科学の分野において卓越した業績を重ねられ、特に神経難病の病態機序の解明と治療法の開発において、極めて多大なご功績を残してこられました。その研究成果は国際的にも高く評価されており、平成23年には紫綬褒章を受章され,平成27年には世界神経学会より,Medal for Scientific Achievement in Neurology を受賞されています。
神経内科学の対象となる疾患には、治療可能なものもある一方で、有効な治療法が確立していない進行性難病もなお数多く存在します。こうした難治性疾患の原因や病態を明らかにし、治療法を見出すことは、神経内科学における喫緊かつ重要な課題であり、臨床脳神経医学研究の最前線をなすテーマの一つです。
先生は、ゲノム医科学的手法を駆使し、神経難病の病因遺伝子の発見と病態解明を力強く推進され、本分野における世界的な研究リーダーとして、学術の発展に大きく寄与されてきました。これらの先駆的な成果は、神経内科学のみならず、脳神経科学やゲノム医科学を含む広範な医学領域において極めて高く評価されています。
具体的には、歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)、脊髄小脳失調症2型(SCA2)、眼球運動失行と低アルブミン血症を伴う早発型失調症(EAOH)、常染色体劣性脳小血管病(CARASIL)など、数多くの単一遺伝性疾患において、病因遺伝子を世界に先駆けて同定されました。さらに、良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん(BAFME)、神経核内封入体病(NIID)、眼咽頭遠位型ミオパチー(OPDM)などの原因遺伝子も明らかにされ、分子病態の解明においても大きな貢献を果たされました。家族性および孤発性の多系統萎縮症やパーキンソン病において、疾患の原因またはリスクとなるrare variantを同定し、研究領域を切り拓かれました。さらに、多系統萎縮症に対する還元型コエンザイムQ10の臨床治験や、成人期大脳型副腎白質ジストロフィーへの造血幹細胞移植療法の実施など、神経難病に対する革新的な治療法の開発にも尽力されておられます。
このたびの瑞宝中綬章のご受章は、先生の長年にわたる先駆的かつ継続的な研究成果と、臨床医学への献身的なご尽力に対する極めて高い評価の証と存じます。
謹んでお祝い申し上げるとともに、今後ますますのご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(大学院医学系研究科・医学部 佐竹 渉)
(2025/5/20)
高校生が困った時に友人に助けを求めやすいかは、仲間を積極的に助ける学級の雰囲気と関連
東京大学医学部附属病院精神神経科の森島遼届出研究員(兼:帝京平成大学健康メディカル学部心理学科講師)、笠井清登教授(国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)、同大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻教育心理学講座の宇佐美慧准教授らの研究グループは、関東圏の中学生・高校生21,845人のデータを分析し、向社会性(積極的に他者を助ける行動や考え)の高い学級に所属している高校生は友人への援助希求行動(困ったときに他者に助けを求める行動)をとりやすいことを見出し、高校生の援助希求行動が学級の向社会性と関連することを明らかにしました。これまで、思春期の向社会性が援助希求行動と関連するという報告では、それが個人ごとの向社会性にもとづくものか、学級など所属集団の向社会性の影響を受けたものかの検討は行われていませんでした。そこで本研究では、向社会性を学級全体の平均と、各生徒の学級平均からの差(偏差スコア)に分けて検討し、学級全体の向社会性と個人ごとの向社会性のいずれもが援助希求行動と関連することを初めて明らかにしました。本研究の知見から、学校現場における他者と助け合う学級の雰囲気作りが、他者に助けを求めやすい環境作りにつながり、虐めや自殺への対策のひとつとなると期待されます。
なお、本研究は米国医学雑誌「JAMA Network Open」(オンライン版:米国中部夏時間5月15日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/5/16)
三毛猫の毛色を決める遺伝子をついに発見
~ 60年間の謎だった三毛猫の毛色の仕組みを解明 ~
三毛猫やサビ猫はメスばかりであること、オレンジ/黒の毛色を決める「オレンジ遺伝子」がX染色体上にあることは120年以上前から知られていました。1961年、メスの細胞では一対のX染色体の片方がランダムに選ばれて不活性化されるという仮説が提唱され、三毛猫やサビ猫の模様はこの仮説と合致する例として広く受け入れられてきました。しかし、それから60年以上経った今日まで、オレンジ遺伝子の正体やその働きについては明らかになっていませんでした。
九州大学生体防御医学研究所(研究当時)の佐々木裕之特別主幹教授(現:高等研究院)、同大学大学院歯学研究院の松田美穂准教授、国立遺伝学研究所の藤英博特命准教授、中村保一教授、国際基督教大学の歐陽允健助教、東京大学の鵜木元香准教授、アニコム先進医療研究所株式会社の松本悠貴研究員(麻布大学特任准教授兼任)および、近畿大学農学部の佐渡敬教授らの研究グループは、オレンジ遺伝子の正体が「ARHGAP36」であることを突き止めました。
本研究グループは、福岡市内の様々な毛色を持つ18匹の猫のDNAを解析し、オレンジ毛を持つ猫のX染色体にはARHGAP36遺伝子内に約5,000塩基の欠失があることを見つけました。さらに50匹以上の猫を調べ、海外のデータも参照したところ、この欠失の有無とオレンジ毛の有無が完全に一致していました。この欠失領域には、動物種を超えて高度に保存された配列が含まれ、この配列がARHGAP36の発現を制御している可能性が強く示唆されました。次に、オレンジ毛が生えた皮膚での遺伝子発現を調べたところ、欠失によってARHGAP36の発現が上昇し、その結果としてメラニン合成遺伝子群が抑えられ、黒色のユーメラニンからオレンジ色のフェオメラニンへと合成の切り替えが起きることが示唆されました。さらに、遺伝子の発現を抑制するDNAメチル化の状態を調べたところ、ARHGAP36はX染色体の不活性化に伴って高度にメチル化されることが分かりました。これらの結果から、オレンジ遺伝子の正体はARHGAP36であり、60年前に提唱された通り、この遺伝子の不活性化がオレンジ/黒の斑の形成に関与することが明らかになりました。
本研究成果は、⽶国の雑誌「Current Biology」に2025年5月16日(金)午前0時(日本時間)に掲載されました。なお、同雑誌の同じ号にはStanford大学のGregory Barsh教授らの類似の論文が掲載されており、日米の独立した研究がほぼ同時に同じ結論に到達しました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/16)
抗血小板薬の効果を“見る”時代へ
冠動脈疾患患者において、血栓は重要な役割を果たし、血小板凝集を抑制する抗血小板薬は冠動脈疾患管理に必須の薬剤です。しかし、生体内における血小板凝集の程度を直接評価することは、これまでの検査方法では困難でした。
東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授、東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)検査部の矢冨裕教授(研究当時)・蔵野信教授、同循環器内科の武田憲彦教授らによる共同研究チームは、東大病院に入院し心臓カテーテル検査・治療を受けた冠動脈疾患患者(207名)から採取した血液内の循環血小板凝集塊を、マイクロ流体チップ上で高速流体イメージングにより大規模撮影し、取得した循環血小板凝集塊の画像ビッグデータをAIを使って解析しました。
その結果、冠動脈疾患患者では健常者と比較して血小板凝集が亢進し、特に急性冠症候群で顕著でした。また、血小板凝集塊の出現頻度は抗血小板薬の数が増えるほど低下していました。さらに、冠動脈疾患は動脈の疾患であるにも関わらず、血小板凝集の程度は静脈血と動脈血のいずれの検体においても良好な相関を認めることを発見しました。本研究結果は、冠動脈疾患のスクリーニング及び抗血小板療法の個別化、最適化、非侵襲モニタリングに貢献することが期待されます。
本研究成果は、日本時間2025年5月15日(18時)にNature Communicationsのオンライン版で公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/5/16)
時間栄養学の視点からみた食行動
~ 食事の質および肥満との関連 ~
東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、20~69歳の日本人1047人を対象として、時間栄養学からみた食行動を幅広く調査し、食事摂取時刻や頻度といった時間栄養学的食行動と食事の質および肥満との関連は、時間栄養学的行動をどのような方法で調べるかによって大きく異なることを明らかにしました。本研究は、時間栄養学的行動と食事の質および肥満との関連を、異なる二つの調査法(質問票法と日記法)を用いて検討した世界で初めての研究です。本研究の成果は、世界で急速に進む時間栄養学分野において、調査方法を慎重に吟味することの必要性を改めて強調する貴重な科学的根拠となることが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/13)
日本人集団におけるアイソフォームの発現量に影響する遺伝的多様性の同定
東京大学大学院医学系研究科の名倉祐哉大学院生(研究当時)、藤本明洋教授らによる研究グループは、アイソフォームの発現量と関連する遺伝的多様性を明らかにしました。
本研究では、ロングリードシークエンス技術を用いて健康な日本人67人のB細胞のアイソフォームを解析し、アイソフォームに関するeQTL(ieQTL; isoform eQTL)を同定しました。その結果、17,119個のieQTLが発見され、その70.6%は遺伝子レベルの解析では検出されませんでした。ieQTLの特徴を調べたところ、ieQTLはスプライシングに関係している部位や、特定のヒストン修飾(H3K36me3、H3K4me1、H3K4me3、H3K79me2など)に多いことが分かりました。実験的検証により遺伝子から離れた遺伝的多様性がアイソフォームの発現量に影響すること、従来の知見では重要と考えられなかった遺伝的多様性がスプライシングに関与することが確認されました。また、先行研究で発見された疾患リスクに影響する遺伝的多様性との重なりを調べたところ、遺伝子のeQTLと比較して、ieQTLは疾患リスクに関わる遺伝的多様性の数が多いことが明らかになりました。これらの結果は、人類遺伝学研究におけるアイソフォームの解析の重要性を示唆しています。
本研究では、アイソフォームを区別し、発現量に影響する遺伝的多様性(eQTL)を検出し、多くの新規eQTLを同定しました。本研究は新たな疾患関連遺伝子の同定に寄与すると考えられます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/9)
呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患の遺伝的背景の多様性を解析
~ 東アジア系集団と欧州系集団では、両疾患が逆方向の遺伝的相関を示す ~
大阪大学大学院医学系研究科の山本悠司さん(博士課程)(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学)、白井雄也 助教(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学)、岡田随象 教授(遺伝統計学/東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームリーダー)、東京大学 大学院医学系研究科の山内敏正 教授、門脇孝 東京大学名誉教授(虎の門病院 院長)らの共同研究グループは、喘息などの3種類の呼吸器・免疫疾患と、関節リウマチ、脂質異常症などの7種類の心血管代謝疾患、およびこれらに関連する特徴や性質を対象に、遺伝的関連を調査しました。
その結果、呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患の遺伝的リスクの関係が東アジア系集団と欧州系集団で異なることを発見しました。また、これらの疾患で遺伝的リスクが逆方向に関連する生物学的パスウェイを発見し、メタボロームやプロテオームなどとの統合解析により、遺伝的リスクとの関連が異なるバイオマーカーを発見しました。
本研究成果によって呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患を合併するメカニズムの理解が進み、将来的にこれらの疾患の予防や個別化医療へ貢献することが期待されます。
この成果は、2025年4月28日(月)18時(日本時間)に英国科学雑誌Nature Communicationsにオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/30)
時間栄養学のための簡易評価ツール(Chrono-Nutrition Behavior Questionnaire; CNBQ)
~ 11日間食事日記との比較による妥当性研究 ~
東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、時間栄養に関する幅広い行動を簡易的に評価することを目的とした「Chrono-Nutrition Behavior Questionnaire; CNBQ」が、11日間にわたって収集された食事日記との比較において、十分な妥当性を有することを明らかにしました。CNBQは、時間栄養に着目した研究で必要とされる、さまざまな食行動や睡眠行動を十分な妥当性をもって測定できる、世界初の簡易ツールです。CNBQは、時間栄養に関する大規模な観察研究や介入試験で広く活用され、食に関する政策立案に不可欠である信頼できる科学的根拠の構築に大きく寄与することが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/25)
家庭で心不全を早期発見するAIシステムを開発
~ 心不全重症度の新たな指標を構築 ~
東京大学大学院医学系研究科先進循環器病学の荷見映理子特任研究員、藤生克仁特任教授らの研究グループは、SIMPLEX QUANTUM株式会社と共同で、人工知能(AI)を活用した新しい心不全の早期検出システムを開発しました。
本システムは、単一誘導心電図データのみから、心不全の重症度を高精度(91.6%)で分類できることを実証しました。これにより、従来、植込み型心臓電気デバイス(CIED)に依存していた心不全の在宅モニタリングが、スマートウォッチを含む携帯型心電計で計測できる単一誘導心電図データのみを用いてできるようになり、心不全の進行を早期に検出することが可能になりました。さらに、AIによる独自の「HF(Heart failure)インデックス」を開発し、心不全の重症度を数値化する新たな指標を確立しました。
このようなアプローチによる心不全のリアルタイム評価システムの報告はこれまでになく、心不全管理のより良い医療を提示するものです。本システムの導入により、心不全患者さんは自宅で簡便に病状をモニタリングできるようになるため、再入院のリスク低減や早期の治療介入につながります。さらに、遠隔医療の発展や、心不全管理の効率化や患者さんの生活の質向上にも寄与することが期待されます。本研究成果は、日本時間4月24日に循環器領域の国際的な学術誌 「International Journal of Cardiology」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/25)
肝臓由来のタンパク質「アクチビンB」が糖代謝を制御する新たな仕組みを発見
~ 糖尿病のすべての病態を改善できる治療薬開発への期待 ~
糖尿病は我が国のみならず全世界的に有病者が増加しており、血管合併症のみならずがんや老年症候群の要因ともなることが明らかになってきており、深刻な公衆衛生課題となっています。こうした中、国立健康危機管理研究機構(JIHS)糖尿病研究センターの植木浩二郎センター長および分子糖尿病医学研究部の小林直樹上級研究員らのグループは、東京大学大学院医学系研究科の山内敏正教授、門脇孝東京大学名誉教授やドイツ・ライプツィヒ大学Matthias Blüher教授らとの国際共同研究により、肝臓由来のタンパク質「Activin B」が糖代謝を改善する新たな仕組みを発見しました。Activin Bは、肝臓でFGF21の産生を促進しインスリン感受性を高める一方で、肝臓のグルカゴンに対する反応性(グルカゴン感受性)を低下させることで、血糖を改善するしくみを持つことが明らかになりました。また、肥満に伴いこの作用を阻害するタンパク質であるFSTL3が増加することも示され、糖尿病の新たな治療標的としての可能性が期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/24)
寄付講座設立による臓器移植体制の充実と次世代育成
~ 東大病院内に「次世代臓器移植開発推進講座」を開設 ~
東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)の脳死下臓器移植の受け入れ数は国内最多となっています。一方、増加する国内の脳死ドナーに対応するための人材育成、体制・設備の整備が急務です。そこで、移植を受けられた患者さんが設立した一般社団法人N28からの寄附をもとに「次世代臓器移植開発推進講座」を2025年4月1日に東大病院内に開設しました(協力講座:大学院医学系研究科 呼吸器外科学)。
本講座では、肺移植だけでなく、他臓器の移植や麻酔科、集中治療分野など、臓器移植に関わる多岐にわたる分野で、高度な専門知識と技術を持つ人材を育成します。これにより、これまで海外でしか学べなかった最先端の臓器移植に関する教育を国内で実現し、日本の臓器移植医療の国際的なレベル向上を目指します。また患者管理の効率化を図るための情報管理システムの研究開発を加速させ、より安全で質の高い臓器移植を実現するための基盤を構築します。
また本講座と関連して、臓器移植を優先して実施する高規格手術室の増設や、臓器移植患者を優先して受け入れるICUの増設など、臓器移植に必要な医療環境の整備を計画しています。
本講座の設置は、日本の臓器移植医療における大きな転換点となることが期待されます。当院は、この寄付講座を起点として、臓器移植に関する臨床、研究、教育の基幹施設としての「東大モデル」を構築し、日本の臓器移植医療を次のステージへと導いていきます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/23)
メタボリックシンドロームの基準値を外れる肥満・内臓脂肪蓄積・脂質異常症と慢性腎臓病の関連
~ 大規模職域健診を受診した約30万人のデータ解析結果 ~
東京大学大学院医学系研究科の吉田 唯助教、松山 裕教授らの研究グループは、国内大規模職域健康診断実施団体である公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターの308,174名の約3年分のデータを解析し、追跡開始時点(ベースライン)のウェスト径、HDLコレステロール・中性脂肪値がメタボリックシンドロームの基準から外れている場合、及びBMI≧25kg/m²の場合に、将来尿蛋白が発生するリスクが高いことを明らかにしました。また、HDLコレステロール値が低いと、その後の腎機能低下と関連していることが分かりました。
本結果は、血糖・血圧のみでなく、肥満・脂質異常症・内臓脂肪蓄積が独立して慢性腎臓病の発症・進行と関連していることを示唆し、該当者の早期の発見・介入により慢性腎臓病の予防・進行の抑制に役立つことが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/16)
認知機能が低下した高齢運転者は同乗者がいると事故を起こしにくい
高齢運転者による交通事故を防ぐため、運転免許更新時の高齢者講習や認知機能検査が長年行われ、近年では先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の普及が図られています。本研究では、高齢運転者について、同乗者がいると事故を起こすリスクが低いという海外での知見や、同乗者を要する条件付き免許を採用している国があることに注目し、認知機能が低下した運転者においても、同乗者がいると事故を起こすリスクは低いという仮説をたて、これを検証しました。
2014年から2017年までに認知機能検査を受検し運転免許を更新した75歳以上の免許保有者のうち、免許更新後3年間に車両相互事故に遭った運転者を第1当事者(過失の重い方)と無過失の第2当事者に分けて、事故時の同乗者の有無を、認知機能検査の結果ごと(認知症の恐れがある人、認知機能低下の恐れがある人、いずれの恐れもない人の3群)に男女別で比較しました。
分析の結果、認知機能の程度にかかわらず、男女とも、第1当事者より第2当事者の方が同乗者を伴っているケースが多いことが分かりました。一方、二者間で事故の発生に寄与しうる要因(年齢、過去の事故経験、事故時の時間帯・天候・場所)に大きな違いは見られませんでした。
この結果は、認知機能検査で認知症や認知機能低下の恐れがあると判定された高齢運転者でも、同乗者がいれば、車両相互事故で第1当事者になりにくい可能性を示唆しています。因果関係を示すものではありませんが、高齢運転者の安全運転に同乗者が重要な役割を果たしているのかもしれません。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/15)
ニチバン、東京大学に「社会連携講座」を開設
~ 「世界から難治性創傷をなくす」ために、「次世代創傷ケアの開発」を目指す ~
ニチバン株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:高津敏明、以下「ニチバン」)は、国立大学法人東京大学(東京都文京区、総長:藤井輝夫、以下「東京大学」)において2025年4月1日より大学院医学系研究科に産学連携の社会連携講座「次世代創傷ケア開発学」を開設いたしました。本講座は5年間の期間を通じて次世代創傷ケア技術の開発と人材養成、並びに研究成果を看護教育に反映させることで患者の創傷治癒プロセスを加速させ、社会課題の解決を目指します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/8)
尿酸輸送体GLUT9の立体構造を解明
~ 腎臓で尿酸値を協調的に調節 ~
横浜市立大学大学院生命医科学研究科の松下大輝さん(研究当時博士前期課程1年)、西澤知宏教授、李勇燦助教らの研究グループは、東京大学医学部附属病院の高田龍平教授、防衛医科大学校の松尾洋孝教授、豊田優講師(学内准教授)らとの共同研究により、体内で尿酸値の制御に関わる尿酸輸送体GLUT9の、尿酸が結合しているときの構造と結合していないときの構造をクライオ電子顕微鏡単粒子解析により明らかにし、それを基に行った機能解析から尿酸認識機構を解明しました。GLUT9を分子標的とする新たな尿酸降下薬の創製につながる重要な成果であると考えられます。
本研究には、本研究成果は、Cell Pressが発行する米国科学誌「Cell Reports」のオンライン版に先行公開されました(2025年4月5日)。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/8)
『行動するか?しないか?』は、高次運動野へ入力する二つの脳内経路の相反する信号によって決定される
~ To act or not to act の脳回路を解明 ~
東京大学大学院医学系研究科の吉田恵梨子大学院生(当時)、近藤将史助教、松崎政紀教授(理化学研究所脳神経科学研究センター脳機能動態学連携研究チームチームリーダー、東京大学大学院理学系研究科教授 兼担)、中江健特任准教授(当時、自然科学研究機構生命創成探索センター)、石井信教授(京都大学大学院情報学研究科)、小林憲太准教授(自然科学研究機構生理学研究所)らによる研究グループは、行動するかしないかを決定する大脳皮質回路機構を解明しました。マウスを用いた神経活動の計測・操作と、行動履歴と神経活動の数理解析によって、行動するかしないかに関する相反する信号が大脳皮質内と皮質下から高次運動野(M2)へ入力され、M2の神経細胞がこれらの信号を統合することで、行動開始信号が生成されるかどうかが決まることがわかりました。自律的なより良い行動を促す(行動変容)手法の開発や、行動決定異常に関わる疾患の理解への貢献が期待されます。
本研究成果は、米国のシュプリンガー・ネイチャー社(Springer Nature)が発行する学術雑誌『Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)』のオンライン版に 2025年4月4日(英国夏時間)に公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/4)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報