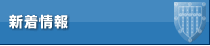広報・プレスリリース情報(2016年(平成28年))
世界で初めて長期埋め込み可能な人工硝子体を開発
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の酒井崇匡准教授(鄭雄一教授(同バイオエンジニアリング専攻/大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 臨床医工学部門兼務)グループに所属)と筑波大学医学医療系の岡本史樹講師(眼科学)は、JST課題達成型基礎研究(さきがけ)の一環として行った共同研究により、長期埋め込み可能な人工の硝子体の開発に世界で初めて成功しました。
網膜のさまざまな疾患に対して行われる硝子体手術では、硝子体置換材料が必須です。従来の材料であるガスやシリコンオイルなどは疎水性であるため生体適合性が低く、長期の使用には適さないことから、長期的かつ安全に置換可能な人工硝子体材料の開発が望まれていました。また、眼の透明組織としては、水晶体と角膜は人工物が開発されていましたが、人工硝子体は未だ開発されていませんでした。
本研究グループは、新たな分子設計により、生体内に直接注入可能な、含水率のきわめて高い高分子ゲル材料を作製し、人工硝子体として有用であるという結果を得ました。
今後、網膜疾患を含む眼科系疾患の治療に役立つことが期待されます。将来的には、癒着防止剤、止血剤、再生医療用足場材料等への応用も期待されます。
本研究成果は、『Nature Biomedical Engineering』に掲載されました。
詳細は工学系研究科HPをご参照ください。
(2017/3/3)
ゲノム医療研究プロジェクト始動
がんゲノム医療を実践するために、東京大学分子ライフイノベーション棟6階に国際基準に準拠したシークエンス室、インフォマティクス解析室を整備し、がん患者の腫瘍部及び正常部ゲノムを解析し、患者に最適な治療法の選択に役立てる研究を行います。 本研究事業は、東京大学大学院医学系研究科の間野教授を始め、医学系研究科・医学部附属病院あるいは東京大学他施設の関連講座全体が参画する大きな研究プロジェクトです。
シークエンス室の運営は検査会社との共同で行い、シークエンス品質・再現性が担保された形でゲノム解析がなされます。 本研究事業で用いるがん関連遺伝子パネルを東京大学で独自に開発し、またその解析結果のうちどれを薬剤選択に役立てるべきかを判定するための知識データベースも構築します。
東京大学全体で、がんゲノム医療を実践するシステムを構築します。 また本研究事業で開発するターゲット遺伝子パネルや知識データベースは、近い将来、がんゲノム医療が日本に普及する上で必要な基盤となります。
難病を対象としたクリニカルシークエンスのために、上記分子ライフイノベーション棟6階および同3階の東大病院ゲノム医学センターの中に、国際基準に準拠したシークエンス室を整備します。 難病のゲノム医療の実践は、日本医療研究開発機構(AMED)の「臨床ゲノム情報統合データベース整備事業」として行うもので、辻教授が研究代表者を務め、東大病院の多くの診療科が協力して行います。
がん・難病のゲノム医療研究事業は、共に臨床ゲノム情報統合データベース整備事業に参画しており、この事業に参加している多くの拠点が協力して、診療、研究に役立つデータベースの構築を進めていきます。
![]() リリース文書[PDF:336KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:336KB](東大病院HP掲載)
(2017/2/14)
C型肝炎ウイルス排除後の肝発癌に関わる遺伝要因(体質)を発見
近年、C型肝炎ウイルス(HCV)感染症に対する治療法は劇的に進歩し、従来使用されてきたインターフェロンを用いない直接作用型抗ウイルス薬の組み合わせにより著効率は90%を超え、難治であった肝硬変患者においても同等の治療効果が得られるようになりました。 ウイルス排除により、肝発癌リスクは減少しますが、完全にリスクが消失することはないため(5年累積肝発癌率2.3-8.8%)、ウイルス排除後の発癌の予測・予防が重要な課題となっていました。
この度、名古屋市立大学大学院医学研究科の田中靖人教授、松浦健太郎研究員は、東京大学大学院医学系研究科の徳永勝士教授との共同研究により、HCV排除後の肝発癌に関わる遺伝要因を世界で初めて発見することに成功しました。 我々が発見した「TLL1(トロイド様遺伝子1)」という遺伝子型を測定することによって、HCV排除後の肝発癌リスクの高い患者群を絞り込むことが可能となり、肝癌の早期発見・治療につながるものと考えられます。 また、さらなる研究によりHCV排除後やその他の疾患(B型肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎、糖尿病など)を原因とする肝発癌のメカニズムの解明、新規の治療法の開発も期待できます。
本研究成果は、米国科学誌「Gastroenterology(ガストロエンテロロジ―)」2017年2月3日オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.15MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.15MB]をご覧下さい。
(2017/2/7)
回顧と自己省察を実現する大脳メカニズムを発見!
~ 自身の記憶を内省的に評価する「メタ記憶」の神経基盤の解明 ~
順天堂大学大学院医学研究科特任教授の宮下保司(東京大学大学院医学系研究科客員教授)、東京大学大学院医学系研究科の宮本健太郎(日本学術振興会特別研究員)らによる共同研究グループは、自分自身の記憶を内省的にモニタリングする能力「メタ記憶」の神経基盤を世界で初めて同定し、「メタ記憶」が記憶実行機能自体と乖離しうることを発見しました。 この成果は、従来、ヒト特有の能力だと考えられてきた回顧や内省などの自己言及的な認知情報処理の大脳メカニズムを神経ネットワーク動作レベルで解明し、脳機能の科学的根拠に基づいた効果的な教育法の開発や、前頭前野を病巣とする記憶に関わる高次脳機能障害の診断・治療法の確立に貢献すると期待されます。
本研究成果は米国Science誌1月13日号にて発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 682KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 682KB]をご覧下さい。
(2017/1/16)
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の細胞死を引き起こすメカニズムを更に解明
~ 活性化カルパインが核膜孔複合体構成因子を切断し、核-細胞質輸送を障害 ~
国際医療福祉大学臨床医学研究センター 郭伸特任教授(東京大学大学院医学系研究科 客員研究員)、東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 神経病理学分野 山下雄也特任研究員らの研究グループは、東京医科大学 相澤仁志教授との共同研究で、カルパインというカルシウム依存性プロテアーゼの活性化が核膜孔複合体(NPC)の構成因子であるヌクレオポリンを異常に切断し、核-細胞質輸送を障害することが筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因メカニズムであることを、分子生物学的手法により世界に先駆けて明らかにしました。
本研究グループは、ALSの病因解明研究を進めるなかで、異常なカルシウム透過性AMPA受容体が発現していることが病因に関わる疾患特異的分子異常であり、細胞内カルシウム濃度の異常な上昇がカルパインの活性化を通じてALS運動ニューロンに特異的に観られるTDP-43病理を引き起こすことを既に明らかにしていました。 今回、カルパインの活性化がNPCの構成因子であるヌクレオポリンを異常に切断することで、核-細胞質輸送を障害することを解明しました。 この障害は運動ニューロンでの必要な遺伝子発現を抑えるので、細胞の生理活動が阻害され細胞死に陥ることが考えられます。
ALS患者の大多数を占める孤発性ALSの病因を説明するメカニズムである点に研究の特色があり、治療へ向け一歩前進したといえます。 また最近一部の家族性ALSの病因にも核-細胞質輸送障害が生じていることが報告され、共通のカスケードが関係していることから一部の家族性ALSをも含めた治療法開発につながる可能性のある成果です。
以上の成果は、「Scientific Reports」(2017年1月3日オンライン版)に掲載されました。
なお、本研究は一般財団法人日本ALS協会のALS研究奨励金、および公益信託「生命の彩」ALS研究助成基金、日本学術振興会(JSPS)の科研費の支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 407KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 407KB]をご覧下さい。
(2017/1/4)
体の一日を刻むタイマー機構を発見
~ 遺伝子導入マウス個体高速作成法を用いた概日時計周期長制御の解明 ~
理化学研究所(理研)生命システム研究センター合成生物学研究グループの上田泰己グループディレクター、大出晃士客員研究員、鵜飼英樹上級研究員、洲﨑悦生客員研究員らの共同研究グループは、さまざまな遺伝子改変マウスを並列的に作製する手法を確立し、「クリプトクロム1(CRY1)」と呼ばれるタンパク質の特定の領域がリン酸化によって制御されることが「概日時計」の周期の長さ(周期長)を決めるために重要であることを発見しました。
私たちが夜眠りにつき朝目覚めるように、地球上の生物の多くは24時間周期のリズムを持って行動しています。こうした行動リズムは、概日時計と呼ばれる全身の細胞が持つ時計機能によって生み出されます。しかし、周期長がなぜ24時間なのかは、不明な点が多く残されています。
今回、共同研究グループはさまざまに機能を変化させたタンパク質を持つ遺伝子改変マウスを効率よく作製する新しい手法「遺伝子導入マウス個体高速作製法」を確立しました。そしてこの手法により、概日時計機能を失ったマウスに、さまざまに機能を変化させたタンパク質をコードする遺伝子を導入し、概日時計機能を補完することが可能となりました。その結果、概日時計を動かすために重要な働きをするCRY1タンパク質の特定の領域がタイマーのように働き、マウスの周期長を決定していることを発見しました。このタイマー領域は、生体内でタンパク質機能の制御によく用いられるリン酸化と呼ばれる化学修飾(リン酸化修飾)を受けていることから、タンパク質内のリン酸化修飾が巧みに時間を数えることで、正確に24時間の周期を刻む可能性が強く示唆されました。
今後、このタイマー領域のリン酸化を薬物で制御することができれば、概日時計の周期長を効率的にコントロールし、概日リズム睡眠障害等の効果的な治療につながると期待できます。
また、遺伝子導入マウス個体高速作製法を用いると、全身の細胞が遺伝子改変されたマウスをこれまで1年以上かけて作製していたのを数カ月で作製できようになります。そのため、この手法により遺伝子改変マウスを用いる多くの研究が加速すると期待できます。
本成果は米国の科学雑誌『Molecular Cell』(1月5日号)に掲載されるのに先立ち、オンライン版(12月22日付け:日本時間12月23日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 873KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 873KB]をご覧下さい。
(2016/12/26)
神経ストレスが胃がんの進行を加速させるメカニズムを解明、新たな治療標的に
人間の神経細胞は脳だけでなく全身に分布しており、中でも胃腸には1億個以上のさまざまな神経細胞が存在し、胃腸の動きや消化ホルモンの分泌を調節しています。 以前から神経ストレスががんやさまざまな病気の原因になる可能性は指摘されていましたが、その理由や重要性についてはよく分かっていませんでした。 今回、東京大学医学部附属病院消化器内科の早河翼助教、小池和彦教授らは、米国コロンビア大学などと共同で、胃がんの発育と神経ストレスの密接な関連とそのメカニズムを明らかにしました。 早河助教らはマウスの胃がん組織を詳しく観察し、胃がんが進行する過程で、がん細胞が「神経成長因子」と呼ばれるホルモンを産生し、これに反応した神経細胞ががん組織に集まり、そこからの強いストレス刺激を受けることで、胃がんの成長が加速していくことを世界で初めて明らかにしました。 この「神経成長因子」を抑える薬や、神経ストレスを放出する細胞を除去することで、胃がんの進行を抑えることができました。 がん細胞の増殖を直接抑える従来の抗がん剤に加えて神経細胞との相互作用を抑える薬剤を使うことで、胃がんに対する効果を高めて未来の治療に応用できると考えられます。 実際、神経成長因子を標的にした薬剤はすでに臨床試験や実際の臨床でさまざまな疾患に使用されており、胃がんに対しても早期の臨床応用が期待されます。
本研究成果は、日本時間12月16日に米国のがん研究に関する学術誌「Cancer Cell」オンライン版にて発表されました。
なお、本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)次世代がん医療創生研究事業(P-CREATE)、中山がん研究所消化器疾患研究助成金などの支援を得て行われました。
![]() リリース文書[PDF:380KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:380KB](東大病院HP掲載)
(2016/12/16)
微弱なノイズ電流により、高齢者の体のバランスが持続的に改善する
内耳に存在する前庭器官は身体のバランスを保つのに重要な役割を果たしており、前庭の働きが悪くなると身体のバランスが悪くなります。 高齢者の前庭障害は、従来の治療では改善しないことが多く、有効な治療法がありません。
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科の藤本千里助教、岩﨑真一准教授、山岨達也教授らの研究グループはこれまでに、耳の後ろに装着した電極より微弱なノイズ電流を加える、経皮的ノイズ前庭電気刺激(nGVS)により、健常者と両側前庭障害を有する患者において、身体のバランスが著明に改善することを明らかにしました。 ただこれまでの研究は、短い時間(30秒間)の刺激中の改善が示されただけであり、長期的な改善の有無については明らかではありませんでした。
本研究では、高齢な健常者に30分間nGVSを加えたところ、刺激を停止した後も数時間にわたり身体のバランスが安定化する、という新しい現象をとらえました。 この研究成果は、常に電流の刺激をしなくても身体のバランスが持続的に改善することを示し、治療への応用に有効であると考えられます。
本研究グループは今後、nGVSの両側の前庭障害を有する患者に対する長期的なバランス改善効果を証明する試験を行う予定であり、その効果が証明できれば、nGVSが両側前庭障害によるバランス障害に対する、世界初の科学的信頼性の高い治療法となるものと期待されます。
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の「障害者対策総合研究開発事業」の支援によって行われたものであり、日本時間11月21日にScientific Reportsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:272KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:272KB](東大病院HP掲載)
(2016/11/22)
NF-κB シグナルは軟骨細胞を両面的に制御する
東京大学大学院医学系研究科整形外科学の小林寛助教、齋藤琢講師らは、軟骨細胞を制御する新たな分子メカニズムを明らかにしました。 齋藤琢講師らは以前、転写因子HIF-2αが変形性関節症を促進すること、さらにHIF-2αがNF-κBシグナルによって誘導されることを報告しましたが(Nature Medicine. 16:678-86, 2010)、NF-κBシグナルの軟骨での作用は不明であったことから、NF-κBシグナルの主要な転写因子Rela/p65に焦点をあてた研究を行いました。
軟骨細胞でRelaを完全にノックアウトしたマウスでは、アポトーシスが亢進して軟骨細胞が減少し、変形性関節症が進みましたが、Relaのノックアウトを半分にしたマウスでは逆に変形性関節症が抑えられ、HIF-2αなどの軟骨を変性させる分子が減少していました。 NF-κBシグナルの活性が低いとRelaは抗アポトーシス分子を誘導することで軟骨細胞を保護しますが、NF-κBシグナルの活性が高くなるとRelaはHIF-2αなどを強く誘導して関節軟骨を変性させることが分かりました。 NF-κBシグナルの活性が軟骨の状態に強く影響することから、その活性の制御が変形性関節症の予防・治療に繋がると期待されます。本研究成果は、日本時間11月10日にNature Communicationsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:0.97KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:0.97KB](東大病院HP掲載)
(2016/11/11)
生きた細胞内のグルタチオンを可視化し、定量する
~ がん治療研究や創薬研究への応用に期待 ~
グルタチオンは、主に活性酸素・酸化ストレスの除去や異物(薬剤など)の排出を担う、いわば“細胞が生き延びるための防御物質”として働きます。 がん細胞はグルタチオン濃度を高く保っているといわれており、そのため放射線治療や抗がん剤に対して高い耐性をもち、治療効果が弱まってしまうことが示唆されています。 従って、細胞内のグルタチオン濃度やその増減を“生きたまま”測ることは、がんの治療研究や創薬研究に不可欠です。 しかし従来法では、細胞を破砕しないと測れないなどの制約があり、実現が困難でした。
東京大学大学院薬学系研究科/医学系研究科 (兼担)の浦野泰照教授、同医学系研究科の神谷真子講師らの研究グループは、グルタチオンに対して可逆的に反応し、グルタチオン濃度に応じて蛍光強度や蛍光波長が変化する新しい蛍光プローブの開発に成功しました。 これを生きた細胞に適応することで、生きた細胞(正常細胞やがん細胞)内のグルタチオン濃度の定量、正常細胞とがん細胞のグルタチオン濃度の違いや酸化ストレス耐性の違いを初めて可視化しました。 この結果より、本蛍光色素は、がん研究や酸化ストレス分野における基幹的研究から、がん治療や創薬といった医薬研究への貢献が期待されます。
本研究成果は「Nature Chemistry」11月7日(イギリス時間)オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 319KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 319KB]をご覧下さい。
(2016/11/8)
オートファジーの活性を簡便かつ定量的に測定できる新規プローブの開発
~ 生体内のオートファジーの活性も測定可能に ~
オートファジーは細胞内の代表的な分解システムです。 オートファジーの分子機構、生理機能、疾患との関連については近年急速に研究が進んでいます。 しかし一方で、オートファジーの活性を定量的に評価することは容易ではなく、未だに十分確立された方法がありません。
このたび、東京大学大学院医学系研究科の貝塚剛志特任研究員、森下英晃助教、水島昇教授らの研究グループは、オートファジーの活性を簡便かつ定量的に測定できる新規プローブを開発しました。 このプローブは培養細胞だけでなくマウスやゼブラフィッシュなどの動物個体内でも利用可能なことが特徴です。 本プローブを用いることで、受精卵や特定の筋肉細胞では高いオートファジー活性を認めることが分かりました。 さらに本法を用いて、株式会社LTTバイオファーマとの共同で、同社が独自に構築した既承認薬ライブラリー(日本とアメリカで市販されている医薬品だけを集めた化合物ライブラリー)を用いてスクリーニングを行い、新規オートファジー誘導薬・阻害薬を同定しました。
今後、本プローブの利用によってオートファジーの基礎的研究や疾患研究が進展することが期待されます。 本研究は日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)などの一環で行われました。
本研究成果は、2016年11月4日に国際科学誌「Molecular Cell」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.07MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.07MB]をご覧下さい。
(2016/11/7)
視覚情報処理を行うための最小の機能単位構造が大脳に存在することを解明
九州大学大学院医学研究院・東京大学大学院医学系研究科の大木研一教授、東京大学大学院医学系研究科の根東覚助教の研究グループは、視覚情報処理を行うための機能的単位構造がマウスの大脳に存在するかどうかを調べました。 大脳は、複雑でかつ大量の情報を逐次処理していますが、これらの情報を素早く正確に行うためにヒトや高等哺乳類には、マクロコラムと呼ばれる単位構造が存在しています。 マウスもヒトと同じように物を見ていると考えられますが、マウスの視覚に関係する大脳には同様なマクロコラムがないことが分かっていました。 今回の研究では、高速かつ3次元に2光子カルシウムイメージングが可能な顕微鏡を開発し、生きたマウスの脳から視覚応答を計測しました。 その結果、マウスの脳には方位選択性と呼ばれる視覚情報に対して、高等哺乳類に見られるコラムよりも小さな「ミニコラム」が存在することを発見しました。 「ミニコラム」は最小の機能単位構造と考えられ、哺乳類に共通な視覚情報処理のメカニズムの解明につながることが期待されます。
本研究結果は2016年10月21日(金)午前10時(英国時間)に「Nature Communications」にオンライン発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 248KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 248KB]をご覧下さい。
(2016/10/24)
オートファゴソームの内膜分解を促進するメカニズムを哺乳類細胞で発見
~ オートファジー分解機構の解明の糸口となるか? ~
オートファジーは代表的な細胞質分解システムです。 オートファジーが誘導されると、オートファゴソームと呼ばれる二重膜構造体が細胞質の一部を取り囲みます。 その後、オートファゴソームの外膜にリソソームが融合すると、オートファゴソームの内膜とともに内容物が分解されます。 オートファジーの前期過程にあたるオートファゴソーム形成については詳しく調べられており、約20種類のオートファジー関連タンパク質群(ATGタンパク質群)が必要であることが酵母や哺乳類で知られています。 一方、オートファゴソームの成熟、リソソームとの融合、オートファゴソームの内膜と内容物の分解といったオートファジーの後期過程についてはまだ多くのことがわかっていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、オートファゴソームの内膜分解を可視化することに初めて成功しました。 次に、ATG結合系と呼ばれる一連の修飾反応に関わるタンパク質群が、オートファゴソームの形成やオートファゴソームとリソソームの融合には必ずしも必須ではなく、その後におこるオートファゴソーム内膜の効率的分解に必要であることを明らかにしました。 オートファゴソーム形態の解析から、ATG結合系はオートファゴソームの閉鎖に必要であることが示唆され、閉鎖による外膜と内膜の切り離しがオートファゴソーム内膜の効率的分解に必要であると考えられました。 本発見は、オートファジーの分解機構の解明の大きな糸口になることが期待されます。
本研究は日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)などの一環で行われました。
本研究は東京医科歯科大学医歯学研究支援センター 酒巻有里子氏、順天堂大学医学研究科神経機能構造学講座 小池正人教授との共同研究で行われました。
本研究成果は、2016年10月20日に国際科学誌「Science」でオンラインFirst releaseにて公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 332KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 332KB]をご覧下さい。
(2016/10/21)
ネコに腎不全が多発する原因を究明
~ ネコではAIMが急性腎不全治癒に機能していない ~
少子化や人口の老齢化も一因となり、愛玩動物(ペット)の数は近年急激に増加している。 特にネコの保有率は、日本やアメリカを含む多くの地域で犬を抜いて第一位となり、現在日本では1千万頭を超えている。 興味深いことに、ネコは腎不全が原因で死亡する率が、他の動物に比べて突出して高いことが以前から知られていた。
腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として排泄する重要な器官であり、腎臓の機能が低下すると、血液中に老廃物が溜まり、身体の色々な臓器の働きに支障をきたす。 色々な原因により腎臓が障害され、急速に腎機能が低下する状況を急性腎障害というが、ネコでは5-6歳頃に尿管結石や腎炎などによる急性腎障害に罹った後、腎機能が完全に回復しないまま慢性腎不全、尿毒症となり15歳前後でなくなるケースが多い。 しかしながら、これまでなぜネコで腎機能が回復せず、最終的に致死性の腎不全に至ってしまうのかは謎であり、そのために腎不全に対する確かな治療法もなかった。
最近、東京大学大学院医学系研究科の宮崎徹教授らの研究グループは、自ら発見したタンパク質AIMが、直接腎臓に働きかけ急性腎障害を治癒させることを明らかにし、Nature Medicine誌に発表した。 急性腎不全が生じると、腎臓の中の尿の通り道(尿細管という)に“ゴミ”(細胞の死骸)が詰まり、そのことが腎機能の低下を招く引き金となることが知られているが、腎臓の機能が低下すると、通常血液中に存在するAIMが活性化し、尿中に移行してゴミを掃除する役目を果たす。 それにより迅速に尿細管の詰まりが解消され、その結果、腎機能は速やかに改善することを明らかにしていた。
今回本研究グループは、ネコのAIMはマウスやヒトのAIMと異なる特徴を持ち、急性腎障害が生じても活性化せず尿中に移行もしないことを見出した。 したがって、ネコは血液中にAIMをじゅうぶん持っているにもかかわらず、急性腎障害が生じても腎臓の機能は回復せず、そのまま慢性腎不全へと進行してしまう可能性が高いことが明らかになった。
それをより詳細に確かめるために、AIMをマウス型からネコ型に変えたマウス(AIMネコ化マウス)を作製し急性腎障害を起こした。 すると予想通り、尿細管中に詰まったゴミは掃除されることなく、腎臓の機能は著しく悪化し続け多くが死んでしまう。 そして急性腎障害を起こしたAIMネコ化マウスに、マウスのAIMを静脈注射することで、尿細管の詰まりは劇的に解消され、腎機能が速やかに改善し致死率は著しく低下することを見出した(注:致死率は100%であったものが、AIM投与により20%となった)。 すなわちネコの場合も、ヒトやマウスの場合(文献6)と同じようにAIMを投与することで急性腎不全を速やかに改善させ、慢性化する危険を回避することが可能であると考えられる。
本研究結果により、これまで謎であったネコの腎不全の原因の解明が大きく進み、AIMにより急性腎障害から良好に回復させうる可能性が示された。 また、急性腎障害を治癒した後も、定期的にAIMを投与し腎臓のゴミを掃除することにより、慢性化のリスクを低下させ、ネコの健康寿命を大きく延長できる可能性がある。 さらに本研究成果は、前回の論文と合わせ、ヒト患者においても、AIMによる急性腎不全の治療や慢性化の予防への期待と現実性をさらに高めるものであると考えられる。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)の研究開発領域「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」(研究開発総括:永井 良三)における研究開発課題「生体内の異物・不要物排除機構の解明とその制御による疾患治療」(研究開発代表者:宮崎 徹)の一環で行われた。 なお、本研究開発領域は、平成27年4月の日本医療研究開発機構の発足に伴い、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)より移管されている。
本研究成果は、2016年10月12日(英国夏時間)に「Scientific Reports」オンライン版で公開された。
※詳細は![]() こちら[PDF: 415KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 415KB]をご覧下さい。
(2016/10/13)
臨床研究・治験の質の向上を目指し、産学官で生物統計家を育成
~ 生物統計家の人材育成拠点として2大学院を選定 ~
質の高い臨床研究・治験を実施するためには、生物統計家がその初期段階から最終段階まで関与することが重要ですが、生物統計家の人材不足という問題があります。 実務家としての生物統計家を育成し臨床研究実施機関に送り出すことは喫緊の課題です。
このたびAMEDは、製薬業界の協力のもと、生物統計家を育成することを目的として、「東京大学大学院」と「京都大学大学院」を各々核とする2つの育成拠点として選定しました。 各大学院は「生物統計講座」を新たに設置し、連携病院とともに育成拠点を形成しOJT研修も行います。
本事業は、製薬企業からの寄附金と国の研究資金を基として、産学官が一体となって臨床研究・治験の質の向上に繋げる環境整備事業であり、このような資金の流れの産学官共同プロジェクトは日本で初めての取り組みです。
※詳細は![]() こちら[PDF: 303KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 303KB]をご覧下さい。
(2016/10/4)
NASH(ナッシュ:非アルコール性脂肪肝炎)治療アプリの臨床研究を開始
このたび、東京大学医学部附属病院 消化器内科の佐藤雅哉特任臨床医、建石良介特任講師、小池和彦教授らのグループと株式会社キュア・アップが共同で開発したNASH専用の治療アプリの臨床研究を開始します。 NASHは肝硬変や肝癌に進行することが知られており、将来的にNASHを基盤とした肝癌の増加が懸念されております。 肥満を背景に発症するNASHは国内に200万人程度(予備軍は推定1000万人程度)存在すると考えられておりますが、現状確立された治療法がなく、減量のための栄養指導や医師からの運動の励行など個々の施設の取り組みにとどまっています。 また、外来受診時の限られた時間で患者に適切な行動療法を行うことは現実的に困難です。 そこで、個々の患者に最適化された診療ガイダンスを外来受診時以外もアプリが継続的に行うことで、患者と医療従事者双方の負担を著しく増やすことなく効果が得られれば、NASHに対する有望な治療法になると期待されます。 また、患者の認知と行動の改善を通じた減量による治療が達成されれば、NASHにより生じる肝硬変や肝癌のみでなく、肥満がリスクとなり生じる他の疾患の予防にもつながり、日本の医療費削減への貢献も期待されます。
なお、本アプリの開発は、新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)研究開発型ベンチャー支援事業/シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援により行われたものです。
![]() リリース文書[PDF:204KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:204KB](東大病院HP掲載)
(2016/9/30)
細胞内リサイクルシステム“オートファジー”を起こせないマウスの新生仔死因を解明
~ 新しいマウスモデル作製により全身解析が可能に ~
細胞の中では、生体成分が常にリサイクルされています。 この細胞内リサイクルを担う仕組みの一つがオートファジーです。 東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、オートファジーを起こすことができない遺伝子改変マウスを作製し、このマウスが生後約12時間で死亡することを報告しています。 しかし、その死因は長らく不明でした。 今回、新生仔死亡の原因として神経異常による吸啜障害を疑い、全身でオートファジーをおこせない遺伝子改変マウスの神経細胞でのみオートファジーを回復させたマウスを作製しました。
その結果、従来、新生仔死亡であったオートファジー遺伝子改変マウスが成獣まで生存できるようになりました。 よって、オートファジー遺伝子改変マウスの死因は、神経異常にあることがわかりました。 また、全身におけるオートファジー不全の影響を成獣で調べることが可能となりました。 全身観察の結果、このマウスは鉄吸収不全による貧血や性ホルモン低下を伴う性腺委縮を呈することが分かりました。 この新しいマウスモデルの解析から得られた知見は、今後、オートファジーの生理機能の理解に役立つことが期待されます。
本研究成果は、Developmental Cell (2016年9月29日オンライン版)へ掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 293KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 293KB]をご覧下さい。
(2016/9/30)
反復配列RNA の異常発現が膵癌発生を促進するメカニズムを解明
膵癌は抗癌治療の発展した現在においても予後不良であり、難治癌の代表的存在として知られています。 この発癌の過程において、単純な配列の繰り返しで構成される反復配列RNAと呼ばれるタンパク質情報を持たないRNA(ノンコーディングRNA)が、癌になる前段階から異常に発現していることが明らかになってきました。 東京大学医学部附属病院 消化器内科の岸川孝弘 特任臨床医、大塚基之 助教(特任講師(病院))、小池和彦 教授らの研究グループは、マウスの膵臓の良性腫瘍から樹立した細胞を用いて研究を行い、これまで機能を持たないと考えられてきた反復配列RNAの一種であるMajSAT RNAが、ゲノムやミトコンドリアのDNAの突然変異を蓄積させることで、細胞を癌化させることを見出しました。 さらに、その機序として、MajSAT RNAがYBX1というタンパク質と結合してその細胞内局在を変化させることで、正常なDNAダメージ修復機能を阻害して、突然変異の蓄積を促進させていることを示しました。
これらの結果は、癌化の過程の早期から、反復配列RNAが いわば「細胞内変異原」として機能し、発癌プロセスを進める機構として重大な働きをしていることを示唆しており、発癌機序の解明、発癌予防という観点からも重要な成果であるといえます。 本研究成果は、日本時間9月26日にNature Communicationsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:280KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:280KB](東大病院HP掲載)
(2016/9/28)
細胞外情報を集積・統合し、適切な転写応答へと変換する細胞内「ロジックボード」分子の発見
多細胞生物の形成ならびに個体維持には、「形態形成シグナル経路」という細胞内シグナル伝達経路群が重要な役割を担っています。 しかしながら、2種類以上の異なる形態形成シグナルが細胞の中でどのような仕組みにより統合・処理され、適切な遺伝子発現ならびに細胞機能の調節がなされるのかはこれまで不明でした。
東京大学大学院医学系研究科の畠山昌則教授らの研究グループは、核内に局在するタンパク質「parafibromin」が主要な形態形成シグナル経路群の転写共役因子と協調的あるいは拮抗的に複合体を形成することで、適切な遺伝子セットの選択的な転写応答を制御していることを世界で初めて明らかにしました。 parafibrominは細胞が受け取った複数のシグナルの入力を細胞内で統合し、適切な出力へと変換するコンピューターの「ロジックボード」のような機能を持つ重要な分子であると考えられます。 形態形成シグナル経路の異常は消化器がんをはじめとするヒトのがん発症に深く結びついていることから、本研究の成果はそれらのがんに対する新たな治療法ならびに予防法の開発につながるものと期待されます。
本研究成果は、Nature Communicationsへ掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 549KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 549KB]をご覧下さい。
(2016/9/26)
糖尿病診療の質を大規模レセプトデータで評価
~ ガイドラインで推奨される年1回の網膜症検査実施率は36% ~
糖尿病は失明や人工透析導入の原因の上位を占めるため、糖尿病の適切な診療および合併症の予防は喫緊の課題になっています。 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の小林廉毅教授と田中宏和(大学院生)らの研究グループは、レセプト(診療報酬請求明細書)データベースを用い、診療行為や受診頻度、糖尿病治療薬の処方などの記録を用いてデータの精度を高めて分析することで、これまでにない大規模かつ高い精度で糖尿病診療のプロセス評価を行うことを可能としました。
この研究の結果、組合管掌健康保険に加入し、2010年度に糖尿病治療薬の処方を受け、定期受診していた糖尿病患者7,464人において、翌年度のHbA1c検査や血中脂質検査の実施率は90%以上と高かったものの、日本糖尿病学会による糖尿病診療ガイドラインで推奨される年1回以上の糖尿病網膜症の検査を受けた者の割合は35.6%と低かったことが明らかになりました。 この割合は欧米の同様の報告に比べても低い数値です。また、治療を中断した患者の割合は6.4%でした。
糖尿病患者が継続して糖尿病診療を受け続けられるための取り組み(受診勧奨)が行われていますが、糖尿病診療の質の向上には糖尿病患者への受診勧奨だけでなく、勤労層が受診しやすい環境の整備、診療ガイドラインの普及、糖尿病を診療する医師と眼科医との連携推進などが重要であると考えられます。
本研究はBMJ(英国医師会雑誌)とアメリカ糖尿病学会が共同で発行する国際医学雑誌 "BMJ Open Diabetes Research & Care" に2016年9月9日付けで掲載されました。 なお、本研究は同誌の"Editor's Choice"にも取り上げられました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 271KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 271KB]をご覧下さい。
(2016/9/15)
成熟した神経回路を維持する仕組みを解明
~ 自閉症の病態解明に期待 ~
『三つ子の魂百まで』と言われるように、発達期の経験に応じて獲得された神経回路は大人になっても維持されます。 自閉症のモデル動物では成熟した神経回路が正しく維持されないことが報告されていましたが、神経回路を維持する仕組みは謎に包まれていました。
東京女子医科大学 医学部 生理学(第一)講座の鳴島(行本)円准講師、宮田麻理子教授・講座主任、東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 生理学講座 神経生理学分野 狩野方伸教授らの研究グループは、視覚をつかさどる神経回路の発達過程を調べることで、代謝型グルタミン酸受容体1型(mGluR1)が成熟した神経回路の維持に必須であることを証明しました。
今後は神経回路を維持する仕組みが脳の機能に果たす普遍的な役割を明らかにすることで、自閉症や脳機能障害の病態理解につなげていきます。
本研究成果は、Neuron 8月18日オンライン版へ掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.16MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.16MB]をご覧下さい。
(2016/8/18)
脳内マリファナがてんかんを抑えるしくみを解明
マリファナに含まれる精神作用物質(カンナビノイド)は脳内のカンナビノイド受容体と呼ばれる蛋白質に作用する。 しかし、もともと脳の中にはカンナビノイド受容体に作用する物質が存在し、シナプス伝達を調節するなどの生理機能を営んでいる。 このような脳内のマリファナ類似物質を“内因性カンナビノイド”と呼んでいる。
今回、東京大学大学院医学系研究科の狩野方伸教授らの研究グループは、主要な内因性カンナビノイドである2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)がてんかんの症状であるけいれん発作を強力に抑制していることを明らかにした。 遺伝子操作によって2-AGを作ることができないようにしたマウスでけいれん発作を誘発すると、野生型のマウスに比べて重篤なけいれん発作が観察された。さらに、 2-AGが合成できないマウスではてんかんを発症するまでの時間が短くなっていた。 これらの結果は2-AGがけいれん発作だけでなく、てんかんの発症を抑える効果をもつことを示唆している。
マウスで見出された本研究の成果は、てんかんの病態の解明と新しい治療法につながる可能性がある。 本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」(平成27年度に文部科学省より移管)および科学研究費補助金の助成を受けて行われた。
本研究成果は、『Cell Reports』7/21オンライン版へ掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 342KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 342KB]をご覧下さい。
(2016/7/22)
化学の力で見たい細胞だけを光らせる
~ 遺伝学・脳科学に有用な画期的技術の開発 ~
レポーター遺伝子とは、目的遺伝子の発現、またその発現部位を容易に判別するために、目的遺伝子に組み換える別の遺伝子のことです。 LacZは最も汎用されているレポーター遺伝子の一つで、LacZを導入された細胞は細胞内でβ-ガラクトシダーゼという酵素を発現します。 これまで、LacZ発現細胞の染色には、β-ガラクトシダーゼと反応して青い色素を生成するX-Galという発色基質が使用されてきましたが、発色には固定処理が必要であり、LacZ発現細胞を生かしたまま可視化することはできませんでした。 また、β-ガラクトシダーゼの酵素活性によって蛍光性になる蛍光プローブも開発されてきましたが、細胞膜を透過しない、酵素反応生成物が細胞外に漏出するといった問題があり、LacZ発現細胞のみを生きたまま検出・特定することは困難でした。
東京大学大学院薬学系研究科/医学系研究科(兼担)浦野泰照教授らの研究グループは、β-ガラクトシダーゼとの酵素反応によって蛍光性になると同時に細胞内のさまざまな分子に結合する蛍光プローブの開発に成功しました。 開発した蛍光プローブを用いることで、LacZ発現細胞の1細胞レベルでの蛍光検出が可能であること、また蛍光検出したLacZ発現細胞における電気生理学実験にも成功しました。 本蛍光プローブを用いることで、今後、これまで困難であったさまざまな生命現象の解明に役立つことが期待できます。
本研究成果は、「Angewandte Chemie International Edition」(7月8日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 260KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 260KB]をご覧下さい。
(2016/7/11)
経口AMPA受容体拮抗剤による筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療法確立
~ 孤発性ALS分子病態モデルマウスへの長期投与試験 ~
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は主に中高年に発症する、進行性の筋力低下や筋萎縮を特徴とし、健康人を数年の内に呼吸筋麻痺により死に至らしめる神経難病で、この経過を遅らせる有効な治療法はありません。 これまで、国際医療福祉大学臨床医学研究センター 郭伸特任教授(東京大学大学院医学系研究科 講師)らの研究グループは、ADAR2という酵素が低下することで、過剰な細胞内カルシウム流入を引き起こすことによりALSの大多数を占める遺伝性のない孤発性ALSの運動ニューロン死に関与していることを突き止めていました。
今回、郭伸特任教授と東京大学大学院医学系研究科赤松恵特任研究員らの研究グループは、この過剰なカルシウム流入を抑える作用が期待される、既存の抗てんかん薬であるペランパネル(製品名「フィコンパ」エーザイ株式会社)をALSモデルマウスに90日間連続で経口投与したところ運動機能低下の進行、及びその原因となる運動ニューロンの変性脱落が食い止められ、しかも、運動ニューロンで引き起こされているALSに特異的なTDP-43タンパクの細胞内局在の異常(TDP-43病理)が回復・正常化しました。 また、発症前のみならず発症後に投与した場合でも、運動ニューロン死による症状の進行が抑えられました。
モデルマウスでの結果ではありますが、ペランパネルは既に承認されているてんかん治療薬であり、ヒトに換算した場合にてんかん治療に要する用量以下でマウスに有効性が確認出来たことから、臨床応用へのハードルも低いと考えられ、ALSの特異的治療法になるものと期待されます。
以上の成果は、「Scientific Reports」(6月28日オンライン版)に掲載されました。
なお、本研究は一般財団法人日本ALS協会の「IBCグラント」研究奨励金、および公益財団法人難病医学研究財団研究奨励助成金、日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 385KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 385KB]をご覧下さい。
(2016/6/29)
骨が免疫力を高める
~ 感染から体を守るためには骨を作る細胞が重要 ~
敗血症は細菌感染により引き起こされる全身に及ぶ炎症状態です。 発症早期には体を守るために免疫細胞から炎症性サイトカインが大量に放出されますが、その時期を過ぎると新たな感染症にかかりやすくなります。 その原因として、末梢血中の一部の免疫細胞が減少するため免疫力低下により感染しやすい状態が長期間続くことが考えられます。 従って、発症早期の治療に加えて、発症後の免疫力低下のメカニズムを解明し、新たな治療法を開発することで、生存率の大幅な改善が期待できます。
このたび、東京大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学分野の寺島 明日香研究員(当時)と、岡本 一男助教(当時)、高柳 広教授らの研究グループは、敗血症のモデルマウスを用いて、急性炎症反応によって免疫抑制状態が生じるメカニズムを検討しました。 その結果、敗血症モデルマウスでは急激に骨量が減少しており、骨髄におけるリンパ球の初期分化が障害されていることを見出しました。 骨を作る役割を持つ骨芽細胞は、免疫細胞分化に重要なサイトカインIL-7を産生し、T細胞やB細胞のもととなるリンパ球共通前駆細胞を維持することが分かりました。 敗血症では、感染症の防御に重要なリンパ球を維持する骨芽細胞が減少するため、免疫力低下につながると考えられます。
本研究は日本学術振興会 科学研究費補助金、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業「高柳オステオネットワークプロジェクト」(研究総括:高柳 広)などの一環で行なわれました。
本研究成果は2016年6月14日(米国東部夏時間)に国際科学誌「Immunity」オンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 415KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 415KB]をご覧下さい。
(2016/6/15)
膵癌の早期診断に役立つ血中の反復配列RNA の高感度測定法を開発
日本でも罹患数が増え続けている膵癌は、早期診断が現状では困難で高度進行状態で見つかることの多い難治性癌の代表です。 このため、膵癌の早期発見を可能にする、検診レベルで導入できるバイオマーカーの開発が急がれています。 東京大学医学部附属病院 消化器内科の岸川孝弘 特任臨床医、大塚基之 助教(特任講師(病院))、小池和彦 教授は、膵癌組織中で多量に発現していることがマサチューセッツ総合病院の研究グループから以前に報告されたものの、簡便な定量が困難であったHSATII RNAと呼ばれる反復配列RNAを、血清から簡便かつ高感度に測定する方法を世界で初めて開発しました。 患者血清を用いた検討により、本方法を用いた血中HSATII RNA の測定は、膵癌患者の早期診断だけでなく前癌病態の囲い込みにも有用である可能性が示されました。 本成果は、今後 さらに多数の検体での検証を重ねることにより、採血による膵癌の簡便な早期診断・前癌病態の囲い込みの実現に道を開く、極めて重要な成果といえます。
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」、日本学術振興会・科学研究費補助金、国際科学技術振興財団などの支援によって行われたものであり、日本時間6月2日に米国科学雑誌JCI Insight にて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:320KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:320KB](東大病院HP掲載)
(2016/6/3)
転写因子STAT3を介した子宮内膜の再構築と子宮の再生の仕組み
~ マウス子宮の脱細胞組織移植モデルの新規確立 ~
子宮では、月経や分娩のあとに次の妊娠に向けてダイナミックに組織が再構築・再生されますが、この子宮が持つ組織の再生の仕組みや過程はこれまでよくわかっていませんでした。 細胞の周りで細胞を支持したり細胞の足場となって働きを調節したりしている「細胞外基質」を温存したまま細胞だけを破壊する、「脱細胞化」という技術が新たな再生医療技術として最近注目されています。 東京大学医学部附属病院の廣田泰講師らは、摘出したマウス子宮に脱細胞化の処置を行って細胞を取り除いた脱細胞化子宮を作製しました。 次に、あらかじめ子宮を部分切除する処置を行った別のマウスに対して、脱細胞化子宮の組織片を移植する手術を行いました。 脱細胞化子宮組織の移植部位では1か月後に完全に子宮が再生し、移植部位での妊娠が可能になりました。 またこの子宮の再生には転写因子のSTAT3という物質が関与していることが、遺伝子改変マウスを用いた研究で明らかとなりました。 本研究により、子宮の再構築の生理的な仕組みや子宮再生の応用研究に役立つ新しい動物モデルを確立しました。 この脱細胞化技術は、将来的には子宮の異常で起こる不妊症の新しい治療へ応用されることが期待されます。
![]() リリース文書[PDF:1.38MB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:1.38MB](東大病院HP掲載)
(2016/6/3)
食道癌診断におけるDPP-IV活性検出プローブの有用性
東京大学大学院薬学系研究科・医学系研究科の浦野泰照教授らの研究グループは、癌細胞で活性が上昇している特定のタンパク質分解酵素によって蛍光性へと変化する試薬(蛍光プローブ)を開発し、癌モデル動物でその機能を証明してきました。 しかし、ヒトの癌の性質は極めて多様であり、実際のヒト組織で真に有効であるかどうかはわかりませんでした。 今回、東京大学大学院医学系研究科消化管外科学瀬戸泰之教授らと共同して、食道扁平上皮癌に対して有用な蛍光試薬の開発を行いました。 まず、さまざまな酵素をターゲットとした蛍光試薬のライブラリーを作成し、ヒト生検検体を用いてスクリーニングを行ったところ、DPP-IV活性検出プローブが癌特異性を示すことを明らかにしました。 そこで本プローブを、ヒト外科手術において摘出した検体や内視鏡治療において摘出した検体にスプレーしたところ、わずか数分で食道癌を選択的に光らせ、周囲の正常組織と識別できることを明らかにしました。 食道癌は、通常の内視鏡観察では早期発見が困難であることが知られており、本手法の活用によって早期食道癌の診断率の向上が期待できます。 現在、本蛍光試薬の臨床医薬品としての市販を目指し、プローブの有用性を更に多数の症例で実証するとともに、体内使用を目指して、東京大学エッジキャピタル(UTEC)からの投資を受けた五稜化薬株式会社と共同で臨床試験の適用に向けた準備を進めています。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく革新的医療基盤技術の創出」研究開発領域(研究開発総括:清水孝雄)における研究開発課題「臨床検体を用いた疾患部位特異的な代謝活性のライブイメージング探索技法の確立と創薬への応用」(研究開発代表者:浦野泰照)の一環で行われました。 なお、本研究開発領域は、平成27年4月の日本医療研究開発機構の発足に伴い、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)より移管されたものです。
![]() リリース文書[PDF:1.00MB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:1.00MB](東大病院HP掲載)
(2016/6/3)
痛みを支えるKIF分子モーター
全45種類以上のKIF分子モーターはヒトのすべての細胞内において、ミクロの貨物列車のような細胞内物質輸送の鍵を担っている機能分子ですが、その機能的意義はまだ少ししかわかっていません。 今回、東京大学大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授、田中庸介助手らの研究グループは、分子モーターKIF1Aの遺伝子機能を半分失ったマウスを作出し、その表現型を調べたところ、熱さ・痛みの感覚に進行性の障害があることがわかりました。 さらにその詳細な分子機構として、KIF1Aが末梢の一次感覚ニューロンの軸索末端へと神経栄養因子受容体TrkAの載ったオルガネラを輸送することで、感覚ニューロンの生存率ならびに炎症の際に特に問題となる神経栄養因子依存性の疼痛増強メカニズムを統御しているというメカニズムを発見しました。 このことは、生命の根源的な機能を担うKIF分子モーターの一次感覚ニューロンにおける新しい生理機能・臨床的意義をはじめて解明するとともに、受容体型チロシンキナーゼのシグナル伝達制御の観点から、疼痛制御等の分野における新たな創薬ターゲットとしてのKIF系の可能性を拓くものです。
本研究成果は、「Neuron」(6月2日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 314KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 314KB]をご覧下さい。
(2016/6/3)
脳の神経活動の空間パターンは脳血流のパターンに写し取られる
~ 安静時脳活動の詳細な時空間構造を神経発火と脳血流の両面から解明 ~
九州大学大学院医学研究院・東京大学大学院医学系研究科の大木研一教授、東京大学大学院医学系研究科の松井鉄平助教、九州大学大学院医学研究院の村上知成博士課程3年生らの研究グループは、安静時における脳活動の詳細な時空間構造、更にそれが脳血流に変換される様子を観察することに成功しました。 行動していない状態の動物で自発的に起きる安静時脳活動は、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)により脳血流信号でも観察できるため近年活発に研究され、脳疾患診断などへの応用が期待されています。 これまで、安静時における神経活動の詳細や、それがどのように脳血流信号に変換されているのかは不明でした。 今回の研究では、神経活動を可視化した遺伝子改変マウスで神経活動と脳血流信号を同時計測するシステムを開発し、安静時脳活動の詳細な時空間パターンと、それが脳血流へ反映される過程を解明しました。 この知見は、安静時脳活動を利用した脳のネットワーク構造の解明や脳疾患診断の技術開発へ繋がることが期待されます。
本研究結果は2016年5月16日(月)午後3時(米国東部時間)に「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」にオンライン発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 511KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 511KB]をご覧下さい。
(2016/5/17)
不整脈と生活習慣病の関連性を解析する臨床研究を開始
~ 脈の揺らぎを自己管理するスマホアプリを公開 ~
このたび、東京大学と株式会社NTTドコモとの社会連携講座として設置された東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター健康空間情報学講座では、Apple社のResearchKitを用いて、脈の揺らぎを管理・記録するスマホアプリ「HearTily(ハーティリー)」を開発し、成人(20歳以上)を対象に、このアプリを用いた不整脈と生活習慣病の関連性を解析する臨床研究を開始しました。
「HearTily」はスマートフォンのカメラを活用して脈を検知し、脈拍を定期的に収集することによって脈の揺らぎを簡単に測定することができるアプリです。 一般的に初期の不整脈は短い時間しか生じず、また数日に一回しか生じないため、健康診断時の心電図では捉えることが難しいものも多く存在します。
本研究では、参加者に脈の揺らぎを自己管理できるスマホアプリを提供し、日常生活内で1日1回、脈拍を記録していただきます。 継続的に記録していただく脈拍の情報とスマートフォン内に記録される運動量等の生活情報を組み合わせた大規模なデータを解析することによって、不整脈と生活習慣病の関連性を調べることができるので、不整脈の発生を予測することへの応用に役立ててまいります。
![]() リリース文書[PDF:436KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:436KB](東大病院HP掲載)
(2016/4/22)
印刷業で多発した職業性胆管がんと関連する、発がん性候補物質の胆汁排泄を発見
平成24年、塩素系有機洗浄剤を大量に使用してきた印刷工場の従業員がきわめて高頻度で胆管がんを発症していることが報告され、大きな社会問題となりました。 労働環境の調査結果などから、塩素系有機洗浄剤の主成分であったジクロロプロパンという工業用化学物質が原因物質として強く疑われています。 しかしながら、ジクロロプロパンへの大量ばく露と胆管がん発症とをつなぐ分子機序は未解明でした。
東京大学医学部附属病院薬剤部の豊田優 特任助教、高田龍平 講師、鈴木洋史 教授は、質量分析装置を駆使した胆汁の網羅的成分分析や肝臓の大部分がヒト肝細胞に置換されたマウスを用いた実験などから、ジクロロプロパンから生じた発がん性候補物質が胆汁排泄されることを見出しました。 本成果は、塩素系有機溶剤への大量ばく露と職業性胆管がんの発症とを結びつける重要な発見です。 胆管がんの発がん機序が解明されたわけではありませんが、肝臓で生じた反応性代謝物が胆汁中に排泄される結果、胆管での発がんリスクが高まる可能性を新たに提唱するという点で、本報告は将来のがん研究の発展に貢献する重要な成果であると考えられます。
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的がん医療実用化研究事業」、ならびに、日本学術振興会・科学研究費補助金などの支援によって行われたものであり、日本時間4月18日に英国科学雑誌Scientific Reportsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:328KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:328KB](東大病院HP掲載)
(2016/4/20)
自閉症を脳回路から見分ける先端人工知能技術を開発
~ 人種を超えたバイオマーカー・自閉症の実体:脳回路の変位 ~
東京大学医学部附属病院の八幡憲明研究員、笠井清登教授、(株)国際電気通信基礎技術研究所・脳情報通信総合研究所の森本淳室長、川人光男所長、昭和大学発達障害医療研究所の橋本龍一郎客員教授、加藤進昌所長らのグループは、最先端の人工知能技術を開発して、自閉スペクトラム症(ASD)を脳回路から見分けるバイオマーカーを世界に先駆けて発見しました。
本研究成果は4月14日にNature Communications 誌・オンライン版に掲載されました。
詳細は、株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)のホームページをご覧ください。
(2016/4/20)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報