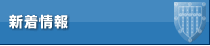広報・プレスリリース情報(2017年(平成29年))
1細胞解像度を有する点描脳アトラスの創出
~ 組織の膨潤および透明化を利用しマウス脳内の全細胞を解析 ~
この度、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻薬理学講座システムズ薬理学分野の上田泰己教授(同大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)及び理化学研究所生命システム研究センター兼任)と村上達哉日本学術振興会特別研究員らの共同研究グループは、新しい全脳膨潤・透明化手法「CUBIC-X」を開発することで、マウス脳の全ての細胞を詳細に観察することを可能とするイメージング技術を確立し、全脳全細胞解析を行うことにより、1細胞解像度でマウスの全脳アトラス(地図)を創出しました。(動画:CUBIC-X によるマウス全脳全細胞の"点描画" )。 この全脳アトラスを用いることにより脳内に存在する全ての細胞を網羅的に分析することが可能となり、1細胞レベルでの脳機能の理解に繋がることが期待されます。 脳は、膨大な数・種類からなる細胞が複雑なネットワークを形成することで、その多様な機能を有することが可能としています。 研究グループは、脳内の全ての細胞を解析する技術基盤を作り上げ、全細胞の位置情報を含む1細胞解像度脳アトラスを作ることで、脳機能を細胞レベルで理解することを目指しました。
研究グループは、約1,650個の化合物の中から組織膨潤と組織透明化を同時に可能とする試薬を同定し、実際に脳組織を膨潤させながら透明にする手法の作成に成功しました。 さらに、シート照明型蛍光顕微鏡により得られた画像から全脳の全細胞を正確に抽出し、まるでジョルジュ・スーラの絵画のような点描で表示されたマウス脳の全細胞アトラスを創出しました。 完成したマウス脳アトラスを用いて、マウス脳に含まれる脳細胞の数を正確に数えるとともに、臨界期の際に大脳皮質視覚野、体性感覚野の第2, 3, 4層で脳細胞数が減少することを発見しました。 また、薬物を導入された際に活動する脳細胞を検出し、脳アトラスに脳細胞の活動情報を書き込むことで、脳細胞の活動パターンを1細胞解像度で解析することを可能にしました。 更なる解析を進めることで、脳の一領域である海馬歯状回顆粒細胞層が機能的に異なる領域を複数有していることを発見しました。
この1細胞解像度マウス脳アトラスは、脳細胞数を数えることや脳細胞の活動情報を書き込むことにとどまらず、遺伝子発現情報や接続様式などさまざまな情報を書き込むことが出来ます。 研究コミュニティに広く利用してもらうことで、脳機能を1細胞レベルで理解し解明することが期待されます。 本研究成果は、英国の科学雑誌『Nature Neuroscience』に掲載されるのに先立ち、オンライン版(3月5日付け:日本時間3月6日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 927KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 927KB]をご覧下さい。
(2018/3/8)
てんかんの新しい発症機構の解明
~ 繰り返し配列の異常伸長によっててんかんが生じることを発見 ~
●てんかんの一つのタイプである、良性成人型家族性ミオクローヌスてんかんの新たな発症機構を解明しました。この疾患は、国が定める指定難病の一つである進行性ミオクローヌスてんかんに含まれる疾患です。
●51家系100名のご協力をいただき、次世代シーケンサーを駆使した研究によってその原因を突き止めました。
●タンパク質を作る情報を持たないイントロンと呼ばれる領域(非コード領域)に、元のゲノム上には存在しない、異常に伸長した新規の5塩基繰り返し配列が挿入されていることが原因となっていることを発見しました。このような配列の変化は、これまで、てんかんでは全く知られていなかった現象です。
●この5塩基の繰り返し配列の異常伸長は、49家系において、SAMD12という遺伝子のイントロン中に生じていることを見出しましたが、2家系では、TNRC6A、RAPGEF2という別の遺伝子に存在することを見出しました。繰り返し配列の繰り返し数は、おおよそ440~3,680回の範囲でした。3つの遺伝子に同じ繰り返し配列の異常伸長が認められることは、このような繰り返し配列の異常伸長そのものが重要で、存在する遺伝子の種類に依存しないことを強く示しています。
●異常伸長したTTTCAという5塩基の繰り返し配列は、RNAとして転写された後、神経細胞内に集積、凝集して、 RNA fociという凝集体を形成していることを見出しました。TTTCA繰り返し配列から転写されて生じるRNA分子が、てんかんの病態を引き起こすと考えられました。
●今までいくつかの疾患でイントロンの繰り返し配列の異常伸長が見いだされてきましたが、てんかんにおいて繰り返し配列を持った異常RNAが病態に関与していることを示した初めての例になります。
●非コード領域の繰り返し配列の異常伸長に伴う疾患は、今後さらに拡大していくと思われます。これまでは、抗てんかん薬を用いた、対症的な治療が行われていましたが、発症機構が判明したことから、その機構に直接介入するような、より効果的な治療法の開発研究が今後大きく発展することが期待されます。また、本研究の成果は、進行性ミオクローヌスてんかんはもとより、様々な原因未解明の疾患の研究に幅広く応用され、発症機構の解明研究、さらには,治療法開発研究に結びつくことが期待されます。
●本研究は日本医療研究開発機構(AMED)「難治性疾患実用化研究事業(課題名:オミックス解析に基づく希少難治性神経疾患の病態解明)」、「臨床ゲノム情報統合データベース整備事業(課題名:希少・難病分野の臨床ゲノム情報統合データベース整備)」の支援により行われました。
●研究成果は、Nature Geneticsオンライン版にて3月6日(日本時間)に発表されました。
![]() リリース文書[PDF:808KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:808KB](東大病院HP掲載)
(2018/3/6)
神経突起の形状を整える巧みなメカニズムの解明
~ 生後の記憶、学習、神経疾患の鍵を握っていたタンパク質(KIF2A) ~
東京大学大学院 医学系研究科の廣川 信隆 特任教授と本間 典子 講師らの研究グループは、サウジアラビアの王立アブダラ大学 先端ゲノム医科学センターのイムラン ナジール准教授、アディール チャウダリー教授、モハマンド アルカタニ教授との共同研究によって、マウスの生後の海馬において、歯状回顆粒細胞に特に多く存在するKIF2Aが、細胞骨格である微小管に働きかけて神経突起の長さと形状を巧みに調節することによって、その突起が将来軸索と樹状突起のどちらになるかを決定づけ、さらには精緻な神経回路の形成と維持に重要な役割を果たしていることを明らかにしました。
KIF2Aは、細胞内骨格の1つである微小管を端から解体して脱重合させることで、その長さを調節するタンパク質です。 KIF2Aは、哺乳類胎児の脳に多く存在し、胎児の神経系が発達する時に、神経細胞の軸索の伸長を抑制し、神経細胞の移動や伸び縮みに重要な働きをすることが知られていました。 このKIF2Aは、近年のマウスを使った他の研究で、神経細胞の新生が生後も長く続くとされる海馬や嗅球で多く見られることから、生後の脳の成長や機能に重要な役割を果たしていると考えられており、さらには、大脳皮質形成異常をもつ一部のヒト乳児において、KIF2Aの遺伝子に異常がみつかったことから、大脳皮質の発達にも関わりがあると注目を集めていました。 しかし、既存のKIF2A欠損マウスは、生後1日で死んでしまうため、生後の機能解析ができずにいました。
そこで今回、研究グループは、タモキシフェンという薬剤を投与すると好きなタイミングでKIF2Aを欠損させられる「条件つきKIF2A欠損マウス」を作成し、生後のいくつかの時期にKIF2Aを欠損させました。 その結果、幼若期にKIF2Aを欠損させたマウスは、過活動やてんかん発作を起こして多くが死亡しました。 KIF2Aが海馬の中でも特に「歯状回顆粒細胞」に多く存在したことから、歯状回に注目して解析を進めたところ、KIF2Aは、歯状回顆粒細胞の突起が適正な長さになると、その伸長を抑制することで、軸索を軸索として、樹状突起を樹状突起として成長させることを明らかにしました。 また、条件付きKIF2A欠損マウスの歯状回には、異常な神経回路ができていて海馬全体が興奮しやすくなっていたことから、歯状回顆粒細胞の神経突起が正常な長さに伸長して適正な軸索や樹状突起に成長することは、正確な神経回路の形成と維持・再編に重要であることが示唆されました。
ヒトの海馬では、歯状回の顆粒細胞のみが、一生を通じて作り続けられており、新生した細胞の突起形成や神経回路の精緻な再構成が、記憶に特に重要と考えられていることから、KIF2Aは、記憶や学習の要となる過程に深く関わっていることが示唆されました。 また、KIF2Aのさらなる機能の研究は、神経系疾患の病態解明・創薬にも応用できる可能性があります。
本研究は文部科学省科研費 (JP18002013,JP23000013,JP16H06372)、およびの王立アブダラ大学の科学技術革命戦略プラン内戦略技術プロジェクト (12-BIO3059-03) と学部長裁量科学研究費 (DSR: 1-6-1432/HiCi)の支援により得られました。 また日本時間2月14日(水)午前2時に「eLife」に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.38MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.38MB]をご覧下さい。
(2018/2/14)
発達期のシナプス刈り込みを調節する分子を発見
~ 前頭側頭型認知症の関連遺伝子グラニュリンの新たな機能の解明 ~
統合失調症や自閉スペクトラム症の病態の根底には、神経回路の発達異常があると考えられています。 生後間もない脳においてシナプスはいったん過剰に形成された後、環境や経験に依存して必要なシナプスは強められて残り、不要なシナプスは除去されます。 この現象は「シナプス刈り込み」と呼ばれており、生後発達期の脳内で普遍的に起こる重要な現象であり、成熟した機能的神経回路を作るために不可欠な過程であると考えられています。 しかし、シナプス刈り込みがどのような仕組みによって起こるかは完全には理解されておらず、とくに必要なシナプスが強められる仕組みはほとんど不明でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の上阪直史助教と狩野方伸教授らの研究グループは、発達期の小脳において、前頭側頭型認知症の関連遺伝子グラニュリンがシナプス刈り込みを調節することを発見しました。
研究グループは発達期のマウス小脳の登上線維とプルキンエ細胞との間のシナプスにみられるシナプス刈り込みに注目しました。 シナプス後部のプルキンエ細胞から放出されたプログラニュリン分子が、シナプス前部の登上線維に存在するSort1受容体に、逆行性シグナルとして働き、特定の登上線維シナプスを強くするとともに、不要なシナプスの除去を遅らせることを明らかにしました。 グラニュリン遺伝子の変異は認知症の一種であるヒト前頭側頭型認知症で見られ、また血中内でのプログラニュリン濃度の減少がヒト自閉スペクトラム症で見られています。 本研究の成果は生後発達期の機能的神経回路形成のメカニズム解明に貢献するとともに、前頭側頭型認知症や自閉スペクトラム症の病態解明につながることが期待されます。
本研究成果は、アメリカ東部標準時間2月1日 午前12時にNeuron誌のウェブサイトに掲載されました。(http://www.cell.com/neuron/home)
本研究は、科学研究費補助金の助成を受けて行われました。また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」および「脳科学研究戦略推進プログラム」の一環として実施されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 282KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 282KB]をご覧下さい。
(2018/2/6)
神経細胞のつながりは積極的に壊される
~ シナプスで放出されるBMP4の新しい役割を解明 ~
東京大学医学系研究科の岡部教授らの研究グループは、これまで注目されてこなかった、シナプスの破壊に直接的に関わる分子に着目し、初期神経発生の過程で重要な役割を持つ分子であるBMP4(骨形成因子4)が記憶や高次認知機能に重要な海馬や大脳皮質のシナプスを除去することを示しました。 BMP4は軸索末端に存在するシナプス前部から放出されますが、その受け手は通常の神経伝達物質の場合の様に樹状突起ではなく、同じ軸索末端側でした。 更に放出されたBMP4は細胞表面に留まってシナプスの近くに長く存在し、局所的に働くことがわかりました。 このようなBMP4の性質は通常の神経伝達物質のふるまいとは大きく異なり、新しい神経回路の制御機構であると考えられます。 今回新しく発見されたシナプスを積極的に壊すメカニズムは、精神疾患・発達障害の患者に認められる脳神経回路の障害の理解、さらにはこれら疾患の診断・治療にも結び付くことが期待されます。 本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 (CREST)「生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出(研究総括:山本 雅)」の一環として、またおよび文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて行われました。 本研究成果は「Cell Reports」(オンライン版:1月23日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 378KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 378KB]をご覧下さい。
(2018/1/29)
統合失調症における社会機能障害への大脳皮質下領域の関与を発見
~ 神経回路のかなめである視床体積の低下が関連 ~
東京大学大学院医学系研究科精神医学分野の越山太輔大学院生、笠井清登教授、大阪大学大学院連合小児発達学研究科の橋本亮太准教授らの研究グループは、磁気共鳴画像法(MRI)を用いた研究により、統合失調症において、大脳皮質下領域に存在する視床の体積が健常者に比べて小さいという既知の報告を再現するとともに、統合失調症の社会機能障害に、大脳皮質下領域における神経回路のかなめである視床の体積異常が関与することを新たに見出しました。
本研究の結果は、統合失調症を持つ当事者にとって社会生活の支障となっている社会認知機能(社会通念や文脈の理解)や日常生活技能(金銭出納やコミュニケーション能力)の障害の基盤として、視床を中心とする神経回路の機能不全が重要であることを示した初めての報告です。これにより、統合失調症の病態解明の一助となるとともに、統合失調症の社会生活機能リハビリテーション法の開発に貢献すると考えられます。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」や文部科学省科学研究費補助金などの支援により行われました。
本研究成果は、1月19日(英国時間)にScientific Reports(オンライン版)にて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:1.00MB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:1.00MB](東大病院HP掲載)
(2018/1/22)
シナプスの情報量を決める超分子ナノ構造
シナプス伝達は神経回路における情報処理の素過程です。 哺乳類の脳には数十兆から数百兆に及ぶシナプスが形成されていると言われていますが、個々のシナプスが持ち得る情報量はどの程度なのかよく分かっていませんでした。 また、シナプスの情報量を決定する分子構造はこれまで同定されていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻神経生物学分野の廣瀬教授らの研究グループは、脳の主要な神経伝達物質であるグルタミン酸のイメージング技術とシナプス分子の超解像可視化技術を組み合わせて、タンパク質分子Munc13-1を中心とした超分子集合体の個数が個々のシナプスの情報量を決定している事を明らかにしました。 本研究成果は、分子と細胞内小器官の中間のサイズにあたるナノサイズの超分子構造とシナプス機能とを結びつけた重要な成果であります。 今回の発見はシナプス伝達の根本的仕組みの一端を明らかにするものであり、脳の仕組みの理解や精神神経疾患の理解や克服にとって重要な知見であると考えられます。 また、タンパク質の超分子集合現象は、シナプス機能だけではなく、さまざまな生理機能を実現するための生命の本質であると考えられます。
本研究成果は「Nature neuroscience」(オンライン版:12月11日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 329KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 329KB]をご覧下さい。
(2017/12/12)
発達期小脳における自発神経活動の成熟過程を解明
生後間もない脳には過剰な神経結合(シナプス)が存在しますが、発達の過程で必要なシナプスが強化されて残るとともに不要なシナプスは除去されて、機能的な神経回路が完成します。 この過程は「シナプス刈り込み」と呼ばれ、機能的な神経回路が出来上がるために不可欠です。 これまでの研究からシナプス刈り込みは神経活動に依存して進むと考えられていますが、生後発達期にどのようなパターンの神経活動が生じているのか、またそれがシナプス刈り込みとどのような関係にあるのかは不明でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野のジャンマルク グッド研究員(研究当時)と狩野方伸教授の研究グループは、山梨大学大学院総合研究部医学域神経生理学の喜多村和郎教授らの研究グループと共同で、発達期の小脳における自発的な神経活動の成熟過程とシナプス刈り込みの関係を明らかにしました。
本研究グループは、発達期のシナプス刈り込み過程の詳細な解析が進んでいるマウス小脳の登上線維とプルキンエ細胞に着目しました。 生後間もないマウスにおいては、プルキンエ細胞同士の自発活動が高い同期性を示し、その同期性は発達が進むにつれて減少することを明らかにしました。 さらに、この同期性の減少がシナプス刈り込みによる登上線維の配線の変化と登上線維の活動パターンの変化の両方によって起こっていることが明らかになりました(「本研究成果のまとめ」の図を参照)。
本研究成果は、11月22日(水)午前2時(米国東部標準時間11月21日(火)正午)に「Cell Reports」オンライン版に掲載されました。
本研究は、科学研究費補助金の助成を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 246KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 246KB]をご覧下さい。
(2017/11/27)
予定帝王切開率の地域差の背景に周産期医療体制
世界では、社会的理由(訴訟リスクの回避、患者医療従事者双方にとって予定を立てやすい等)により、一出生あたりの帝王切開件数(帝王切開率)が増加傾向にあり、母子の健康に与える影響が懸念されています。 わが国では、これまで年間通した帝王切開の状況が把握されておらず、詳細な要因分析もされていませんでした。 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学の小林廉毅教授は、秋田大学大学院医学系研究科環境保健学の前田恵理助教、村田勝敬教授、埼玉医科大学産科婦人科学の石原理教授らと共同で、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の分析を行い、全国の帝王切開術実施状況について初めて明らかにしました。
2013年に全国の医療機関から提出されたレセプトのうち、診療行為コードに帝王切開術を含むレセプト件数は190,361件で、2013年の出生数が1,029,816人であることから、全国の帝王切開率は18.5%でした。 一方、都道府県別の帝王切開率は14.0%から25.6%までの差が見られ、母親の年齢で調整しても、その差は殆ど変わりませんでした。 母親の年齢で調整した帝王切開率と周産期医療体制の関連について都道府県別に分析したところ、予定帝王切開率は、周産期医療におけるマンパワー(分娩担当医師数)や新生児集中治療室病床数(NICU病床数)が少ない県や、分娩取扱機能が分散している(診療所で分娩を多く取り扱う)県で高い傾向にありました。 緊急帝王切開率については、地域の周産期医療体制と明らかな関係はなく、曜日ごとの変動も少ないことから、場所や時によらない緊急対応が行われていることが示唆されます。
本研究から、わが国では世界保健機関が示す基準(10~15%)に近い割合で、総じて適切に帝王切開術が行われている一方、予定帝王切開率の地域差の背景に地域の周産期医療体制の違いのある可能性が示唆されます。 本研究は、地域周産期医療の向上に向けた議論の貴重な資料になると考えられます。
本研究は、日本産科婦人科学会とアジアオセアニア産婦人科連合が共同して発行する国際医学雑誌 " The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research " オンライン版に2017年11月2日付けで掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 295KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 295KB]をご覧下さい。
(2017/11/20)
次世代型マウス遺伝学の実現
~ 交配を用いないノックインマウス個体並列作製方法の確立 ~
大規模ながんゲノム研究によって、多数の臨床的意義不明な遺伝子変異(variants of unknown significance: VUS)が報告されましたが、それらが、がんと関連性を持つかは不明のままです。
理化学研究所(理研)生命システム研究センター合成生物学研究グループの上田泰己グループディレクター(東京大学大学院医学系研究科教授)、鵜飼英樹上級研究員、ライフサイエンス技術基盤研究センター生体モデル開発ユニットの清成寛ユニットリーダーの共同研究チームは、これまで1~2年をかけて作製していた「ノックインマウス」を、2~3カ月かつ同時進行(並列)で多種類作製する方法を確立しました。
外来遺伝子が体の全細胞の染色体DNAの任意の位置に挿入されたマウス(ノックインマウス)を作製し、その挿入遺伝子の影響を解析する技術は、生物個体で観察される生命現象を研究する上で欠かせません。 個体レベルでの生命現象には多数の遺伝子が関与しているため、多種類のノックインマウスを作製する必要があります。 しかし通常、ノックインマウスの作製には非常に煩雑な操作が必要なため、1~2年かかります。 また、多種類のノックインマウスを並列に作製することは困難でした。
そこで、共同研究チームはまず、ノックインマウスの作製に必要なノックインES細胞の作製手法を簡便化・高効率化することで、多種類のノックインES細胞を並列に短期間(約1カ月)で作製する技術を確立しました。 次に、2010年に清成ユニットリーダーらが開発した、体の全細胞がES細胞に由来するマウス(ESマウス)を、キメラマウスの交配を介さずに直接作製する技術と組み合わせることで、ノックインESマウスを並列・短期間(2~3カ月)で作製する技術体系を確立しました。 そして、この“次世代型マウス遺伝学”技術を誰もが実践できるように、操作上の注意点などを詳細に記したプロトコルにまとめ、報告・公開しました。
本成果のノックインES細胞およびノックインESマウス作製技術は、マウスを用いた基礎生物学的研究だけでなく、ヒトiPS細胞などを用いた疾患研究、ヒト疾患モデル臓器や疾患モデルマウスの作製にも応用できることから、医学・医薬品開発の研究においても重要な基盤技術といえます。 今後、国内外の研究者が本技術を利用することにより、多くの医学・生物学研究が大きく加速するものと期待できます。
本研究は、英国の科学雑誌『Nature Protocols』オンライン版(11月16日付け:日本時間11月17日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 970KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 970KB]をご覧下さい。
(2017/11/17)
がん遺伝子変異の高速評価を可能とするハイスループット機能解析法の開発
~ がんゲノム医療への応用に期待 ~
大規模ながんゲノム研究によって、多数の臨床的意義不明な遺伝子変異(variants of unknown significance: VUS)が報告されましたが、それらが、がんと関連性を持つかは不明のままです。
東京大学大学院医学系研究科の高阪真路特任助教および間野博行教授らのグ ループは、革新的なハイスループット遺伝子変異機能解析手法(mixed-all-nominated-mutants-in-one method: MANO法)を構築しました。
この手法を用いて、肺腺がんで高頻度に見られる101種類のEGFR遺伝子変異を評価したところ、64種類ががん化能をもつ遺伝子変異であることが判明しました。 さらに、医療現場で使用されている、EGFRのチロシンキナーゼ阻害剤に対して耐性を起こさせる変異を数多く発見しました。 特に、EGFRエクソン19番内の非同義変異やL833V、A839T、V851I、A871T、G873Eなどが、チロシンキナーゼ阻害剤であるゲフィチニブやエルロチニブ等のがん治療薬への耐性を生じさせるのに関係する重要な変異であるということを今回明らかにしました。 また肺腺がんにおいて最も多くみられるEGFR(L858R)変異は、EGFRの858番目のアミノ酸がロイシン(L)からアルギニン(R)に置き換わるものですが、この変異のあるがん患者のうち約20%では、EGFR(L858R)変異の存在する同じ染色体上のEGFR遺伝子内に重複変異が存在することがわかり、12.8%では、変異があることによりゲフィチニブへの感受性が減弱することが明らかになりました。 さらにMANO法を用いた解析で、いくつかのEGFR変異では、試験に用いた全てのEGFRチロシンキナーゼ阻害剤への耐性が生じていたにもかかわらず、EGFRを標的とするモノクローナル抗体であるセツキシマブへの感受性は保たれ、有効な治療薬となり得ることが判明しました。
本研究は、これまで意義不明であったEGFR遺伝子のマイナー変異(稀な遺伝子変異)を検査し、それぞれのがん化能、および薬剤感受性を明らかにしたと同時に、今後のゲノム医療を実装する際には、マイナー変異もシークエンス解析し同定することの重要性をも示唆した画期的な成果です。 MANO法は、今後がん化関連遺伝子のVUSを網羅的に評価することで、個別化医療を実現するための基盤的な手法になると期待されるとともに、一度に多数の遺伝子変異に対してがん治療薬の効果を評価できることから、新しい分子標的治療法の研究開発にも大きな貢献をするものと考えられます。
本研究は高阪真路特任助教が研究開発代表者を務める国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の革新的がん医療実用化研究事業と間野博行教授が研究開発代表者を務める国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(LEAP)の研究が連携して行ったもので、研究成果は「Science Translational Medicine」(11月15日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 614KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 614KB]をご覧下さい。
(2017/11/16)
孤発性アルツハイマー病において神経細胞特異的なエピゲノム解析を元に乳癌の原因遺伝子BRCA1の関与を特定
アルツハイマー病の発症には、遺伝、環境など様々な要因が絡み合っていると考えられていますが、未だ根本的な治療法にはたどり着けていません。それは、未だ病気の発症に関わる理解が足りないからです。アルツハイマー病の病態に迫るためには、亡くなった患者さんの脳からどのようにして病気にとって重要かつ異常な情報を抽出して解析できるかが鍵となります。
東京大学医学部附属病院神経内科の岩田淳講師、間野達雄特任臨床医らは、神経細胞特異的なDNAメチル化解析という方法を用いて孤発性アルツハイマー病患者の脳内において乳癌の原因遺伝子BRCA1の機能異常が生じていることを世界で初めて明らかにしました。神経細胞が静かに衰えていくと考えられているアルツハイマー病と「癌」という一方で激しく増殖していく疾患の表裏一体性を示した画期的な発見と言えます。BRCA1はDNAの損傷を修復すると考えられており、その機能異常がアルツハイマー病の脳で生じているという新たな発見は、DNA修復という観点からの新しい治療法開発へ繋がることが期待されます。
なお、本研究は東京都医学総合研究所、東京都健康長寿医療センター、理化学研究所、国立がん研究センター研究所、九州大学、筑波大学、新潟大学、愛媛大学との共同研究で行われました。研究成果は、米国科学アカデミー紀要 オンライン版に10月17日午後(米国東部夏時間)に掲載されます。
![]() リリース文書[PDF:364KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:364KB](東大病院HP掲載)
(2017/10/17)
ピロリ菌がんタンパク質の1アミノ酸多型が日本人胃がん多発の背景に
~ ピロリ菌の発がん活性を規定する分子構造基盤 ~
ほぼ全ての胃がんはヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)感染を背景に発症し、その発がん過程にはピロリ菌が産生する病原因子CagAタンパク質が重要な役割を果たします。 東アジア諸国(日本、中国、韓国)は世界的な胃がんの最多発地域として知られています。 疫学調査から東アジアで見られるピロリ菌が保有する東アジア型CagAは、それ以外の地域で見られる欧米型(世界標準型)CagAに比べ、胃がん発症に、より深く関与することが指摘されていますが、これら2種のCagA間の発がん活性に違いが生じる構造基盤は不明でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の畠山昌則教授、高エネルギー加速器研究機構の千田俊哉教授らの研究グループは、X線結晶構造解析を通してCagAが標的とする発がんタンパク質SHP2との複合体の構造を原子レベルで解明し、東アジア型CagAと欧米型CagAの間に存在する1つのアミノ酸残基の違いによる立体構造の差異がCagAのSHP2結合能に大きな影響を与えることを明らかにしました。 さらに、東アジア型CagAが示す欧米型CagAに比べて圧倒的に強固なSHP2結合が、SHP2の酵素活性を著しく増強し、胃の細胞のがん化を促す異常なシグナルを強力に誘導することを見出しました。 本研究の成果は、革新的な胃がんの予防法・早期治療法の開発に繋がることが期待されます。
本研究成果はCell Reports(9月19日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 2.18MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 2.18MB]をご覧下さい。
(2017/9/21)
血糖・血圧・脂質に対する厳格な統合的治療の効果
~ 2型糖尿病における新たなエビデンス ~
様々な血管合併症を引き起こす2型糖尿病は大きな社会問題となっていますが、どのような治療が合併症予防に有効なのかは、これまで十分に分かっていませんでした。 このたび東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 門脇孝教授、国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター 植木浩二郎センター長らのグループは、2006年に厚生労働省の戦略研究の一環として開始された臨床試験J-DOIT3の主な解析結果を発表しました。
この試験では全国81施設で2型糖尿病の2542例が参加し、ガイドラインに沿った治療を受ける従来療法群か、血糖値・血圧・脂質に対してより厳格な統合的治療を受ける強化療法群に割り付けられました。 平均8.5年の治療により、強化療法は主要評価項目(心筋梗塞・冠動脈血行再建術・脳卒中・脳血管血行再建術・死亡)を、統計学的に有意ではなかったものの19%抑制し、登録時の喫煙情報などの危険因子で補正すると24%有意に抑制していました。 このうち脳血管イベント(脳卒中・脳血管血行再建術)を58%有意に抑制したことが事後解析で分かり、その他腎イベント(腎症の発症・進展)も32%有意に減っていました。
以上の結果により、今後の国内外の糖尿病診療ガイドラインの治療の目標値について、より厳格な方向で見直しが進む可能性があります。 なお本研究は厚生労働省の戦略研究、並びに指定研究の一環として行われました。 その成果は日本時間2017年9月15日午後7時から、ポルトガル・リスボンで開催される欧州糖尿病学会で発表され、また英国科学雑誌Lancet Diabetes & Endocrinology誌に掲載予定です。
![]() リリース文書[PDF:240KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:240KB](東大病院HP掲載)
(2017/9/19)
ロタウイルスワクチン株の広がりが日本で初めて明らかに
~ ワクチン導入移行期の小児急性胃腸炎多施設共同疫学研究 ~
ロタウイルス胃腸炎は乳幼児が多く罹患する感染症です。RotarixとRotaTeqという有効なワクチンが開発されましたが、日本では2011年より希望する児のみ接種を受ける任意接種としての使用に留まり、ワクチンの影響(益と害)に関するデータも不足していました。
東京大学大学院医学系研究科の高梨さやか助教、金子明依修士学生(研究当時)、水口雅教授らは、牛島廣治博士(日本大学)、藤本嗣人博士、木村博一博士(国立感染症研究所)らと連携して、わが国における急性胃腸炎罹患児からの同ワクチンの検出、解析を目指して研究を進めました。
2012年7月~2015年6月の間に、急性胃腸炎患児1824人のうち、372人からロタウイルスが検出されました。 そのうちワクチン株と野生株を峻別するリアルタイム RT-PCR法にて、6人(1.6%)からRotarix株が検出され、RotaTeq株は検出されませんでした。 これは日本で初めて示された検出率であり、過去の米国での検討より低い値でした。この6人は便検体を採取する2~14日前にRotarixワクチン接種を受けており、今回の胃腸炎症状へのワクチン株の関与は明らかではありませんでした。 次世代シークエンスという新しい手法を用いて詳細な遺伝子解析を行い、リアソータントの発生ではなく、ワクチン接種直後で感染防御が成立する前に野生株に感染して急性胃腸炎を発症したと考えられる興味深い例を見出しました。
今回の研究で得られた結果は、国として定期接種化を検討する際の重要な資料となると考えられます。
なお、本研究は公益財団法人予防接種リサーチセンター調査研究費補助金及び日本学術振興会研究助成事業の支援を受けて行われ、研究成果はPLOS ONE(9月13日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 210KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 210KB]をご覧下さい。
(2017/9/14)
細胞内骨格の賢い「解体屋」
~ 微小管を解体する分子モーターが効率良く働く仕組みを解明 ~
東京大学大学院 医学系研究科の廣川 信隆 特任教授と小川 覚之 助教らの研究グループは、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の西條 慎也 特任助教(研究当時)と清水 伸隆 准教授との共同研究によって、細胞内の骨格である微小管の「解体屋」が効率良く働く仕組みを明らかにしました。
微小管は、チューブリンというタンパク質が重合して集まったチューブ状の構造をしています。 神経細胞の形成や細胞分裂などの生命現象には、微小管の形成(重合)と解体(脱重合)が秩序立って進められることが重要です。 キネシンというタンパク質のひとつであるKIF2がこの微小管の解体を担い、少ない数のKIF2が、多くのチューブリンからなる巨大な微小管を、先端から順番に解体することは知られていましたが、それがなぜ可能なのかはわかっていませんでした。
研究グループは、KIF2が微小管を解体する過程を詳細に解析し、生体内のエネルギー源ATPを加水分解する過程で、KIF2分子1つがチューブリン2量体2セットを相手にしてまとめて解体することを明らかにしました。 KIF2は、少ない分子数でATPを効率良く利用し微小管を解体する「省エネモーター」であったのです。
本研究成果は、9月12日オンライン版Cell Reportsに掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.47MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.47MB]をご覧下さい。
(2017/9/13)
統合失調症患者に対するベタインの治療効果を調べる臨床試験を行います
東京大学医学部附属病院精神神経科は、統合失調症の患者さんを対象にベタインの有効性や安全性を調べる臨床試験を行っています。これまでは既に当院に通院中の方から参加者を募っていましたが、この度、当院に通院中の方に限らず広く参加者を募ることになりました。
統合失調症の治療法としては抗精神病薬や心理社会的治療がありますが、これらの治療法で症状を十分にコントロールできない方が少なくありません。当院精神神経科では以前に統合失調症の患者さんで血液中のベタイン濃度が低下していることを見出しており、ベタインを補うことで治療効果が得られることを期待して今回の臨床試験を計画しました。臨床試験で良い結果が得られた場合、新たな治療薬の開発につながることが期待されます。
なお、本研究は、日本医療開発研究機構「脳科学研究戦略推進プログラム」の「臨床と基礎研究の連携強化による精神・神経疾患の克服(融合脳)」の一貫として行われています。
![]() リリース文書[PDF:128KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:128KB](東大病院HP掲載)
(2017/9/11)
スマホゲームアプリ「Pokémon GO」は労働者の心の健康の保持・増進に有効
拡張現実を活用した新しいスマホゲームアプリ「Pokémon GO」が及ぼす影響は、その新規性から様々な方面で論じられてきました。 しかし、そのほとんどは事例証拠や専門家の意見によるものにとどまっていました。
東京大学医学系研究科精神保健学分野の渡辺和広大学院生、川上憲人教授らは、「Pokémon GO」が労働者のメンタルヘルスを改善する効果に着目し、労働者を対象に調査を実施しました。 2015年11月から追跡していた、日本に居住している正社員・正職員の労働者2,530名を対象に、2016年12月にインターネットを用いて、「Pokémon GO」を1ヶ月以上継続してプレイしたことがあるか、および心理的ストレス反応の程度について調査を実施しました。 その結果、「Pokémon GO」を1ヶ月以上継続してプレイした労働者(246名、9.7%)は、そうでない労働者(2,284名、90.3%)に比べ、1年後の心理的ストレス反応が有意に減少していました。
本成果は、「Pokémon GO」がメンタルヘルスの改善に及ぼす効果を示した世界で初めての研究です。 様々な世代や特徴を持った人々に広くプレイされるスマホゲームアプリを普及させることで、労働者のメンタルヘルス改善に大きなインパクトをもたらすことが期待されます。 なお、本成果はNature Publishing Groupの専門誌「Scientific Reports」に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 292KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 292KB]をご覧下さい。
(2017/9/8)
ヒトゲノムと結核菌ゲノムの統合的解析による新規結核発症リスク因子の同定
結核は世界三大感染症のひとつであり、世界で約3人に1人が結核菌に感染していますが、その生涯の発症率は10%であり、宿主であるヒト側の遺伝要因の関与が示唆されています。
東京大学大学院医学系研究科の徳永勝士教授らの研究チームは、結核患者のヒトゲノム試料と感染結核菌ゲノム試料の両方をタイ国内で収集し、今回、結核菌の遺伝的系統の情報を組み合わせたヒトゲノム解析により、CD53というヒトの遺伝子が、特定の系統の結核菌の感染における発症のしやすさと関わることを明らかにしました。 今回用いた方法をさらに対象を拡大して実施していくことにより、今後さらに多くの結核発症リスク遺伝子群が同定され、ひとりひとりの発症リスク予測を行うことが出来るようになると期待されます。
本研究成果は「Journal of Human Genetics」オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 244KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 244KB]をご覧下さい。
(2017/9/7)
過去30年におけるわが国の職業別死亡率格差と死因別の寄与を解明
本研究では人口動態統計職業・産業別調査の匿名化済み個票データを用いて、職業間の絶対的な死亡率格差や相対的な死亡率格差、格差に寄与している死因を分析することで、過去30年におけるわが国の職業別死亡率格差の詳細を明らかにしました。
30-59歳の日本人男女について、職業を「管理職」「事務職」「公務員」「サービス職従事者」など12分類し、職業別の年齢調整死亡率を1980年から2010年まで5年毎に算出し経年変化を調べました。 また、職業間の死亡率の差と死亡率の比の経年変化を算出し、それぞれ絶対的な死亡率格差、相対的な死亡率格差としました。 さらに、職業間で死亡率格差の生じる要因として、どのような死因の寄与が大きいかを分析しました。
男性の職業別死亡率は「管理職」を除いてすべて低下しており、とりわけ「事務職」「公務員」では大きく低下していました。 職業間の絶対的な死亡率格差が低下傾向にある一方で、相対的な死亡率格差は「管理職」「農林業従事者」「漁業従事者」「サービス職従事者」で拡大傾向にありました。 死因別の寄与では、脳血管疾患、悪性新生物による死亡減少が職業間の死亡率格差緩和に寄与する一方で、自殺が職業間の死亡率格差拡大に関与していました。 女性では職業間の絶対的な死亡率格差、相対的な死亡率格差ともに小さく、格差が解消される傾向にありました。
「働き方改革」が社会的課題となるなか、働く世代の早世を予防し、職業間の健康格差を解消する施策を推進するにあたって、本研究の成果は有用な資料になると考えられます。 本研究成果は国際医学誌「BMJ Open」(2017年9月5日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 264KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 264KB]をご覧下さい。
(2017/9/6)
肥満症の治療標的として期待される「褐色脂肪組織」の新規制御因子を同定
肥満症とそれに起因するメタボリックシンドロームや肥満2型糖尿病は、心血管疾患、腎疾患や悪性腫瘍のリスクを高めることから、健康寿命の延伸を目指す上で大きな障害です。近年、エネルギーの貯蔵を担う「白色脂肪組織」以外に、熱産生を介してエネルギーを消費する「褐色脂肪組織」がヒト成人にも存在することが分かり、褐色脂肪組織の数や働きを高めることが肥満症の新しい治療法につながり得るとして期待されています。
このたび東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 門脇孝教授、山内敏正准教授、脇裕典特任准教授、平池勇雄特任研究員及び東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 油谷浩幸教授、堤修一特任准教授らの研究グループは、褐色脂肪組織に特異的なDNA上のオープンクロマチン領域の解析から、褐色脂肪組織の新規の主要制御因子としてNFIAを同定しました。NFIAを欠損させたマウスでは褐色脂肪の遺伝子プログラムが著しく障害されていた一方、NFIAを導入した場合には、筋芽細胞や白色脂肪細胞においても褐色脂肪の遺伝子プログラムが活性化されました。更に、ヒト成人の褐色脂肪組織でも白色脂肪組織と比較してNFIA遺伝子が高発現していました。この結果は、NFIAの働きを高めることで「エネルギー摂取の抑制」ではなく「エネルギー消費の促進」に基づく肥満症、メタボリックシンドローム、肥満2型糖尿病の新しい治療につながる可能性があると期待されます。
本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の革新的先端研究開発支援事業(AMED‐CREST)「エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」研究開発領域における研究開発課題「2型糖尿病・肥満における代謝制御機構とその破綻のエピゲノム解析」(研究開発代表者:山内敏正)の一環で行われました。なお、本研究開発領域は、2015年4月の日本医療研究開発機構の発足に伴い、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)より移管されたものです。その成果は日本時間2017年8月15日午前0時(英国時間 2017年8月14日16時)に英国科学雑誌 Nature Cell Biology オンライン版に掲載されました。
![]() リリース文書[PDF:256KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:256KB](東大病院HP掲載)
(2017/8/17)
精神疾患をもつ人の平均余命は一般人口に比べて20年以上短い
~ 精神障がい者の健康格差 ~
東京大学医学部附属病院精神神経科の近藤伸介助教、笠井清登教授らは、東京都三鷹市の社会福祉法人巣立ち会(田尾有樹子理事長)と共同で、同会設立時の1992年から2015年末までに精神科病院長期入院を経て退院し地域生活に移行した利用者254名のうち、死亡した45名について調査を行い、損失生存年数(YLL)という指標を用いて、精神疾患を有する人の平均余命が一般人口に比べて22.2年以上短いことを明らかにしました。また、標準化死亡比(SMR)という指標が全体で3.28、死因別では心血管疾患5.09、自殺7.38と一般人口に比べて有意に高いことも明らかにしました。
日本では精神疾患を有する人の死因について正確な統計がなく、精神疾患をもつ人のYLLを算出した報告は国内初です。本研究結果は精神障害のリカバリーを目指す上で身体的健康が重要であることを示唆するもので、今後は精神疾患をもつ人の身体的健康についての正確な実態把握と適切なケアの充実が進み、精神疾患を有する人の健康格差が是正される契機となることが期待されます。
本成果は、British Journal of Psychiatry Openにて8月11日(英国夏時間)にオンライ掲載されました。
なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)、科学研究費補助金、精神・神経科学振興財団の助成により行われました。
![]() リリース文書[PDF:185KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:185KB](東大病院HP掲載)
(2017/8/17)
眼科手技を模擬した眼科手術シミュレータの開発
~ 網膜硝子体手術用眼球モデルの開発と計測システムの統合に成功 ~
名古屋大学大学院工学研究科(研究科長:新美智秀)の新井史人教授、丸山央峰准教授、益田泰輔特任准教授、小俣誠二特任助教の研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の相原一教授の研究グループと東京大学大学院工学系研究科の光石衛教授の研究グループとの共同研究で、人間そっくりな眼科手術シミュレータを、この度、開発しました。
近年、医学教育の効率化や難手術の効果的訓練のため、精巧な手術シミュレータが強く求められています。しかし、実際の人間の眼球や頭部の可動性を十分忠実に再現したものは存在していません。また、一部の網膜硝子体手術は難手術と言われているにも拘らず、適切な模擬眼球が開発されておらず、術者の手技評価を行うためのセンサシステムも開発されていません。
本研究では、上記の課題を踏まえ、二つの網膜硝子体手術の手技の模擬と一つの変形表示機能を搭載することにより、全く新しい眼科手術手シミュレータを開発することに成功しました。これにより、従来では行うことの出来なかった手技の模擬と評価を行うと共に、一連の手術トレーニングを行うことが可能になりました。
なお、この研究は、平成27年度から始まった内閣府『ImPACT プロジェクト』の支援の下で行われたものです。
![]() リリース文書[PDF:396KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:396KB](東大病院HP掲載)
(2017/8/8)
胃癌手術前後の運動トレーニングに関する臨床試験を開始します
東京大学医学部附属病院22世紀医療センター 肥満メタボリックケア(社会連携講座)は、東京大学とライザップ株式会社との共同研究として、臨床試験「運動・栄養介入による胃癌周術期のサルコペニア予防効果に関するランダム化比較試験」を9月より開始する予定です。
加齢などに伴う骨格筋量の低下はサルコペニアと呼ばれ、近年注目されている社会的課題です。本研究は、胃癌手術の前後の運動・栄養療法で術後のサルコペニアが予防できるかを検証することを目的としています。東京大学医学部附属病院 胃・食道外科にて胃癌手術を受ける高齢者を対象とした、ランダム化比較試験として行われます。試験群に割り付けられた場合は、手術の前後、運動トレーニングと補助栄養食品摂取を行います。術後のサルコペニアの有無や治療経過、血液検査所見などを解析し、その妥当性を検証します。
高齢化、肥満人口の増加が大きな社会問題となっており、その対策として、運動・栄養管理は非常に重要となっています。日本人の高齢者に合わせた適切な運動・栄養療法の検討を行うことは、安全な手術やがん治療の提供につながると同時に、一般高齢者の健康維持・増進に大きく寄与するものと考えられます。
![]() リリース文書[PDF:292KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:292KB](東大病院HP掲載)
(2017/8/8)
発達期小脳において、脳由来神経栄養因子(BDNF)はシナプスを積極的に弱め除去する「刈り込み因子」としてはたらく
統合失調症や自閉スペクトラム症の病態の根底には、神経回路の発達異常があると考えられています。 生後間もない脳には過剰な神経結合(シナプス)が存在しますが、発達の過程で不要なシナプスは除去されて、機能的な神経回路が完成します。 この過程は「シナプス刈り込み」と呼ばれ、機能的な神経回路が出来上がるために不可欠とされています。 しかし、シナプス刈り込みがどのような仕組みによって起こるかは完全には理解されておらず、特にどの分子がどの細胞で働くことでシナプス刈り込みが実現するかは不明でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の秋明貞研究員と狩野方伸教授らの研究グループは、発達期の小脳において、脳由来神経栄養因子(BDNF)がシナプス刈り込みを促進することを発見しました。
本研究グループは発達期のマウス小脳の登上線維とプルキンエ細胞との間のシナプスにみられるシナプス刈り込みに注目しました。 シナプス後部のプルキンエ細胞から放出されたBDNF分子が、シナプス前部の登上線維に存在するTrkB受容体に、逆行性シグナルとして働き、シナプスの刈り込みを促進することを明らかにしました。 さらに、BDNF分子は代謝型グルタミン酸受容体(mGluR1)やクラス7セマフォリン(Sema7A)と協調して、シナプス刈り込みを促進することを見出しました。 脳の様々な部位において、BDNFはシナプスを強める「栄養因子」として働くことは広く知られていましたが、発達期の小脳においては、BDNFはシナプスを積極的に刈り込む「懲罰因子」として働くことが明らかになりました。
本研究は、科学研究費補助金の助成を受けて行われました。 また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」および「脳科学研究戦略推進プログラム」の一環として実施されました。
本研究成果は、8月4日(金)に「Nature Communications」オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 414KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 414KB]をご覧下さい。
(2017/8/4)
「主要ながん免疫抗原である硫酸化グリコサミノグリカンの同定」
~ 次世代シーケンスによる胃がん免疫ゲノム解析の成果に基づく新規治療法開発への期待 ~
東京医科歯科大学難治疾患研究所ゲノム病理学分野の石川俊平教授と加藤洋人助教、河村大輔助教らは、東京大学 先端科学技術研究センターゲノムサイエンス部門(油谷浩幸教授)及び大学院医学系研究科人体病理学・病理診断学分野(深山正久教授)との共同研究により、胃がん組織におけるリンパ球の抗原受容体の全体像を次世代シーケンサーを用いた免疫ゲノム解析で明らかにしました。 そのなかで糖鎖の一つである硫酸化グリコサミノグリカンががん組織における主要ながん免疫抗原であることを突き止めました。 また免疫ゲノムのDNAシーケンス情報をもとに、抗腫瘍活性を有するヒト抗体を作成することに成功しました。
この研究は、東京大学医学部附属病院胃・食道外科および横浜市立大学外科治療学教室の協力のもと、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」「次世代がん医療創生研究事業(P-CREATE)」および文部科学省科学研究費補助金等の支援で行われたものです。 研究成果は、国際科学誌Cell Reports(セル・リポーツ)に2017年8月1日(米国東部標準時間)付で発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 634KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 634KB]をご覧下さい。
(2017/8/3)
小児の難治性てんかん症候群・ウエスト症候群/レット症候群の原因遺伝子CDKL5の欠損が大脳の興奮性を異常亢進するメカニズムの一端を解明
CDKL5遺伝子の変異は、ウエスト症候群/レット症候群という小児の難治性てんかん症候群を引き起こしますが、これまでその発症機序は全く分かっていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科発達医科学分野の田中輝幸准教授、奥田耕助博士らは、CDKL5を欠損させたCdkl5ノックアウト(KO)マウスを作製し、東京大学医科学研究所神経ネットワーク分野の小林静香助教、真鍋俊也教授、北里大学医学部解剖学教室の深谷昌弘講師、阪上洋行教授らとの共同研究によって、このマウスでは大脳の興奮性シナプスにおいて興奮性神経伝達物質を受け取る受容体の一型(GluN2BタイプNMDA型)が過剰集積することで、ニューロンの興奮性が亢進し、痙攣感受性が異常亢進することを明らかにしました。 更に過剰集積する受容体蛋白に対する阻害薬がCdkl5 KOマウスのニューロンの興奮性と痙攣感受性の亢進を効果的に抑制することを示しました。
本研究は世界で初めて、CDKL5欠損が大脳の興奮性を異常亢進するメカニズムの一端を明らかにすると共に、興奮性シナプス受容体を構成する蛋白質に特異的に作用する薬物がCDKL5変異によるてんかんの治療原理となる可能性を示し、今後の小児難治性てんかんの分子病態機序と効果的治療法の解明への重要な基盤になるものです。
本研究成果は、学術誌 Neurobiology of Disease(2017年7月6日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 217KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 217KB]をご覧下さい。
(2017/7/21)
日本の都道府県別の疾病負荷研究(1990~2015年)
~ 停滞する健康指標と拡大する都道府県間の健康格差 ~
日本は今日、超高齢化時代を迎え健康転換が進んでいる。健康転換のペースは国内の地域によって異なるため、地域的な健康格差に対する懸念が高まっている。 東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室と米国ワシントン大学保健指標・保健評価研究所(IHME)では、この度、1990年から2015年における日本全国並びに各47都道府県における各種健康指標の変化について分析を行った。
1990年から2015年にかけて、 平均寿命は4.2歳上昇(79.0歳から83.2歳)した。 一方、都道府県の平均寿命の格差(最も寿命が長い県と短い県の差)も2.5歳から3.1歳に拡大し、健康寿命の格差も同様2.3歳から2.7歳へと増大を見せた。 死亡率に関しては同期間で大幅な減少を達成したものの、その減少率には都道府県間で顕著な差が見られた。 さらに、国全体の平均死亡率の低下は2005年以降鈍化の傾向にある。 2015年における死亡や疾病負荷の主要なリスク要因は、不健康な食事とタバコの喫煙であった。 都道府県レベルにおいて、保健システムの主なインプット(医療費・医療人材)と保健アウトカム(死亡率・疾病負荷)には統計学的に有意な関係は認められなかった。
本研究によって、1990年以降我が国では平均寿命・健康寿命ともに伸長し、死亡率も多くの疾患で減少していることが明らかになった。 しかし、健康の増進は2005年以降鈍化傾向にあり、また、都道府県間の健康格差は拡大傾向にあることがわかった。 都道府県レベルの保健アウトカムと保健システムへのインプットには限られた関係しか認められず、医療資源(医療費や人材)の増加は、必ずしも健康指標の改善に結びついていないことが示された。 健康指標の鈍化や国内の健康格差の要因の探索は喫緊の課題である。
本研究成果は、世界に先駆けて超高齢社会に突入した我が国の主要な健康課題を都道府県レベルで評価し、それらに対応する最善の方法を見つけるための新たなデータを提示するものである。 国レベルで、持続可能な保健システムの実現に向けた具体的施策を検討するのみならず、都道府県レベルで、健康格差是正に向けた保健システムに関する研究や政策立案などに生かされることが期待される。
本研究成果は「The Lancet」7月19日(英国夏時間)オンライン版に掲載された。
※詳細は![]() こちら[PDF: 217KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 217KB]をご覧下さい。
(2017/7/21)
後頭葉の脳回形成の変化が統合失調症発症を予測することを解明
富山大学附属病院神経精神科の笹林大樹助教、同大学大学院医学薬学研究部(医学)神経精神医学講座の鈴木道雄教授らのグループは、東京大学大学院医学系研究科精神医学分野の笠井清登教授、東邦大学医学部精神神経医学講座の水野雅文教授、東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野の松本和紀准教授らと共同で、「統合失調症の発症高リスク群のうち、のちに発症する群は、発症しない群と比較して、左後頭葉の脳回の過形成を示す」ことを世界で初めて明らかにしました。 この知見は、統合失調症の発症メカニズムの解明や早期診断法の開発に繋がる可能性があります。
今回の研究成果は、7月11日に米国科学誌「Biological Psychiatry」にオンライン掲載されました。
詳細は下記URL(富山大学 プレスリリース)をご覧下さい。
![]() https://www.u-toyama.ac.jp/outline/publicity/pdf/2017/0704.pdf
https://www.u-toyama.ac.jp/outline/publicity/pdf/2017/0704.pdf
(2017/7/13)
組織透明化による全身全細胞解析基盤の構築
~ がん転移を1細胞ごとに見ることが可能に ~
がんは局所に生じた後に全身に転移する全身性疾患です。 がんはそれを取り巻く微小環境と互いに作用し合いながら転移していくことが古くから知られていました。 しかし、これまで、がん細胞やがんの微小環境を1個の細胞ごとに高い解像度で、かつ全身・全臓器で包括的に観察することは極めて困難でした。
このたび、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学分野の上田泰己教授(理化学研究所生命システム研究センター 合成生物学グループ グループディレクター 兼任)、久保田晋平日本学術振興会特別研究員と病因・病理学専攻分子病理学分野の宮園浩平教授、高橋恵生特任研究員らの共同研究グループは、すでに開発していた全身・全脳イメージングと解析技術「CUBIC」の透明化試薬を、屈折率の観点からさらに発展させることにより、マウス個体の全身・全臓器に存在するがん微小転移を1細胞レベルの解像度で解析することを可能にする技術を開発しました。 この技術を応用してがん転移の時空間的解析を行うことで、がん細胞による初期の転移巣の形成機構を解明したり、抗がん剤の治療効果を臓器や個体レベルで検証したりすることが可能となりました。
本研究成果は「Cell Reports」7月5日(米国東部夏時間)オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.15MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.15MB]をご覧下さい。
(2017/7/6)
小児T細胞性急性リンパ性白血病における極めて高い悪性度に関連する融合遺伝子を発見
~ PU.1/SPI1融合遺伝子 ~
白血病は血液中の細胞のうち、白血球になるもとの細胞から発生する悪性腫瘍です。小児期の悪性腫瘍の中では最も高頻度に発生し、T-ALLは小児白血病の約15%を占めています。薬物療法を中心とした集学的治療の強化により全体として約70%の治癒が期待できますが、小児では特に成長障害、臓器機能障害、不妊など、治療後に発生する障害(晩期障害)が大きな課題となっています。また、治療抵抗例や再発した場合の治癒は極めて難しいのが現状です。従って、分子病態に立脚した治療の最適化は、小児T-ALL患者さんの治癒率改善と重篤な副作用や晩期障害の回避に重要といえます。
東京大学医学部附属病院小児科の滝田順子准教授、関正史助教、木村俊介研究員らは京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座の小川誠司教授らと共同で、次世代シーケンサー技術を用いて小児T-ALL 123例のゲノム上にみられる遺伝子異常や融合遺伝子を含む構造変化、遺伝子発現の異常の全体像を解明しました。その結果、極めて高い悪性度に関連するSPI1融合遺伝子を約4%の例に同定しました。SPI1融合遺伝子は、T細胞の分化の停止と細胞増殖をもたらし、それが白血病化を引き起こす可能性を示しました。また遺伝子発現パターンと分子学的特徴から小児T-ALLは5群に分類されることを見出し、それぞれの群を特徴づける遺伝子発現や遺伝子異常と臨床的特性を明らかにしました。SPI1融合遺伝子を有する群は、他とは異なる特徴的な一群であることを示し、新たなT-ALLのサブグループであることを示しました。この成果は、T-ALLの予後予測、精度の高い分子診断法の開発に貢献し、治療の最適化の実現に役立つものと期待されます。
本研究は、文部科学省「次世代がん医療創生研究事業(P-CREATE)」の一環として行われたものであり、その成果は2017年7月4日午前0時(英国時間7月3日午後4時)にNature Geneticsのオンライン版で公開されました。
![]() リリース文書[PDF:520KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:520KB](東大病院HP掲載)
(2017/7/4)
免疫機能の個人差に関わる遺伝子カタログを作成
~免疫疾患の遺伝的メカニズムの新しい解析手法を開発~
理化学研究所 統合生命医科学研究センター統計解析研究チームの石垣和慶特別研究員、自己免疫疾患研究チームの高地雄太副チームリーダー、山本一彦チームリーダー、東京大学医学部附属病院アレルギー・リウマチ内科の藤尾圭志講師らの共同研究チームは、免疫機能の個人差に関わる遺伝子カタログを作成し、免疫疾患の遺伝的メカニズムの新しい解析手法を開発しました。
私たちの健康状態や免疫機能の一部は、DNA配列の個人差(DNA多型)によって決まります。近年、ゲノムワイド関連解析(GWAS)によって免疫疾患の発症に関与するDNA多型(リスク多型)が多く同定されています。しかし、その遺伝的メカニズムの解明は十分に行われていません。リスク多型がどの免疫細胞において、どの遺伝子の発現量に影響しているのかを明らかにすることが、免疫疾患の遺伝的メカニズムの解明には重要です。
今回、共同研究チームは、105人の健常人から5種類の主要な免疫細胞を回収し、遺伝子発現量の個人差を次世代シーケンサーを用いて網羅的に解析することで、免疫機能の個人差に関わる遺伝子カタログ(eQTLカタログ)を作成しました。複数の免疫細胞を対象とした研究はアジア初の試みです。また、この遺伝子カタログを応用し免疫疾患の遺伝的メカニズムの全体像を評価する新規手法を開発しました。具体的な例として、関節リウマチ患者と健常人の遺伝子情報を用いて、CD4陽性T細胞において176個の遺伝子がTNFパスウェイに与える影響を予測し、それらを総合評価し一つの活性情報に集約しました。これを解析した結果、CD4陽性T細胞におけるTNFパスウェイの活性化は関節リウマチの病態で重要な役割を持つことが確認できました。
本研究で得られたeQTLカタログや解析手法は、関節リウマチなどの自己免疫疾患に加えて、花粉症・喘息・がんなどの免疫が関わる多くの疾患に適応することができます。それらは今後、遺伝的メカニズムに基づいた創薬標的の探索と治療法の開発に貢献すると期待できます。
本研究は、米国の科学雑誌『Nature Genetics』オンライン版(5月29日付け:日本時間5月30日)に掲載されました。
本研究の一部は、武田薬品工業株式会社の支援を受けて行われました。
詳細は 理化学研究所 プレスリリース をご覧ください。
(2017/5/31)
統合失調症におけるグルタミン酸系神経伝達異常の一端を解明
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻の笠井清登教授、千葉大学社会精神保健教育研究センターの橋本謙二教授らの研究グループは、統合失調症を主とする初発精神病群において、NMDA受容体機能を反映するMMNが有意に小さく、血漿グルタミン酸濃度が有意に高いことを見出しました。また、血漿グルタミン酸濃度が高いほどMMNが小さいという有意な相関を世界で初めて報告しました。
本研究成果は、初発精神病の一群において、NMDA受容体機能低下などのグルタミン酸系神経伝達の変化を示唆するものであり、統合失調症を主とする精神病性障害の病態解明の一助となることが期待されます。
なお本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」および日本学術振興会・科学研究費補助金の助成により行われ、国際的な学術誌Scientific Reports(オンライン版)にて日本時間5月23日(火)に掲載されました。
![]() リリース文書[PDF:252KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:252KB](東大病院HP掲載)
(2017/5/24)
オートファゴソームはPI合成酵素が濃縮されている部位から形成される
~ オートファゴソーム形成初期過程の分子機構の一端を解明 ~
オートファジーは細胞内の代表的な分解システムです。オートファジーが誘導されると、オートファゴソームと呼ばれる二重膜構造体が細胞質の一部を取り囲みます。オートファゴソームを形成するためには多くのオートファジー関連タンパク質群(ATGタンパク質群)が必要ですが、実際どのようにオートファゴソームが形成されるかはまだ多くは不明です。
東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授、西村多喜助教(研究当時)らの研究グループは、ATGタンパク質群のなかでも最上流に位置するULK複合体が、まず小胞体膜に局在し、次にホスファチジルイノシトール(PI)3-キナーゼ依存的にATG9A陽性の隔離膜構造体に局在することを明らかにしました。さらに、ULK複合体が局在する小胞体膜上には、PI合成酵素が豊富に存在していることを見出しました。PIを分解させるとオートファゴソーム形成が阻害されたことから、小胞体膜上のPI合成酵素を含む部位がオートファゴソーム形成に重要であることが示唆されました。本発見は、オートファゴソーム形成初期過程の分子機構の全容解明の糸口になることが期待されます。
本研究成果は、2017年5月11日に国際科学誌「EMBO Journal」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 249KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 249KB]をご覧下さい。
(2017/5/23)
薬剤のみを用いて多能性幹細胞(ES細胞・iPS細胞)から三次元的に骨様組織を作製することに成功
ES細胞やiPS細胞といった多能性幹細胞から種々の細胞を作製し、培養皿上で三次元的に組織様構造体を作ることは、再生医療のみならず、組織形成過程の理解や治療用薬剤の開発に貢献すると考えられます。 作製にあたっては、安全性やコストの観点から、従来から用いられてきたウシ胎仔血清のように組成が不明なものや、遺伝子導入、組換えタンパク質を使用せずに、目的とする細胞を三次元的に誘導できることが理想的です。
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター臨床医工学部門の大庭伸介准教授と鄭雄一教授の研究グループは、薬剤のみを誘導剤として用い、組成が不明なものを一切含まない培養系(培地や担体の組成の全てが明らかな培養系)で、マウス多能性幹細胞から三次元的な骨様組織を作製する方法を開発しました。 本研究成果は、生体内の臓器を模倣した三次元組織を培養皿上や試験管内で作製する基盤技術となると期待されます。
本研究の内容は、2017年5月12日に、米国科学振興協会(American Association for the Advancement of Science: AAAS)のオンライン科学雑誌「Science Advances」で発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 476KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 476KB]をご覧下さい。
(2017/5/15)
オートファジーはマウスの聴覚に重要である
聴覚系の感覚細胞である、蝸牛有毛細胞は一度障害されると機能的回復は困難であり、その生存・恒常性維持は聴覚機能に非常に重要です。東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の藤本千里助教、山岨達也教授らは、細胞の恒常性維持に重要であるオートファジーが、マウスの聴覚機能に重要な役割を果たすことを明らかにしました。
藤本助教らは、オートファジーに必須の分子であるautophagy-related 5(Atg5)を有毛細胞にて欠損させた遺伝子改変マウスを作製し、有毛細胞におけるオートファジー活性が聴覚機能および細胞形態に及ぼす影響を検討しました。有毛細胞におけるAtg5の欠損により、マウスは先天性の高度難聴を呈しました。また、Atg5欠損マウス有毛細胞の組織学的検討では、14日齢において聴毛の変性、および一部の細胞の脱落を認めました。8週齢においては、有毛細胞の変性がさらに進行していました。
本研究により、有毛細胞における恒常的オートファジーは聴覚機能および細胞形態の維持に重要であることが示されました。オートファジーと聴覚障害の病態形成との関連性について、さらなる研究の進展が期待されます。
なお、本研究は、日本時間5月11日に英国科学雑誌「Cell Death & Disease」にて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:765KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:765KB](東大病院HP掲載)
(2017/5/15)
可逆的リン酸化反応による自律的な空間パターン形成
東京大学大学院医学系研究科の上田泰己教授らの研究グループは、可逆的リン酸化という細胞内で最もよく見られるタンパク質の翻訳後修飾反応を用いて、自律的な空間パターン形成が起こりうることを、コンピュータシミュレーションによって示しました。 多くの生命現象において観察される空間パターン形成のしくみを説明するために、反応拡散系と呼ばれるモデルがしばしば用いられます。 リン酸化などのタンパク質の翻訳後修飾によって空間パターンが形成されることを説明しようとするこれまでの多くの反応拡散モデルでは、パターン形成を誘導するために空間的な不均一性や自己触媒的な酵素反応メカニズムを前提としていました。
今回、研究グループはそうした前提のない、可逆的リン酸化とそれに関わる酵素・基質分子の自由拡散のみからなる系において、均一な初期条件から自律的に不均一な空間パターンが生じることを明らかにしました。 さらに、分子的な性質を記述するパラメータが、パターン全体の形を制御する仕組みも明らかにしました。 この結果は、自然界のパターン形成のメカニズム解明や、その調節を人工的に行う際に役立つと期待されます。
本研究成果は、「Cell Reports」2017年4月25日版(アメリカ東部夏時間)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 337KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 337KB]をご覧下さい。
(2017/4/26)
慢性胆管障害が胆管癌発症を促進するメカニズムを解明
胆管癌発症の危険因子として、原発性硬化性胆管炎や肝吸虫症などの慢性胆管障害・炎症の存在が以前から知られていましたが、そのメカニズムはよくわかっていませんでした。 特に肝臓の外の胆管にできる肝外胆管癌においては、適切な動物モデルが存在しないことが、病態解明を遅らせる大きな要因となっていました。 今回、東京大学医学部附属病院消化器内科の中川勇人助教、小池和彦教授らは、遺伝子改変技術によってヒトの病態を模倣した新しい肝外胆管癌マウスモデルさらにはオルガノイドモデルを樹立し、その発癌機序を解明するとともに、治療標的の候補となる分子を同定しました。
このモデルでは障害をうけた胆管上皮細胞がIL-33という分子を放出し、胆管上皮の幹細胞が存在すると考えられている胆管周囲付属腺という組織を増殖させることで胆管再生を誘導していました。 しかしながら遺伝子の異常によりこの反応が持続して胆管付属腺の増殖を抑制できなくなると、結果としてそこからの発癌を促進していることがわかりました。 IL-33の中和抗体を投与することによって発癌が抑制されたことから、IL-33が治療標的の一つとなる可能性が示唆されました。 本マウスモデルは胆管の慢性炎症からの癌化過程を模倣した世界初の画期的なモデルであり、機序解明・治療標的探索のツールとして今後大いなる発展が期待されます。 なお、本研究成果は4月24日の週(米国東部夏時間)に米国科学アカデミー紀要にて発表されます。
![]() リリース文書[PDF:332KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:332KB](東大病院HP掲載)
(2017/4/25)
心不全の新しいメカニズムを解明
千葉大学大学院医学研究院・真鍋一郎教授、自治医科大学・永井良三学長、東京大学大学院医学系研究科・藤生克仁特任助教/科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者、九州大学大学院理学研究院・岩見真吾准教授の研究グループは、心不全に係わる新しいメカニズムを解明しました。心不全や慢性腎臓病の新たな治療法に結びつくと期待され、実用化に向けて開発を進めています。
なお、本研究成果は日本時間4月11日に英国学術誌Nature Medicineにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:430KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:430KB](東大病院HP掲載)
(2017/4/11)
コレステロール運搬体(LDL)は薬も運ぶ
一般に悪玉コレステロールとも呼ばれるLDLは、血液中で水に溶けにくい脂質(コレステロールや中性脂肪など)を体の各組織に運搬する役割を担っています。LDLコレステロール値(濃度)が高いと、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患に繋がる動脈硬化症を発症する可能性が高まることから、これらの疾患のリスクを予測するためのバイオマーカーとして、多くの健康診断で検査されています。近年、LDLには脂質のみならず、ビタミンEやビタミンKなどの一部の栄養素も分布することが明らかとなり、さまざまな生体内物質の運搬にLDLが関わることが分かってきました。一方、病気の治療に用いられる薬も、服用後は血液中を循環して体の各組織に運ばれますが、薬の運搬にLDLが関与しているのかについては、これまで注目されていませんでした。
東京大学医学部附属病院薬剤部の山本英明大学院生(当時)、高田龍平講師、山梨義英助教、鈴木洋史教授らのグループは、水に溶けにくい性質をもつ薬の多くがLDLに分布すること、そして、それらの薬の体内挙動(血液中から体の各組織への移行)は、LDLコレステロールと同様にLDL受容体によって制御されていることを見出しました。
本研究の成果は、脂質のみならず薬の運搬体としても機能するLDLの新たな側面を明らかにするとともに、LDLの血液中濃度の変動を考慮した薬の投与設計や薬物治療の最適化に繋がるものと期待されます。
なお、本研究成果は日本時間4月4日にScientific Reportsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF:632KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:632KB](東大病院HP掲載)
(2017/4/5)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報