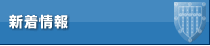広報・プレスリリース情報(2019年(令和元年))
がん全ゲノムにおけるマイクロサテライト不安定性の解明
~ がん免疫療法の適応診断や遺伝性腫瘍診断に有効 ~
理化学研究所(理研)生命医科学研究センターがんゲノム研究チームの藤本明洋副チームリーダー(研究当時、現 東京大学大学院医学系研究科教授)、中川英刀チームリーダーらの共同研究グループは、2,700例以上のがん全ゲノムシーケンスデータについて、「マイクロサテライト(MS)」と呼ばれる繰り返し配列の変異を同定し、その特徴を明らかにしました。本研究は、国際連携による全ゲノムがん種横断的解析プロジェクト(PCAWG)の一環として行われ、がん全ゲノムの「マイクロサテライト不安定性(MSI)」に関するこれまでで最も網羅的な研究と診断となりました。
本研究成果は、がん免疫療法の適応診断、遺伝性腫瘍の診断に有効であり、次世代のがんゲノム医療研究の進展に貢献すると期待できます。
高変異率のMSマーカーを用いたMSI判定は、現在、遺伝性腫瘍の診断やがん免疫療法の適応診断のために行われています。しかし、繰り返し配列の解析は非常に難しく、全ゲノムでどのようなMS変異が起きているかは不明でした。
今回、共同研究グループは、全ゲノムにおけるMS変異同定のための高精度解析法「MIMcall」を開発し、PCAWGで解析された2,717例の21種類のがんの全ゲノムシーケンスデータについて、1例あたり平均約765万カ所、合計約200億カ所のMS変異解析を行いました。その結果、ほとんどのMSに変異が見つかりませんでしたが、解析できたMS全体の約2.6%に当たる約20万カ所のMSにおいて複数個のがんゲノムに変異があることが分かりました。31例のがん(大腸がん、子宮体がん、胃がんなど)にMS変異が極端に多く見つかり、MSIと判定できました。さらに、高頻度に変異している20個のMSマーカーを新たに同定し、既存のMSマーカーと同程度の変異頻度を持ち、MSI判定の精度も同等であることが分かりました。
本研究は、科学雑誌『Genome Research』の掲載に先立ち、オンライン版(3月24日付:日本時間3月25日)に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/3/25)
好中球を介した腎がん肺転移メカニズムの解明
~ エピゲノムを標的とした新しい治療の可能性 ~
腎がんは、画像診断技術の向上から早期診断が可能になり、罹患数が年々増加しています。転移を有する進行腎がんの症例には、分子標的治療薬も使用されるようになっていますが、その治療成績は十分ではありません。腎がんの進展・転移の分子メカニズムが解明され、新たな治療法が確立されることが課題になっています。
このような現状で、東京大学大学院医学系研究科の西田純特任研究員(研究当時)、江帾正悟准教授、宮園浩平教授らの研究グループは、腎同所性移植法を用いて進行腎がんを再現し、がん細胞の性質を調べることで、腎がん肺転移の分子メカニズムの解明を試みました。その結果、進行腎がんのがん細胞は、ケモカインを強力につくりだすことで炎症を引き起こし、活性化された好中球が肺転移の成立に重要な働きをしていることをつきとめました。また、そのケモカインの産生には、スーパーエンハンサーを介したエピゲノム制御機構が関与することを見出しました。同時に、スーパーエンハンサーの活性を減弱させるBET 阻害剤を用いることで、マウスにおいて腎がん肺転移が抑制されることを発見し、この薬剤の有用性を実証しました。
この成果に基づき、腎がんの新たな治療法が創出されることが期待されます。本研究成果は「Nature Cell Biology」オンライン版に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/3/24)
統合失調症治療薬(ドーパミンD2受容体阻害剤)や妄想症状の機構を解明
脳内報酬物質といわれるドーパミンの2型受容体(D2受容体)は抗精神病薬の主要な標的ですが、シナプスや行動の制御機序は不明でした。東京大学大学院医学系研究科・IRCNの飯野祐介研究員、澤田健大学院生、山口健治研究員、河西春郎教授、柳下祥講師およびIRCN・京都大学工学部情報学研究科の石井信教授らのグループは、マウスの行動実験において光による神経活動の操作・観察技術を組み合わせることで、環境情報から報酬を予測する記憶が間違っていた際に側坐核で生じるドーパミンの一過性低下をD2受容体発現細胞が検出し、間違った記憶を訂正していることを発見しました。さらにマウスの脳スライスを光操作で観察したところ、微小なドーパミン信号変化をD2受容体が検出しスパインが頭部増大を起こすことを見いだしました。この鋭敏な検出機構は覚せい剤によりドーパミン濃度がわずかに亢進すると破綻しますが、D2受容体阻害薬(抗精神病薬)により回復しました。
本研究は脳の新しい学習原理を明らかにし、統合失調症などにおける精神病症状を説明する新しいシナプス仮説を導きました。
本研究は、文部科学省科学研究費助成事業 、IRCN、日本医療研究開発機構(AMED)、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)の支援を受けて、国際科学誌「Nature(電子版)」に2020年3月18日付オンライン版で発表されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/3/23)
動脈硬化における炎症の新しいメカニズムを解明
東京医科歯科大学難治疾患研究所の東島佳毅研究員、東京大学アイソトープ総合センターの神吉康晴助教らは東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームらと共同で、動脈硬化におけるエピジェネティックな転写抑制機構の破綻とそれに引き続く炎症性遺伝子活性化のメカニズムを明らかにしました。この成果は、これまで分かっていた動脈硬化における血管内皮細胞の炎症反応の誘導という現象が抑制系ヒストン修飾の脱メチル化というメカニズム介して起こることを示したという点で画期的です。さらに、このメカニズムのターゲット分子であるLysine demethylase 7A (KDM7A)および6A(UTX)を遺伝学及び薬理学的に抑制することで動脈硬化を改善できることを培養細胞およびマウスを用いた実験で示しています。動脈硬化は先進国における主要な死因である心血管疾患の原因の多くを占めることから、本研究成果が新しい動脈硬化治療法の開発、ひいては心血管疾患患者の予後改善に寄与することが期待されます。
※詳細は下記のページをご覧下さい。
東京大学アイソトープ総合センターホームページ プレスリリース詳細
(2020/3/9)
統合失調症における脳予測性の障害メカニズムの一端を解明
統合失調症を脳予測性の障害として説明しようとする研究が近年行われつつあります。脳予測性を反映すると考えられている指標としてミスマッチ陰性電位があり、統合失調症の患者さんではミスマッチ陰性電位が低下していることが知られています。しかし、ミスマッチ陰性電位のメカニズムとして音の繰り返しによる慣れの影響も指摘されており、統合失調症の患者さんではミスマッチ陰性電位の低下が脳予測性の障害を反映するのか、他のメカニズムを反映するのか、結論が出ていませんでした。日本学術振興会の越山太輔海外特別研究員、東京大学医学部附属病院精神神経科の切原賢治助教、笠井清登教授らの研究グループは、ミスマッチ陰性電位を計測する際に、通常用いられるオドボール課題に加えて、メニースタンダード課題を用いることで、統合失調症のミスマッチ陰性電位の低下が、脳予測性に関連する成分の障害に由来することを明らかにしました。この結果は、統合失調症におけるミスマッチ陰性電位の低下が、脳予測性の障害を反映することを示唆しており、今後のモデル動物を用いた治療法の開発に向けた研究への応用が期待されます。本研究は日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」などの支援により行われ、日本時間2月19日『Schizophrenia Bulletin』(オンライン版)にて発表されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/2/19)
マウスが見ている世界を再現:不安定な脳活動に隠された安定な知覚
目に入ってきた外の世界の情報は脳へと伝達され、脳細胞の電気的な活動へと変換されます。その脳細胞の活動が、我々の意識に上って来ることにより、私たちは外の世界を見ることが出来ていると考えられています。しかしながら、同じ画像を見ても、脳細胞の活動の様子は毎回異なり、安定していないことが知られています。このような不安定な脳細胞の活動を使って、どのようにして脳は視覚情報を処理しているのでしょうか。人を含む動物の脳がどのように外界からの視覚情報を処理しているのかを明らかにすることは、脳科学の分野において重要な問題の一つです。また、人工知能の分野における脳を模倣したニューラルネットワークの成功に見られるように、脳の視覚情報処理の解明は、優れた人工知能アルゴリズム開発への応用が期待されます。
東京大学大学院医学系研究科統合生理学分野/東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構の大木 研一教授、吉田 盛史助教の研究チームは、様々な画像に対するマウス一次視覚野の神経細胞の活動を網羅的に記録し、その活動からマウスが見ていた画像を再現する手法を開発しました。この手法を用いた解析により、一つ一つの画像の情報はごく少数の神経細胞活動から抽出できることを明らかにしました。また、同じ画像を見ても、脳細胞の活動の様子は毎回異なり、安定していないのですが、その不安定さにも関わらず画像の情報は安定して表現されていることを明らかにしました。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」、文部科学省科学研究費助成事業などの支援を受けて行われました。本研究の成果はNature Communications誌(2月13日付けオンライン版)に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/2/14)
統合失調症と関連するヒトの染色体微細欠失を再現した新しいモデルマウスを作製
統合失調症は、思春期から青年期にかけて発症し、陽性症状(妄想・幻覚など)、陰性症状(感情の平板化・活動意欲の低下など)を主要な症状とする精神疾患です。このほか、知能・記憶力・注意力・実行機能などの認知機能の障害も認められ、社会的機能の低下から日常生活に支障をきたします。統合失調症はおよそ100人に1人が罹患する頻度の高い精神疾患ですが、その原因や発症に関わるメカニズムは未だ明らかになっておらず、それに基づく治療法・診断法は確立されていません。そのため、発症メカニズムの解明や治療法開発の研究に適用できる有用な動物モデルの創出が求められています。
今回、東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター動物資源学部門の饗場篤教授、齋藤遼大学院生、名古屋大学大学院医学系研究科精神医学・親と子どもの心療学分野の尾崎紀夫教授、同大大学院医学系研究科医療薬学の山田清文教授、永井拓准教授、同大医学部附属病院ゲノム医療センターの久島周病院講師、同大脳とこころの研究センターの森大輔 特任准教授らの共同研究グループは、高い統合失調症の発症リスクを伴う22q11.2欠失症候群に着目し、ゲノム編集技術を用いて、この症候群の原因である染色体の微細欠失[3.0-Mb(メガベース)の22q11.2欠失]をマウスで再現することに成功しました。この遺伝子改変マウスを解析したところ、プレパルス抑制の低下や視覚誘発電位の異常という統合失調症と関連する表現型が観察されました。
本研究により、22q11.2欠失というヒトの染色体微細欠失を再現した、新しい統合失調症モデルマウスが作製されました。このモデルマウスは、統合失調症の発症メカニズムの理解や治療法の開発に貢献することが期待されます。
本研究は、日本医療研究開発機構「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」の一環として行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/2/7)
胃の前がん病変の真の起源を同定~これまでの定説を覆す
ヘリコバクター・ピロリ菌の感染などによる慢性胃炎は、正常の胃粘膜を障害し腸上皮化生と呼ばれる前がん病変を胃内に生み出し、最終的に胃がんを引き起こすものと考えられています。これまでの報告では、前がん病変である化生性細胞は、正常の胃粘膜に存在し消化酵素などを分泌する主細胞と呼ばれる特定の細胞群が、ピロリ菌などの炎症刺激によって脱分化することで生じるものと考えられてきました。しかし、主細胞が化生性細胞やがんに変化していく詳細な時間経過やメカニズムについては分かっていませんでした。今回東京大学消化器内科の畑昌宏医師、木下裕人助教(研究当時)、早河翼助教、小池和彦教授らのグループは、独自に作成した新規のマウスモデルを用い、主細胞は胃粘膜障害の過程で脱分化せずに消失し、実際には化生性細胞の起源とはなりえないことを証明しました。これまでの報告で用いられていたマウスモデルはいくつかの致命的な欠点がありましたが、早河翼助教らの新しいマウスモデルはこうした欠点を補完し、化生性細胞の発生をより精密に再現することを可能にしました。その結果、これまで主細胞が脱分化していたために生じていると思われていた数々の現象が、実は主細胞が死んでいく様を反映していたものに過ぎず、化生性細胞の真の起源は胃に元々存在する幹細胞および前駆細胞だったことが分かりました。これは、これまでの定説を真っ向から覆す驚くべき知見です。さらに、この主細胞の消失が、主細胞に選択的に発現しているGPR30という受容体を介した細胞競合というメカニズムによって生じることを明らかにしました。今回の新しい発見により、胃の前がん病変の真の起源とその発生メカニズムが明らかになったことから、今後の胃がん研究のさらなる発展と新規胃がん治療の開発に結び付く可能性があります。本研究は科研費若手研究(A)、AMEDの革新的先端開発支援事業(PRIME)、次世代がん医療創生研究事業(P-CREATE)などの支援を受け、岐阜大学・東京理科大学・豪州アデレード大学・米国コロンビア大学などの協力の下に行われました。 本研究成果は、米科学誌『Gastroenterology』に掲載されるのに先立ち、2月4日にオンライン版にて公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/2/5)
慣性(Inertia)が患者の薬剤選択に影響を与える
~ 「ナッジ」が後発医薬品促進に有効 ~
後発医薬品(ジェネリック薬)の使用は、先発医薬品に比べて低価格にもかかわらず、諸外国に比べて低率です。その要因としては、先発医薬品への高い選好(価値付け)や消費者の慣性(Inertia)という行動パターンが考えられます。Inertiaとは、消費者が以前に選択したものを引き続き選択する行動パターンのことを指し、近年の研究で様々な場面におけるInertiaの存在が明らかにされています。しかし、患者の先発/後発医薬品の選択に影響を与えているか否かの報告はこれまでありませんでした。
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学客員研究員の伊藤佑樹(研究当時:博士課程大学院生)、経済学研究科特任研究員の原湖楠(研究当時:博士課程大学院生)、公衆衛生学の小林廉毅(教授)のグループは、大規模な後期高齢者医療広域連合の2013年9月から2014年8月までの医科・調剤レセプトの匿名データを用いて、患者の薬剤選択におけるInertiaの影響を調べました。脂質異常症の治療薬であるピタバスタチンの後発医薬品が調査期間中(2013年12月)に発売されたことに着目し、発売前後の患者の先発/後発医薬品間の選択を分析しました。
ピタバスタチンの先発医薬品は後発医薬品と比べて、自己負担額にして1日あたり3-5円程度負担が増えます。それに対して、平均的な患者は先発医薬品を後発医薬品に比して4.7円/日ほど高い選好(価値付け)をもつことが示されました。また、平均的な患者にとってInertiaの効果は3.1円/日程度の大きさであり、先発医薬品に対する患者の選好(価値付け)の約2/3の大きさであることが示されました。これらの値はそれぞれ統計学的に有意なものでした。また、シミュレーションの結果として、Inertiaを取り除く何らかの施策を実施した場合、総医療費に換算すると、施策を導入しない場合に比べて、12%の削減効果を認めました。
本研究の結果から、先発/後発医薬品の選択においてInertiaが大きな影響を持つことが示唆されました。それと共に、Inertiaを取り除くような施策、つまり行動変容を促す「ナッジ」と呼ばれる施策が有効である可能性が示唆されました。本研究成果は国際学術誌「Journal of Economic Behavior & Organization」(オンライン出版日:2020年1月21日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/1/23)
成人期発症の大脳型副腎白質ジストロフィーに対する造血幹細胞移植の臨床効果
国が定める指定難病に登録されてい神経系の難病である副腎白質ジストロフィーは、国内の患者数が400人程度と推定され、病状の分類も多彩です。そのひとつ、大脳型副腎白質ジストロフィーは、もともと小児科領域でよくみられる疾患で、小児期の大脳型(120人程度の患者数)に対しては発症早期の造血幹細胞移植が有効であることが確立されてきおり、早期に診断、治療することが重要と考えられています。一方で、成人の大脳型については、その患者数は120人程度と推定されており、比較的頻度の高い臨床病型ですが、造血幹細胞移植の報告例が少なく、その治療効果はさまざまで、成人の大脳型副腎白質ジストロフィーに対する造血幹細胞移植の治療効果は、確立されていませんでした。
そこで、成人大脳型副腎白質ジストロフィーに対する造血幹細胞移植の治療効果を明らかにするため12症例に対して移植を行い、長期間の観察に基づき、治療効果を評価しました。その治療効果は顕著で、症状の進行を抑制できることが示されました。すなわち、早期に診断して早期に造血幹細胞移植を行うことで、病状の進行を止める事が可能となります。造血幹細胞移植を行った12症例と、行うことができなかった8症例について、大脳・小脳などの病変の出現時点を起点として生存率を比較すると、造血幹細胞移植を行った症例では全員生存しており、有意に生存率が高いという結果が得られました。診療現場では、診断が遅れ、治療のタイミングを逸してしまうケースが少なくなく、本症の早期診断が大切であることを広く認識していただくことが大切であると考えられます
なお本研究は、一部、日本医療研究開発機構(AMED)「難治性疾患実用化研究事業(課題名:オミックス解析に基づく希少難治性神経疾患の病態解明)」、文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」の支援により行われ、日本時間1月14日に国際科学誌Brain Communicationsに掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/1/15)
筋肉の神経支配に必要な25型コラーゲンの機能を解明
~ 先天性の脳神経発達異常の病因が明らかに ~
筋肉の動きを制御する信号は、脊髄の運動ニューロンから伸びる軸索が筋肉との間に形成するシナプス(神経筋接合部)を介して伝達されます。しかし、発生の過程で筋肉に到達した神経が、筋肉に対する直接の支配を促す分子機構は未解明でした。
東京大学大学院医学系研究科の岩坪威教授と若林朋子特任助教らのグループは、胎生期の筋肉に発現する25型コラーゲンが、筋肉の神経支配に必須であることを明らかにしました。また、受容体型チロシン脱リン酸化酵素であるPTPσ/δがその結合相手として働くことも見出しました。これまでに、眼球や瞼を動かす外眼筋を支配する運動ニューロンの先天的な発達異常を示す患者さんから、25型コラーゲン遺伝子の変異が見つかっていました。本研究では、それらの変異が25型コラーゲンとPTPσ/δとの結合、ひいては軸索との結合を障害する結果、筋肉の運動神経支配に異常を来すことを明らかにしました。
本研究により、25型コラーゲンが、その存在は長らく予想されながらも実体の不明であった筋肉由来の軸索発達促進因子である可能性が示されました。今後はさまざまな神経筋疾患の発症原理の理解や、治療的応用にもつながってゆくと期待されます。この成果は日本時間12月25日にCell Reports誌に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/12/25)
低〜中等度の飲酒もがん罹患のリスクを高める
世界的に、低〜中等度の飲酒によるがん罹患リスクの上昇が注目されています。しかし、日本では、低〜中等度の飲酒とがん罹患のリスクの関連に着目した研究は少なく、容量反応関係なども詳細には明らかになっていませんでした。そこで、東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室の財津將嘉助教 (Harvard T.H. Chan School of Public Health 研究員兼任)は、同教室の小林廉毅教授と、Harvard T.H. Chan School of Public HealthのIchiro Kawachi教授らとともに、独立行政法人労働者健康安全機構が保有している全国33箇所にある労災病院から登録された入院患者の病職歴データベースを用いて、新規がん63,232症例および性・年齢・診断年・病院が等しい良性疾患対照63,232症例を同定し、低〜中等度の飲酒とがん罹患のリスクの関連を多施設症例対照研究として求めました。
その結果、がん全体についてみると、飲酒をしなかった人が最もがん罹患のリスクが低く、また、飲酒した人のがん全体の罹患リスクは低〜中等度の飲酒で容量依存的に上昇し、飲酒指数が10 drink-yearの時点で(例えば1日1杯を日常的に10年間継続)オッズ比が1.05倍に上昇しました。喫煙習慣、生活習慣病、職業階層で調整しても、同様の傾向が観察されました。また、各種がんによって低〜中等度の飲酒の影響は様々でしたが、大腸がん、胃がん、乳がん、前立腺がん、食道がんなどの比較的頻度の高いがんが、本研究で観察された低〜中等度の飲酒による全体的ながん罹患リスクの上昇に関わっていることが示唆されました。
本研究により、日本では、低〜中等度の飲酒においても、がん罹患のリスクが軽度上昇する可能性が明らかになりました。現在、日本の死因の第1位はがんであり、がんを予防するため、飲酒によるがん罹患リスクの啓発活動をさらに強化する必要があると考えられます。本研究成果は、American Cancer Societyが発行する国際的医学雑誌である「Cancer」に、オンライン先行掲載されました(2019年12月9日)。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/12/9)
複数の精神疾患に共通する大脳白質の異常を発見
~ 統合失調症と双極性障害に共通の異常 ~
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)精神保健研究所 精神疾患病態研究部の橋本亮太部長、東京大学医学部附属病院精神神経科の越山太輔医師(留学中)、同科の笠井清登教授(東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)らの研究グループは、認知ゲノム共同研究機構(COCORO)によるオールジャパンでの多施設共同研究体制のもと、日本全国の12の研究機関から統合失調症 696名、双極性障害 211名、自閉スペクトラム症126名、うつ病(大うつ病性障害)398名、健常者1506名の計2937名のMRI拡散強調画像データを収集し、大脳白質微小構造についての大規模解析を行いました。統合失調症においては、健常者と比較して、鉤状束、脳梁体、帯状束、脳弓のFAの低下やMD、AD、RDの増加が認められました。
次に精神疾患共通及び特異的な異常についての検討を行いました。健常者に比べ、統合失調症、双極性障害、自閉スペクトラム症では大脳白質領域のひとつである脳梁体に共通してFAの低下もしくはMD、RDの増加が見られ、特に統合失調症と双極性障害では、脳弓や帯状束のような大脳辺縁系の白質領域に共通してFAの低下もしくはMD、AD、RDの増加が見られました。一方で、健常者と比べた場合に統合失調症にのみ、鉤状束のような大脳新皮質同士をつなぐ大脳白質領域にMD、AD、RDの増加が見られることがわかりました。
しかしながら健常者とうつ病では大脳白質領域に微小構造の違いは見られませんでした。疾患同士での直接比較では、統合失調症と双極性障害との間に大脳白質領域の微小構造の違いは見られませんでした。一方で、統合失調症および双極性障害ではうつ病よりも大脳辺縁系領域でMDとRDが増加しており、これらは統合失調症および双極性障害と健常者との間の違いと同じようなパターンが見られました。以上の結果により、統合失調症と双極性障害は似通った病態生理学的特徴をもち、うつ病は健常者に近い生物学的特徴を有しているかもしれないことが本研究で新たに明らかにされました。また、自閉スペクトラム症では、脳梁体にのみFAの低下が見られたため、自閉スペクトラム症もまた、より健常者に近い生物学的特徴を有しているかもしれないことがわかりました。本研究の成果は、近年進みつつある精神疾患の客観的診断法の開発に役立つと考えられます。
本研究成果は、日本時間2019年11月29日(金)午前10時に「Molecular Psychiatry」オンライン版に掲載されました。
※詳細は下記のページをご覧下さい。
国立精神・神経医療研究センターホームページ プレスリリース詳細
(2019/12/2)
名誉教授 藤田敏郎先生 Homer W. Smith Award 受賞
2019年11月上旬にワンシントンDCで開催された米国腎臓学会(ASN)において、名誉教授の藤田敏郎先生が、ASNの最高栄誉賞であるHomer W. Smith賞を受賞されました。藤田先生はNIHに留学し、食塩と高血圧の研究を始められました。帰国後、筑波大学を経て東京大学医学部腎臓・内分泌内科教授を長く勤め、定年退職後現職(東京大学先端科学技術研究センター・フェロー)の今日に至るまでの間、一貫して食塩感受性高血圧の機序解明に取り組み、Nature Medicine誌やJ Clin Invest誌等の一流誌に数多くの研究成果を報告されてきました。Rac1による鉱質コルチコイド受容体活性化機序や視床下部-腎臓交感神経活性化によるβ受容体-NCC経路を解明し、腎生理の分野において顕著な研究業績を挙げ、また、食塩感受性高血圧における世界的第一人者としての活躍が高く評価されたことが主な受賞理由です。特筆すべきは、これらの基礎研究で得られた結果を、我が国では実施困難とされた医師主導の二重盲検比較臨床試験(EVALUATE 試験)によって証明されたことです。本賞は第一回の1964年から今回で56回目を迎え、ASNの最も伝統ある賞で、アジア人では初めての受賞です。
(2019/11/29)
キネシン分子モーターKIF3Bの遺伝子異常は統合失調症の原因となる
統合失調症は日本人の100人に1人が罹る精神疾患であるが、その生物学的な病態にはまだ不明な点が多く、それに基づいた治療薬もまだ開発の途上にある。今回、東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻の廣川信隆特任教授、アルサバンアシュワック特任研究員(研究当時)、森川桃特任研究員、田中庸介講師、武井陽介准教授(研究当時、現・筑波大教授)らの研究チームは、キネシン分子モーターKIF3Bの異常が統合失調症の分子的基盤になることを発見した。チームはまず患者さんの遺伝子データから、KIF3Bの遺伝子異常を同定した。次に、KIF3Bの発現が半分に減っているKif3bヘテロ欠損遺伝子操作マウスを作って解析してみると、記憶・学習能力の低下や聴覚驚愕応答のプレパルスによる減弱の低下という統合失調症に特有の表現型が観察された。さらに、このマウスの神経細胞ではNMDA型グルタミン酸受容体の樹状突起スパイン表面における発現量が減少し、記憶・学習の基盤となるシナプス可塑性の変化が観察された。そこで、患者さんの変異を導入したKIF3Bタンパク質と野生型のKIF3Bタンパク質をそれぞれKif3bヘテロ欠損神経細胞に導入して活性を調べたところ、確かに患者さんではKIF3Bタンパク質の機能が低下していることがわかった。本研究から、統合失調症に対する新規治療法開発の基盤となる、細胞レベルでの新しい病態が解明された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/11/21)
肺動脈性肺高血圧症の疾患関連遺伝子ATOH8の同定
肺動脈性肺高血圧症(PAH)は厚生労働省の指定難病に認定されている病気で、さまざまな原因により心臓から肺に血液を送るための血管(肺動脈)の細い部分(肺細動脈)が異常に狭くなり、肺動脈の血圧が上昇して右心不全をきたします。PAH患者では骨形成因子(BMP)の働きに関係した遺伝子の異常が多く見つかっているので、病気の発症・進展にBMPが関与していると考えられています。しかし、その役割については完全には解明されていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の森川真大 助教、鯉沼代造 准教授、宮園浩平 教授、三重大学の三谷義英 准教授、丸山一男 教授の研究グループは、京都大学の影山龍一郎 教授、スウェーデン ウプサラ大学のCarl-Henrik Heldin(カールヘンリク・ヘルディン)教授らとの国際共同研究で、BMPに関係する新規疾患関連遺伝子候補の網羅的解析を行った結果、これまで詳細な機能が知られていなかった転写因子ATOH8を見出しました。さらに、肺動脈血管内皮細胞のBMPからATOH8に至る信号伝達経路は、低酸素応答で中心的な役割を果たすHIF-2αの蛋白量を減らすことで低酸素に対して保護的役割を果たし、肺高血圧症の発症・進展に関わっていることを、ゼブラフィッシュ、マウス、ヒト培養細胞を用いた解析で明らかにしました。本研究の成果は、PAHの発症・進展におけるBMPの役割の解明につながるとともに、将来的な新規治療法の開発に大きく貢献することが期待されます。
本研究は、文部科学省科学研究費補助金、科学研究費助成事業 新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御」、グローバルCOEプログラム「生体シグナルを基盤とする統合生命学」、などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/11/13)
将来の認知症治療薬・予防薬の開発へ
認知症のプレクリニカル期・プロドローマル期を対象とした50~85歳の健常者2万人の登録を目指す、国内最大のオンライン研究への参加者募集プロジェクト
『トライアルレディコホート(J-TRC)構築研究』を10月31日より開始!
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻・神経病理学分野、附属病院 早期・探索開発推進室(教授 岩坪 威/いわつぼ たけし)では、認知症の治療薬・予防薬を早期に実用化することを目標に、認知症のプレクリニカル期・プロドローマル期の研究への参加者を、オンライン上で募集する国内最大規模のプロジェクト、『トライアルレディコホート(J-TRC)構築研究』を10月31日より開始します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
「J-TRC」サイトURL: https://www.j-trc.org/
(2019/11/7)
子宮移植、代理懐胎、養子縁組に対する国内の意識調査について
東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科の平田哲也医師、女性外科の大須賀穣教授らは、子宮移植、代理懐胎、養子縁組に対する国内の意識調査を行いました。ロキタンスキー症候群などの先天的に子宮を持たない女性は、自らの子宮で妊娠、出産をすることは不可能です。また、これらの女性が児を得るには、養子縁組や代理懐胎などの選択肢がありますが、代理懐胎は、多くの倫理的、社会的問題のために日本では行われていません。最近、海外では、そのような女性に対して、研究段階ですが、子宮移植という新たな方法が行われています。そして、2014年にスウェーデンのグループより、生体ドナーからの子宮移植で出産に成功したという報告が、2019年にブラジルのグループより、脳死ドナーからの子宮移植で出産に成功したという報告がありました。世界で既に10名以上のこどもが生まれています。日本でも、臨床研究に向けた指針が策定され、今後、子宮移植を臨床研究として行われる可能性があります。一方で、子宮移植は、安全性の問題、倫理的、社会的問題を内包しています。以前に20代30代の女性を対象とした意識調査で、40%以上の人が子宮移植に肯定的であったとの報告がありました。しかしながら、意識調査としては、ドナーとなる可能性のある40代以上の女性や男性の意見も反映されるべきと考えました。そこで今回、子宮移植に対する意識調査を20歳~59歳の男女を対象に行いました。
子宮性不妊の患者に対する「子宮移植」や「代理懐胎」に対する意識は、肯定的な意見が否定的な意見を上回っていました。さらに、その差は性別、年齢、不妊経験の有無、子宮移植に対する知識の程度に影響を受けていることもわかりました。また、肯定的な意見の理由で最も多かったのが「子宮移植が子宮性不妊の患者にとっての希望になること」、否定的な意見の理由で最も多かったのが、「子宮移植のための手術のリスクが高い」でした。一方で、ほとんどすべての質問において30%以上の人が「わからない」と答えています。また、子宮移植の知識のレベルが高いことで、「わからない」と答えた人が減り、子宮移植に対する肯定的意見は増えました。また同時に、否定的な意見は女性では変わりませんでしたが、男性では増えました。このことから、より広く社会的合意を得るためには、子宮移植の発展と安全性についての知識を提供し、議論を活発化させる必要があると考えられます。また、代理懐胎について肯定的な意見も少なくなく、子宮移植とともに同時に議論していく必要性も示唆されました。本研究成果は、これらの結果も踏まえて、今後の子宮移植に関する課題に向き合う早期のルール作りにつながることが期待されます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「成育疾患克服等総合研究事業」の「生殖補助医療により出生した児の長期予後と技術の標準化に関する研究(研究開発代表者:苛原稔)」及び「生殖補助医療の技術の標準化と出生児の安全性に関する研究(研究開発代表者:苛原稔)」により実施され、日本時間10月31日に米国の科学雑誌PLOS ONEにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/11/1)
急性腎障害(AKI)における炎症の新しいメカニズムを解明
東京大学医学部附属病院の前川洋医師、東京大学大学院医学系研究科の稲城玲子特任教授らは、急性腎障害(acute kidney injury:AKI)におけるミトコンドリアの機能異常とそれに引き続く炎症誘導のメカニズムを解明しました。この成果は、これまでわかっていたAKIにおける尿細管のミトコンドリア障害と炎症反応の誘導という二つの現象がミトコンドリアDNAによる自然免疫機構の活性化というメカニズムを介して起こることを示したという点で画期的です。さらに、このメカニズムのターゲット分子であるstimulator of interferon genes(STING)というタンパク質を遺伝学及び薬理学的に抑制することでAKIを改善できることをマウスを用いた実験でも示しています。AKIは入院患者で高い罹患率を有し、重症例では透析が必要となり死亡率を上昇させることから、本研究成果が新しいAKI治療法の開発、ひいてはAKI患者の予後改善に寄与することが期待されます。本研究成果は日本時間10月30日にCell Reports(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/10/31)
硫化水素の産生過剰が統合失調症に影響
~ 創薬の新たな切り口として期待 ~
理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター分子精神遺伝研究チームの井出政行客員研究員(筑波大学医学医療系講師)、大西哲生副チームリーダー、吉川武男チームリーダー、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部の木村英雄教授、福島県立医科大学医学部神経精神医学講座の國井泰人准教授、東京大学大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授らの共同研究グループは、脳内の硫化水素の産生過剰が統合失調症の病理に関係していることを発見しました。
本研究成果は、硫化水素というシグナル分子を標的とした、統合失調症に対する新たな創薬の切り口になると期待できます。
今回、共同研究グループは、統合失調症に関係するマウス系統とそうではない系統で、網羅的なプロテオミクス解析を行い、硫化水素産生酵素の一つであるMpstタンパク質の上昇の関与を見いだしました。また、ヒト由来の試料を用いた解析から、統合失調症での硫化水素の産生過剰を示すデータを得ました。特に、統合失調症患者の死後脳におけるMPSTタンパク質の高発現は、生前の臨床症状の重篤さに関連し、毛髪中のMPST遺伝子の発現量は感度の優れたバイオマーカーになる可能性が示されました。さらに、持続的な硫化水素の産生過剰が生じる原因は脳発達期の炎症・酸化ストレスに対する代償反応の一環である可能性、そのメカニズムとしてエピジェネティック変化が根底にあることを明らかにしました。なお、硫化水素の産生過剰は、エネルギー代謝の減少、スパイン密度の低下などを引き起こし、それらが統合失調症のリスクにつながることも示しました。
本研究は、ヨーロッパ分子生物学機構の科学誌『EMBO Molecular Medicine』のオンライン版(10月28日付け:日本時間10月28日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/10/29)
コモン・マーモセットの大脳皮質運動野を光刺激することで腕の運動を誘発することに成功
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻生理学講座細胞分子生理学分野の松崎政紀教授(理化学研究所脳神経科学研究センター脳機能動態学連携研究チーム チームリーダー)、蝦名鉄平助教、自治医科大学分子病態治療研究センター遺伝子治療研究部の水上浩明教授、自然科学研究機構生理学研究所生体システム研究部門の南部篤教授、理化学研究所脳神経科学研究センター高次脳機能分子解析チームの山森哲雄チームリーダーらの研究チームは、霊長類コモン・マーモセット大脳皮質運動野の神経活動を光遺伝学の技術で操作(光刺激)することによって腕の運動を誘発できる事、また運動関連領域を網羅的に光刺激することで、異なった方向への腕の動きが運動野の中の別々の領域で表現されている事を明らかにしました。
マーモセットはヒトと似た生物学的な特徴を持っており、遺伝子改変動物を含む疾患モデルの開発が進められています。今回開発した技術によって、運動学習やリハビリの過程で起こる健常脳の機能再編や、パーキンソン病などの運動失調の異常機構への理解が進み、運動失調をもたらす精神・神経疾患に対する新たな治療方法の開発が期待できます。本研究は、日本医療研究開発機構『革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト』の一環として行われました。
本研究の成果はProceedings of National Academy of Sciences of the United States of America誌に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/10/23)
酸化ストレスによる統合失調症の発症メカニズムを解明
~ カルボニルストレスを伴う統合失調症におけるタンパク質の機能異常を発見 ~
東京大学大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授と理化学研究所の吉川武男チームリーダーらの共同研究グループは、カルボニルストレスを伴う統合失調症においてCRMP2タンパク質がカルボニル化修飾を受けて多量体化し、その細胞骨格の制御機能を失うことが疾患発症の分子基盤の1つである可能性を示しました。 カルボニルストレスは酸化ストレスの一種で、反応性カルボニル化合物の増加や反応性カルボニル化合物の除去機構の低下により引き起こされる代謝状態であり、統合失調症患者のおよそ2割においてカルボニルストレスが亢進していることが近年報告されています。 しかしカルボニルストレスがどのような分子メカニズムで統合失調症に関わっているのか、特に神経発達に及ぼすメカニズムはこれまで不明でした。 共同研究グループは、カルボニルストレスを伴う統合失調症の患者で変異が確認されたカルボニルストレス除去機構に関わるGLO1遺伝子に着目し、この遺伝子を破壊したiPS細胞を作製したところ、このiPS細胞から作成した神経細胞は神経突起の伸長低下を示しました。 また、このiPS細胞の中でカルボニルストレスによってカルボニル化修飾(AGE修飾)を受ける主要なタンパク質として、神経突起の伸長に関わるCRMP2を同定し、質量分析によってiPS細胞内でのCRMP2の全修飾部位を決定しました。 さらにこのカルボニル修飾を受けたCRMP2の構造をX線結晶解析などにより詳細に解析し、CRMP2の機能に重要である2量体・4量体形成部位にカルボニル化修飾が集積していることを見出しました。 さらに、カルボニル化されたCRMP2は不可逆的に多量体化してしまうために、細胞の骨格である微小管を束化する機能が失われることを明らかにしました。 今回の研究成果から、これまで不明であったカルボニルストレスを伴う統合失調症の分子病態、特に神経発達段階での新しい分子経路が明らかになり、CRMP2のカルボニル化を阻止、ないしは改善する創薬が新たな統合失調症の治療標的となる可能性が期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/10/8)
心不全患者の予後や治療応答性を高精度で予測する手法を開発
心不全は、さまざまな原因により心臓の機能が悪くなり、息切れやむくみが生じ、がんと並んで世界中の人の命を脅かす病気です。心不全の経過や治療に対する効果は非常に多様であり、治療薬が効いて心臓の機能が回復する患者がいる一方で、あらゆる治療を尽くしても心臓機能が回復せずに早い段階で心臓移植をしなければ命を救うことができない患者もいます。このような治療に対する効果や予後(病状の経過)を治療前に評価できれば、患者一人ひとりに合った適切な治療を施すことが可能になる(これを個別化医療・精密医療と言います)と考えられますが、現段階ではまだ簡便かつ正確に治療応答性(薬による効果)を予測することが難しいため、基本的に画一的な治療を施すしかありません。
東京大学医学部附属病院 循環器内科の小室一成教授、野村征太郎特任助教、候聡志特任研究員、同大大学院医学系研究科の藤田寛奈大学院生、同大先端科学技術研究センターの油谷浩幸教授らの研究グループは、これまでに、マウスを用いた心不全の病態解明研究を行い、心不全になると心臓にある心筋細胞の核の中のDNAにキズが生じ(DNA損傷と言います)、このDNA損傷の程度が心不全の病態の程度を規定している可能性を見出していました。
今回新たに、本研究グループは、ヒトの心筋細胞のDNA損傷の程度を解析する手法を開発し、58例の心不全患者(本研究では拡張型心筋症という原因不明の心筋障害により心不全となった患者を対象に解析)の心筋DNA損傷の程度を解析しました。すると、治療応答性や予後が悪い患者において、治療前の心筋DNA損傷の程度が有意に強いことがわかりました。さらに解析を進めたところ、治療前の心筋DNA損傷の程度によって、非常に高い精度で(感度・特異度ともに8割程度)治療応答性を予測できることを明らかにしました。これらの成果により、心不全患者の「治療応答性の事前予測」を可能にする手法を開発することができました。本手法の開発は長らく待たれていたところであり、また、臨床現場において診断目的で採取する心筋生検組織の検体を用いる方法であることから、患者への追加となる侵襲が存在しないことも非常に大きな利点です。さらに、心不全の治療において、近年叫ばれている患者一人ひとりに合った「個別化医療・精密医療」を実践する上での基盤的技術となると考えられます。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「DNA損傷応答・核形態の機械学習による心不全の予後・治療応答予測モデルの構築」、ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業(先端ゲノム研究開発)「マルチオミックス連関による循環器疾患における次世代型精密医療の実現」等の支援により行われ、日本時間9月26日に米国の科学雑誌JACC: Basic to Translational Science(Article in Press)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/9/26)
リポタンパク質の分泌の仕組みの解明に新たな手がかり
~ 小胞体膜タンパク質VMP1 の新規機能を発見 ~
脂質は水に溶けにくい性質を持っています。そのため、小腸から吸収した脂質や、肝臓で合成した脂質を全身の組織に供給するには、脂質を運搬タンパク質と結合させてリポタンパク質という水に溶けやすい状態にする必要があります。リポタンパク質は、小胞体の膜内で合成されたコレステロールや中性脂質が小胞体内腔へ離脱し、リン脂質一重層とアポリポタンパク質に取り囲まれることで形成されます。しかし、この過程の分子メカニズムには不明な点が多く残っています。
今回、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、マサチューセッツ州立大学のZhao Yan(チャオ・ヤン)博士、東京医科歯科大学の酒巻有里子氏、岡崎三代名誉教授らと共同で、オートファジーに必要な小胞体膜タンパク質VMP1 が、リポタンパク質の小胞体膜から内腔への離脱にも必要であることを、ゼブラフィッシュ、マウス、ヒト培養細胞を用いた解析から明らかにしました。最近、ヒトVMP1 遺伝子の一塩基多型(SNP)と血中のコレステロール値との関連が報告されていますので、本研究の成果は、リポタンパク質の形成・分泌機構の解明につながるとともに、脂質異常症などの疾患の理解に貢献することが期待されます。
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)、日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)の計画研究「オートファジーの生理・病態生理学的意義とその分子基盤」、および若手研究「ゼブラフィッシュを用いたオートファジー関連因子群の生理機能の解明」(研究代表:森下英晃)の支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/9/20)
がん細胞を骨に引き寄せる有害な可溶性タンパク質の発見
~ がん骨転移の新たな治療法の開発に期待 ~
骨はがんが転移しやすい部位の一つです。がんが骨に転移すると、激しい骨痛や骨折、麻痺など、がん患者のQOL (生活の質)低下に直結する症状を来し、予後悪化に繋がります。近年免疫チェックポイント阻害剤の登場により、がん治療は大きな変革期を迎えようとしていますが、いまだがん骨転移の予防法・治療法は確立できていません。サイトカインRANKLは破骨細胞分化の必須因子であり、現在その中和抗体が、骨折などがん骨転移に伴う症状を抑える薬として用いられています。しかしながら、がん細胞が骨に転移するプロセス自体を阻害できる治療法は存在しません。また抗RANKL抗体は、転移していない正常な骨の破骨細胞機能も総じて阻害するため、低カルシウム血症等の副作用にも配慮することが必要です。一方、RANKLは細胞膜結合型と可溶型の二種類の形態を取ることが知られていましたが、両者の機能的な違いについてはよく分かっていませんでした。
東京大学医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学分野の浅野 達雄 特任研究員と高柳 広 教授、骨免疫学寄付講座 岡本 一男 特任准教授らの研究グループは、可溶型RANKLのみを欠損させた遺伝子改変マウスを作製し、膜結合型RANKLと可溶型RANKLの生体内における役割の違いについて検討しました。その結果、破骨細胞分化や免疫組織形成には膜結合型RANKLが中心に働いており、可溶型RANKLは必要ないことが判明しました。一方で、可溶型RANKLはがん細胞を骨に引き寄せることで、がん骨の転移に関与していることが明らかとなりました。本研究成果より、血中の可溶型RANKLが骨転移の発症リスクを予測できるバイオマーカーとして有用である可能性が示されました。また、可溶型RANKLを標的とすることで、従来の抗RANKL抗体療法よりも副作用の少ない骨転移治療の開発に繋がると期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/9/10)
キネシンによる軸索基部形成の時間的空間的制御機構の解明
正常な神経伝達回路を形成するためには、神経細胞の多数の突起から1本だけを軸索に分化させ、他の神経細胞の樹状突起へと接続することが必要です。軸索基部は軸索のタンパク質だけを軸索内部へと輸送させる関門として働いており、神経の成長過程において、軸索基部の形成が神経突起を軸索へと分化させる重要な1ステップであると考えられてきました。しかし、どのような時期に、どのような制御機構のもとで、どのような分子群が軸索基部を形成するのか、詳細は不明でした。このたび東京大学大学院医学系研究科の一ノ瀬聡太郎 特任研究員(研究当時)、小川覚之 助教、蒋緒光 大学院生、廣川信隆 特任教授の研究グループは、キネシンモータータンパク質KIF3複合体による神経軸索への物質輸送に着目した解析を進め、kif3bヘテロノックアウトマウス由来の培養神経細胞やKIF3複合体のリン酸化解析により軸索基部形成の時間的空間的制御機構を明らかにしました。神経軸索基部の形成に重要なリン酸化酵素と基質およびリン酸化部位を同定し、リン酸化によって神経軸索基部形成分子の輸送が制御されている仕組みを解明したことにより、これらの分子群の異常によって生じる病気の病因の解明や、軸索基部異常と関連があるてんかんや自閉症などの精神疾患の新規治療薬開発の基盤となると考えられます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/9/4)
死亡前3か月間の訪問介護利用が高齢者の在宅死と関連
~ 望む場所での最期を支える環境整備を ~
世界の人口構造は高齢化が進んでいます。先進国では2050年までに4人に1人が65歳以上の高齢者となり、日本では同年に2.5人に1人が高齢者になると推計されています。それに伴い高齢化社会に備えた医療・介護サービス提供体制の整備が進んでいます。国内外の調査においては、多くの高齢者が自宅で最期を迎えることを望んでいます。また、高齢者が望む場所で療養して最期を迎えることができたときに、その家族の満足度が高いことが報告されています。ところが、日本における病死及び自然死であった65歳以上の在宅死亡割合は12.3%であり、73.4%が病院で最期を迎えています(2017年)。つまり、日本の高齢者が望む死亡場所と実際の死亡場所には大きな隔たりがあります。
自身が在宅療養を行うか否かを検討する際に、70%以上の高齢者が家族にかかる介護負担を気にかけると答えています。そこで、東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の小林廉毅教授と阿部計大特任研究員らは筑波大学などの研究者らと共同して、介護保険制度下で提供されている訪問介護サービスが高齢者の死亡場所にどのような影響を及ぼしているのか分析しました。統計法による承認を得て全国の介護給付費実態調査と人口動態統計死亡票等の代表性のあるリアルワールドデータを用いて分析したところ、死亡前3か月間に訪問介護サービスを利用すると在宅死の確率が高くなることが示されました。訪問介護サービスを利用しない場合に比べて、死亡前月に利用した場合は9.1%(95%信頼区間, 2.9-15.3)、死亡2か月前から利用した場合は10.5%(3.3-17.6)、死亡3か月前から利用した場合は11.4% (3.6-19.2)だけ在宅死の確率が高いことが分かりました。訪問介護サービスの利用を通して、高齢者やその介護者の身体的、精神的な負担が軽減することで、在宅療養の継続やその結果としての在宅死が可能となった可能性が推察されます。
日本の高齢者の多くが自宅での最期を望んでいるものの、実際には自宅以外の場所で最期を迎えていることを考慮すると、訪問介護サービスを利用しやすいように各自治体の環境を整え、自宅で療養し、自宅で最期を迎えたいと望む高齢者とその介護者を支援することが求められます。
本研究は2019年8月27日、国際学術誌「BMJ Open」にオンライン掲載されました。引き続き、日本で提供されている介護サービスが高齢者やその介護者にもたらす影響について研究を進め、制度の異なる他国との情報共有を進めて行く必要があります。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/8/30)
新たなヒト血液型「KANNO」の国際認定
~ 国立国際医療研究センターなど、日本の研究グループとして初めての登録 ~
国立国際医療研究センター・ゲノム医科学プロジェクトの徳永勝士プロジェクト長、大前陽輔特任研究員らの研究グループは、ヒトゲノム解析により、これまでに国際輸血学会に登録されている36種類の血液型に加え、37種類目の新たな血液型「KANNO(カノ)」を特定し、この度国際輸血学会の血液型命名委員会から認定を受けました。 これは日本の研究グループが特定した初めての血液型です。 この新たな血液型「KANNO」を決める血液型抗原はプリオンタンパク質というクロイツフェルト・ヤコブ病の原因となる分子であり、今回特定された血液型を決める変異はプリオン病抵抗性との関連も注目されます。
私たちの血液には非常に多くの血液型があります。 なかでも、ABO血液型とRh血液型は輸血をするうえで極めて重要な血液型であることはよく知られています。 安全で有効な移植や輸血のためには、その他の血液型も一致することが重要で、これまでに36種類の血液型が国際輸血学会によって公認されていました。
今回、国立国際医療研究センター、日本赤十字社、福島県立医科大学の共同研究チームは、日本医療研究開発機構(AMED)ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業(先端ゲノム研究開発)による支援のもと、KANNO抗原という、既知の血液型と一致しない血液を持つ人の全ゲノム解析を行うことによって、その血液型抗原とその変異を同定し、KANNOが新たな37番目の血液型であることを明らかにしました。 これは日本の研究グループが原因を特定した初めての血液型であり、この度国際輸血学会から血液型「KANNO」として認定を受けました。 その抗原は意外にもプリオンタンパク質でした。 これはクロイツフェルト・ヤコブ病などのプリオン病の原因ともなる分子で、KANNO(–)(マイナス)型ではこのタンパクの一つのアミノ酸が変化しています。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/8/8)
全国レセプトデータにおける糖尿病診療の質指標を測定
~ 網膜症検査・尿検査実施割合の低さと都道府県別・施設別のばらつきが課題 ~
糖尿病が悪化したまま放置すると、失明や透析、足切断など重篤な合併症を引き起こすことがあり、糖尿病は透析導入原因の第1位、視力障害原因の第3位と報告されています。 そのため、糖尿病診療では血糖、血圧などのコントロールの他に、合併症を早期診断するために合併症検査を定期的に行うことが重要です。 これまで、一部の保険者や施設における適切な検査の実施割合は報告されてきましたが、全国における状況を調べた研究はありませんでした。
東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座の門脇孝特任教授、国立国際医療研究センター 研究所 糖尿病情報センターの杉山雄大室長などで構成される研究グループは、全国で行われた保険診療のほぼ全ての情報が含まれている大規模データ「レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)」を用いて、2015年度に糖尿病薬の定期処方を受けている外来患者が、糖尿病治療ガイド(日本糖尿病学会 編・著)等で推奨されている糖尿病関連の検査を受けている割合を糖尿病診療の質指標として測定しました。 また、都道府県別、日本糖尿病学会認定教育施設としての認定有無別の指標も計算し、更に施設単位の指標のばらつきを観察しました。
研究の結果、約415万人の当該患者において、血糖コントロール指標(HbA1cまたはグリコアルブミン)を測定したのは96.7%、網膜症検査を受けたのは46.5%(都道府県別範囲:37.5%−51.0%、認定有無別:44.8%(認定無し)対59.8%(認定有り))でした。 診療報酬から尿検査の施行を観測できる200床未満の病院と診療所で診療を受けた患者のうち、尿定性検査を受けたのは67.3%(都道府県別範囲:54.1%−81.9%、認定有無別:66.8%対92.8%)、尿アルブミンまたは蛋白の定量検査を受けたのは19.4%(都道府県別範囲:10.8%−31.6%、認定有無別:18.7%対54.8%)でした。 施設別指標の分布を見ると、網膜症検査、尿検査の実施割合のばらつきが特に大きく、尿定量検査は認定無しのほとんどの施設で行われていないと同時に、認定教育施設でも実施割合の低い施設が少なからずあることが判明しました。
本研究には200床以上の施設における尿検査の実施割合が反映されていないなど限界もあり、解釈の際には注意が必要です。 一方で、今回の結果を受けて、医療従事者が着実な検査実施に注意を払うことで、今後の糖尿病診療の質が向上することが期待されます。 また、今回の結果は都道府県が医療計画等を立案する際の資料になるなど、エビデンスに基づいた政策立案を推進することが考えられます。
本研究は厚生労働科学研究補助金、循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究」(研究代表者 門脇孝)の一環で行われた研究であり、国際糖尿病連合が発行する“Diabetes Research and Clinical Practice”の電子版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/8/8)
日本人集団ゲノムにおける、未検出のゲノムの欠失の発見と機能的意義の解明
東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類遺伝学分野のWong特任研究員、藤本教授らのグループは、30-5000塩基の欠失を正確に検出する方法を考案した。この方法を用いて、先行研究において次世代シークエンサーで決定された174人の日本人ゲノムを解析し、日本人集団で多型的な(個人差が大きい)約4000個の欠失を発見した。また、長鎖シークエンサー(Oxford Nanoporeシークエンサー)を用いて全ゲノムシークエンスを行い、その結果と比較したところ、一致率が97%であり、今回の方法の精度が高いことが示唆された。
そこで、欠失と遺伝子発現量の関連について調べたところ、約4%の欠失が遺伝子発現の個人差と関連していた。また、遺伝子発現の個人差に関連する欠失をそれ以外の欠失と比較したところ、関連する欠失は遺伝子発現を調整するスーパーエンハンサー領域やプロモーター領域に多かった。遺伝子発現に関連する欠失のうち2つ(イントロンの中にある欠失と約1万塩基離れた遺伝子の発現量に関連する欠失)を選び、ゲノム編集技術CRISPR-Cas9法を用いて細胞株に導入したところ、遺伝子発現量が変化し、これらの欠失が機能的であることが強く示唆された。
本研究は、これまで検出が難しかった欠失を高い精度で検出する方法を構築し、欠失の個人差の中には遺伝子発現量に直接影響するものが存在することを示した。この方法を疾患研究に適用することで、新たな疾患関連遺伝子の発見につながると考えられる。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/7/27)
別々の3疾患に共通する原因がヒトゲノムCGG塩基の繰り返し配列の異常伸長であることを解明
神経核内封入体病は、近年、認知症を呈する神経変性疾患の一つとして注目されており、発症年齢は幼少期から高齢まで幅広く分布し、家族性の発症もあることが知られていましたが、その原因は不明でした。東京大学医学部附属病院の分子神経学講座 辻省次特任教授、脳神経内科 石浦浩之助教および東京大学大学院新領域創成科学研究科 森下真一教授らの研究グループは、発症者の全ゲノム配列のデータから、未知の繰り返し配列の異常伸長を効率良く検出できる解析プログラム(TRhist)を開発し、NBPF19 遺伝子の5’非翻訳領域に存在するCGG繰り返し配列の異常伸長が原因であることを発見しました。
そして、次の2疾患にも同様の異常伸長が認められました。
白質脳症を伴う眼咽頭型ミオパチーは、頭部MRI画像で神経核内封入体病に類似した大脳白質の異常を示し、加えて眼球の運動を司る筋肉、嚥下・発声を担う咽頭の筋肉、四肢の筋肉を侵す疾患です。解析の結果、LOC642361・NUTM2B-AS1という別の遺伝子に、同じCGG繰り返し配列の異常伸長が存在することを見いだしました。
眼咽頭遠位型ミオパチーは、眼球運動、咽頭、さらに四肢の遠位部の筋力低下が特徴的な筋疾患で、国が定める指定難病の一つである、遠位型ミオパチーに含まれる疾患です。前述の白質脳症を伴う眼咽頭型ミオパチーと筋の罹患部位の分布が非常に類似していることをヒントに解析した結果、LRP12遺伝子に、やはりCGG繰り返し配列の異常伸長変異が存在することを見いだしました。
上記の3疾患はこれまで別個の疾患と考えられていましたが、MRI所見や症状に重複する部分が存在し、原因遺伝子は異なっても、共通してCGG繰り返し配列の異常伸長が認められたことから、CGG繰り返し配列の異常伸長そのものが、その病態機序において中心的な役割を果たしていることが明らかとなりました。
本研究成果は、日本時間7月23日に国際科学誌Nature Geneticsにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/7/25)
思春期に家族や友人を大切にしていた人ほど自殺しにくい
~ 思春期における身近な人を大切にする価値観の有無と、成人期における自殺念慮の発症の関連性を確認 ~
思春期は人間の成長過程において、生物学的にも社会学的にも重要な時期であり、その時期に形成された価値観(思春期主体価値)は、その後の人生における考え方、行動様式、健康やwellbeing(幸福)に影響を与えるといわれています。しかし、思春期主体価値と成人期における自殺関連行動(自殺念慮、自殺の計画、自殺企図)の発症の関連については明らかにされていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野の安間尚徳大学院生、川上憲人教授らは、思春期主体価値が自殺関連行動の発症にどのような影響を及ぼすかに着目し、20歳から50歳までの東京および周辺地域の住民を対象とした、まちと家族の健康調査(J-SHINE)の2010年と2017年の調査データを用いて研究を行いました。思春期主体価値は、シュワルツ理論に基づいて独自に作成した11の価値領域に関する調査票と日本語版Personal Values Questionnaire II (PVQ-II)による価値へのコミットメントに関する調査票を用いて測定し、研究参加者に15歳時を想起して回答してもらいました。その結果、思春期において、家族や友人などの身近な人を大切にすることを重要な価値とすることは成人期における自殺念慮の生涯経験、過去12か月の経験と有意な負の関連を認め、また価値にコミットすること(価値をどれくらい大事にし、これに沿って行動するか)も自殺念慮の過去12か月の経験と有意な負の関連を認めました。
本成果は、思春期主体価値と自殺関連行動の発症との関連を示した世界で初めての研究です。今後は、家庭や学校などの教育現場において、身近な人を大切にするという価値を大事にすること、自分の価値にコミットすることを促すことが検討されると、成人期における自殺念慮の発症予防に、大きなインパクトをもたらすことが期待されます。なお、本成果はBMC Groupの専門誌「BMC Psychiatry」に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/7/17)
肝静脈血流の速度変化(肝静脈波形)を数値化した新しい肝線維化診断法の開発
慢性肝炎によって肝臓は線維化をきたし、肝硬変・肝臓がんへと進行してしまいます。したがって慢性肝疾患においては肝線維化がどの程度進行しているかを正確に診断することが重要です。肝線維化の診断は肝生検による組織学的な評価で行うとされますが、この方法は患者の負担が大きく制約があります。最近では肝生検に代わる肝線維化評価法として、エラストグラフィを用いた肝臓の硬さを測定する機器が登場しましたが、測定のためには高額な専用機器が必要となり、本来リスクの高い慢性肝疾患患者を拾い上げるための健診施設などで普及されるには至っていません。そうした背景から、より簡便かつ正確な肝線維化評価法の登場が望まれています。
東京大学医学部附属病院 検査部の揃田陽子登録研究員、佐藤雅哉助教、矢冨裕教授、同院 消化器内科の中塚拓馬助教、中川勇人特任講師、小池和彦教授らの研究グループは、肝臓の静脈を流れる血流速度の変化(肝静脈波形)を超音波パルスドプラ法で解析し数値化したものが、肝線維化の優れた指標となることを明らかにしました。さらに、本手法はエラストグラフィと違って肝臓の脂肪沈着や炎症の影響を受けにくい可能性があることも分かりました。
本研究で開発された手法は、一般の超音波機器に標準搭載されるパルスドプラを利用した非常に簡便なものであり、健診などで肝臓の状態を評価するツールとして広く実用化される可能性があります。また、生体内で計測される波形変化を定量化する技術はこれまでによいものがなく、本研究で開発された技術は肝臓以外の様々な生体情報に対する応用も期待されます。
本研究成果は日本時間の2019年7月12日に学術誌Ultrasound in medicine and biology(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/7/16)
リスク細分化した腎代替療法(透析・腎移植)導入率を初めて算出
~ 健診結果と医科レセプトを用いた約5年間の縦断分析 ~
わが国では毎年約39,000人が新規に透析導入となっており、そのうち4割の原疾患が糖尿病です(糖尿病性腎症)。現在、日本医師会、日本糖尿病対策推進会議、厚生労働省は、ハイリスク者に対して受診勧奨・保健指導等を行うことで新規透析導入者を減らすことを目指す「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を、各自治体において推進しています。しかし、プログラム開始時点でどのようなリスクを持つ者が何年後に透析導入に至るかという詳細な情報は今までほとんど明らかにされていませんでした。東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の小林廉毅教授と杉山雄大特任研究員らは、関東の1政令市における国民健康保険被保険者の健診結果と医科レセプトを用いて、種々のリスク因子で細分化した腎代替療法(透析・腎移植)導入率を初めて算出しました。
2012年度の健診受診時39~74歳の被保険者約50,000人を最大5年間フォローアップした結果、37名が腎代替療法を導入していました(導入率0.21/1,000人年、全て透析導入)。健診で高血圧でない者が約半数いましたが、この群から腎代替療法を導入した人は皆無でした。高血圧投薬あり群、糖尿病投薬あり群、蛋白尿あり群における導入率はそれぞれ0.60/1,000人年、1.40/1,000人年、3.17/1,000人年でした。その他、高齢、男性、喫煙、推定糸球体濾過量(eGFR)の低下などがリスク因子として同定されました。糖尿病性腎症病期分類3期(顕性腎症期)の者の導入率は1.18/1,000人年、糖尿病のない慢性腎臓病(CKD)重症度分類G3b(eGFR 30〜44)の者の導入率は1.23/1,000人年で、両者はほぼ同程度の率でした。
「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」ではその名のとおり糖尿病患者のみをプログラム対象者としていますが、糖尿病でない腎機能低下者にも腎代替療法導入のハイリスク者が存在することが明らかになりました。今回の研究成果は「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」において、対象者選定やプログラム評価の際の重要な資料となることが期待されます。
本研究は2019年6月26日に学術誌「Tohoku Journal of Experimental Medicine」(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/7/1)
心臓の線維化を予防する因子オンコスタチンMを同定
心臓の線維化は収縮能の保持された心不全Heart failure with preserved ejection fraction(HFpEF)の原因になることが知られています。HFpEFの治療は現状困難であり、特に心筋組織の線維化がどのように制御されているかについてはこれまで明らかではありませんでした。
東京大学医学部附属病院 循環器内科 武田憲彦特任講師らの研究グループは、心臓に集積するマクロファージが心臓の線維化を抑制していることを明らかにしました。心不全の病態において心筋組織が低酸素状態になることに着目し、マクロファージが産生するサイトカインであるオンコスタチンMが心臓線維芽細胞の活性化を制御することを同定しました。オンコスタチンMの抗線維化作用に注目することで、今後心不全に対する新たな治療アプローチを開発できる可能性が期待されます。
本研究は、日本時間6月27日に英国科学誌Nature Communications(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/7/1)
東京大学、国立がん研究センター研究所、コニカミノルタ、 グローバル最先端の次世代がん遺伝子パネルに関する共同研究開発を開始
~ ゲノム分野の医療技術開発を牽引する産学連携強化 ~
東京大学先端科学技術研究センター 油谷 浩幸教授および当時の東京大学大学院医学系研究科 間野 博行教授(現国立がん研究センター研究所 細胞情報学分野長)が中心となり開発してきた世界最先端の東大オンコパネルを基盤とし、コニカミノルタグループの米国Ambry Genetics Corporationが保有するグローバルな遺伝子診断技術の知見を融合させる共同研究開発を行い、世界最高峰の次世代包括的がん遺伝子パネル検査を開発します。
DNAパネルにおけるがん原性の体細胞遺伝子変異の対象の多さとRNAパネルにおける融合遺伝子検出解析等とに強みをもつ東大オンコパネルと、コニカミノルタ傘下で、生殖細胞系列遺伝子変異検出技術で世界をリードし、世界に先駆けて生殖細胞系列遺伝子変異を評価するRNA検査を商品化した米国Ambry Genetics Corporationの強みを掛け合わせたシナジー効果が期待されます。
開発された次世代包括的がん遺伝子パネル検査は、日本のがんゲノム情報管理センター(C-CAT)のがんゲノム情報レポジトリーの拡充に寄与します。更に、コニカミノルタがグローバルに展開・普及させることにより、世界レベルでのがんゲノム情報蓄積を図ります。これらにより、日本人特有の遺伝子変異の解明、革新的ながん治療法や診断法の開発、新薬の創出、患者の生活の質(Quality of Life: QOL)の向上や、膨張する医療費の抑制などへの貢献をめざしています。
本共同研究開発により、がん遺伝子パネル検査の高機能化を推進するとともに、ゲノム分野の医療技術開発を牽引する産学連携を強化します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/6/7)
医学系研究科 畠山昌則 教授が紫綬褒章を受章
この度、医学系研究科病因・病理学専攻微生物学講座微生物学分野の畠山昌則教授が春の褒章で紫綬褒章を受章しました。これは医学研究の発展への貢献が評価されたことによるものです。
畠山教授は永年にわたって、医学教育ならびに分子腫瘍学・感染腫瘍学の研究に尽力し、基礎医学研究の進展と若手研究者の育成に大きく貢献されました。特に、ヘリコバクター・ピロリ感染を基盤とする胃がん発症機構に関する先駆的な研究を展開し、ピロリ菌の病原タンパク質CagAが細胞をがん化させることをマウス個体レベルで明らかにしました。細菌がウイルス同様に発がん因子を持つことを世界で初めて示した研究成果として位置付けられます。ピロリ菌CagAは菌が保有する注射針様のIV型分泌機構によって胃上皮細胞内に直接注入されます。畠山教授は、CagAが極性制御キナーゼPAR1の抑制を介して胃粘膜の上皮極性を破壊するとともに、発がん性ホスファターゼSHP2の脱制御により異常な細胞増殖シグナルを生成することで細胞がん化を促す機構を解明しました。さらに、X線結晶構造解析ならびにNMRによりCagAの三次元構造を明らかにし、CagA-PAR1相互作用ならびにCagA-SHP2相互作用の構造基盤を解明するとともに、CagAを標的とする胃がん抑制化合物の探索への道を拓きました。これらの優れた業績に対し、平成18年 JCA-Mauvernay Award、平成23年 佐川特別賞、平成26年 日本医師会医学賞、平成28年 野口英世記念医学賞などを受賞されています。
研究の詳細については、畠山研究室の下記ホームページをごらんください。
http://www.microbiol.m.u-tokyo.ac.jp/
(2019/5/31)
人工知能により患者データから肝がんの存在を予測
~ 患者データからがんの存在を予測するAIの開発 ~
多要因が組み合わさり発症するさまざまな“がん”に対し、単一腫瘍マーカーでの存在予測には限界があり、患者背景や臓器の炎症などの情報も統合することが望ましいと考えられます。情報技術に大きな進展をもたらしたニューラルネットワークを用いたディープラーニングの登場により近年注目される機械学習は、複数因子を組み合わせる際に関数の最適化を行い、予測能を最大化させるアルゴリズムを作成することを可能とします。
東京大学医学部附属病院 検査部の佐藤雅哉 助教、矢冨裕 教授、同院 消化器内科の建石良介 特任講師、小池和彦 教授らおよび島津製作所基盤技術研究所 AIソリューションユニット 梶原茂樹 主幹研究員らの研究グループは、ディープラーニングを含むさまざまな手法から、収集された患者データから得られる予測能を最大化する学習アルゴリズムと学習パラメーターを自動抽出するフレームワークを作成し、患者データを用いた肝がんの有無の予測精度を検討しました。
肝がんの有無の予測には、腫瘍マーカーの他、背景肝の線維化や炎症、肝炎ウィルスの有無、患者年齢などが重要であることが知られています。これらに関連する検査項目を含めた16項目の患者データを、本フレームワークを用いて統合することで、従来の腫瘍マーカーと比較して診断率が飛躍的に向上しました。
ディープラーニングは多くの分野で革新的な成果をもたらした非常に強力な学習アルゴリズムですが、その複雑さのために大きな成果を生み出すには莫大な量のサンプルが必要になります。今回1582人の患者(肝がん患者539人、非肝がん患者1043人)を対象とした肝がん予測に対しての最適アルゴリズムはディープラーニングではない、従来の手法でした。
患者を対象とする医学研究においては、同意取得の必要性や倫理的な側面への配慮から、多数の(数万人の)患者サンプルを収集することは現実的に困難です。このような状況の中で、現存するデータに対して予測能を最大化するアルゴリズムを抽出することは非常に重要です。本フレームワークは肝がんに限らず、さまざまなデータに適用が可能であり他分野への応用も期待されます。
本研究成果は日本時間の2019年5月30日に学術誌Scientific Reports(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/5/31)
日本と韓国では管理職・専門職男性の死亡率が高い
~ 日本・韓国・欧州8カ国を対象とした国際共同研究で明らかに ~
欧米では一般的に管理職・専門職の死亡率が低いのに対し、日本においては1990年代後半(バブル経済崩壊後の「失われた20年」の初期)に管理職・専門職男性の自殺率を含めた死亡率が上昇したことが報告されています。この特徴的な健康格差(死亡率格差)の全体像を明らかにするため、東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の小林廉毅教授と田中宏和氏(研究当時:同博士課程大学院生)らはオランダのエラスムス大学医療センターのヨハン・マッケンバッハ(Johan P. Mackenbach)教授らの研究グループと国際共同研究を行い、日本と韓国および欧州8カ国における職業階層別死亡率の格差を分析しました。
欧州8カ国では全ての国で非熟練労働者(生産工程従事者・運転従事者など)の死亡率が最も高く、上級熟練労働者(管理職・専門職)の死亡率が最も低い傾向が継続して観察されました。一方で2015年の日本と韓国においては上級熟練労働者の死亡率が、農業従事者に次いで、最も高くなっていました。日本では1990年代後半、韓国では2000年代後半、それまで最も死亡率の低かった上級熟練労働者の死亡率が上昇し、他の職業階層の死亡率と傾向が逆転するという変化が観察されました。韓国では管理職・専門職男性の死亡率上昇はいわゆるリーマン・ショックに端を発した世界金融危機の時期と一致していました。なお、同じ時期に欧州各国と日本では特定の職業階層での死亡率上昇は観察されませんでした。さらに欧州においては死亡率が高い非熟練労働者の死亡率が日本と韓国では低く、特に日本で健康格差が小さいことが明らかになりました。
本研究により、日本と韓国において「管理職・専門職男性の死亡率が高い」という点が、欧州と異なる職業階層別死亡率格差の要因であることが明らかになりました。今後の展望として、日本と韓国における管理職・専門職の高い死亡率の要因の分析を進め、健康格差縮小に向けた施策につなげていきたいと考えています。
本研究は日本時間5月29日に英国の疫学・公衆衛生専門誌「Journal of Epidemiology and Community Health」(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/5/30)
ヒトパピローマウイルス(HPV)関連中咽頭がんのゲノム・エピゲノム異常の全体像を解明
ヒトパピローマウイルス(HPV)によって引き起こされる中咽頭がん(HPV関連中咽頭がん)は、同じウイルスを原因とする子宮頸がんよりも患者数の増加が著しい悪性腫瘍であり、比較的若年者に生じることから、その克服が大きな課題となっています。HPVと関連がない中咽頭がんと比べてがん関連遺伝子変異などゲノムの異常が少ない一方、DNAメチル化などのエピゲノムの異常が多いことが知られていますが、その全体像は明らかになっていません。
東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科の安藤瑞生講師らは、米国カリフォルニア大学のJoseph Califano教授らと共同で、次世代シーケンサーを用いてHPV関連中咽頭がんのゲノムにみられる遺伝子異常、エピゲノム異常の全体像を解明しました。そして、エピゲノム異常の標的が遺伝子転写開始点にあることを世界で初めて明らかにしました。また、HPV関連中咽頭がんの患者さんの中に、DNAメチル化が高度に生じている(高DNAメチル化腫瘍)症例を見出し、この一群に特徴的な発がん経路の活性化があることも解明しました。
この成果は、HPV関連中咽頭がんの病態解明に貢献し、治療の最適化の実現に役立つものと期待されます。本研究は、文部科学省科学研究費(国際共同研究加速基金)の支援を受けて行われ、日本時間5月16日に英国科学誌Nature Communications(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/5/20)
脳情報動態の多色HiFi記録を実現する超高感度カルシウムセンサーの開発に成功
カルシウム(Ca2+)が神経発火に伴い細胞内に流入することを生かして、蛍光Ca2+センサーを用いて脳情報を解き明かす試みが近年急速に広まっています。しかしながら、従来のCa2+センサーは、1)遅い反応動態のため発火パターンの読み取りが不十分であることと、2)蛍光の色が少なく、用途が制限されていました。特に、脳は複数の異なる神経細胞種の協調的な発火パターンにより正常機能を発揮すると考えられていますが、これを解明するための高性能多色Ca2+センサーの開発が望まれていました。
この度、東京大学大学院医学系研究科の井上昌俊 特任助教(研究当時)、竹内敦也 大学院生(研究当時)、尾藤晴彦 教授らの研究グループは、山梨大学総合研究部医学域の真仁田聡 助教、喜多村和郎 教授らと共同で生きた哺乳類脳の神経発火活動・シナプス活動を計測するための超高感度・超高速Ca2+センサーの青、緑、黄及び赤色の『XCaMP』シリーズを開発しました。その結果、マウス生体内において高頻度発火神経細胞の発火パターンの読み取り及び3種の異なる細胞種の多重計測に成功しました。この成果は、今後生きた哺乳類脳における神経活動およびそのダイナミクスの多重計測を容易にし、精神疾患や学習・記憶障害などの病態解明および治療法の開発につながるものと期待されます。本研究は日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト(革新脳)」の研究開発課題「革新的プロ-ビングによる神経活動の高速3D測定と活動痕跡の長期可視化」、ならびに文部科学省新学術領域研究「脳情報動態」の支援によって実施されました。
本研究成果は、「Cell」(アメリカ東部夏時間2019年5月9日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/5/10)
がんの発症・進展におけるヒアルロン酸の「ジキルとハイド的」役割
細胞外基質の主要構成成分であるヒアルロン酸は、組織の構造維持や水分保持などに深く関わっており、最近では、美容医療や整形外科領域でヒアルロン酸投与が行われています。今回、東京大学大学院医学系研究科の畠山昌則教授らの研究グループは、分子サイズの大きなヒアルロン酸(高分子量ヒアルロン酸)ががん抑制性の細胞内シグナル経路であるHippoシグナル経路を活性化する一方、高分子量ヒアルロン酸の分解によって生じる分子サイズの小さなヒアルロン酸(低分子量ヒアルロン酸)はHippoシグナルの不活化を介してがんの発症・進展を逆に促すことを明らかにしました。さらに、予後不良な乳がんとして知られるトリプルネガティブ乳がんでは高分子量ヒアルロン酸の分解酵素であるHYAL2が過剰発現しており、高分子量ヒアルロン酸の分解産物である低分子量ヒアルロン酸がHippoシグナルを抑制することでがんの悪性度増強に寄与することを見出しました。今後、ヒアルロン酸や HYAL2を分子標的とすることで、トリプルネガティブ乳がん等への革新的な予防・治療法開発が期待されます。同時に、本研究は若返りや美容を謳ったヒアルロン酸の安易な使用に警鐘を鳴らすものです。
本研究成果は、「Developmental Cell」(アメリカ東部夏時間2019年5月9日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/5/10)
シナプス可塑性の最初の数分間でアクチン線維は再編される
~ 細胞内の微小空間でおこる分子動態を解読する新しい技術 ~
東京大学大学院医学系研究科の小橋一喜特任研究員、岡部繁男教授、京都大学工学研究科の井上康博教授らの研究グループは、細胞内の分子動態を読み出す技術である蛍光相関分光法(FCS)、ラスター走査画像相関分光法(RICS)と二光子励起の技術を組み合わせて、細胞内の微小体積からの分子動態情報を読み出す手法を開発しました。この手法により神経細胞の樹状突起スパイン(スパイン)内での分子の動きを測定することが可能になりました。スパインは記憶・学習の基盤とされているシナプス可塑性によってその性質が変化します。それに伴ってスパイン内部でアクチン線維が変化し、分子の動きも変化すると考えられてきましたが、直接的な測定は不可能でした。新技術によりスパイン内の分子動態を直接測定した所、大きな分子に限ってスパイン内での動きがアクチン線維によって抑制されていること、更にシナプス可塑性誘発直後の数分間だけ抑制が解除されることがわかりました。分子量の大きな複数の情報伝達分子でこのような抑制の解除が観察され、この現象はシナプス可塑性に伴う情報伝達分子の分布の変化にも関与していました。以上の結果は、非常に短時間だけ分子の動きが変化することが、記憶学習の基盤となるシナプス可塑性に重要な役割を持つという新しい可能性を提案するものです。
本研究成果は、「Cell Reports」4月30日オンライン版(米国東部夏時間)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/5/7)
オートファジーによる小胞体分解の新規受容体を発見
マクロオートファジー(以後、オートファジー)とは、オートファゴソームが細胞質の一部を取り囲み、リソソーム(多数の分解酵素を含む細胞小器官)と融合することで分解する細胞内分解システムの一つです。従来オートファジーは非選択的な分解機構(非選択的オートファジー)と考えられてきましたが、最近になって傷ついた細胞小器官や変性たんぱく質、細胞内病原体などを選択的に識別して分解できること(選択的オートファジー)もわかってきました。また、これらの選択的に分解されるターゲットのほとんどは、オートファゴソーム膜上のたんぱく質LC3と結合する性質を持っていることも明らかにされてきています。
東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究センターの夏目徹研究センター長らのグループと共同で、オートファジーによって選択的に分解される分子の同定を目的とし、LC3分子種の一つであるLC3Bに結合するたんぱく質を網羅的に探索しました。その結果、細胞小器官の一つである小胞体に存在する膜貫通たんぱく質TEX264の同定に成功しました。TEX264を欠損させた細胞ではオートファジーによる小胞体の分解(小胞体オートファジー)が顕著に抑制されたため、TEX264は小胞体オートファジーに関与する主要な受容体として機能していると考えました。さらに、TEX264に存在する長く柔軟な天然変性領域が、リボソーム(直径約20ナノメートル)により隔てられている小胞体とオートファゴソームの間を連結していることが明らかになりました。本研究成果は、オートファジーによって小胞体の品質を保つことの生理的重要性や細胞内の恒常性維持機構への関与、その破綻と疾患との関連の解明につながると考えられます。
本研究は科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)、日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)の計画研究「オートファジーの生理・病態生理学的意義とその分子基盤」として行われました。
本研究成果は、「Molecular Cell」(米国東部夏時間4月18日:オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/4/19)
2型糖尿病におけるインスリン抵抗性がアルツハイマー病脳のアミロイド蓄積を促進するメカニズムを解明
アルツハイマー病(AD)は老年期の認知症として最も頻度の高い疾患です。AD患者の脳に特徴的な病理変化として、アミロイドβペプチド(Aβ)からなる老人斑があり、Aβの蓄積はAD発症の原因であると考えられています。近年、2型糖尿病がAD発症のリスクとなることが明らかになっています。特に、2型糖尿病の中心的な病態であるインスリン抵抗性がADの発症を促す可能性が予測されてきました。しかし、インスリンシグナルの変化とAβの蓄積との因果関係は未解明でした。
東京大学大学院医学系研究科の岩坪威教授らの研究グループは、脳にAβの蓄積を生じるADモデルマウスを用い、高脂肪食により誘発されたインスリン抵抗性と、インスリンシグナルの鍵分子であるIRS-2の欠損に伴うインスリン抵抗性による影響を比較、解析しました。その結果、インスリンの作用低下そのものではなく、インスリン抵抗性発症の要因となる代謝ストレスが、Aβの脳内の除去速度を低下させ、結果として蓄積を促進することを示しました。また、食事制限により、脳のAβ蓄積は可逆的に抑制できることを明らかにしました。
2型糖尿病がAD発症のリスクとなることは広く知られてきましたが、本研究はその背後にあるメカニズムの一端を解明し、未だ確立していないADの治療法創出に向け、新たな標的を明らかにしました。
本研究は日本医療研究開発機構(AMED)の脳科学研究戦略推進プログラム「新機軸アミロイド仮説に基づくアルツハイマー病の包括的治療開発」の支援を受け、東京大学医学部附属病院・門脇孝特任教授、窪田直人准教授らとの共同研究により行われ、4月12日にMolecular Neurodegeneration誌に発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/4/12)
臓器透明化(CUBIC)を用いて腎臓全体の交感神経系の3次元構造を可視化し、その機能障害を解析
腎臓は血液をろ過して尿を生成することで老廃物を排出し、体内の環境を一定に保つ働きをしています。腎臓の複雑な動きを制御するために交感神経系が重要な働きを担っていると考えられてきましたが、これまで腎臓における神経系の3次元構造を把握することは困難でした。
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科の長谷川 頌医師・南学 正臣教授らは、大学院医学系研究科 システムズ薬理学の洲﨑 悦生講師・上田 泰己教授らが開発した臓器透明化手法「CUBIC」を用いてマウスの腎臓を透明化し、3次元免疫染色を組み合わせることで腎臓全体の交感神経の構造を把握することに成功しました。
その結果、交感神経は動脈の周囲を取り巻くように走行していることが明らかとなり、交感神経が動脈の収縮を制御していることが裏付けられました。また、腎臓の虚血再灌流障害(腎臓の血流が一時的に急激に低下することによる障害:急性腎障害)後に、交感神経の機能異常が長期間にわたって遷延していることを明らかにしました。急性腎障害が慢性腎臓病に移行するメカニズムには未解明の部分が多いですが、今回見出した腎交感神経の機能異常が病態に影響している可能性もあり、今後の研究につながる成果です。
さらに研究チームは、交感神経・動脈だけでなく、腎臓の他構造(集合管・近位尿細管・糸球体)を臓器全体で可視化することにも成功しました。この臓器透明化(CUBIC)と3次元免疫染色を組み合わせた観察法は、今までにない包括的な視点を提供することで、今後の腎臓病研究において強力なツールとなることが期待されます。
本研究成果は、日本時間2019年4月9日に、国際学術誌Kidney Internationalにオンライン掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/4/10)
日本成人における異性間性交渉未経験の割合の推移について
~ 出生動向基本調査の分析, 1987 – 2015年 ~
日本は、世界で最も出生率が低い国の一つである。その理由として成人における性交渉未経験の人の割合が増えていることが示唆されているものの、国民全体を代表するデータでの調査研究はこれまでのところ行われていない。
東京大学大学院医学系研究科 渋谷健司教授(研究当時)らの研究グループは、1987年から2015年の間に実施された合計7回分の出生動向基本調査(18–39歳の成人を対象、1987年の調査のみ18–34歳が対象)、サンプルサイズは11,553–17,850名 [1987–2010年]、回答率は70.0–92.5%))のデータを使用し、性別・年齢グループ別の年齢調整異性間性交渉未経験割合を算出した(異性間性交渉の定義は、異性との性交渉経験の有無に関する回答とした)。加えて、本研究グループは、2010年調査において、異性間性交渉未経験に関連する要因を同定するために、年齢調整を行い、ロジスティック回帰を用いた重回帰分析を行った。同性間性交渉経験に関する情報は利用不可能であった。
1992年から2015年の間において、18–39歳の成人における年齢調整異性間性交渉未経験の割合は、女性では21.7%から24.6%に(p値<0.001)、男性では20.0%から25.8%に増加していた(p値<0.01)。30–34歳の年齢層では、年齢調整異性間性交渉未経験の割合は、1987年から2015年の間で、女性では6.2%から11.9%へ(p値=0.4)、男性では8.8%から12.7%へ増加していた(p値=0.2)。35–39歳の年齢層では、女性ではその割合は1982年には4.0%だったのが、2015年には8.9%に増加していた(p値<0.05)。男性では有意ではないが5.5%から9.5%への上昇であった(p値=0.4)。25–39歳の男性では、無職、時短・非正規雇用、及び低収入が異性間性交渉未経験と有意に関連していた。
日本人成人における異性間性交渉未経験割合は、過去20年間の間で増加していることがわかった。30代で見ると、10人に1人が、性交渉経験が無いとの回答であった。無職、非正規・時短雇用及び低い収入が、男性では異性間性交渉経験が無いことに関連していることがわかった。異性間性交渉は、人間の生殖活動の基本であり、また性の健康や性への満足はより良く生きるために重要である。日本人成人において、性交渉未経験割合が増えていることの要因や、それがもたらしうる公衆衛生への影響、人口動態への影響については、今後さらなる研究が必要である。
本研究成果は、BMC Public Health 2019年4月8日オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/4/8)
小児医療費助成の政策評価
~ 子どもの健康と医療費効率化の両立は可能か? ~
我が国では、公的医療保険に加え、各自治体が「小児医療費助成」により患者の医療費の自己負担を軽減する政策を行っています。しかし、一般に、過大な医療費の軽減は、コストに比して得られるベネフィットが小さい医療サービスの利用が増えることで、無駄な医療の増加につながる可能性があります(モラルハザードと呼ばれる現象です)。その解決策の1つとして、患者自己負担の仕組みを利用することが考えられます。
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の宮脇敦士(研究当時:博士課程4年生)、同分野の小林廉毅 教授は、西日本に位置する一県の国民健康保険レセプトデータを用い、2つの方式の小児医療費助成が、医療費を中心とする医療サービスの利用に与える影響を評価しました。本研究が行われた県では、研究期間中、2つの方式の小児医療費助成が自治体ごとに別々のタイミングで導入されたため、これを「自然実験」とみなしました。2つの方式の一方は、外来・入院医療費に関しては、月あたりの自己負担額の上限が決まっており、その額を超えると、超えた分は全額自己負担額分が助成されるというものです。これは医療サービスの利用が多い(健康状態の悪い)子どもをより手厚く助成する政策と考えられます。もう一方は受診回数に関わらず、薬剤費が全額助成され、自己負担がなしとなるというものです。
解析の結果、医療費助成は、外来・入院医療費には統計学的に有意な効果は与えていなかった一方、薬剤費を16%増加させていました。また、対象となった子どもを健康状態で2群に分けて解析したところ、医療費助成による薬剤費の増加は、健康状態の良い群の子どもだけで見られました。また、この薬剤費の増加は処方確率・処方量の増加だけでなく、ジェネリック薬使用率の減少によっても説明されました。
本研究の結果から、1)自己負担を全額助成する医療費助成による医療費の増加は、主に比較的健康な子どもの医療費の増加によって説明され、2)一定額の自己負担を設けて、より医療サービスを必要としている子どもに選択的に助成を行うことで、医療費全体の増加を抑制できる可能性が示唆されました。本研究成果は学術誌「Health Policy」(2019年4月号)に掲載され、同号の巻頭言にも取り上げられました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/4/2)
軟骨にかかる過剰な力学的負荷が変形性関節症を引き起こすメカニズムの解明
変形性関節症は高齢者の健康寿命を脅かす代表的な疾患ですが、進行を止める治療薬はいまだに存在しません。肥満、重労働、関節の外傷など、過剰な力学的負荷が関節軟骨を変性させることは古くから知られていますが、その分子メカニズムは分かっていませんでした。東京大学大学院医学系研究科外科学専攻整形外科学の張成虎大学院生(研究当時)、東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎外科齋藤琢准教授らのグループは、細胞や組織に対して周期的に力学的負荷をかける装置を開発し、軟骨細胞において強い負荷によって発現が変化する遺伝子をスクリーニングして、分泌タンパクGremlin-1を同定しました。Gremlin-1は強い力学的負荷によって誘導され、NF-κBシグナルの活性化を介して軟骨を変性させることなどを、細胞、マウスを用いて証明しました。また、Gremlin-1を標的にすることで変形性関節症の進行を抑制できることも示しました。過剰な力学的負荷が変形性関節症を惹起するメカニズムの全体像を証明したのはこの研究が初めてであり、同時に変形性関節症の本質的な治療法の開発に繋がる成果と考えられます。
本研究は日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業(PRIME)「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医療技術の創出」研究開発領域における研究開発課題「ストレス強度に応じた関節軟骨細胞のメカノレスポンスの変容機構の解明」(研究開発代表者:齋藤琢)の支援により行われ、日本時間3月29日に英国科学誌Nature Communications(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/4/2)
加齢による幹細胞の機能低下を回復する方法を発見
老化による機能低下は、組織をつくる基となる幹細胞の機能低下と密接な関係があります。しかし、加齢による幹細胞の機能低下の原因は十分にはわかっていませんでした。そこで、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 五十嵐正樹助教、三浦雅臣医師、山内敏正教授のグループは、マサチューセッツ工科大学Leonard Guarente教授との共同研究で、マウスの腸管上皮幹細胞を用いて、加齢による幹細胞の自己複製機能低下に長寿遺伝子SIRT1の活性低下が重要な役割を果たすことを見出しました。さらに、NAD+前駆体のニコチンアミドリボシド(NR)投与によりSIRT1/mTORC1経路を活性化することで、加齢に伴う幹細胞増殖能力と組織修復能力の低下を改善することを明らかにしました。今回の新しい発見により、加齢により低下する幹細胞機能を回復する有効な手段の開発につながり、健康長寿社会の実現に貢献する可能性があります。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/4/2)
慢性の脳虚血がアルツハイマー病を加速させるメカニズムを解明
東京大学医学部附属病院神経内科坂内太郎登録研究員、間野達雄助教、岩田淳講師らは、高血圧や糖尿病による動脈硬化が慢性的な脳血流低下(慢性脳低灌流)を引き起こし、高齢者のアルツハイマー病(AD)を加速するメカニズムを明らかにしました。アルツハイマー病(AD)の患者さんを対象とした観察研究から、高血圧や糖尿病などが原因の動脈硬化による慢性的な脳血流の低下(慢性脳低灌流)が、ADの症状を進行させることが知られていました。特に、慢性脳低灌流は、ADの病状に大きくかかわる物質であるアミロイドβ(Aβ)によって構成された老人斑の形成も促進することが分かっていましたが、その詳細な機構は不明でした。そこで、 ADのモデルマウスに対して持続的に脳血流の低下を生じさせる処置を施し、脳内のAβの状態がどのように変化するかを検討しました。処置を受けたマウスでは、より大きな老人斑がみられるようになりましたが、Aβの総量は変わりませんでした。Aβにはお互いにくっつきやすい性質があります。処置を行ったマウスの脳でも、もともとばらばらに存在していたAβ分子が集まって、より毒性の高い高分子量Aβオリゴマーを形成していることが判明しました。これは、慢性脳低灌流によって脳の細胞と細胞の間を流れる間質液の動きがゆっくりになった結果、よどんだ間質液の中でAβ同士がよりくっつきやすくなってしまうことが原因であると考えられます。本研究成果は、アルツハイマー病の進行を遅らせるために、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の管理をすることが有用であることを示唆していると考えられます。
本研究は東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻神経病理学分野、東京医科歯科大学難治疾患研究所神経病理学分野との共同研究で行われ、日本時間の2月26日に学術誌Scientific Reports(オンライン版)にて発表されました
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/4/2)
日本人の軽度認知障害からアルツハイマー型認知症への移行に血清カルシウム低値が関連することを同定
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻の佐藤謙一郎大学院生および岩田淳講師は、軽度認知障害からアルツハイマー型認知症への移行に、血液中のカルシウム値が低いことが関連することを新たに見出しました。本研究は、J-ADNI研究の血液データを中心に詳細な追加解析を、北米ADNI研究のデータと比較しつつ行ったものです。
J-ADNI研究では、ものわすれを主症状とする軽度認知障害の被験者234名の認知機能を最長3年間観察したところ、約半数の被験者が3年のうちにアルツハイマー型認知症へ移行・進行していることが確認されました。このアルツハイマー型認知症への移行に関与する因子をさまざまに検討した結果、観察開始時点での血液中のカルシウム値が正常範囲ながらも低め(血清カルシウム値が補正後9.2 mg/dL未満)であることが関連因子として見出されました。一方で北米ADNI研究データでの解析ではそのような結果は見出されませんでした。
これまでの主に欧米からの研究報告では血液中のカルシウム値と軽度認知障害の進行の関連は不透明でした。本研究は、日本人の包括的な前向き観察データから軽度認知障害と血液中のカルシウム値との関連を示したアジアでは初の報告です。
血清カルシウム低値がアルツハイマー型認知症への移行に関連する理由は現時点では不明ですが、例えば、脳内の神経細胞の活動に影響を与える、またそれに伴い脳内のアミロイドβという物質の蓄積が促進される、などの機序が想定されています。一方でビタミンD欠乏も認知機能悪化に寄与することが知られていますが、J-ADNI研究ではビタミンDは測定されておらず、潜在的なビタミンD欠乏による低カルシウムを反映した結果である可能性もあります。また軽度認知障害に伴う屋外活動量や食生活の変化といった要素による影響の可能性も考えられます。
今後の認知症の観察・介入研究においては、これまで十分には検討されてはこなかった、血清カルシウム値およびビタミンD値、またそれらにかかわる活動量や食生活などの情報も検討していく必要があると言えます。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/4/2)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報