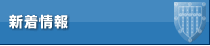広報・プレスリリース情報(2020年(令和2年))
冠動脈・心臓リンパ管発生を制御する新たなシグナルを同定
~ 心筋梗塞への治療応用の可能性 ~
心臓は冠血管とリンパ管により循環が維持されています。冠動脈の血流障害は心筋梗塞、リンパ管の障害は心筋障害時の炎症反応調節や微小循環障害を引き起こすことがわかっていますが、冠動脈や心臓リンパ管の発生過程には不明な点が多く残されていました。今回、東京大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻・代謝生理化学分野の丸山和晃研究員、栗原裕基教授らは、冠動脈と心臓リンパ管の発生に関わる新しいシグナル経路を同定しました。細胞移動を制御するセマフォリン-プレキシンシグナルファミリーメンバーであるセマフォリン3E-プレキシンD1の遺伝子欠損マウスを解析したところ、これらのマウスでは冠動脈の数が増加し、大動脈周囲のリンパ管形成に障害が起こることを見出しました。さらに心筋梗塞モデルマウスでセマフォリン3E-プレキシンD1シグナルを阻害することでリンパ管新生が促進され、心臓機能保護に働くことを見出しました。これらの結果はセマフォリン3E-プレキシンD1シグナルが冠動脈、リンパ管を含む冠循環の発生過程並びに心筋損傷時の血管・リンパ管新生においても重要であることを示唆し、新たな創薬ターゲットとなり得ることを示しています。本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業CREST「細胞動態の多様性・不均一性に基づく組織構築原理の解明」(研究総括:栗原裕基), 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究A「多種細胞連環に基づく冠循環系の発生・進化・病態・再生の統合的理解」(代表:栗原裕基)および科学研究費助成事業 若手研究「臓器特異的リンパ管発生機構の解明」(代表:丸山和晃)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/3/30)
心臓が正しく動くために必要な新しい仕組みを発見
~ 心臓突然死の治療に期待 ~
心臓が血液を送り出すポンプとして正常に動き続けるためには、心臓を構成する多数の心筋細胞が同期して、正しいリズムで収縮することが必要です。心臓へのストレスやさまざまな心臓病によって、この同期が保てなくなり、心臓が正常の動きでなくなるために、心臓のリズムが狂ってしまう不整脈が出現し突然死につながることが知られています。しかし、そもそも、どのように心筋細胞どうしの収縮の同期が維持され、正常な心臓の動きが維持されているのかについては、よく分かっていませんでした。
東京大学医学部附属病院の藤生克仁特任准教授、小室一成教授、および千葉大学大学院医学研究院の真鍋一郎教授らの研究グループは、心臓に存在している免疫細胞に注目して、この細胞が分泌するタンパク質が、心筋細胞どうしの小さな穴を通したつながりに必要であることを世界で初めて発見しました。この免疫細胞や、免疫細胞が分泌するタンパク質をなくしたマウスでは、心筋細胞どうしの同期が失われ、さまざまな不整脈が出現し、わずかなストレスで高率に心臓突然死を起こしました。心臓が正常に働くために必要な新しい仕組みが分かったことで、今後、不整脈や心臓突然死の新しい診断・治療・予防へつながることが期待されます。
本研究成果は、日本時間3月26日に英国科学誌Nature Communications(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/3/29)
ウェブ上での簡単なテストで、アルツハイマー病の前駆状態に該当する可能性を予測するアルゴリズムを開発
東京大学大学院医学系研究科・佐藤謙一郎医師、岩坪威教授らのグループは、「ウェブ上での簡単なテスト(https://www.j-trc.org)により、アルツハイマー病の前駆状態に該当する可能性を予測する」アルゴリズムを開発しました。アルツハイマー病に対する根本治療薬の開発において、認知機能が低下する前の前駆期に薬剤を投与することが重要と考えられるようになってきています。このアルツハイマー病前駆期(プレクリニカル期)に該当する方を適切に見出していくことが臨床試験を実施する上で必要になりますが、それに要する労力・コストがかかることが壁となっていました。本研究によってアルツハイマー病前駆期に該当するかどうかについてのスクリーニング効率を高めることが期待でき、ひいてはアルツハイマー病の根本治療薬の開発促進に貢献しうるものと考えられます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)・認知症研究開発事業における研究開発課題「認知症プレクリニカル期・プロドローマル期を対象とするトライアルレディコホート構築研究」(研究開発代表者:岩坪威)の一環として行われました。
本研究成果は、2021年3月24日に国際学術誌「Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions」にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/3/25)
ラミニンβ2鎖の変異による腎障害メカニズムの解明ニズムの解明
~ 遺伝的要因による蛋白尿の治療法開発に期待 ~
東京薬科大学・薬学部・病態生化学教室の吉川大和准教授および東京大学・大学院医学系研究科・小児医学講座の張田豊准教授、山形大学・医学部・小児科の橋本多恵子助教らの研究グループは、糸球体基底膜の構成分子であるラミニンβ2鎖の異常による腎障害のメカニズムを明らかにしました。
糸球体の基底膜は、血液をろ過して尿を生成するフィルターとして機能する膜状の構造体です。ラミニンβ2鎖は、ラミニン-521のサブユニットであり、糸球体基底膜のろ過機能に関わっています。ラミニンβ2鎖の欠損は、神経や目の異常と尿中に蛋白を多量に漏出する重症のネフローゼ症候群を合併するピアソン症候群を引き起こすことが知られています。しかしながら、日本人で同定されたLAMB2遺伝子の特定の変異では腎臓の異常(蛋白尿)だけを呈します。LAMB2の様々な変異により重症度の異なる病態が発症するメカニズムの解明が求められていました。
本研究では、腎臓にのみ異常をきたす変異がラミニンβ2鎖の一部に多いことに着目しました。まずこれらの変異(p.R469Q, p.G699R, p.R1078C)が、古典的なピアソン症候群を起こす変異と異なり、ラミニンβ2鎖を欠損させるものではないことを見出しました。さらに生化学的な解析により、その変異がヘパリン結合性およびラミニン結合性などを上昇させ、ラミニン-521によるフィルター形成を妨げることで選択的なろ過機能が失われ、血漿蛋白を漏出させる可能性を明らかにしました。
ラミニンβ2鎖の新たな機能を明らかにし、特定の変異がなぜ腎臓病を起こすのかというメカニズムの解明は、変異の種類に応じた症状の予測や、メカニズムに基づいた治療法の開発に繋がるものと期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/3/23)
関節リウマチの骨破壊の新しいメカニズムを解明
~ 自己抗体をつくる細胞が傍関節性骨粗鬆症を誘導する ~
関節リウマチは炎症に伴って骨破壊が誘導される自己免疫疾患です。関節リウマチでは関節破壊だけでなく、炎症関節の近傍や全身性に骨粗鬆症がおき、骨折リスクを上げ生活の質を下げます。傍関節性骨粗鬆症は関節リウマチの臨床所見が現れる前に発症することが知られていましたが、そのメカニズムはよくわかっておらず、新しい治療法の確立が喫緊の課題となっています。
東京大学大学院医学系研究科の小松紀子助教、高柳広教授らは、関節リウマチのマウスモデルを用いた解析により炎症関節近傍の骨の骨髄に存在する抗体を産生する形質細胞が破骨細胞分化誘導因子RANKLを発現することで破骨細胞を誘導し、傍関節性骨粗鬆症をひきおこすことを明らかにしました。さらに関節においては滑膜線維芽細胞が主要なRANKL発現細胞として関節破壊に関わることを生体レベルで実証することに成功しました。本研究により関節リウマチにおける傍関節性骨粗鬆症の新しいメカニズムを解明するとともに形質細胞が治療標的になりうることがわかりました。
本研究は日本学術振興会 科学研究費補助金(15H05703、18H02636、18K19438、20K21515、19K18943)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)免疫アレルギー疾患実用化研究事業における研究開発課題「関節リウマチの病原性間葉系細胞サブセットを標的とした骨破壊治療法の開発」(研究開発代表者:高柳 広)、革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域における研究開発課題「組織修復型免疫細胞の解明とその制御による疾患治療の開発」(研究開発代表者:高柳 広)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/3/16)
身体のあらゆる場所にできる「稀少部位」子宮内膜症
~ 大網子宮内膜症の症例レポート ~
東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 博士課程3年の荒川知子大学院生(東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 病院診療医)と、東京大学医学部附属病院 大腸・肛門外科の石原聡一郎教授らは、同院で診療にあたった大網子宮内膜症という極めて稀な症例について経過・治療内容を報告しました。
子宮内膜症とは、子宮内膜(子宮の内側にある粘膜)に似た組織が子宮の外で増えてしまう病気で、身体のあらゆる場所に発生します。しかし多くは卵巣・ダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)・子宮のまわりの靭帯といった女性の生殖器に発生し、今回の大網(胃から垂れ下がり、腸の前面をおおう腹膜)のような臓器に発生することは稀です。このような生殖器以外の場所に発生する子宮内膜症は「稀少部位子宮内膜症」と呼ばれていますが、その稀有さにより診断がつきにくく、結果として治療に難渋することがしばしばあります。
今回の症例では、女性診療科・産科、女性外科、放射線科、消化器内科、大腸・肛門外科など、院内の複数の診療科が綿密な連携を取り、大網に発生した子宮内膜症という極めて稀な疾患を病歴や磁気共鳴画像(MRI)等の所見から診断し、腹腔鏡手術で摘出したところ、良好な経過をもたらすことに成功しました。
本報告を通して、稀少部位子宮内膜症という稀な疾患が多くの医療従事者ならびに国民に認知されることで、今後のより適切な診断や治療の一助となることが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/2/18)
新型コロナウイルス感染症流行下における日本での自殺者数の変化について
東京大学大学院医学系研究科の坂元晴香特任研究員らの研究グループは、日本におけるパンデミック下での自殺率の変化について、厚生労働省が所管する2011年1月から2020年11月までのデータ(研究時点で最新の情報;文献1)をもとに、性、年齢層、職業別に分析を行った。その結果、2020年の自殺率は2016−2019年と比べ、男性では10月と11月、女性では7月から11月にかけて増加していることが分かった。増加は、男性では30歳未満で顕著で、特にこの年齢層では7月から11月にかけて著しく、また女性では30歳未満と30~49歳で増加幅が最大であることが明らかになった。
本研究成果は、2021年2月2日(米国東部時間)に「JAMA Network Open」にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/2/8)
『この先、報酬はもらえる?もらえない?』は異なった神経細胞で表現されている
~ 背側前頭皮質内側部は報酬期待-行動の情報処理における起始点である ~
大脳皮質は運動・感覚・意思決定など種々の情報処理に重要な役割を果たします。動物が外界からの感覚入力と過去の経験にもとづいて適切な運動出力を行うときの『報酬』の脳内表現を知ることは、いわゆる意思決定の神経基盤を探る上で非常に重要です。これまで皮質以外の脳領域が報酬を強く反映することがわかっていましたが、背側大脳皮質の報酬に関する情報処理はあまり調べられていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻生理学講座細胞分子生理学分野の近藤 将史 助教、松崎 政紀 教授(理化学研究所脳神経科学研究センター脳機能動態学連携研究チーム・チームリーダー)らは、マウス背側前頭皮質内側部が報酬の有無とそれに関連する感覚表現において他の皮質領域より特異な場所であり、『報酬がもらえないだろう』や『報酬がもらえなかった』ことを強く表現することを、光遺伝学による神経活動操作、広域カルシウムイメージングおよび光子カルシウムイメージングによって明らかにしました。本研究成果は、報酬が関わる複雑な意思決定機構を紐解く上での基礎的知見となることが期待されます。
本研究成果は、日本時間2月3日にCell Reports(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/2/3)
神経活動の光制御とモニタリングを同時に可能にするケージド化合物の開発
光照射により生理活性物質を放出するケージド化合物は、神経科学をはじめとする生命科学研究で広く用いられてきました。しかし、従来のケージド化合物は、その活性化のために生体組織にダメージを与える紫外線などの短波長光を必要とし、長波長化しても物質の放出が遅いことや、有害な活性酸素も放出されるという問題がありました。
東京大学大学院医学系研究科の浦野泰照教授、山梨大学大学院総合研究部の小田賢幸教授らの研究グループは、蛍光色素KFL-1を基にして、黄色光(580nm)という長波長光で活性化できるKFL-1ケージド化合物を開発しました。本研究では、神経細胞にカプサイシン受容体TRPV1を発現した線虫C.elegansに対し、光照射でカプサイシンを放出するKFL-1ケージドカプサイシンを適用することで、光による神経活動の活性化を実現しました。さらに、無麻酔の線虫において上記手法で神経活動を活性化しながら、蛍光カルシウムセンサーGCaMP6sを用いることで、光制御・神経活動観察・行動観察の3つを同時に行うことに成功しました。
本研究は、神経活動に人為的に介入しながら同時に神経活動をイメージングする手法を提供するもので、神経回路の破綻により生じる精神疾患、記憶学習障害の病態解明・治療法開発につながると期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/2/2)
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染モデルにおける嗅上皮の変化
~ COVID-19による嗅覚障害の病態解明や治療法開発の加速に期待 ~
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)によって引き起こされるCOVID-19の症状に嗅覚障害があります。SARS-CoV-2による嗅覚障害は初期症状の1つとして知られているだけでなく、発症後約2か月経過しPCRが陰性化した方の18~45%で何らかの嗅覚障害が残存していることも明らかになっています。一般的に傷害された嗅上皮(鼻の奥にある匂いを感知する部位)は一度脱落し菲薄しますが、再生して正常厚に戻ります。しかし傷害が重度の場合、嗅上皮は正常化しないことが知られています。SARS-CoV-2が嗅上皮に感染した場合、嗅上皮が脱落することがわかっていましたが上皮厚が正常化するかは不明でした。東京大学医学系研究科外科学専攻耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学、東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頚部外科の山岨達也教授らの研究グループは、テキサス大学医学部ガルベストン校の研究グループとの共同研究で、SARS-CoV-2ウイルス量に関わらず、感染が成立すると感染後数日で広範囲にわたって嗅上皮が脱落することを明らかにしました。また、大部分の嗅上皮は感染後21日で正常厚になることも見出しました。本研究の成果は、SARS-CoV-2感染による嗅覚障害の病態解明や治療シーズ開発を加速させると期待されます。
本研究成果は、2021年2月1日に「ACS Chemical Neuroscience」(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/2/2)
認知機能低下患者の顔を見分けることができるAIモデルの開発
認知症は、近年患者数の増加がみられる疾患で、大きな社会問題となっているため、認知症を早期に発見することが必要とされています。この度、東京大学医学部附属病院 老年病科の秋下雅弘教授、亀山祐美助教(特任講師(病院))らのグループは、東京都健康長寿医療センター 放射線診断科の亀山征史医長らと共同して、人工知能(AI)が認知機能の低下した患者と健常者の顔写真を見分けることができることを世界で初めて示しました。顔による認知症の早期発見は、非侵襲的で時間もかからない安価なスクリーニングとして期待されます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業の支援により行われ、日本時間1月26日に米国科学誌Aging(Albany, NY)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/1/26)
相分離した液滴のオートファジー分解に新たなメカニズムを発見
~ 表面張力が関わるオートファジー「fluidophagy」の提唱 ~
マクロオートファジー(以下「オートファジー」)は細胞内の主要な分解系の一つです。細胞の一部を非選択的に、あるいは細胞にとって有害な成分や不要なものを選択的に、隔離膜によって捕捉し、分解するプロセスです。液-液相分離は、均質な液体が二つ以上の液相に分離する現象のことです。細胞内でも、たんぱく質や核酸が液-液相分離を起こして球状の「液滴」を生じることがあり、膜のない細胞内構造として近年注目されています。これまで、オートファジーによって選択的に分解されるたんぱく質が液滴を形成する場合があることはわかっていましたが、その根底にある普遍的な物理的仕組みについてはわかっていませんでした。
今回、マックスプランク研究所のRoland Lutz Knorrグループリーダー(研究開始当時:東京大学大学院医学系研究科 分子細胞生物学専攻 分子生物学分野 特任助教)を中心とし、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らを含む、ドイツ、日本、イギリス、ノルウェー等の国際共同研究チームは、オートファジーが液滴を捕捉する物理的基盤を明らかにし、これを「fluidophagy(液滴のオートファジー)」と命名しました。今回細胞内の液滴の例として使ったp62たんぱく質は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)を含む複数の疾患との関連が示唆されています。本研究の成果は、液滴のオートファジーによる分解機構の解明とともに、神経変性疾患などの病態の理解に貢献することが期待されます。
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)の支援を受けて行われました。
本研究成果は、国際科学誌「nature」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/1/21)
血流シグナル伝達の新しい仕組み~内皮細胞膜とミトコンドリアの連携プレイ
血管内面を覆う内皮細胞には血液の流れ(血流)を感知し、その情報を細胞内に伝達することで形態や機能の変化を伴う細胞応答を起こす特性が備わっています。この特性は血液循環系の働きを正常に保つうえで必須で、これが適切に働かなくなると、高血圧、血栓症、動脈瘤や動脈硬化症の発生につながります。しかし、内皮細胞がどの様に血流刺激(shear stress)を感知・伝達するか、その仕組みは完全には解明されていません。今回、東大医学部の山本希美子准教授らは細胞膜とミトコンドリアが連携する新しい血流シグナル伝達経路を見出しました。内皮細胞にshear stressが加わると、即座に細胞膜のコレステロールが減少し、それに依存してミトコンドリアのATP(アデノシン3リン酸)の産生が増加することが示されました。産生されたATPは細胞外に放出され、細胞膜のATP受容体を刺激することで様々な細胞機能や遺伝子発現が変化します。こうした血流シグナル伝達経路の詳細が明らかになると、血流が増加するエクササイズの生体作用の理解だけでなく、血流依存性に起こる様々な血管病の病態の解明や新しい治療法の開発にも貢献が期待されます。
本研究成果は、米国科学アカデミー紀要のオンライン版で公開されました。
本研究は国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)(研究代表:山本希美子)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費の支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/1/21)
十二指腸乳頭部に存在する胆管幹細胞および乳頭部癌起源細胞を同定
~ 胆管再生治療や新規乳頭部癌治療法の足掛かりに ~
十二指腸乳頭部癌は、進行し切除不能になると有効な化学療法が確立しておらず、非常に予後不良です。また治癒切除できた場合にも、術後の胆管狭窄などの合併症が問題となっています。東京大学医学部附属病院 消化器内科の早田有希医師、中川勇人助教[特任講師(病院)]、小池和彦教授らのグループは、十二指腸乳頭部の胆管周囲付属腺という小さな腺組織の中に、胆管上皮幹細胞が存在することを世界で初めて発見しました。また同細胞集団は高い発癌ポテンシャルを有し、十二指腸乳頭部癌の起源細胞にもなっていることを明らかにしました。興味深いことに、乳頭部の胆管周囲付属腺は、隣接する平滑筋細胞(Oddi括約筋)との相互作用を通じて幹細胞機能を維持しており、この相互作用を阻害することによって乳頭部癌の発症を著明に抑制できることもわかりました。本研究成果は、肝胆膵領域の術後合併症である胆管狭窄の病態解明や胆管再生療法の足掛かりとなると同時に、十二指腸乳頭部癌に対する新規治療法開発など、これまで遅れていた胆管・乳頭部領域のさまざまな病態の解明に結びつく可能性があります。
本研究成果は、米国科学誌『Gastroenterology』の本掲載に先立ち、日本時間1月16日にオンライン版にて公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/1/19)
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)が心理的ストレスを減らす
~ 全国労働者オンライン調査(E-COCO-J)から ~
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野の川上憲人教授、佐々木那津大学院生らは、日本での新型コロナウイルス感染症が拡大するつれ、企業従業員の心の健康がどのように変化するかを調べるため、「新型コロナウイルス感染症に関わる全国労働者オンライン調査(E-COCO-J)」(https://plaza.umin.ac.jp/heart/e-coco-j/)を行っています。全国の企業の従業員約1,500人を対象に、2020年3月に初回調査を行い、その後、第2回調査(2020年5月22から27日)と第3回調査(8月7から12日)を実施しました。第2回と第3回調査の結果、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードが労働者の心理的ストレスを軽減する可能性が示されました。COCOAのダウンロードを行った者は、行わなかった者と比較して、心理的ストレスありと答えた者の割合が低下していました。COCOAをダウンロードすることで、コロナ禍で増加している心理的ストレスを減らすことができるかもしれません。
今後、労働者以外の一般住民でも効果がみられるかどうか確認し、またCOCOAが心理的ストレスを改善する機序に関する研究が進むことで、感染症流行時の心理的ストレス対策の方法論が確立できると期待されます。
本成果は専門誌「JMIR Mental Health」に1月12日付けで掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/1/15)
ミトコンドリアにバレル(円筒)型膜タンパク質を組み込む仕組みを解明
京都産業大学、東京大学、フライブルグ大学、産業技術総合研究所、千葉大学の研究チームは、ミトコンドリア外膜の(膜タンパク質複合体)SAM複合体について、構成サブユニット(タンパク質)が異なる二つの複合体の高分解能立体構造をクライオ電子顕微鏡解析で決定しました。SAM複合体が構成タンパク質を入れ替えながら、基質となる膜タンパク質に円筒形(バレル型)の形を作らせつつ外膜に組み込む、新規の仕組みを明らかにしました。
ミトコンドリア外膜には小分子やタンパク質の通り道を提供するバレル型構造の膜タンパク質(β-バレル型膜タンパク質)が存在し、ミトコンドリアの機能に必須ですが、それらの膜タンパク質がどのようにバレル型をつくって膜に組み込まれるのかはこれまで不明でした。細菌の外膜にも進化的に近い組み込み装置がありますが、それとは組み込みの仕組みがかなり異なることもわかりました。
ミトコンドリア外膜の機能に必須のβ-バレル型膜タンパク質組み込みのメカニズムの解明により、ミトコンドリアの膜タンパク質組み込みやβ-バレル型膜タンパク質に関連する病気の治療法の開発や、ミトコンドリア膜へのタンパク質組み込みの効率を制御することで老化を防ぐなどの可能性が開けることが期待されます。
本研究成果は、「Nature]オンライン版に2021年1月6日16時(ロンドン時間)付で掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/1/8)
健康関連行動(adherence)が長期の医療・介護費用や生命予後に与える影響の予測モデルを開発:人工知能(AI)と医療ビッグデータを応用
医療・介護保険財政がひっ迫する中、社会保障の持続的な発展には、新たな疾病予防や財政管理の介入モデルが望まれます。また、疾病予防行動や服薬コンプライアンス、重複受診などのアドヒアランス(健康関連行動)の低下は、臨床成績のみならず医療財政に影響を及ぼすことが明らかとなっています。一方で、アドヒアランスが臨床経済に及ぼす影響の評価は、多様で複雑な因子が絡み合うた め、通常の臨床試験での評価が困難です。そこで、東京大学大学院医学系研究科の医療経済政策学の田倉智之特任教授らは、広義のアドヒアランスをスコア化して、将来の死亡と費用との関係を長期的に予測するデータサイエンス研究を世界で初めて実施しました。具体的には、医療ビッグデータとAIを応用し、アドヒアランスが長期(48か月間)の医療・介護費用や生命予後、他の臨床指標に与える影響を約5万人(循環器領域)のコホートで検証しつつ、予測モデル(10水準のASHROスコア)を開発しました。このスコアは、対象者(被保険者や患者)の 将来の臨床経済的なリスクを予見するため、行政者は保険財政(医療・介護)の管理に、医療者は疾病予防の促進に活用することで、疾病負担の改善と社会保障の発展に貢献すると期待されます。
本研究成果は日本時間2021年1月7日にBMC medicine(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/1/8)
子宮内膜上皮の細胞増殖の持続が着床障害を起こす
~ 黄体ホルモンによる着床成立のメカニズム解明 ~
生殖医療において体外受精・胚移植の技術の進歩は目覚ましく、日本では出生児16人に1人が体外受精・胚移植妊娠によるものとなっています。体外受精・胚移植の成功率を高めることは少子化に対する1つの対策になります。体外受精で得られた良好胚を子宮内に移植しても反復して不成功することを着床障害と呼びますが、着床障害に対する有効な診断・治療法が確立していないため、生殖医療の大きな課題となっています。
東京大学大学院医学系研究科の廣田泰准教授、赤枝俊特任臨床医、大須賀穣教授らは、子宮内膜において子宮内膜上皮の細胞増殖が停止した状態になることが胚浸潤に必要であることを、遺伝子改変マウスやヒト着床期子宮内膜を用いた研究を行いて明らかにしました。黄体ホルモンの作用によって、子宮側の最初のバリアである子宮内膜上皮が細胞増殖を停止させ、自ら細胞死を起こして消失し、胚が子宮内膜に入り込むことができることを示したのは世界初です。本研究成果は着床障害の新規診断・治療法の開発につながると期待されます。
本研究成果は日本時間2021年1月5日にEMBO Reports(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/1/7)
記憶の書き換えに重要なキネシン分子モーターKIF17による新しい樹状突起内輸送制御機構
神経細胞内における記憶の書き換えメカニズムの解明は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を代表とする記憶障害を伴った精神疾患の治療開発において重要な役割を担っているが、実際に神経細胞がどのように記憶の書き換えや恐怖記憶の消去を行っているかについては現在十分には理解されていない。今回、東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻の廣川信隆特任教授、岩田卓特任研究員、森川桃特任研究員(研究当時、現・理化学研究所)、武井陽介准教授(研究当時、現・筑波大教授)らの研究チームは、キネシン分子モーターKIF17による受容体輸送が神経活動を契機としてKIF17の分解により一時的に廃止され、その後すぐに樹状突起内において再開されるということを発見した。この分子機構は必要物資を細胞体から遠位の神経突起内へと輸送するという従来の分子モーターの役割とは異なり、神経活動を契機として突起内の受容体の位置を分子モーターが制御すると考えられ、樹状突起内に輸送の起点と終点が存在する新しいメカニズムである。本研究チームがこのKIF17による分子機構が正常に働かないマウスを開発したところ、恐怖記憶がほとんど消去できないPTSD様の症状を示した。分子モーターによる受容体位置制御を基盤とした1つの樹状突起での記憶の書き換えメカニズムが本研究により解明されたことは、記憶の書き換え障害が関与するPTSD等の精神疾患治療に新たな戦略をもたらすものである。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/12/21)
肺や浮袋が膨らむ仕組みの解明~オートファジーの新たな役割を発見
哺乳類の肺や魚類の浮袋は、それぞれ呼吸や水中での浮力発生に必須な空気を含む臓器です。これらの臓器を空気で膨らませるためには、肺胞や浮袋の内側を覆っている水の表面張力を弱めることが重要です。この役割を担うのが、サーファクタント(表面活性物質)という脂質に富む物質で、空気との境界の水面に広がって水の表面張力を弱めます。このサーファクタントは肺胞や浮袋の上皮細胞の内部に存在するラメラ体と呼ばれるリソソーム関連の細胞小器官で生成・貯蓄された後に分泌されますが、ラメラ体が形成される仕組みについては十分に解明されていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科の森下英晃助教(現:同客員研究員、順天堂大学大学院医学研究科 講師)、水島昇教授らの研究グループは、細胞内分解系であるオートファジーが肺や浮袋のサーファクタントの生成に必要であることを、マウスやゼブラフィッシュを用いた解析により明らかにしました。肺や浮袋の上皮細胞ではオートファゴソームと未成熟なラメラ体の融合が起きており、オートファジーを抑制すると、ラメラ体への成熟が不十分となることがわかりました。このようなマウスは出生直後に呼吸困難となり、ゼブラフィッシュは水中で浮いた姿勢を保てなくなることが明らかになりました。サーファクタント生成メカニズムを明らかにすることは、サーファクタントの不足や異常によって引き起こされる新生児呼吸窮迫症候群などの呼吸器疾患の理解につながることが期待されます。
本研究成果は、国際科学誌「Cell Reports」のオンライン版で公開されました。
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/12/9)
骨を壊す「破骨細胞」がつくられる仕組みを1細胞解像度で解明
~ 骨粗鬆症やリウマチなど骨破壊性疾患の新たな治療法開発に期待 ~
骨は私たちの身体を支え、運動を可能にするだけでなく、カルシウムなどミネラルの貯蔵庫としての役割、血液細胞を育てる造血器官としての役割など、多彩な機能を宿しており、脊椎動物の高度な生命制御システムを特徴付ける臓器です。骨の恒常性は、破骨細胞による骨の破壊と骨芽細胞による骨の形成の厳密なバランスにより維持されており、破骨細胞が古くなった骨を壊すことで常に新陳代謝を繰り返しています。生まれつき破骨細胞を欠損した人や、破骨細胞が正常に働かない人は、重篤な「大理石骨病」を発症し、古い骨が蓄積することで骨が脆くなり、その生命予後は極めて悪いことが知られています。破骨細胞は健康な骨を保つためになくてはならない重要な細胞ですが、一方で、破骨細胞が過剰に活性化してしまうと、骨粗鬆症、関節リウマチ、歯周病、がん骨転移といった様々な疾患に伴う病的骨破壊の原因になります。破骨細胞が関与する様々な疾患の病態を理解し、新しい治療法の開発を目指す上で、破骨細胞がつくられる仕組みの全容解明が喫緊の課題となりますが、その詳細なメカニズムに関しては未だ不明な点が多く残されていました。
東京大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学分野の塚崎雅之 特任助教と高柳 広 教授らの研究グループは、個々の細胞の遺伝子発現を網羅的に解析できる「シングルセル解析技術」を用いて破骨細胞の分化経路を詳細に解析し、コンピューターによる予測とマウス遺伝学による証明を組み合わせることで、破骨細胞がつくられる分子メカニズムの全容を1細胞レベルで明らかにしました。本研究成果は、骨代謝システムの基本原理の理解を深めると同時に、骨破壊性疾患の原因解明や治療法開発につながることが期待されます。
本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金(15H05703, 18H02919, 19H03485, 18K19438, 19K18943, 18J00744,18F18095)や、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域における研究開発課題「組織修復型免疫細胞の解明とその制御による疾患治療の開発」(研究開発代表者:高柳 広)、免疫アレルギー疾患実用化研究事業「免疫疾患領域」病態解明研究(基礎的研究)における研究開発課題「関節リウマチの病原性間葉系細胞サブセットを標的とした骨破壊治療法の開発」(研究開発代表者:高柳 広)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/12/8)
正常の膵臓の細胞が癌になる根本原因の一つを明らかにしました
~ (プロ)レニン受容体が遺伝子と染色体の異常を生じ、癌のような性質を持つ細胞をもたらすことを世界で初めて発見 ~
これまでの香川大学医学部薬理学・柴山弓季研究員と西山成教授らの研究によって、(プロ)レニン受容体[(P)RR]が膵臓癌の病態に関連することがわかっていました(Shibayama et al. Scientific Report 2015)。今回の研究では、共同責任著者である東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻の藤本明洋教授の協力のもと、藤田医科大学、大阪大学、東北大学、宮城県立がんセンター、姫路市、大阪市立総合医療センター、岐阜大学、神戸大学、大阪医科大学、四日市看護医療大学などの数多くの研究グループとコラボレーションすることにより、正常な膵臓の細胞(培養ヒト膵管上皮細胞)に(P)RRが発現すると、以下に説明するようなゲノム不安定性、すなわち遺伝子と染色体の異常が生じて、癌の性質を持つ細胞になることが世界で初めて明らかとなりました。
ヒト膵管上皮細胞に(P)RRを発現させると、癌で見られる形態の細胞になりましたが、そのような変化には、染色体全体に渡る多数の遺伝子と染色体の異常が伴っていることが判明しました。さらに、DNA複製や修復、テロメアの伸長維持といった「DNAを健全に保つための機能」が軒並み破綻していることがわかりました。実際、(P)RRをたくさん発現するヒト膵管上皮細胞を免疫不全マウスに移植すると、腫瘍を形成することも確認されました。以上の結果は、(P)RRが膵臓癌の発症に根本的に関わっていることを強く示唆するものであることから、現在、香川大学医学部薬理学教室では (P)RRをターゲットにした癌に対する新しい治療法や診断法の開発を進めています。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/12/7)
複数酵素活性を同時に可視化できるactivatable型ラマンプローブの開発
光で分子振動を検出するラマン顕微法は、特にラマンプローブと組み合わせることで、蛍光法と比べて高い多重検出能を実現できることから近年注目を浴びています。しかし、既存のラマンプローブは常に信号を示すalways-on型のプローブであり、生体内の分子と反応してラマン信号がoffからonに変化するactivatableな特性を有するラマンプローブは開発されていないため、その応用が限定されていました。
東京大学大学院医学系研究科の神谷真子准教授、同大学院工学系研究科の小関泰之准教授らの研究グループは今回、epr-SRSを原理とするactivatable型ラマンプローブの開発に成功しました。本プローブでは、分子の吸収波長によって検出感度が変化することを利用して、標的酵素との反応前は吸収波長が短いためラマン信号がoffですが、反応後は長波長化してラマン信号がonとなるよう分子を設計しました。さらに、ラマン検出タグであるCN基を同位体置換することで、同時検出が可能な4種類のラマンプローブを開発し、2種類の生きた培養細胞間における酵素活性パターンの違いを可視化することに成功しました。
本研究で創出した、分子の吸収波長に基づくラマン信号の制御原理は、機能性ラマンプローブの分子設計において一般化され得るものです。この設計法に基づいて更なる機能性ラマンプローブが開発されれば、ラマン顕微法の多重検出能を活かした生命科学研究の大きな発展が期待できます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/11/24)
日本成人における草食化(異性間交際及び交際への関心の有無)の傾向及び関連する因子について
~ 出生動向基本調査の分析、1987-2015年 ~
日本では、恋愛関係に興味を持たない若者の増加が指摘されており、草食化という言葉で表されている。草食化する若者が増えていることが示唆されているものの、その実態に関して国民全体を代表するデータでの調査研究はこれまでのところ行われていない。
1987年から2015年の間に実施された合計7回分の出生動向基本調査のデータを用いた。この調査は18~39歳の成人を対象としており(1987年の調査のみ18~34歳が対象)、サンプル数は11,683~17,675名[1987~2010年]であった。各回の調査において、性別・年齢グループ別の異性との交際状況の割合を算出した(1.既婚、2.未婚で交際相手あり、3.シングル(未婚で交際相手無し))。また3.未婚で交際相手無しの回答者に対しては、さらに「異性との交際に対する関心の有無」に関する割合も算出した。加えて、我々は2015年調査において、異性との交際状況及び交際に対する関心に関連する要因を同定するために、年齢調整を行い、ロジスティック回帰を用いた重回帰分析を行った。同性間の交際に関する情報は調査には含まれていなかった。
1992年から2015年の間、18~39歳のシングルの年齢調整割合は、女性では27.4から40.7%に、男性では40.3から50.8%に着実に増加していた。これは、25~39歳の女性と30~39歳男性における既婚割合が減少したことが大きく影響しているが、一方で、交際中の未婚者の割合は女性で微増にとどまり、男性では横ばいで推移している(すなわち、既婚割合の現象はほぼそのままシングルの増加につながった)。2015 年におけるシングル女性の割合は、30~34歳で30.2%、35~39歳で24.4%であった。男性ではこの割合は39.3%、32.4%であった。シングルの約半数(女性全体の21.4%、18~39歳男性の25.1%)が「異性との交際を望んでいない」と回答していた。男女ともに、異性との交際に関心がないと回答したシングルでは、関心があると回答した人に比べて、収入や学歴が低く、定職に就いている可能性も低かった。
健康や生活の満足度に恩恵をもたらす社会的なつながりは異性との交際以外にもあり、中には恋愛関係を持たずに生きたいと考える人もいるであろう。また、出生動向基本調査では同性間の交際に関する質問が含まれていないことにも留意が必要である。とはいえ、恋愛関係に興味を失ったり、あきらめたり、恋愛関係を築くのが難しいと感じている若年成人の割合が高いことは、公衆衛生や出生率に大きな示唆をもたらしうるものである。日本人成人において、異性と交際していない人の割合が増えていることの要因や、それがもたらしうる公衆衛生への影響、生活の質や満足度への影響、人口動態への影響については、今後さらなる研究が必要である
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/11/11)
関節リウマチの遺伝素因と関連する新規治療標的を同定
~ 炎症環境下における滑膜線維芽細胞の統合的解析で実現 ~
関節リウマチは、持続的な滑膜の炎症が関節破壊をもたらす代表的な自己免疫疾患です。近年登場した生物学的製剤や分子標的薬は、関節リウマチの治療を大きく発展させました。しかし、これら薬剤の効果が十分に得られない患者の存在や、これら薬剤の投与による全身的な免疫抑制が原因の重篤な有害事象が、治療を行う上で課題となっています。
東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科の土屋遥香 助教、太田峰人 特任助教(免疫疾患機能ゲノム学講座)、藤尾圭志 教授と、理化学研究所 生命医科学研究センターの鈴木亜香里 自己免疫疾患研究チーム副チームリーダー、山本一彦 センター長らの研究グループは、関節リウマチと変形性関節症(各30例)の滑膜線維芽細胞のゲノム、トランスクリプトーム、エピゲノムを統合的に解析し、炎症環境下の滑膜線維芽細胞における炎症メディエーター(炎症の引き金や増幅につながる物質)の発現とクロマチン(細胞核内にあるDNAとタンパク質の複合体)の構造変化および疾患感受性多型の関連を、初めて明らかにしました。この研究により、関節局所に存在する滑膜線維芽細胞を標的とした創薬候補が発見されたことで、既存の薬剤とは全く異なる経路を介した、より全身的な免疫抑制作用の少ない治療開発につながることが期待されます。
なお、本研究は、日本時間11月2日にヨーロッパリウマチ学会・学会誌Annals of the Rheumatic Diseasesに掲載されました
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/11/6)
新たな乳腺腫瘍特異的バイオマーカー酵素の発見
~ 1mm以下の微小な乳がんを光らせて正確に検出する技術の開発 ~
乳がんは、女性で最も罹患率の高いがんで、早期では手術による摘出が行われますが、その取り残しによる再発や、良性腫瘍との識別などが患者の予後を左右する課題となっていました。
東京大学大学院薬学系研究科・医学系研究科の浦野泰照教授らの研究グループは今回、乳がんが持つ糖鎖分解酵素群の特徴を明らかにするべく、これらの活性を光らせて検出する試薬群を開発しました。開発した試薬を乳がん患者由来の臨床組織で評価する事により、α-マンノシダーゼの活性を光らせる試薬が乳がん組織を高い感度・特異度で光らせる事が可能である事を発見しました。実際に、本試薬を用いることで、肉眼では確認できない微小な乳がん組織を10分程度で高感度に光らせる事が可能でした。さらに同グループは、α-マンノシダーゼの中でもMAN2C1が乳がんを光らせる鍵となっている事を突き止めました。また、乳腺の良性腫瘍の一部では乳がんよりもMAN2C1 の活性が高い事を見出し、この差を利用して両腫瘍を異なった色に光らせて識別する事に成功しました。
今後、見出した試薬はがんの取り残しによる再発の防止に、同定されたMAN2C1は乳がんの新規バイオマーカーとして利用されることが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/11/6)
喘息による入院が激減
~ COVID-19流行による「生活様式」の変化が影響か ~
喘息の基本的病態は気道の慢性的な炎症であり、我が国で100万人以上が治療を受けています。喘息の増悪要因として知られる呼吸器感染症や花粉、大気汚染物質等は、気道を刺激して入院につながる喘息発作を引き起こします。喘息発作は、呼吸不全による死亡につながるだけではなく、学校の欠席や仕事の欠勤等の社会的影響をもたらします。したがって、喘息の増悪要因を回避し、薬物治療を受けることで、喘息の良好なコントロールを保ち、喘息発作を予防することが大切とされています。
今般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は呼吸器感染症であるため、その流行に伴って喘息発作による入院が増加することが危惧されたものの、大規模な疫学的調査が不足していました。そこで、東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の阿部計大特任研究員、宮脇敦士助教、小林廉毅教授らのグループでは、株式会社メディカル・データ・ビジョンより提供された全国272の急性期病院における診断群分類包括評価レセプトデータを用いて、2020年のCOVID-19流行後の喘息による入院数が、2017年から2019年の同時期の入院数と比較してどのように推移しているのかについて検討しました。
その結果、2020年第9週以降(2/24-5/31)に喘息による入院数が、2017年から2019年までの同時期と比較して、顕著に減少傾向にあったことがわかりました。統計学的に年・週によるトレンドを調整した後では、2017-2019年と比較して、週あたり平均55%(95%信頼区間 45%-63%; p<0.001)の減少が認められました。この喘息による入院の減少傾向は、18歳未満と18歳以上の喘息患者の双方で認められました。
本研究結果は、喘息患者が生活様式を変えることで、喘息による入院の多くを予防できる可能性があることを示唆しています。そして、喘息のケアに関わるすべての者が、薬剤による治療だけではなく、患者の予防行動や生活環境への配慮の重要性について再認識する必要があります。
本研究は10月14日付で、米国アレルギー・喘息・免疫学会(AAAAI)の公式機関誌「Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice」のウェブサイト上に掲載されました。本研究は、株式会社メディカル・データ・ビジョンよりデータの無償提供を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/11/5)
オートファゴソーム膜を伸ばす仕組みを解明
~ オートファジー最後の未知たんぱく質の正体が明らかに ~
JST戦略的創造研究推進事業において、微生物化学研究所の野田 展生 部長、的場 一晃 上級研究員らは、オートファジーを担うたんぱく質群のうちの1つであるAtg9が脂質二重層の2つの層の間でリン脂質を往来させる活性(脂質スクランブル活性)を持つことを発見し、その活性がオートファゴソーム膜の伸展を引き起こすことを明らかにしました。
細胞内のたんぱく質を分解する仕組みの1つであるオートファジーにおいて、オートファゴソームの形成は分解対象を決定する極めて重要なステップです。これまでに本研究グループは、脂質輸送たんぱく質Atg2がオートファゴソームを作るためのリン脂質を小胞体から運ぶことを明らかにしましたが、運ばれたリン脂質を使ってどのように膜が伸びるのか、その仕組みは分かっていませんでした。
研究グループは、機能が分かっていなかった酵母およびヒト由来の膜たんぱく質Atg9が、脂質スクランブル活性を持つことを試験管内の実験で明らかにしました。さらに酵母Atg9の立体構造をクライオ電子顕微鏡で調べた結果、脂質二重層の2つの層をつなぐ細孔を持つことが分かりました。また、細孔を形成するアミノ酸に変異を入れたところ試験管内でのAtg9の脂質スクランブル活性が失われ、この同じ変異により酵母におけるオートファゴソームの形成も阻害されることを見いだしました。これらのことから、Atg9は新規脂質スクランブラーゼであり、脂質輸送たんぱく質Atg2と協力してオートファゴソームの形成に働くという全く新しい仕組みを明らかにしました。
本研究によりオートファジーの基本原理が解明され、今後のオートファジーの特異的制御剤の開発に向けた基盤となることが期待されます。
本研究成果は、2020年10月26日(英国時間)に英国科学誌「Nature Structural & Molecular Biology」のオンライン版で公開されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/10/27)
自閉スペクトラム症の病態解明に寄与するメカニズムを発見
~ 自閉スペクトラム症の治療戦略と創薬の発展に期待 ~
自閉スペクトラム症状(ASD)は社会的コミュニケーション障害と常同行動・限定的興味行動の2つの中核症状を特徴とした神経発達障害です。近年のASDのゲノム解析により、100以上の関連遺伝子が同定されてきました。またASD病態の原因のひとつとして、神経細胞のシナプス機能の異常が考えられています。しかし、多くのASD関連遺伝子はシナプスにどのような機能的影響を及ぼすのか、ASDで見られる行動異常とどの程度関連しているのか、はよくわかっていません。さらにシナプス機能異常と行動異常の因果関係もほとんど明らかにされていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の酒井浩旭大学院生(研究当時)、上阪直史講師(研究当時)と狩野方伸教授らの研究グループは、ASD関連遺伝子としてよく知られているCNTNAP2遺伝子とAHI1遺伝子に注目しました。社会性行動に関連する重要な脳領域である大脳皮質前頭前野に着目し、マウス大脳皮質前頭前野の2/3層錐体細胞特異的にCNTNAP2もしくはAHI1遺伝子の発現を抑制し、シナプス機能と行動を包括的に解析しました。その結果、CNTNAP2もしくはAHI1の発現低下は共通して興奮性シナプスの機能低下とASDによく似た行動異常を引き起こすことを発見しました。また、これらのマウスに興奮性シナプス伝達を増強させる薬剤を投与すると、ASD類似行動が抑制されました。
ASDの中核症状に対する有効な治療薬はなく、ASD患者は多種多様な臨床症状を伴い、機序も多岐に渡り薬物治療は困難と予測されます。本研究はASDの症状の中で共通してみられる社会性障害のメカニズムの一端を解明したことにより、ASDの体系的な治療法の確立や興奮性シナプス機能を標的とした治療薬の開発に貢献することが期待されます。
本研究成果は、2020年10月12日(英国時間)午前10時に「Nature Communications」のオンライン版に掲載されます。
本研究は、科学研究費補助金(課題番号:24220007、25000015, 18H02539, 18H04012、19H05204)の助成を受けて行われました。また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「脳科学研究戦略推進プログラム:臨床と基礎研究の連携強化による精神・神経疾患の克服(融合脳)」の一環として実施されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/10/12)
冠動脈疾患発症に関する遺伝的変異の影響を解明
~ 60万人超の大規模ゲノム解析で明らかに ~
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター循環器ゲノミクス・インフォマティクス研究チームの伊藤薫チームリーダー、小山智史特別研究員、久保充明副センター長(研究当時)、東京大学の小室一成教授、鎌谷洋一郎教授、油谷浩幸教授、村上善則教授、野村征太郎特任助教らの国際共同研究グループ※は、京都大学ゲノム医学センター、JPHC研究、J-MICC研究、OACIS研究と共同で、日本人約17万人のゲノムデータに加え、約5,000人の全ゲノムシークエンスデータを応用し冠動脈疾患を対象としたゲノム解析を行いました。さらにヨーロッパ人集団との統合解析により、冠動脈疾患に関わる疾患感受性座位を新たに同定し、日本人における冠動脈疾患の発症リスクを予測する遺伝的リスクスコア(GRS)を作成しました。
本研究成果は、冠動脈疾患の発症に関わる分子機構の詳しい理解に役立つだけでなく、遺伝情報に基づいた予防・治療の個別化に貢献すると期待できます。
今回、国際共同研究グループは、バイオバンク・ジャパンのゲノムデータを用いて、日本人約17万人のゲノムワイド関連解析(GWAS)を行い、これまでのヨーロッパ人集団を対象とした研究では同定されていなかった8領域を含む、48の冠動脈疾患に関わる疾患感受性座位を同定しました。さらに、過去に行われたヨーロッパ人集団でのGWASの結果と統合し、計60万人を超える大規模な民族横断解析を行った結果、新たに同定された35領域を含む175の疾患感受性座位を同定しました。これまでヨーロッパ人集団のGWASの結果はGRSの作成において日本人をはじめとする非ヨーロッパ人集団への応用が難しいと考えられていましたが、本研究ではヨーロッパ人集団のデータに日本人のデータを加えることによって、高い予測性能を示すGRSの作成に成功しました。
本研究は、科学雑誌『Nature Genetics』の掲載に先立ち、オンライン版(10月5日付:日本時間10月6日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/10/6)
小児胚細胞腫瘍における分子生物学的な特性の解明と治療標的の同定
胚細胞腫瘍は幼児期の小児と若年成人に発症が多く認められる腫瘍性疾患ですが、未だ発症の原因は明らかではありません。胚細胞腫瘍の全体的な治療成績は7~8割程度と悪性腫瘍の中では比較的良好ですが、既存の治療に抵抗を示す難治性の症例が存在することや、悪性腫瘍の治療に伴って引き起こされる晩期障害が近年問題となってきています。これらの問題を克服するためには、遺伝的な要因を分子レベルで解明し、病態に即した最適な治療法を見つけ出すことが非常に重要だと考えられています。
東京大学医学部附属病院 小児科の久保田泰央医師、現京都大学大学院医学研究科 発達小児科学の滝田順子教授らの研究グループは、小児の胚細胞腫瘍51例のDNAメチル化や遺伝子発現、コピー数、遺伝子変異などのゲノム、エピゲノムに認められる異常の全体像を解明し、分子標的治療の対象となりうる遺伝子を同定しました。本研究によって小児のみならず成人の胚細胞腫瘍に対する治療成績の向上と、治療に伴う晩期障害の軽減が期待できます。
本研究成果は、日本時間9月30日に英国科学誌Communications Biologyに掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/10/1)
統合失調症の治療抵抗性の症状に関与する分子・神経回路メカニズムを発見
~ 統合失調症関連遺伝子SETD1A の新たな機能の解明 ~
統合失調症は、幻覚・妄想、社会活動の低下や情報処理能力の低下など多彩な臨床症状を示すことが知られています。近年の大規模な遺伝子解析で、多数の遺伝子が病態に関与することが示唆されています。しかし、それらの遺伝子変異が神経細胞においてどのような機能的な異常を引き起こし、統合失調症の発症にどれだけ影響を及ぼすのかよくわかっていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の長濱健一郎研究員(研究当時)、上阪直史講師(研究当時)と狩野方伸教授らの研究グループは、ヒトで統合失調症の発症に強く関与することが知られている遺伝子SETD1Aに注目しました。ヒトの統合失調症患者でみられるSETD1Aの変異と同等の変異を持つ新たな遺伝子変異マウスを作製し、その解析によって、Setd1a遺伝子の機能低下が大脳前頭前野の神経回路の働きに障害を起こし、統合失調症と関連する行動異常を起こすことを発見しました。
研究グループは統合失調症患者で発症に強く関連する遺伝子変異を再現したSetd1a変異マウスをゲノム編集技術により作製し、遺伝子発現、神経回路の働き、マウスの行動について、包括的な解析を行いました。その結果、このマウスは統合失調症によく似た(幅広く臨床的特徴を反映している)行動異常を示すことがわかりました。またSetd1a遺伝子の発現低下によって、大脳前頭前野において、神経細胞同士の機能的な結合を反映する興奮性のシナプス伝達が、一部の神経細胞(2/3層の錐体細胞)において低下し、マウスの社会性行動の異常が起こることがわかりました。統合失調症患者は、症状の一部として社会生活の中での会話や行動に障害を持ち、現存の薬物治療にも抵抗性を示すことが多く、治療が難しいことが知られています。本研究の成果は、複数の精神疾患に共通してみられる社会性障害のメカニズム解明に貢献するとともに、統合失調症の治療抵抗性の症状へのシナプス機能を標的とした新規治療法開発に貢献することが期待されます。
本研究成果は、2020年9月15日(米国東部夏時間)に「Cell Reports」のオンライン版に掲載されます。
本研究は、科学研究費補助金(課題番号:18H04012、19H05204、19H05253)の助成を受けて行われました。また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」の一環として実施されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/9/18)
オートファゴソーム形成の膜変形ダイナミクスの数理モデル
オートファジーにおいて、オートファゴソーム形成は膜の大規模な形態変化を伴う現象です。その変化は極めてユニークで、隔離膜といわれる扁平なディスク状の小胞が、成長とともにカップ状に弯曲し、最後にカップの口が閉じて球状のオートファゴソームが形成されます。多くのオートファジー関連因子はこのオートファゴソーム形成過程に関与しており、隔離膜の形態変化はこれらの因子により制御されていると考えられます。しかし、どのような物理機構により隔離膜の形態変化が制御されているのかは謎のままでした。
東京大学大学院医学系研究科の境祐二助教、水島昇教授らの研究グループは、曲率因子による隔離膜の形態制御の数理モデルを構築し、オートファゴソーム形成における隔離膜の形態変化を解析しました。その結果、隔離膜成長とともに曲率因子の膜上分布が自発的に変化することで、隔離膜の一連の形態変化を理解できることを示しました。この数理モデルは、実際に細胞内で観測されるオートファゴソーム形成時の隔離膜変形を定量的に説明します。さらに、オートファゴソームの大きさは曲率因子量によって制御されていることを予測します。本研究成果は、一見複雑に見えるオートファジーの膜動態が、単純な物理機構に基づく数理モデルによる解析が有効であることを示唆しています。今後、膜動態の計測とそれに基づく数理解析とを組み合わせることで、オートファジー動態の制御機構について統合的な理解が進むことが予想されます。
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)および科学研究費助成事業 若手研究「数理手法を用いたオートファジー・ダイナミクスの解明」(代表:境祐二)として行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/9/4)
膵癌で高発現する新規環状RNA の同定とバイオマーカー応用
~ 新しい膵癌診断マーカーの開発をめざして ~
膵癌は、かなり進行した状態で見つかることが多く、死亡者数は年々増加傾向にあり、極めて予後不良な癌とされています。このため、膵癌の早期発見を可能にする、新しいバイオマーカーの開発が強く求められています。その一環として、癌で発現するRNAを、血中で検出することでマーカーとする、いわゆるリキッドバイオプシーの試みがなされてきました。近年、環状RNAと呼ばれる特殊なRNAがさまざまな癌で異常発現することが徐々に明らかとなり、新しいバイオマーカーとして注目されてきました。
東京大学医学部附属病院 消化器内科の清宮崇博 大学院生、大塚基之 講師、小池和彦 教授らの研究グループは、環状RNAに特異的なRNAシークエンス解析を行い、膵癌において高発現する環状RNAを網羅的に探索しました。その結果、既存のデータベースにない新規環状RNAを見出し、その全長配列を同定しました。また、この新規環状RNAは膵癌の進行度に対応して高発現する傾向がみられることから、膵癌進行に関与している可能性が示唆されました。さらに、この新規環状RNAは膵癌組織で高発現するのみならず、膵癌患者およびその前癌病態にある患者の血液からも高頻度に検出されることを確認しました。この結果は、採血による膵癌の早期診断・前癌病態の囲い込みへ応用できる可能性を示唆しています。
本研究成果は、日本時間9月3日にJournal of Human Genetics(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/9/3)
新型コロナの外出自粛の呼びかけ
知事、専門家より「現場の医師」のメッセージで効果大
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、世界各国でロックダウンが実施され、日本でも4月~5月の緊急事態宣言下で、不要不急の外出の自粛が呼びかけられました。しかし、要請を無視した外出行動は日本を含む各国で問題となりました。
緊急事態宣言下では、メディアを通じ、外出自粛要請に関する多くのニュースが発信されました。それらのニュースは、「知事」、「感染症対策の専門家」、「コロナ病棟で働く医師」、「コロナに感染した患者」、「海外の感染爆発地域の住民」等の談話を掲載し、外出自粛を呼びかけました。それでは、誰によるどのような呼びかけが、外出自粛をうながす効果が高いのでしょうか?
東京大学大学院医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 奥原剛 准教授らは、緊急事態宣言下の2020年5月9日~11日に、日本全国の成人1,980人を対象に、ランダム化比較研究を実施しました。研究参加者を①「知事」、②「感染症対策の専門家」、③「コロナ病棟で働く医師」、④「コロナに感染した患者」、⑤「海外の感染爆発地域の住民」による外出自粛の呼びかけを読むグループにランダムに割り付け、外出を自粛しようという気持ちの強さを回答してもらい、①~⑤のグループ間で比較しました。
その結果、医療崩壊の危機を訴える現場の医師によるメッセージが、外出自粛をうながす効果が最も高いことがわかりました。外出自粛をうながすというと、知事や専門家によるメッセージが思い浮かぶかもしれませんが、現場の医師のメッセージが最も効果的だったのです。
今後、感染爆発が懸念され再び外出自粛が要請される場合に、医療崩壊の危機を訴える現場の医師によるメッセージを積極的に発信することの重要性が示唆されました。メディアと公衆衛生に従事する皆様におかれましては、メディアの情報を通じ人々のより適切な行動変容を支援するために、本研究成果をご活用いただけますと幸いです。
本研究成果は国際学術誌「Patient Education and Counseling」(オンライン出版日:2020年8月21日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/9/2)
慢性心不全患者で認められる突然死の原因を解明
高齢化社会が進む中、慢性心不全の患者数は増加し続けています。若年者を含む重症心不全の患者さんにおいて、現時点で最善とされる内科的治療を行っても、致死的な不整脈による突然死を免れられないことが大きな問題となっています。この度、東京大学医学部附属病院 循環器内科の山口敏弘特任助教および野村征太郎特任助教、小室一成教授、現東邦大学医学部医学科 生理学講座の内藤篤彦教授、現エール大学医療学校 神経科学部の住田智一助教らのグループは、これまで明らかになっていなかった心臓ドパミン受容体の役割に着目し、同受容体が心不全時の致死的な不整脈の発症に寄与していることを世界で初めて明らかにしました。今回の研究成果により、重症心不全の患者さんの突然死を抑制する新たな治療法の開発に、大きく貢献することが期待されます。
本研究成果は、日本時間8月31日に英国科学雑誌Nature Communicationsにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/9/1)
線維芽細胞が自己免疫を防ぐ
~ T細胞を「教育」する新たなしくみを発見 ~
免疫系は、私たちが健康に生きるために不可欠な生体システムです。免疫細胞のなかでもT細胞は、微生物やがん細胞などを認識して攻撃する一方、自分自身の成分を攻撃しない性質をもち、免疫系の中心的な役割を担っています。このようなT細胞の性質は、T細胞が胸腺で「教育」を受けることで成立します。特に、胸腺の髄質では、上皮細胞と呼ばれる細胞が自己成分を作り出し、それに反応するT細胞を取り除く作用をもつことが知られています。
胸腺の髄質には、それ以外の細胞も多数存在しており、線維芽細胞はその代表例です。線維芽細胞は従来、動物体内に広く存在し、体を構成する個性のない細胞と思われてきました。しかし近年、線維芽細胞は臓器ごとに異なる性質をもち、様々な生命現象に重要な役割を担うことが注目されています。
東京大学医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学分野の新田 剛 准教授と高柳 広 教授らの研究グループは、マウスを用いて、胸腺の髄質に存在するユニークな線維芽細胞を単離する方法を開発し、それらの遺伝子発現などの特徴を明らかにしました。さらに、髄質の線維芽細胞が自己タンパク質(自己抗原)を作り出し、それに反応するT細胞を取り除き、自己免疫を抑える機能をもつことがわかりました。本研究成果は、免疫系の基本原理の理解を深め、自己免疫疾患の原因解明や治療法開発につながると期待されます。
本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金(15H05703, 16H05202, 17H05788, 19H03485, 19H04802)や、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域における研究開発課題「組織修復型免疫細胞の解明とその制御による疾患治療の開発」(研究開発代表者:高柳 広)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/8/25)
分子生物学分野の水島昇教授が藤原賞を受賞
医学部・大学院医学系研究科 分子細胞生物学専攻 分子生物学分野 水島昇教授が「哺乳類オートファジーの生理学的意義と分子基盤の解明」の研究で第61回藤原賞を受賞しました。藤原賞は、自然科学分野に属する基礎科学及び応用科学を対象に、科学技術の発展に卓越した貢献をした功労者に対して、記念賞として贈呈・表彰されるものです。
公益財団法人 藤原科学財団 藤原賞受賞者 https://www.fujizai.or.jp/prize-J61_.htm
水島研究室のWEBサイト https://molbiolut.jp/
(2020/8/4)
所属病院外において新型コロナウイルス感染症の救援活動を行った医療従事者の心的外傷後ストレス症状に関する調査
これまでの研究から病院内におけるCOVID-19等の新興感染症に対応した医療従事者のメンタルヘルスの問題が報告されていますが、所属病院外においてCOVID-19等の新興感染症に対応した医療従事者のメンタルヘルスの状態やメンタルヘルスの悪化の関連要因は明らかにされていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科精神保健学・看護学分野の浅岡紘季大学院生(修士課程2年)、西大輔准教授らは、DMAT事務局およびDPAT事務局と共同で、2019年2月から3月にかけて所属病院外でCOVID-19の救援活動を行った災害派遣医療チーム(DMAT)および災害派遣精神医療チーム(DPAT)に所属する医療従事者を対象とした調査を行いました。調査は救援活動後の3月11日から4月2日に実施され、年齢や性別に加えて、身体的・精神的疲労などの新興感染症に対応する際のストレス、周トラウマ期の精神的苦痛、派遣活動中COVID-19患者との接触など先行研究からPTSD症状と関連があると考えられている要因についてアンケート調査を行いました。その結果、病院外にてCOVID-19の救援活動を行った医療従事者において身体的および精神的疲労と周トラウマ期の精神的苦痛とがPTSD症状と関連することが示されました。加えて、DMAT隊員はDPAT隊員と比較してPTSD症状との強い関連が認められました。
本研究は、所属病院外においてCOVID-19等の新興感染症の救援活動を行った医療従事者のメンタルヘルスの状態と悪化の関連要因を世界で初めて調査した研究です。本研究成果は、新興感染症の救援活動後にPTSD症状が強く現れる危険性が高い救援者の早期発見や、救援活動後のPTSD予防策の構築に寄与することが期待されます。なお、本成果は「Psychiatryand Clinical Neurosciences」(オンライン版:2020年7月21日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/7/22)
オリーブ油の成分が大動脈を守る
~ オレイン酸を動かし大動脈解離を抑える脂質代謝酵素の同定 ~
大動脈解離は、大動脈壁の中膜が突然破断する予後不良の疾患で、突然死の原因となることから、その診断・予防・治療法の開発は解決すべき喫緊の課題です。しかしながら、大動脈解離にはヒトの臨床を反映する簡便な動物モデルが存在しないため、病態の発症機序は殆ど解明されておらず、それ故に外科的処置以外に予防・治療方策は皆無でした。東京大学大学院医学系研究科 村上誠 教授、山梨大学医学部呼吸器循環器内科 久木山清貴 教授らの研究チームは、脂質を代謝する酵素群の生体内機能に関する研究から、血管内皮細胞から分泌される脂質分解酵素が大動脈の健康を維持する脂肪酸(オリーブ油の主成分であるオレイン酸)を作り出し、大動脈解離を防ぐ役割を持つことを発見しました。この成果は、大動脈解離の新規予防・治療法の開発につながると期待されます。
この研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく革新的医療基盤技術の創出」研究開発領域(研究開発総括:清水孝雄)における研究開発課題「PLA2 メタボロームによる疾患脂質代謝マップの創成とその医療展開に向けての基盤構築」(研究開発代表者:村上誠)、革新的先端研究開発支援事業ステップタイプ(FORCE)、ならびに日本学術振興会科研費(新学術領域研究、基盤研究)の一環として行われました。この研究は、2020年6月1日に米国科学誌『Journal of Biological Chemistry』にオンライン掲載され、特に優れた論文に与えられる“Editors’Picks”に選ばれました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/7/8)
集中治療室での治療を必要とした重症新型コロナウイルス感染症に対する ナファモスタットとファビピラビルによる治療
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染が全世界的に拡大しており、その対策が急がれています。我が国は緊急事態宣言が本年5月25日に解除され、感染はいったん収束しつつありますが、今後の第二波、第三波の到来に備えて、COVID-19の治療薬の開発が喫緊の課題です。東京大学ではナファモスタットメシル酸塩がウイルスのヒトの細胞への侵入を抑制することで、COVID-19に対する有効性が期待できる治療薬として基礎的研究成果を発表してまいりました。今回、東京大学医学部附属病院ではナファモスタットメシル酸塩をCOVID-19に対する治療薬候補として選択し、ファビピラビルとの併用によって、肺炎を発症し集中治療室(ICU)での治療を必要とした重症のCOVID-19症例に対してコンパッショネート(人道的)使用による治療を行いました。
ナファモスタットメシル酸塩は抗凝固薬や膵炎治療薬として国内で使われてきた薬剤です。ファビピラビルはRNAポリメラーゼを抑制することでSARS-CoV-2のヒトの細胞内での増殖を抑制すると考えられています。ナファモスタットメシル酸塩とファビピラビルはウイルスの増殖過程における作用部位が異なることから、両者を併用することで相加的な効果が期待されます。また、COVID-19の一部の患者では、血管内での病的な血栓の形成が病気の悪化に関与していると考えられ、ナファモスタットメシル酸塩の抗凝固作用が有効であると期待されています。
本研究成果は、2020年7月3日に医学雑誌「Critical Care」のオンライン版にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/7/6)
喫煙率の社会格差は縮小していない ~格差を考慮した喫煙対策を~
欧米では喫煙の社会格差の統計をもとにその是正のための対策が健康政策として提起・実施されているのに対し、わが国では喫煙率の社会格差に関する統計がなく、格差が縮まっているのか明らかでありませんでした。東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻公衆衛生学分野の田中宏和客員研究員と小林廉毅教授は、オランダ・エラスムス大学医療センターのヨハン・マッケンバッハ(Johan P.Mackenbach)教授と共同研究を行い、喫煙率の社会格差の経年変化を国民生活基礎調査のデータを用いて分析しました。
2016年の教育歴別の喫煙率(25-64歳)は男性の中学卒業者で57.8%、高校卒業者で43.9%、大学以上卒業者で27.8%であり、女性では中学卒業者34.7%、高校卒業者15.9%、大学以上卒業者5.6%でした。2016年の職業階層別の喫煙率(男性、25-64歳)は管理職・専門職で32.5%、非熟練労働者で47.1%でした。管理職・専門職と非熟練労働者を比較すると、男性で2001年に喫煙率の差は11.9%(95%信頼区間:11.0-12.9)、比は1.24(95%信頼区間:1.22-1.26)であったのが、2016年に差は14.6%(95%信頼区間:13.5-15.6)、比は1.45(95%信頼区間:1.41-1.49)と格差は拡大していました。この傾向は女性でも認められ、人口全体の喫煙率は低下しているものの喫煙率の社会格差は縮小していない(わずかに拡大している)ことが明らかになりました。
わが国では喫煙率の社会格差是正のための目標値の設定や公衆衛生上の施策がなく、このままでは健康格差が拡大する懸念があります。本研究はわが国において喫煙率の社会格差が縮小していない傾向を明らかにしたとともに、将来の健康格差を予防・縮小するための社会格差を考慮した喫煙対策の重要性を示唆するものです。
本研究は2020年6月27日に「Journal of Epidemiology」(オンライン早期公開版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/7/01)
自己免疫疾患の発症を防ぐ新たなタンパク質を特定
~ クロマチン制御因子Chd4は自己抗原の発現を制御し、自己免疫疾患の発症を防ぐ ~
免疫系は、病原体から我々の身体を守るシステムです。T細胞は免疫系において中心的な役割を担っている細胞集団であり、我々の体内に進入してきた病原体を攻撃します。一方で、T細胞は“自己を攻撃しない”性質も持っており、この性質は免疫寛容と呼ばれています。T細胞は胸腺という臓器でつくられますが、胸腺では、末梢組織で機能している多種多様なタンパク質が自己抗原として異所的に発現しており、これらに強く反応する自己反応性T細胞が予め胸腺内で除去されることにより免疫寛容が維持されています。
東京大学大学院医学系研究科病因・病理学専攻免疫学の友藤 嘉彦(医学部医学科;研究当時)、高場 啓之 助教、高柳 広 教授らの研究グループは、胸腺において、末梢組織自己抗原の発現を制御するクロマチン制御因子Chd4を同定しました。研究グループは、胸腺上皮細胞でのみChd4を欠損する遺伝子改変マウスを作成し、胸腺の遺伝子発現パターンやクロマチン構造について検討しました。その結果、Chd4はプロモーター領域、スーパーエンハンサー領域の二領域のクロマチン構造を制御することによって、末梢組織自己抗原の遺伝子発現を制御していました。また、胸腺でChd4を欠損させたマウスは自己免疫疾患を発症しました。以上の結果から、Chd4が末梢組織自己抗原の発現制御を行い、免疫寛容を維持していることがわかりました。
この研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域における研究開発課題「組織修復型免疫細胞の解明とその制御による疾患治療の開発」(研究開発代表者:高柳 広)の一環として行われました。
本研究成果は日本時間6 月30 日にNature Immunology(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/6/30)
高齢者高血圧の発症機序を解明~食塩の関与~
高血圧は、心臓病や脳卒中などの致死的な病気の重要な原因となるが、症状がないことからサイレントキラーと呼ばれています。高齢者は高血圧になりやすいことが分かっていましたが、その原因や機序は不明でした。東京大学先端科学技術研究センター臨床エピジェネティクス寄付研究部門の藤田敏郎名誉教授、河原崎和歌子特任助教らの研究グループは、高齢者高血圧の発症メカニズムを解明しました。
研究グループは、加齢と共に、血中の抗加齢因子Klotho蛋白が減少し、そのため高食塩を摂取するとKlothoにより抑制されていた血管の収縮経路が活性化して、血圧が上昇する一連の過程を高齢のマウスを用いて証明しました。また、それを裏付けるため、Klotho蛋白を補充して予め血中レベルを若いマウスと同程度まで回復させておくと、食塩を投与しても血圧が上昇しないことを示しました。
本研究はKlothoの関与する血管収縮経路の阻害薬を投与することにより食塩による血圧上昇を抑制できたことから、高齢者高血圧の新たな治療薬の可能性を提案しています。さらに、高血圧は予防が大切ですが、生活習慣の改善により血中Klothoを正常に維持することが高血圧発症の予防となることを示唆しており、血清Klothoは高血圧発症の予知マーカーとしても期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/6/30)
統合失調症や双極性障害の男性患者ではセロトニン関連遺伝子のDNAメチル化状態が変化
熊本大学大学院生命科学研究部分子脳科学講座・文東美紀准教授、岩本和也教授および東京大学医学部附属病院精神神経科・池亀天平助教、笠井清登教授らの研究グループは、国内多施設共同研究により、統合失調症や双極性障害患者の血液では、セロトニントランスポーター遺伝子の特定のゲノム領域が高いメチル化状態を示すことを明らかにしました。また、高いメチル化状態は男性およびセロトニントランスポーター遺伝子のプロモーター領域における低活性型の遺伝子多型を持つ患者で顕著に見られ、脳の扁桃体の体積と逆相関することを見出しました。さらに、人工的にメチル化した遺伝子のゲノム領域では、転写活性がほぼ完全に抑制されることを示しました。
セロトニントランスポーターは、脳神経細胞のシナプス間隙で神経伝達物資セロトニン濃度の調節を行っており、抗うつ薬の主要な標的分子であると考えられています。今回、研究グループは、セロトニントランスポーター遺伝子のプロモーター領域における遺伝子多型である5-HTTLPRが、エピジェネティックな状態であるDNAメチル化状態と関連し扁桃体の形態変化を通して精神疾患の病態に関係している可能性を明らかにしました。
本成果により、統合失調症や双極性障害の病態に関する理解が進み、エピジェネティックな状態を標的とした治療薬や診断・治療マーカーの開発など、多方面での応用が期待されます。
本研究成果は、2020年6月19日付(日本時間)の国際科学誌「Schizophrenia Bulletin」において公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/6/22)
虚血性心疾患に関わる新たな疾患感受性座位の発見
~ 発症に関わる遺伝要因の人種差の理解に貢献 ~
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター循環器ゲノミクス・インフォマティクス研究チームの伊藤薫チームリーダー、松永紘研修生、ゲノム解析応用研究チームの鎌谷洋一郎客員主管研究員、東京大学大学院医学系研究科循環器内科学の小室一成教授らの共同研究グループは、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の発症に関わる新たな疾患感受性座位を発見しました。
本研究成果は、虚血性心疾患の発症に影響する生物学的な機序の解明や、遺伝要因の人種差の理解に貢献すると期待できます。
虚血性心疾患の有病率は人種によって異なり、日本人は欧米人に比べて低いことが知られています。この理由として、環境要因だけでなく遺伝要因も発症に関与していることが考えられます。今回、共同研究グループは、約5万人の日本人集団の遺伝情報を用いたゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施し、その結果と約34万人の欧米人集団との人種横断的なメタ解析を行ったところ、虚血性心疾患の発症に関わる3領域の新たな疾患感受性座位を同定しました。さらに、発症に影響する臓器・組織を調べた結果、日本人集団では副腎、欧米人集団では動脈や脂肪組織の影響が大きいことが分かりました。なお、本研究で作成した日本人集団におけるジェノタイプデータは、科学技術振興機構(JST)バイオサイエンスデータベースセンター(NBDC)を通じて公開する予定です。
本研究は、科学雑誌『Circulation: Genomic and Precision Medicine』(6月16日付:日本時間6月17日)の掲載に先立ち、オンライン版(5月29日付)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/6/15)
新型コロナウイルス感染症に対する企業内対策の実施状況
~ 企業規模別・業種別での検討と仕事のパフォーマンスへの影響 ~
新型コロナウイルス感染症に対し、各職場で実施される企業対策は感染拡大防止に重要な役割を担っています。しかし、日本における新型コロナウイルス感染症に対する企業内対策の実施状況は明らかになっていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野の佐々木那津大学院生、川上憲人教授らは、日本での新型コロナウイルス感染症拡大の初期に企業内対策の実施状況を明らかにすることを目的に、全国一般労働者1,488人を対象にオンライン調査を実施しました。新型コロナウイルス感染症に関連して社員向けの通知の有無と、23項目の個別対策の実施状況について今回新たに作成した調査票に回答してもらいました。新型コロナウイルス感染症への不安、心理的ストレス反応、仕事のパフォーマンスについても聴取しました。その結果、労働者のうち79.9%は勤務先から新型コロナウイルス感染症に関する社員向けの通知を受け取っていました。手洗いなどの個人予防対策の励行は約8割の企業で実施されていましたが、高齢者や妊婦などハイリスクな労働者への配慮(39.8%)、感染時の補償に関する情報提供(35.3%)、特別な措置が実施される期間に関する情報提供(33.0%)、テレワークや在宅勤務の励行(26.8%)、働く環境(デスクの配置や動線など)の変更(17.2%)の実施率は低いことが明らかになりました。従業員数が50人未満の小規模事業場では対策の実施数が有意に少なく、業種では製造業と比較して小売業・卸売業、運輸業で対策の実施数が有意に少ないことがわかりました。対策の実施数が多いほど、新型コロナウイルス感染症に対する不安は有意に高い傾向がみられましたが、心理的ストレス反応は有意に低く、仕事のパフォーマンスは有意に高いことがわかりました。
本成果は、新型コロナウイルス感染症に対する企業内対策を企業規模別・業種別に検討した初めての研究です。今後は、従業員50人未満の企業や小売業・卸売業、運輸業などの業種においてさらに対策が推進されることが期待されます。なお、本成果は日本産業衛生学会の専門誌「Environmental and Occupational Health Practice」に掲載される予定です。また、感染症への不安・精神健康・パフォーマンスへの影響については日本産業衛生学会の専門誌「Journal of Occupational Health」に掲載される予定です。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/6/15)
疾患発症に関わる日本人の遺伝的特徴の解明
~ 日本人21万人のゲノム解析により遺伝的変異を検索 ~
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター統計解析研究チーム(研究当時)の鎌谷洋一郎チームリーダー、石垣和慶特別研究員、久保充明副センター長(研究当時)、東京大学の門脇孝名誉教授、山内敏正教授、東京医科歯科大学の稲澤譲治教授らの国際共同研究グループは、バイオバンク・ジャパンのゲノムデータを用いて、東北メディカル・メガバンク計画、JPHC研究、J-MICC研究と共同で日本人約21万人のゲノム解析を行い、27疾患に関わる320の遺伝的変異を同定し、そのうち重要な遺伝的バリアントについて、国立がん研究センターバイオバンク、国立長寿医療研究センターバイオバンクならびにOACIS研究の協力で再現性を確認しました。
本研究成果は、疾患の病態の理解、疾患発症リスクの民族差の理解、個々人の遺伝子情報に基づく個別化医療の発展に貢献すると期待できます。
今回、共同研究グループは、42疾患を対象とした東アジアにおける最大規模のゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施し、320の遺伝的変異を同定しました。そのうち25変異は、欧米での研究では検出されなかった新しい変異であり、虚血性心疾患に関連するATG16L2、肺がんに関連するPOT1、ケロイドに関連するPHLDA3などの遺伝子のタンパク質のアミノ酸配列を変える変異が含まれていました。また、このGWASの解析結果と転写因子の結合部位を統合する解析を実施し、疾患発症に関与する転写因子と疾患の378の組み合わせを同定しました。
本研究は、科学雑誌『Nature Genetics』オンライン版(6月8日付:日本時間6月9日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/6/10)
腸内細菌による食後血糖調節機構の解明
~ マクロファージの食後反応と肥満による破綻から見る新規治療への希望 ~
肥満は種々の合併症を引き起こす2型糖尿病の要因のひとつであり、肥満が引き起こす脂肪組織での慢性炎症は糖尿病の重要な病態であるインスリン抵抗性を促進すると考えられています。炎症は免疫反応の一つですが、最近では短期的な免疫反応が生体の恒常性維持に関与している可能性も示唆されています。
今回、東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科の戸田郷太郎 病院診療医、山内敏正 教授、糖尿病・生活習慣病予防講座 門脇孝 特任教授(研究当時、現 虎ノ門病院 院長)、国立国際医療研究センター研究所の植木浩二郎 糖尿病研究センター長の研究グループは、組織特異的ノックアウトマウスを用いた検討を行い、摂食後の小腸内Lipopolysaccharide (LPS)産生菌の一過性の増加およびインスリン分泌に反応したマクロファージがAkt-mTOR経路の活性化によりインターロイキン10(IL-10)を産生し、IL-10がインスリンと共に肝臓での糖新生遺伝子発現を抑制することを発見しました。肥満したマウスではマクロファージでのインスリンシグナルおよびIL-10産生が減弱しており、アデノウイルスを用いてIL-10を発現させると食後高血糖、高インスリン血症が改善することから、免疫反応の食事摂取に対する生理的な応答を回復もしくは維持することが肥満・糖尿病の治療目標になりうると考えられます。
本研究成果は日本時間2020年5月28日午前0時(米国東部夏時間 2020年5月27日午前11時)にMolecular Cell(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/5/28)
遺伝性乳がん・卵巣がんのリスクとなるBRCA2遺伝子バリアントの新規機能解析法を開発
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所細胞情報学分野 池上政周任意研修生、高阪真路ユニット長、間野博行分野長らの研究グループは、国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科 田村研治科長、国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 田中栄教授、細谷紀子准教授、国立研究開発法人理化学研究所生命医科学研究センター 桃沢幸秀チームリーダーらと共同で、遺伝性乳がん・卵巣がんの原因として知られるがん抑制遺伝子BRCA2遺伝子のバリアントに対するハイスループット機能解析法を開発しました。
本研究グループは、これまでにがん遺伝子に対する革新的なハイスループット機能解析手法(mixed-all-nominated-mutants-in-one method: MANO法)を構築し、EGFRやERBB2といったがん遺伝子の意義不明バリアントの機能解析を行ってきました。この手法を発展させ、BRCA2の機能解析手法であるMANO-BRCA法(MANO-B法)を確立し、186種類の意義不明バリアントを含むこれまでで最大規模の244種類のバリアントについて機能解析を行った結果、新たに37種類の病的バリアントを同定しました。さらに本手法の臨床応用例として、遺伝子検査で新たに発見されたバリアントの病的意義を迅速に判定し、報告するシステムを構築しました。本システムは、適切な治療方針が定まらず不安を抱えていた意義不明バリアント保持者に正しい情報を伝えることができることから、リスク低減手術やPARP阻害薬投与の必要性を判断するためのコンパニオン診断としての活用が期待されます。
本研究成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」に5月22日付で掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/5/25)
血小板凝集塊は分類可能!人工知能が発見
東京大学大学院理学系研究科の周雨奇大学院生、合田圭介教授らは東京大学大学院医学系研究科・東京大学医学部附属病院検査部の安本篤史助教(研究当時)、矢冨裕教授と共同で、血液中の血小板凝集塊が分類できることを世界で初めて発見し、それを定量モデル化した手法「インテリジェント血小板凝集塊分類法(intelligent Platelet Aggregate Classifier; iPAC)」の開発に成功しました。iPACは、特殊な顕微鏡を用いて得られた多数の血小板及び血小板凝集塊の画像をもとにした深層学習によって構築された人工知能です。iPACを用いることで、刺激物質(アゴニスト)の種類により血小板凝集塊の形態(形、大きさ、複雑さなど)が微妙に違うことに気づき、血小板凝集塊の形態から活性化を誘導するアゴニストの種類の同定・分類するという画期的な発見をしました。iPACは、血小板凝集のメカニズムを解明するための強力なツールであり、また、流血中の血小板凝集塊の存在は心筋梗塞や脳梗塞の原因となるアテローム血栓症及び最近の新型コロナウイルス感染による血栓症と関連することから、血栓性疾患の画期的な臨床診断法、薬理学、治療法への応用展開が期待されます。
本研究は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)、日本学術振興会(JSPS)の研究拠点形成事業、ホワイトロック財団の支援を受けて実施されました。本研究成果は、2020年5月12日(英国時間)に「eLife」のオンライン版で公開されました。
※詳細は下記ページをご覧下さい。
東京大学大学院理学系研究科・理学部ホームページ プレスリリース詳細
(2020/5/22)
東アジア人集団の2型糖尿病に関わる新たな遺伝子領域を発見
2型糖尿病は血糖値が上がることでさまざまな臓器を傷害し、脳卒中・心筋梗塞・腎不全・がんなど、糖尿病以外の数多くの疾患の発症や進行につながる重大な疾患です。日本国内で1,000万人、世界中で4億人以上が2型糖尿病であると言われています。2型糖尿病のかかりやすさは、遺伝要因と環境要因の両方によって影響されますが、欧米人集団に比べ東アジア人集団における2型糖尿病の遺伝要因の理解は不十分でした。
東京大学大学院医学系研究科の門脇孝特任教授(研究当時)、山内敏正教授、理化学研究所 生命医科学研究センターの堀越桃子チームリーダーらの研究グループは、東アジアなどの国々の研究機関との研究を共催し(the Asian Genetic Epidemiology Network (AGEN) consortium)、40万人規模の東アジア人集団の遺伝情報を用いたゲノムワイド関連解析(GWAS)の大規模メタ解析を行い、2型糖尿病発症のリスクを高める遺伝子領域を新たに61箇所同定しました。
本研究において、2型糖尿病の遺伝要因に筋肉や脂肪といったインスリン感受性に関わる臓器やマイクロRNAが寄与することが示唆されました。また、1つの遺伝子領域にある独立した異なる2つのシグナルが、異なる臓器における、異なる遺伝子の発現調節を介して2型糖尿病発症のリスクを高める可能性が示唆されました。
これらの結果は東アジア人集団における2型糖尿病の遺伝要因の理解を深めるとともに、将来的には糖尿病の病態解明や治療薬開発に応用できる可能性があります。
なお、本研究の2型糖尿病症例数は約8万人であり、世界最大の症例数です。このうち約半数は日本人集団において実施されたGWASが占めており、バイオバンク・ジャパン、東北メディカル・メガバンク機構、多目的コホート研究(JPHC Study)、日本多施設共同コーホート研究(J-MICC Study)よりご協力をいただきました。
本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のゲノム医療実現推進プラットフォーム事業「先端ゲノム研究開発」(GRIFIN)領域における研究開発課題「糖尿病の遺伝・環境因子の包括的解析から日本発次世代型精密医療を実現するプロジェクト」(研究開発代表者:門脇孝)の一環で行われました。その成果は日本時間 2020年5月7日(ロンドン時間 2020年5月6日)に英国科学雑誌 Natureオンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/5/22)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療法の早期確立を目指す
~ 「肺炎を有するCOVID-19 患者に対するファビピラビルとナファモスタットメシル酸塩の併用療法」に関する多施設共同単盲検ランダム化比較試験(特定臨床研究)の開始 ~
東京大学医学部附属病院では、肺炎を発症している新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)陽性患者を対象に、ファビピラビル(アビガン®錠200mg)とナファモスタットメシル酸塩(注射用フサン®50)の併用療法の特定臨床研究を開始しました。本試験は東京大学医学部附属病院のほか、多施設共同で実施いたします。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2020/5/8)
日本人の胃がんリスクとなる遺伝的背景と生活習慣
~ 人種横断的大規模胃がんゲノム解析の成果 ~
胃がんは、日本をはじめ東アジアで最も頻度の高い悪性腫瘍です。がんゲノムシーケンスの進歩によって、胃がんのドライバーとなる体細胞ゲノム変異についてはその全体像が明らかになってきました。胃がん発生リスクについてはピロリ菌がよく知られていますが、ヒト側の遺伝的素因やそれらと環境因子との関わりについて、その全体像は明らかになっていませんでした。
今回、東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス部門の鈴木章浩 指導委託大学院生(研究当時)、油谷浩幸 教授および大学院医学系研究科 衛生学分野の加藤洋人 准教授、石川俊平 教授らの研究グループは、人体病理学・病理診断学分野の牛久哲男 教授、深山正久 教授(研究当時)、消化管外科学の瀬戸泰之 教授、横浜市立大学 外科治療学の利野靖 診療教授、肝胆膵消化器病学の中島淳 教授、国立がん研究センターの柴田龍弘 がんゲノミクス分野長らのグループとともに、319人のアジア人、212人の非アジア人を併せた531症例の胃がん患者を対象とした大規模なゲノム解析を行い、体細胞ゲノム変異のパターン、胚細胞バリアント、生活習慣およびそれらの関連性について調べました。その結果、アルコールによって引き起こされるとされる特徴的なゲノム変異のパターン(変異シグネチャ)が見られる症例がアジア人に特異的に認められ、日本人の胃がんに限った解析では、6.6%(16/243)に認められました。それらの胃がん症例は、東アジア人に特有のALDH2遺伝子多型(アルコールの分解が出来ない遺伝子型)を持ち、飲酒および喫煙の両者が重なった時に相乗的に変異の数が増えることを特徴としていました。また胃がんの素因となる胚細胞レアバリアントを探索したところ、624個のがん関連遺伝子のなかでE-カドへリン遺伝子上のバリアント密度が最も高いことが分かりました。これらのレアバリアントを保有する患者の胃がんは大部分がびまん型胃がんであり、びまん型胃がん症例のうち13.3%(14/105)を占めていました。
東アジア地域特有のALDH2遺伝子多型と飲酒・喫煙習慣との組み合わせ、およびE-カドへリンの病的胚細胞バリアントの集合が、日本における胃がんの原因の一部として強く示唆されることが明らかになりました。特にびまん型胃がん症例の21.0%(22/105)は上記のどちらかの寄与があるという結果でした。今回の成果は、胃がんのハイリスク群を遺伝的素因によって絞り込み、生活習慣の改善や対象を絞った効果的なスクリーニングによって予防介入するための重要な知見と考えられます。本研究は、AMEDの次世代がん医療創生研究事業および革新的がん医療実用化研究事業、科学研究補助金の支援を受けて行われました。本研究成果は米科学誌『Science Advances』で2020年5月7日に公開されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/5/8)
体に優しいオメガ3脂肪酸を動かし肥満を抑える新しい脂質代謝酵素の発見
東京大学大学院医学系研究科 村上 誠 教授らは、脂質を代謝する酵素の生理的役割に関する研究から、白色脂肪組織に常在するM2マクロファージから分泌される脂質分解酵素がオメガ3(ω3)脂肪酸を作り出し、脂肪の燃焼を促進して肥満の進行を遅らせることを発見しました。この成果は、肥満や糖尿病などの生活習慣病の新規予防・治療法の開発につながると期待されます。
この研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく革新的医療基盤技術の創出」研究開発領域(研究開発総括:清水 孝雄)における研究開発課題「PLA2メタボロームによる疾患脂質代謝マップの創成とその医療展開に向けての基盤構築」(研究開発代表者:村上誠)、革新的先端研究開発支援事業ステップタイプ(FORCE)、ならびに日本学術振興会科研費(新学術領域研究、基盤研究)の一環として行われました。この研究は、2020年5月5日(米国東部時間午前11 時)に米国科学誌『Cell Reports(セル・リポーツ)』にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/5/8)
精神保健学分野教授の川上憲人先生が紫綬褒章を受章
精神保健学分野教授の川上憲人先生が紫綬褒章を受章しました。
2020年春の紫綬褒章受賞者19名が発表となり、当学の川上先生が受章されました。川上先生は、永年にわたって公衆衛生学・精神保健学の教育、研究に従事され、地域住民および労働者を対象とした多数の研究に基づき、わが国における心の健康問題の実態解明と対策立案に貢献されたことが評価されました。また、地域と職場における心の健康問題の研究者、実務家の育成にも貢献されました。
特筆すべきこととして、世界精神保健調査日本調査によって地域住民の心の健康の実態解明とその対策立案に大きく貢献されたこと、および労働者の心の健康対策を推進するためのツールを数多く開発し平成27年に国の施策として導入されたストレスチェック制度にも大きく貢献されたことが挙げられます。新型肺炎による公衆衛生の危機に直面するさなか、公衆衛生学研究者・実践家にとって勇気づけられるニュースとなりました。
(2020/5/7)
3次元組織学による全臓器・全身の観察技術を確立
~ 組織の物理化学的性質に基づき理想的なプロトコルを設計 ~
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター合成生物学研究チームの上田泰己チームリーダー(東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室教授)、洲崎悦生客員研究員(同准教授)らの共同研究グループは、組織透明化技術と組み合わせて利用できる全臓器・全身スケールの3次元組織染色・観察技術「CUBIC-HistoVIsion(CUBIC-HV)」を確立しました。
本研究成果は、現時点において世界で最も高効率な3次元組織染色手法を提供するもので、臓器・全身スケールでの生体システムの理解や、臨床病理学検査の3次元化による診断確度・客観性の大幅な向上に寄与すると期待できます。
今回、共同研究グループは、経験則による組織染色プロトコル開発の限界を突破するため、生体組織の物理化学的物性を詳細に調べた結果、生体組織(特に透明化処理を行なった組織)が、主にタンパク質によって構成される「電解質ゲル」の一種であることを再発見しました。この物性から組織を模倣できる人工ゲルを選別し、組織3次元染色の必須条件を探索するスクリーニング系を構築しました。さらに収集した必須条件を組み合わせることで、理想的な3次元染色プロトコルをボトムアップにデザインすることに成功しました。開発したCUBIC-HV法(CUBICに基づく3次元組織学・3次元イメージング)は、CUBIC透明化法、高速ライトシート顕微鏡との組み合わせにより、マウスの全脳、マーモセットの半脳、ヒト脳組織ブロック等を均一に染色し、3次元的な全臓器組織観察を可能にしました。
本研究は、オンライン科学雑誌『Nature Communications』(4月27日付:日本時間4月27日)に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/4/27)
細胞画像のわずかな特徴の違いの見分け方を教えてくれるAIの開発に成功
~ 細胞周期によって変動する特徴量をディープラーニングによって顕微鏡画像から抽出することに成功 ~
東京大学大学院医学系研究科の高尾大輔 助教と東京大学薬学部の長尾幸子 学部生(研究当時)の研究チームは、国立遺伝学研究所の坂本美佳 特任研究員、東京大学大学院薬学系研究科の知念拓実 助教、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)の岡田康志 主任研究者(東京大学大学院医学系研究科・大学院理学系研究科 教授、理化学研究所生命機能科学研究センター(BDR)チームリーダー)らと共同で、ディープラーニングと定量解析により細胞画像から未知の情報を抽出する技術の開発に成功しました。大量の細胞画像から一つ一つの細胞を自動的に切り出し、ディープラーニングにより細胞周期などを判定するAIツールと、その情報をさらに解析することで、細胞周期によって変動する核の形状やゴルジ体の配置パターンなどを抽出する技術を確立しました。これは、人間の目ではとらえにくいわずかな細胞内の変動をAIが発見し、研究者に教えてくれる技術です。
細胞周期によって細胞内の組成や構造は大きく変わることが予想されますが、実際に何がどのように変動するのかを顕微鏡画像から網羅的かつ定量的に解析するためのアプローチは限られていました。具体的に細胞内の何に着目すればいいのかを知るために、今回、共同研究チームはディープラーニングを使って、細胞周期によって変動するパラメータを画像の中から見つける技術を開発しました。これまで研究者が「なんとなく」「経験的に」とらえていた現象や、そもそも見過ごされていた情報を、AIの手助けにより発掘・定量化しようという試みです。その結果、本研究で開発したAIは、DNAやゴルジ体の染色画像の中から、細胞周期によってわずかに変動する特徴を発見しました。この情報を使って共同研究チームが画像を詳しく解析したところ、核やゴルジ体の面積などの特定のパラメータを測定することで画像から細胞周期を分類できることが分かりました。すなわち「画像のどこに着目すれば目的の情報が得られるのかAIが教えてくれる」という研究サポートツールの開発に成功しました。
本研究で開発したツールは汎用性が高く、他の多くの研究への応用を想定しています。細胞周期以外の判定はもちろん、細胞画像以外の画像データへの応用も可能なため、細胞・発生生物学から医療画像の解析など、基礎から応用まで幅広い分野の研究をサポートする強力なツールとなることが期待されます。本研究の成果は、2020年4月22日に米国細胞生物学会誌Molecular Biology of the Cellに掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2020/4/27)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報