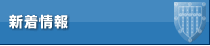広報・プレスリリース情報(2014年(平成26年))
Hes1 を中心とした変形性関節症の制御機構の解明
変形性関節症は高齢者の運動機能を脅かす代表的な疾患であり、膝関節だけで国内に2,530 万人の患者がいると推定されていますが、根治療法は開発されていません。
東京大学大学院医学系研究科/医学部附属病院 整形外科と同医学部附属病院骨・軟骨再生医療講座、同疾患生命工学センターの合同研究チームは、以前Notch シグナルが変形性関節症を強く制御することをマウスの実験によって発見し報告しました(2013年1月15日プレスリリース:http://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/press_archives/20130115.html)。
今回、同チームの杉田守礼医師、田中栄教授、齋藤琢特任准教授らは、遺伝子改変マウスや次世代シーケンサーによる転写解析などを駆使して、Notch シグナルの中心として転写因子であるHes1 タンパク質がさまざまなタンパク分解酵素や炎症性分子を誘導する機構を明らかにしました。
さらに、本研究の成果から変形性関節症の治療標的となりうる候補分子が複数得られました。
Notch・Hes1 は神経系など多くの組織・臓器の構築に重要な役割を果たすことから、これらの知見は生物学の幅広い分野でも役立つことが期待されます。
※![]() リリース文書[PDF:660KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:660KB](東大病院HP掲載)
(2015/3/5)
ビタミンの入り口がわかった!
血液の凝固を活性化する作用を示すビタミンとして古くから知られているビタミンK(VK)は、近年、骨粗鬆症や動脈硬化症の予防・治療に効果があることが報告されるなど、その多様な生理機能に注目が集まっています。
VKは私たちの体内では作ることができないため、主に食物から摂取しています。
しかし、その消化管での吸収のメカニズムについては未解明のままでした。
東京大学医学部附属病院薬剤部の高田龍平講師、山梨義英助教、小西健太郎大学院生(当時)、鈴木洋史教授らのグループは、コレステロールの吸収を担うトランスポーターであるNPC1L1が、VKの消化管での吸収も担うことを世界で初めて見出しました。
血液中のコレステロールなどが増えすぎてしまう脂質異常症の治療薬として使用されているNPC1L1阻害剤のエゼチミブは、抗血液凝固薬のワルファリンと併用されると、ワルファリンの作用を増強することが報告されていましたが、その機序は不明でした。
今回の発見をもとに、この薬物相互作用について検討を行ったところ、エゼチミブによるVKの吸収阻害が原因であることが明らかとなりました。
本研究の成果は、VKの消化管吸収や体内レベルの制御メカニズムのさらなる解明につながるとともに、ビタミンの吸収変動を考慮した適切な薬物治療・薬用量設定に貢献するものと期待されます。
※![]() リリース文書[PDF:536KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:536KB](東大病院HP掲載)
(2015/2/20)
新しく生まれた嗅細胞の生死は特定の時期に匂い入力を受けるかどうかで決まる
~匂い刺激で嗅覚障害の改善が期~
匂いの情報を脳に伝える嗅細胞は、毎日古くなったものが死んでいくため、大人になっても新しく生まれ変わっています。
この新しい嗅細胞が既存の神経回路にきちんと組み込まれるため、古いものが失われても私たちの嗅覚が失われることはありません。
しかし、新しく生まれた嗅細胞がどのようなメカニズムで、既存の神経回路に組み込まれているのかは明らかになっていませんでした。
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科の山岨達也教授、菊田周助教らは、新しく生まれた嗅細胞は匂い入力がないと、既存の神経回路に組み込まれずに細胞死に至ることをマウスにおいて見つけました。
さらに新生した嗅細胞の生死が、神経細胞が生まれてから7~14日目に匂い入力があったか、なかったかによって決められていることを発見しました。
今回の研究によって、嗅細胞には、匂い入力の有無によって新生嗅細胞の生死が決まる「臨界期」が存在することを見出しました。
嗅覚障害に対する確立された治療法はこれまで存在していませんが、今回の発見によって、特定の時期に嗅覚障害患者に匂い刺激を与える、匂いリハビリテーションの開発につながると期待されます。
本研究成果は、2015年2月11日(米国東部標準時間)に米国神経科学学会誌「Journal of Neuroscience(ジャーナルオブニューロサイエンス)」のオンライン速報版で公開されました。
※![]() リリース文書[PDF:520KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:520KB](東大病院HP掲載)
(2015/2/20)
「クラウド型12誘導心電図伝送システム」をドコモより商用提供開始
~ドコモと東大病院による共同研究成果~
株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)と東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)は、社会連携講座「健康空間情報学」(以下、健康空間情報学講座)を東大病院22世紀医療センター内に設置し、共同研究および実証試験を進めてきた「クラウドサーバー型モバイル12誘導心電図伝送システム」において、心筋梗塞患者のカテーテル治療により冠動脈血流を再開する(再灌流)までの時間短縮や、救命率の向上などに対する有用性を明らかにすることができました。
その結果を受け、2015年1月20日(火)より医療機関や自治体消防向けに本システムの商用提供を開始いたします。
なお、商用提供については営業取次と販売促進を担うドコモと、医療機器販売免許を所有しお客様へ営業活動および販売を行う株式会社メハーゲン(以下、メハーゲン)、輸入業務を担当するメディカルテクニカ有限会社(以下、メディカルテクニカ)の3社で実施します。
ドコモと東大病院は、2011年9月の共同研究開始以降、「クラウドサーバー型モバイル12誘導心電図伝送システム」の開発および共同研究における実証試験を実施することで、心筋梗塞患者の再灌流までに要する時間を従来より平均30%の短縮効果が得られることを確認しました。
これは患者の救命率および予後の向上に貢献できる結果です。
また、この結果に関する学術研究発表を国内外で広く行い、医療的な安全性・有効性も評価されております。
今後もドコモと東大病院は健康空間情報学講座を通じて医療をICTでサポートし、医療機関、企業、NPO、行政などとの連携により、生活者と医療機関をつなぐサービスの普及に取り組んでまいります。
※![]() リリース文書[PDF:260KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:260KB](東大病院HP掲載)
(2015/2/20)
自閉スペクトラム症へのオキシトシン経鼻スプレーの治療効果を検証する臨床試験をスタートします
自閉スペクトラム症は、表情や声色を活用して相手の気持ちを汲み取ることが難しいといった対人コミュニケーションの障害を主な症状とし、一般人口の100人に1人以上で認められる代表的な発達障害ですが、その治療法は確立されていません。
東京大学の山末英典准教授らは、金沢大学(責任医師:棟居俊夫特任教授)、名古屋大学(責任医師:岡田俊准教授)、福井大学(責任医師:小坂浩隆特命准教授)との共同研究チームにより、医師主導臨床試験を行って、自閉スペクトラム症における対人コミュニケーションの障害に対する初の治療薬として期待されるオキシトシン経鼻スプレーの有効性と安全性を検証します。
また、医師による診察に加え、視線計測、表情や音声の定量解析、遺伝子解析などを行い、治療効果予測マーカーの確立や、治療効果の分子メカニズムの検討なども行います。
臨床試験は、HP(下記URLよりご覧いただけます)で公開している基準を満たす120名程度の方の参加を予定して募集を始め、平成26年11月に開始して平成27年度中に終了する予定です。
今回の臨床試験は、少人数での検討で示された対人場面でのコミュニケーションの障害そのものに対する効果を大規模な試験を行って検証するものです。
今回の臨床試験の結果により、オキシトシンを医療に用いることを可能にする開発計画が進むことが期待されます。
なお、本研究は、文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」の「精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究(課題F):発達障害研究チーム(拠点長:名古屋大学・尾崎紀夫)」の一環として行われます。
※![]() リリース文書[PDF:203KB](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF:203KB](東大病院HP掲載)
※東京大学医学部精神医学教室HP内「自閉スペクトラム症へのオキシトシン経鼻スプレーの臨床試験」
http://npsy.umin.jp/oxytocin.html
(2015/2/20)
新しい遺伝子治療:メッセンジャーRNA(mRNA)投与による神経障害の治療
神経麻痺やアルツハイマー病などの神経障害は、根治的治療が困難な難治疾患の代表例です。
遺伝子治療は障害された神経細胞を元から治すことができる重要な戦略ですが、これまでの天然のウィルス(ウィルスベクター)や、天然の遺伝子(DNA)の形で投与する手法は、標的細胞自身の遺伝子(ゲノム)を傷つけてしまう懸念があり、治療への応用は困難でした。
メッセンジャーRNA(mRNA)は、通常細胞の中で遺伝子(DNA)からの転写によって産生されるものですが、このmRNAを人工的に合成し、細胞に外部から適切に送達することによって、安全かつ効率よい遺伝子治療を行うことができます。
しかし、mRNAは極めて不安定で生体内では急速に分解されてしまうこと、また自然免疫機構を刺激して生体内で強い炎症反応を引き起こすことから、生体内の細胞に直接mRNAを送達することは容易ではなく、これまでmRNAの治療への応用はほとんどありませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センターの位髙啓史特任准教授・片岡一則教授らの研究グループは、高分子ミセル型ドラッグデリバリーシステム(DDS)を用いたmRNA送達システム(ナノマシン)を構築し、mRNAを用いた遺伝子治療により、嗅覚神経障害を生じた動物の神経組織再生、機能回復が得られました。
神経障害に対する、mRNAを用いた遺伝子治療の世界で初めての成功例です。
本研究の成果により、新しい遺伝子治療用医薬としてのmRNAの可能性が実証され、多くの神経疾患治療への応用が期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF: 139KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 139KB]をご覧下さい。
(2015/2/10)
マンガを使った認知行動療法eラーニングにより働く人のうつ病を1/5に減らすことに成功
うつ病など働く人の心の健康問題(メンタルヘルス不調)の増加は、大きな社会問題となっています。
これまでメンタルヘルス不調の従業員への相談対応や職場復帰の支援が行われてきましたが、最近ではその予防(未然防止)に関心が高まっています。
個人向けのストレスマネジメントは従業員のストレスや気分を改善することがわかっていましたが、うつ病を予防できるかどうかを調べた研究は行われたことがありませんでした。
東京大学大学院医学系研究科の川上憲人教授と今村幸太郎特任研究員は、うつ病の予防効果が知られている認知行動療法に着目し、これを安価で多数の従業員に提供するために、マンガを使った全6回のeラーニングを新しく開発しました。
IT系企業の従業員のうちランダムに選ばれた381人にこのeラーニングを提供し、視聴を促したところ、調査期間後に遅れてeラーニングを提供した同数の従業員にくらべて1年間のうつ病の発症率が1/5に減少することを見出しました。
本成果は、eラーニングによる認知行動療法がうつ病を予防することを明らかにした世界で初めてのものです。
うつ病予防のためのeラーニングが広く企業に導入されることで、働く人の心の健康が大きく向上することが期待されます。
なお、本成果は英国の専門誌「Psychological Medicine」に掲載される予定です。
※詳細は![]() こちら[PDF: 240KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 240KB]をご覧下さい。
(2015/1/13)
免疫タンパク質の不安定さが、自己免疫疾患のかかりやすさに関係
~定説とは異なる発症機序の可能性~
1型糖尿病などの自己免疫疾患は、体の免疫システムが自己の組織を異物(病原体など)と認識して免疫応答することにより引き起こされます。
自己の組織か否かの認識に関与する分子として、ヒト白血球抗原(HLA)と呼ばれるタンパク質があります。
HLA遺伝子の多型(遺伝子の配列が個人間で異なる部分)は1型糖尿病などのさまざまな自己免疫疾患に強く関連します。
しかし、HLAが自己免疫疾患発症に関わる仕組みは十分に解明されていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科の宮寺浩子助教(研究当時)、徳永勝士教授らの研究グループは、HLAタンパク質の安定性を大規模に解析し、1型糖尿病のかかりやすさに関連するHLA遺伝子型が、安定性が顕著に低いHLAタンパク質を作ることを見出しました。
従来の研究では、HLA遺伝子多型と自己免疫疾患との関連はHLAタンパク質のペプチド結合性によって説明されていますが、実際の発症機序については不明な点が多く残されています。
本研究で得られた知見は、自己免疫疾患発症の過程に、これまでの定説とは根本的に異なる発症機序が働いている可能性を示唆します。
研究グループでは、この成果を糸口として、自己免疫疾患発症機序の根幹について、さらなる解明に取り組んでいます。
※詳細は![]() こちら[PDF: 449KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 449KB]をご覧下さい。
(2014/12/9)
神経活動を可視化する超高感度赤色カルシウムセンサーの開発に成功
JST 戦略的創造研究推進事業において、東京大学 大学院医学系研究科の尾藤 晴彦 教授と井上 昌俊 特任研究員らは、生きたマウスの神経活動を計測できる高感度・超高速の赤色蛍光カルシウム(Ca2+)センサーの開発に成功しました。
近年、たんぱく質性蛍光Ca2+センサーは生きている哺乳類の脳の神経活動・シナプス活動を計測するために利用されつつあります。
しかし、これまでの実用的なCa2+センサーは計測波長域が緑色域に限定され、生体内で神経活動を高速・高感度に計測できる赤色Ca2+センサーの開発が望まれていました。
また、従来のCa2+センサーは神経細胞が記憶を成立させるなどの際の高頻度神経発火を計測できないという問題がありました。
本研究グループは、Ca2+結合領域に新規配列を用いることでCa2+に対する結合力を上げ(高感度)、かつ高頻度神経発火の計測が可能な超高感度・超高速赤色Ca2+センサー『R-CaMP2』を開発しました。
この超高感度・超高速赤色Ca2+センサーと従来の緑色Ca2+センサーを組み合わせることで、マウス大脳皮質における興奮性と抑制性の2つの異なる神経細胞種の神経活動を同時に計測することを可能にしました。さらに、光遺伝学的手法との組み合わせも可能であることを自由行動下の線虫において証明し、神経ネットワーク解析に新しい道を拓きました。
この成果は、今後生きている哺乳類の脳の神経活動およびそのダイナミクスの多重計測を容易にし、精神疾患や学習・記憶障害などの病態解明および治療法の開発につながるものと期待されます。
本研究は、主としてJSTのCREST研究の一環として行われました。
また東京大学 大学院医学系研究科の狩野 方伸 教授、喜多村 和郎 准教授(現 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 教授)および埼玉大学 脳末梢科学研究センター 中井 淳一 教授らと共同で行ったものです。
本研究成果は、2014年11月24日(米国東部時間)に米国科学誌「Nature Methods」のオンライン速報版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.02MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.02MB]をご覧下さい。
(2014/11/25)
細胞のナノ分子定規
~細胞内で長さを測るタンパク質の発見~
あなたはナノメートルの長さを測れますか? ナノメートルはミリメートルの百万分の1、髪の毛の先よりもずっと小さいため人の手ではとても測れません。
しかし最新の研究により、私たちの人体を構成する細胞はナノメートル単位の長さを測る定規を持っていて、それが常に体の中で働いていることが明らかになりました。
今回、東京大学大学院医学系研究科の小田賢幸助教、柳澤春明助教、吉川雅英教授らの研究グループは細胞の中で定規の働きをするタンパク質を発見しました。
身長1.6メートルの人間がセンチメートル単位の定規を使うように、大きさ数マイクロメートルの細胞はナノメートル単位の「ナノ分子定規」を使っていることが分かりました(1ナノメートルは1マイクロメートルの千分の1)。
私たちが生きていくために必要な細胞内の微細な構造は、タンパク質でできた非常に小さな定規を基準に作られているのです。
「ナノ分子定規」タンパク質が発見されたのは、私たち人間の気管や精子、卵管、脳室などにある「繊毛」や「鞭毛」と呼ばれる非常に細い糸状の細胞小器官です。
両者の中身はほぼ同じ構造をしているので、以降、両者を含めて「繊毛」と呼ぶことにします。
繊毛を動かしているのは内部にあるダイニンとよばれるモータータンパク質です。
ダイニンは繊毛の中で96ナノメートルを単位とした繰り返し構造を作り綺麗に整列して働いています。
研究グループの発見したナノ分子定規タンパク質は、この96ナノメートルの長さを測ってダイニンがモータータンパク質として効率よく働くように整列させていることが分かりました。
今回得られた知見は、繊毛が関わる不妊、呼吸器疾患、水頭症等の研究に貢献することが期待されるとともに、人工ナノマシンの設計にナノ分子定規の原理を応用できる可能性があります。
本研究は科学技術振興機構CREST、科学研究費補助金、風戸研究奨励会、及び武田科学振興財団の助成を受けて行われました。
本研究の成果は『Science』(2014年11月14日号)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 616KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 616KB]をご覧下さい。
(2014/11/14)
がん発生の基盤となる仕組みを探る
~DNA損傷下における細胞周期の新たな制御因子~
がんとは、細胞周期を制御する仕組みが働かなくなることで、本来起こるべきではない細胞分裂が繰り返されている状態であり、私たちの染色体に記録された遺伝情報に異常が蓄積することによって引き起こされます。
細胞周期を制御する仕組みを支えているのは、細胞内のがん抑制遺伝子群であり、実際に多くのがんでそれらの遺伝子の機能に異常が発見されています。
私たちの体内で頻繁に起こっているDNA損傷がそのような異常の蓄積の引き金となることは判明していますが、その後どのような過程を経てがんが発生するのか、その大部分は明らかになっていません。
今回、東京大学大学院医学系研究科の安原崇哲大学院生と宮川清教授らの研究グループは、DNA損傷後の細胞の生死を決定する仕組みが、がんの発生過程に与える影響の大きさに注目し、その仕組みを制御する新たな遺伝子Rad54Bを発見しました。
Rad54BがDNA損傷下で過剰に働いた場合には、本来停止させるべき細胞周期が進行し、遺伝情報に異常をもった細胞の生存を促進することがわかりました。
このような細胞の生存は、がん発生過程の第一歩となりうることから、将来的にはRad54Bタンパク質を標的としたがん治療によって、がんの進展を抑えるのみならず、がんの発生を未然に防ぐことが可能になると期待されます。
本研究成果は、2014年11月11日に英国科学雑誌『Nature Communications』のオンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 471KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 471KB]をご覧下さい。
(2014/11/12)
マウスを丸ごと透明化し1細胞解像度で観察する新技術
~血液色素成分を多く含む臓器なども脱色して全身を透明化~
理化学研究所(理研、野依良治理事長)と東京大学(濱田純一総長)は、全脳イメージング・解析技術「CUBIC(キュービック)」の透明化試薬を用い、マウス個体全身における遺伝子の働きや細胞ネットワーク構造を三次元データとして取得し、病理解析や解剖学に応用するための基盤技術を開発しました。
この技術によってマウスの全身および臓器を丸ごと透明化し、細胞一つ一つを識別し、1細胞解像度で観察することができます。
これは、理研生命システム研究センター(柳田敏雄センター長)細胞デザインコアの上田泰己コア長、田井中一貴 元研究員(現 東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻薬理学講座システムズ薬理学分野講師)、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻薬理学講座システムズ薬理学分野の久保田晋平日本学術振興会特別研究員らの共同研究グループの成果です。
マウス個体には約300億個の細胞があり、複雑な細胞ネットワークが構築されています。
共同研究グループは、個体全身の遺伝子発現の様子や細胞ネットワークの動きを定量的に取り扱うことで、個体レベルで生命現象を捉え、その現象の仕組みを解明する、新たなイメージング技術の開発を目指しました。
共同研究グループは、CUBICの透明化試薬に含まれるアミノアルコールが、生体組織中の代表的な色素である血液中のヘムを溶出し、組織の脱色を促進することを発見しました。
生体組織による光の散乱だけでなく、光の吸収を抑えることで10日から2週間のうちにマウスの臓器および全身を丸ごと透明化できる新しい透明化プロトコールの開発に成功しました。
さらに、シート照明型蛍光顕微鏡を用いることで、体内の解剖学的構造や遺伝子発現の様子を1細胞解像度で三次元イメージとして高速に取得することが可能となりました。
また、膵臓におけるランゲルハンス島の体積や個数を統計解析する手法を作り、糖尿病モデルマウスのランゲルハンス島の三次元病理解析を可能にしました。
さらに、イメージング画像解析から、各臓器において解剖学的に重要な心臓の心房・心室や肺の気管支樹などの構造を抽出することにも成功しました。
この基盤技術は、遺伝学的に組み込んだ蛍光タンパク質を検出するだけではなく、免疫組織化学的な解析にも適用できます。
本成果は、一個体の生命現象とその原理を解明できることから、生物学だけでなく、医学分野においても大きな貢献が期待できます。
本研究成果は、米国の科学雑誌『Cell』(11月6日号)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 1.09MB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 1.09MB]をご覧下さい。
(2014/11/07)
2型糖尿病発症に関わるモータータンパク質KIF12の発見
~抗潰瘍薬による新しい予防戦略の可能性を拓く~
東京大学大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授と田中庸介助手らは、細胞の中の微小管の上で物質を運ぶKIF12(kinesin superfamily protein 12)モータータンパク質が、2型糖尿病の発症機構に重要な役割を果たしていることを発見しました。
この発見は、市販薬の転用による新たな糖尿病治療・予防法の可能性に結びつくものです。
まず、KIF12遺伝子を人為的に欠損させた遺伝子改変マウスを作製したところ、膵臓のベータ細胞からインスリンが十分に分泌されず、2型糖尿病を発症しました。
この結果から、KIF12モータータンパク質が、抗酸化転写因子Sp1を安定化することで、細胞の酸化ストレスに対する抵抗性(抗酸化能)を高めていることがわかりました。
脂肪をとりすぎると、KIF12モータータンパク質の量が減少し、ベータ細胞の機能が低下することもわかりました。
つまり、KIF12タンパク質が制御する細胞内の情報伝達は糖尿病の治療薬の新たな分子標的となります。
実際、マウスに市販の抗潰瘍薬であるセルベックス®を投与すると、脂肪のとりすぎによってKIF12モータータンパク質が減少していても、ベータ細胞の抗酸化能が失われず、インスリンの分泌が保たれることがわかりました。
すなわち、高脂肪食をとりすぎていても、抗潰瘍薬を飲んでいれば、糖尿病の発症が抑えられる可能性が、分子・細胞・個体レベルを通じて示唆されました。
この研究は、分子モーターという新たなタンパク質分子群の基礎研究から出発して、これまでになかった2型糖尿病の予防・治療戦略を提示するに至ったものです。
※詳細は![]() こちら[PDF: 287KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 287KB]をご覧下さい。
(2014/10/28)
マウス頭部に小さな実験室を作る「ラボ・オン・ブレイン」を開発
~生きた神経細胞のシナプスを53日間観察~
東京大学大学院工学系研究科の一木隆範准教授らと同医学系研究科の河西春郎教授らの研究グループは、マウスの頭部上に搭載する小さな実験室「ラボ・オン・ブレイン」を世界で初めて開発し、生きているマウスの神経細胞の活動を53日間に亘り観察することに成功しました。
昨今の研究トレンドである省エネルギー・省物質の「ラボ・オン・チップ」の、生体への応用を実現しました。
脳機能や脳疾患を解明するには、生きた脳で神経細胞を調べる必要があります。
しかし、脳内へ直接試薬を投与するなどの実験操作を不用意に加えると、脳は容易に損傷して本来の機能が失われる可能性があります。
そのため、本研究グループは、生きている脳の観察を強力に支援し、脳と外界を仲介するインターフェイス機能を備えたマイクロオプト流体デバイスを開発しました。
本デバイスは観察用ガラス窓や髪の毛程度の細い試薬用流路を備えています。
このデバイスと2光子レーザー顕微鏡を用いることで、脳機能に密接に関わる神経細胞の棘状突起構造「スパインシナプス」のわずかな構造変化を、1カ月以上、継続して観察できました。
さらに、脳組織へ光解離性試薬を注入しながら、レーザー光でこの試薬を分解してシナプス可塑性刺激を繰り返し与えたところ、シナプス強度の指標となるスパインの形態の変化を任意のスパインシナプスに生じさせることに成功し、さらにその変化が数日以上持続することを世界で初めて確認しました。
このデバイスの実現に用いられた技術は、記憶・学習などの脳機能の解明や、統合失調症・躁うつ病など、脳の機能不全疾患の治療研究への応用が期待されます。
なお、本成果は、英国科学誌「Scientific Reports」(電子版:英国時間10月22日(水))に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 503KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 503KB]をご覧下さい。
(2014/10/23)
歯周病の男性は心筋梗塞のリスクが約2倍に
歯周病は歯周組織におこる炎症性疾患の総称で、主原因は歯周病細菌群の感染ですが、さらに生体側の因子(歯のかみ合わせ、免疫など)や環境的因子(喫煙、ストレス、食生活、歯周ケアなど)が発症・進展に関連します。
主要な症状は、歯肉の発赤、腫脹、出血であり、進行すると排膿(うみ)や口臭がみられ、最終的には歯の喪失につながります。
近年、歯周病が他の主要な疾患の原因となったり、あるいはその発症の引き金になったりすることが明らかになってきました。
とりわけ、虚血性心疾患の多い欧米では、2000年代以降、歯周病と虚血性心疾患の研究が増えています。
両者の関連を示す報告がある一方、関連がないとする報告もあり、さらなる調査研究が必要とされています。
わが国では、欧米に比して虚血性心疾患の頻度が少ないこともあり、両者の関係を明らかにする研究はほとんど行われていません。
このたび、東京大学大学院医学系研究科の野口都美客員研究員(研究当時は大学院生)、小林廉毅教授らは、産業保健現場の医師らと共同して、金融保険系企業の36歳~59歳の男性労働者3,081人を対象に、質問票を用いて歯周の状態を評価した上で、その後5年間の対象者の健康状態を追跡調査しました。
その結果、歯肉出血、歯のぐらつき、口臭の3項目から歯周病の強く疑われる男性労働者は、そうでない者に比して、心筋梗塞の発症が約2倍多いことを明らかにしました。
歯周病は、40歳以降の日本人男性において頻度の高い疾患である一方、適切なセルフケア(歯磨きなど)や歯科メインテナンス(歯石除去、専門的クリーニング)で予防・改善できるため、今回の研究成果は虚血性心疾患の新しい予防法につながる可能性があります。
本研究は、英国の医学雑誌『Journal of Public Health(10/7オンライン版)』に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 239KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 239KB]をご覧下さい。
(2014/10/10)
メタボのブレーキに肝臓癌を抑制する働きを発見
~新しい肝臓癌治療法の可能性~
東京大学大学院医学系研究科の宮崎徹教授らの研究グループは、本研究グループが発見し、メタボリックシンドロームのブレーキとして働くことが知られているタンパク質AIMが、肝臓に生じた癌細胞を選択的に除去せしめる働きがあることを明らかにした。
AIMは血液中に存在するタンパク質で、通常は脂肪細胞や肝臓の細胞(肝細胞)に取り込まれ、細胞中での中性脂肪の蓄積を阻害することによって肥満や脂肪肝の進行を抑制する、いわばメタボのブレーキとして働いている。
ところが今回、研究グループは肝細胞が癌化するとAIMは細胞の中には入って行かず、代わりに細胞の表面に溜まるようになることを確認した。
さらに、この表面に蓄積したAIMが目印となり、細菌などから最前線で体を守る免疫のひとつである補体が活性化し、癌化した肝細胞を攻撃するようになることをマウスにおいて発見した。
この結果、癌化した肝細胞のみが選択的に取り除かれて、肝臓癌の発症が抑えられるのである。AIMを持たないマウスを作製し、このマウスに高カロリー食を食べさせて肝臓に脂肪が蓄積した状態(脂肪肝)にするだけでマウスは100%肝臓癌を発症した。
しかし、このマウスにAIMを注射すると肝臓癌の発症を抑えられることが分かった。
近年、メタボリックシンドロームの流行と共に、脂肪肝が進む結果、肝細胞が癌化し肝臓癌が発症するケースが注目されている。
ヒトの血液中のAIM値には個人差があり、性別、年齢などによっても異なる。
したがってAIM値が低い場合は細胞が癌化しても上手く取り除かれなくなり、ヒトにおいても肝臓癌が発症しやすくなる可能性がある。
以上のことから、血液中のAIM値は肝臓癌発症のリスクを予測する目印となり得ると示唆される。
また、AIM投与による肝臓癌の新しい治療法を開発できる可能性も高い。
特に、肝臓癌は有効な抗癌剤がなく治療が困難であるだけに期待は大きく、AIMは本来よりヒトの血液中に存在するタンパク質であるため、安全性は高いと期待される。
※詳細は![]() こちら[PDF: 364KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 364KB]をご覧下さい。
(2014/10/3)
長期記憶形成時の脳部位に応じた遺伝子発現調節機構の発見
JST 戦略的創造研究推進事業において、東京大学の尾藤 晴彦 教授らは、マウスを用いた実験により、脳の部位ごとに記憶に応じた遺伝子発現の調節を可能にするメカニズムを解明しました。
脳はさまざまな情報を処理する部位に分かれています。 その1つに「記憶」がかかわっている部位があり、記憶が一時的なものか長期的に持続するものかは、特定の遺伝子発現の有無にかかっていることなどが知られています。
しかし、脳の各部位でどのようにして特定の遺伝子群だけを読み出し、部位ごとに異なる機能を発揮できるのか、これまで謎に包まれていました。
長期記憶注の形成には特定の遺伝子の発現が必要です。 目的の遺伝子上に転写因子と呼ばれる分子が結合することで遺伝子の転写が開始し、特定の遺伝子発現の調節が行われています。
代表的な転写因子の1つにCREBがあり、全身のさまざまな場面で働いており、脳でも、記憶のみならず、発生・細胞の生存維持・体内時計などさまざまな機能が報告されています。
今回、本研究グループはCREBの転写補助分子であるCRTC1に着目し、この因子の神経細胞における性質を具体的に調べ、マウスの脳でCRTC1-CREB経路が脳部位に応じて働くことを見いだしました。
具体的には、長期的な記憶に必要とされる海馬と扁桃体で、海馬ではCRTC1の寄与が少ないのに対し、扁桃体では大きく、しかし、CRTC1を海馬で強化すると記憶が向上するが、扁桃体ではそのような作用がないことが分かりました。
このような部位ごとに異なる転写補助因子の振る舞いは、脳全体に普遍的に存在するCREBという転写因子が、脳部位ごとに異なる遺伝子発現調節を行うことを示唆するものです。
CREBを初めとする記憶固定化にかかわる転写因子は、認知力向上の創薬ターゲットであり、今回の研究成果は、精神疾患や学習・記憶障害などの病態解明および治療法の開発につながるものと期待されます。
なお本研究は、東京農業大学の喜田 聡 教授と共同で行ったものです。 本研究成果は、2014年10月1日(米国東部時間)に米国科学誌「Neuron」のオンライン速報版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 605KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 605KB]をご覧下さい。
(2014/10/2)
ビッグデータを活用したパンデミックの予兆・予測の研究がJST-CRESTプロジェクトとして始動されます
今日、感染症流行に関わる情報は、患者の発生に関する疫学情報だけに留まらず、病原体の遺伝子情報やヒトの接触や移動に関するデータ、伝播に関わる気象データなど多岐に渡ります。
これら大規模データを活用し、数理モデルとデータ同化技術を駆使することにより、パンデミックの予兆や予測を実現することは未だ人類の科学的課題であり続けています。
一方,実験医学的な検証手法を用いて病原体のミクロ情報が感染症伝播というマクロ現象に及ぼす影響は少しずつ明らかにされつつあり、また、現実的な接触の異質性などを取り込んだ数理モデルを利用して感染症流行のリアルタイム予測を実施することも少しずつ可能になりました。
本研究は病原体のゲノム情報や実験データを含む大規模な生物情報を利用したパンデミック予兆の捕捉と流行予測を実現し、それに基づいて最も望ましい感染症対策を明らかにします。
具体的には(1)大規模生物学的情報を取り込んだ流行予測モデルの構築、(2)パンデミックの予兆の探知、(3)これら2つのモデルに基づく感染症対策の改善を行います。
大規模データを効率的に分析することで、パンデミックの予兆捕捉と流行拡大の予測を世界で初めて日常的に実現します。
予測計算には、本年4月から稼働中の世界最大の共有メモリ領域を持つ統計数理研究所のデータ同化スーパーコンピュータシステム(愛称「A」)をフルに活用します。
また、病原体のアミノ酸置換を加味したパンデミックの予兆可能性を検討し、あわせて実験医学的検証を実施します。
予測と予兆の各々が一定の妥当性を確保して可能となるため、関連する感染症対策の社会的インパクトが定量的に記述されるものと期待され、予測は医療体制の整備やワクチン等医療資源の優先的配分に役立てられます。
また、ウイルスのヒト-ヒト感染能獲得を予兆で捉えることによって、パンデミックの警戒度の設定に利用することはもちろん、ワクチンの早期生産開始や事前封じ込め策の有効性の検討にも利用することを計画しています。
本研究は「大規模生物情報を活用したパンデミックの予兆,予測と流行対策策定」と題して、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業CRESTのプロジェクトとして開始されます。
東京大学、北海道大学、統計数理研究所、京都大学で共同研究として実施される学際的プロジェクトで、東京大学大学院医学系研究科の西浦博准教授が研究代表者を務めます。
※詳細は![]() こちら[PDF: 752KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 752KB]をご覧下さい。
(2014/9/29)
ドーパミンの脳内報酬作用機構を解明
~依存症など精神疾患の理解・治療へ前進~
「パブロフの犬」の実験などにより100年以上前から知られている「条件付け」は、行動選択の基本機構として医学的・心理学的にも広く研究・利用されている。
最近では、神経伝達物質であるドーパミンがヒトや動物の報酬学習に関与すると言われている。
しかしながら、ドーパミンがどのような機構により報酬信号として働くかは不明であった。
一般に、学習が成立する際にはグルタミン酸を興奮性伝達物質とする神経細胞のシナプスの結合強度が変わる(シナプス可塑性)。東京大学大学院医学系研究科の河西春郎教授らのグループは、マウスの快楽中枢である側坐核において、グルタミン酸とドーパミンをそれぞれ独立に放出させ、シナプス可塑性に対するドーパミンの作用を調べた。
すると、シナプスがグルタミン酸で活性化され、その直後の狭い時間枠でドーパミンが作用した時のみスパインの頭部増大が起き、シナプス結合を強化することが明らかになった。
また、この時間枠は行動実験において条件付けが成立するために、行動後に報酬を与えなければならない時間枠とほぼ一致した。
本研究により、行動の「条件付け」が起きる分子細胞機構が世界で初めて明らかとなった。
側坐核は、依存症、強迫性障害などと密接に関係するため、本成果は、精神疾患の理解・治療に新しい展望をもたらすと期待される。
本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム (課題G・神経情報基盤)の一環として実施され、科学研究費 特別推進研究・基盤(S)の支援を受けて行われた。
※詳細は![]() こちら[PDF: 307KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 307KB]をご覧下さい。
(2014/9/26)
自閉症モデルマウスに共通の脳神経回路の変化が明らかに
自閉症スペクトラム障害は、社会コミュニケーションの障害などを特徴とし生後早期から発症する疾患ですがその原因は不明な点が多く残されています。
特に、異なる遺伝的な背景をもつマウスにおいて自閉症スペクトラム障害に対応する行動の変化が現れることが知られていますが、これらのマウスに共通する脳の変化は未だ分かっていません。
今回、東京大学医学系研究科の岡部繁男教授らは自閉症スペクトラム障害モデルマウスを用いて成長過程の脳での神経細胞同士のつながりの変化を計測しました。
複数の全く異なる遺伝的な背景を持つモデルマウスの神経回路を調べた結果、これらのモデルマウスに共通してシナプスが過剰に形成・消失していくことが分かりました。
最先端の顕微鏡技術を用いて生きたマウスの脳内でのシナプスの変化を直接イメージングできたことが新しい発見につながりました。
自閉症スペクトラム障害に対する薬剤の効果の指標などとして今回の発見は役立つものと期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF: 259KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 259KB]をご覧下さい。
(2014/8/22)
幼若期の社会的隔離ストレスが引き起こす雄マウスの行動の劣位性
~社会的に隔離された雄マウスは競争心が弱い~
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター 健康環境医工学部門のベナー聖子大学院生と遠山千春教授らの研究グループは、幼若期のストレスが脳発達に与える影響を、動物を用いた実験により明らかにしました。
幼若期の虐待やネグレクト(育児放棄)が人格形成に大きな影響を及ぼすことは知られており、さらには自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)でもみられる社会性の障害の要因となっている可能性が指摘されています。
動物実験でも、幼若期のマウスに社会的隔離ストレスを与えると将来の脳機能に異常が生じることがわかっており、その分子メカニズムについて解析が進められています。
今回研究グループは、独自に開発した行動の評価手法を用いて、マウスにおける社会的隔離ストレスの影響について調べました。
その結果、幼若期に社会的隔離ストレスを受けた雄マウスは、他のマウスと集団で飼育されている時に生じた競争的状態において、行動の劣位性を示すようになることが明らかになりました。
またそれらの雄マウスの前頭前皮質、海馬、扁桃体において神経活動やストレス応答に関する遺伝子発現レベルに異常が現れていたことも確認しました。
このことは、幼若期ストレスによって生じる将来の社会性の障害は、今まで私たちが思っていた以上に、マウスでも再現できる可能性を示すものです。
今後、このマウスモデルの分子メカニズムの解析が一層加速し、また今回用いた行動解析により、社会性の障害の治療薬や介入法の開発が加速することが期待されます。
以上の研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として行われました。
この成果は「Physiology & Behavior」 2014年8月18日オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 430KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 430KB]をご覧下さい。
(2014/8/20)
シナプス刈り込みのしくみを解明
~シナプス結合の強さの絶対値と相対値の両方が重要~
記憶・学習・情動・運動などの高次機能が正常に働くためには生後発達期の神経回路形成が重要であると言われています。
生後間もなく神経細胞同士の結合部位であるシナプスが過剰に形成され、その後必要なものだけが選別される“シナプス刈り込み”と呼ばれる現象が起こることが知られています。
シナプス刈り込みは神経系のさまざまな領域で起こる現象であり、神経回路形成の根幹をなしていると考えられています。
また、シナプス刈り込みの異常は統合失調症や自閉スペクトラム症といった精神疾患の引き金になるとも考えられており、そのメカニズムの解明は臨床的にも重要です。
刈り込まれるシナプスの選別に重要なのはシナプス結合の強さで、より強いシナプス結合を持つシナプスは生き残り、弱いシナプス結合を持つシナプスが刈り込まれるとされています。
しかし、強いシナプス結合と弱いシナプス結合の「相対的な」差が重要なのか、それとも、生き残るシナプスにはある程度のシナプス結合の「絶対的な」強さが重要なのか、これまで明らかではありませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の狩野 方伸教授らのグループは、小脳において、シナプス結合の絶対的な強さが半分程度に弱くなったが、強いシナプス結合と弱いシナプス結合の相対的な強さの差は正常と変わらない遺伝子改変マウスを作製し、シナプス刈り込みを調べました。
その結果、このマウスではシナプス刈り込みが生後11日目までは正常に起こりますが、その後刈り込みが進まなくなることを明らかにしました。
つまり、生後12日までの刈り込みには強いシナプス結合と弱いシナプス結合の相対的な差が、生後12日以降の刈り込みには強いシナプス結合と弱いシナプス結合の相対的な差だけでなくシナプス結合の絶対的な強さが重要であることを明らかにしました。
本研究成果は、2014年8月7日に科学雑誌「Cell Reports」のオンライン版で公開されました。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として、また科学研究費補助金などの助成を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 335KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 335KB]をご覧下さい。
(2014/8/08)
生きた細胞の構造を鮮明に撮る!
~自然に明滅する蛍光色素の開発と超解像蛍光イメージングへの応用~
細胞を生きた状態のまま観察できる蛍光イメージング法は、これまでさまざまな生命現象を明らかにしてきました。
しかし、蛍光イメージング法の空間分解能は約200ナノメートルであり、細胞の中にある複雑な構造を観察するには不十分でした。
近年研究が進められている「超解像蛍光イメージング法」は、蛍光色素を明滅させることでこの限界を超えられる手法です。
しかし、この手法で一般的な蛍光色素を用いる場合には細胞に添加物を加え、強いレーザーを照射する必要があり、このような条件は細胞に悪影響を与え、細胞を元気な状態で観察するのは困難でした。
東京大学大学院医学系研究科、同薬学系研究科浦野泰照教授らは、ローダミンと呼ばれる蛍光色素に最適な化学スイッチを導入し、条件によらず自然に明滅する蛍光色素「HMSiR」の開発に成功しました。
さらに開発した蛍光色素を用いて細胞の骨格を形成する微小管を染色し、細胞に優しい弱いレーザー光によって約1時間にわたって微小管の動く様子を観察することに初めて成功しました。
今回開発した蛍光色素を使うことで生きた状態のまま細胞の詳細な構造を観察することが可能となり、さまざまな生命現象の解明に役立つことが期待できます。
なお、本研究成果は、Nature Chemistry(7月20日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 356KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 356KB]をご覧下さい。
(2014/7/22)
グリア細胞内の微細なカルシウム活動も見逃さない新しい生体内イメージング技術の開発
グリア細胞は神経細胞を取り囲むように脳に存在する細胞で、脳の平常の機能だけでなく病態制御への関与も示唆されている重要な細胞です。
グリア細胞の活動の指標となるのが細胞内カルシウムイオン(Ca2+)の濃度変化(カルシウムシグナル)です。
これまでの研究では、生きた動物個体のグリア細胞のカルシウムシグナルを細胞の中心部(細胞体)で観察する手法が主流であったため、グリア細胞の微細な突起部分で起こるカルシウムシグナルの観察は困難でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 細胞分子薬理学分野の飯野正光 教授らと慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室の田中謙二 特任准教授らの共同研究グループは、超高感度カルシウムセンサーをグリア細胞の隅々まで行き渡らせた遺伝子改変マウスの作製に成功し、グリア細胞全体のカルシウムシグナルを観察しました。
その結果、微細な突起のみで発生する新しいカルシウムシグナルを発見しました。
この新規手法は、検証の余地が多く残されている「グリア細胞活動の謎」を紐解くための、極めて強力なツールとなることが期待され、脳のさまざまな生理機能や神経変性疾患・脳梗塞等の病理機能の解明につながる可能性があります。
本研究成果は、2014年6月26日に米国科学雑誌『Cell Reports』オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 918KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 918KB]をご覧下さい。
(2014/6/27)
生体膜の多様性形成メカニズムの一端を解明
~多様性にかかわる酵素の異常はマウスの呼吸障害を引き起こす~
多様な構造を持つリン脂質は生体膜の主成分であり、その組成は体の組織によって大きく異なっている。
また、様々な疾患時にリン脂質の組成に変化が見られることが知られている。
このような多様性を説明できるような酵素群、リゾリン脂質アシル基転移酵素が近年多く発見されていたが、具体的にリン脂質の組成をどのように調節するかは不明であった。
今回、国立国際医療研究センター研究所の清水孝雄 研究所長(東京大学大学院医学系研究科 細胞情報学分野/リピドミクス社会連携講座 特任教授)らのグループは、これらのリゾリン脂質アシル基転移酵素の活性とそれがもたらすリン脂質の組成変化を詳細に調べることで、主要なリン脂質であるホスファチジルコリンの組成を調節する因子を同定した。
また、このような調節が破綻した場合に生じる影響を調べるために、リゾリン脂質アシル基転移酵素の一種であるLPCAT1を欠損したマウスを作製したところ、急性肺障害での死亡率が高まった。
今回の研究は生体膜ホスファチジルコリンが多様性を獲得するメカニズムの一部を明らかにし、それが正しく働くことが生物の生存に重要であることを示した。
また、呼吸に関与する界面物質(肺サーファクタント)の異常によって低体重出生児で発生する呼吸の障害や成人の急性呼吸窮迫症候群に対して、新たな治療法の可能性が期待される。
なお、本研究は、Cell Metabolism(2014年6月26日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 526KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 526KB]をご覧下さい。
(2014/6/27)
細胞内の高濃度カルシウムイオンをとらえるセンサーを開発
~ミトコンドリア・小胞体内カルシウムシグナルの可視化~
エネルギーを産生するミトコンドリアとタンパク質の合成にかかわる小胞体は、重要な細胞機能を担う、細胞が共通して有する細胞内小器官であり、これらの機能はカルシウムイオンの濃度変化(カルシウムシグナル)によって制御されることが知られています。
しかし、細胞内小器官におけるカルシウムシグナルを時間的・空間的に高い解像度で可視化する手法は乏しく、例えば、「細胞が刺激に応じてカルシウムシグナルが生じるとき、小胞体やミトコンドリア中のカルシウムイオンはどのように変動するのか」などの不明な点が多く残されていました。
今回、東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 細胞分子薬理学分野の飯野正光教授らのグループは、ミトコンドリアと小胞体のカルシウムシグナルを高解像度で捉えることが可能な蛍光タンパク質型カルシウムセンサー群「CEPIA」を開発しました。
これにより、小胞体からのカルシウムイオン放出が細胞内を波状に伝わる様子、あるいは1つの細胞の中にカルシウムイオンを取り込むミトコンドリアと取り込まないミトコンドリアが存在することを鮮明に可視化できるようになりました。
CEPIAによる可視化解析は幅広い細胞種に適用できるため、細胞機能の基礎的理解だけでなく、ミトコンドリアや小胞体が関わる病態研究にも新たな展開をもたらすことが期待されます。
本研究成果は、2014年6月13日に英国科学雑誌『Nature Communications』のオンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 406KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 406KB]をご覧下さい。
(2014/6/16)
4種類の低分子化合物のみを用いて無血清培地下で多能性幹細胞から骨芽細胞を作製
これまで、多能性幹細胞から目的細胞や組織を作製するために広く用いられてきた手法には、①正確な組成が不明なもの(例 ウシ胎仔血清)を細胞の培養に使用すること、②多能性幹細胞が目的としない組織への分化を誘導しかねない胚様体を形成すること、③誘導因子に遺伝子導入や組換えタンパク質を用いること、などによる安全性やコストに関する懸念が存在します。
多能性幹細胞を用いて各種組織を作製する手法は、全て既知の成分を用い、目的としない組織への分化を抑え、さらに経済的かつ安定な低分子化合物を用いた方法が理想的です。
東京大学大学院医学系研究科外科学専攻医学博士課程の菅家康介氏、同大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の大庭伸介特任准教授、鄭雄一教授らは、細胞の培養に組成が不明なものを用いることなく、4種類の低分子化合物のみを誘導因子として用いることにより、多能性幹細胞から中胚葉を経由して効率的に骨芽細胞を作製する方法を開発しました。
この方法では、経済的かつ安定な低分子化合物をはじめとして既知の成分のみを用い、さらに目的としない組織への分化を抑えるため、既存の手法の問題点が解決されると考えられます。
本法は、骨形成メカニズムの解明、骨形成性薬剤のスクリーニング、骨系統疾患の病態解明、骨再生医療の足掛かりになると期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF: 515KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 515KB]をご覧下さい。
(2014/5/23)
クッシング症候群の原因となる遺伝子変異を発見
クッシング症候群は、副腎から持続的かつ過剰にコルチゾールが分泌されることにより、糖尿病や高血圧など多彩な症状を引き起こす疾患です。
このうち副腎腫瘍が、脳下垂体からの制御に従わず勝手にコルチゾールを産生するタイプを、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)非依存性クッシング症候群と呼びますが、これまでその原因は分かっていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科(医学部附属病院 泌尿器科・男性科)教授 本間之夫および京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学講座 教授 小川誠司を中心とする共同研究チームは、ACTH非依存性クッシング症候群の半数以上においてPRKACA遺伝子の変異が生じていることを明らかとし、さらにこの変異によって副腎腫瘍が持続的にコルチゾールを産生するメカニズムを解明しました。
本研究の成果は、2014年5月23日(米国東部時間)に、米国科学雑誌「Science」電子版にて公開されます。
なお、本研究は、文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「システム的統合理解に基づくがんの先端的診断、治療、予防法の開発」ならびに内閣府/日本学術振興会 最先端研究開発支援プログラム(FIRSTプログラム)の一環として行われました。
※詳細は![]() 東大病院HP掲載のリリース文書[PDF:592KB]をご覧下さい。
東大病院HP掲載のリリース文書[PDF:592KB]をご覧下さい。
(2014/5/23)
栄養センサーmTORC1の異常が多様な神経疾患を引き起こす仕組みを解明
細胞の成長や増殖の制御に関与するタンパク質複合体mTORC1は、その機能の異常ががんや糖尿病などさまざまな疾患の原因となります。
脳においては、mTORC1の働きの破綻は結節性硬化症・神経変性疾患など多様な神経疾患との関連が示唆されています。
しかし、mTORC1の異常が多様な神経疾患と結びつく仕組みについては明らかになっていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター動物資源学部門の葛西秀俊助教と饗場篤教授らの研究グループは、mTORC1が恒常的に活性化した遺伝子改変マウスを作製し、脳におけるmTORC1の機能と疾患の関連について検証しました。
その結果、胎生期の脳におけるmTORC1の活性化によって神経細胞が細胞死をおこし、脳の萎縮(小頭症)を引き起こしました。
対照的に、成熟期におけるmTORC1の活性化は、脳が肥大化すると同時にてんかんや神経変性疾患を発症しました。
このことから、mTORC1 は脳の発達時期によって全く異なる役割を持つことが初めて明らかとなり、この違いがmTORC1活性の異常によって引き起こされる神経疾患の多様性の基盤となっていることが裏付けられました。
mTORC1が関与する神経疾患のモデル動物が確立されたことによって、今後、てんかんや神経変性疾患の発症メカニズムの理解や治療戦略に寄与すると期待されます。
本研究成果は、Cell Reports(5月22日(木)オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 407KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 407KB]をご覧下さい。
(2014/5/23)
細胞の開口分泌現象を高精細に可視化する蛍光試薬の開発に成功
~アレルギー治療薬の開発に応用可能か~
生体で起こる現象を理解する上で蛍光可視化の技術は必要不可欠なものとなっています。
今回、東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 神経生物学分野の浅沼大祐助教、廣瀬謙造教授らの研究グループは新たな蛍光試薬を開発し、従来困難であった細胞の物質分泌に関わる開口分泌現象の高精細な可視化に成功しました。
開口分泌現象はアレルギー性疾患においては過度に生じ、過剰な炎症物質の放出を引き起こす原因となっています。
開発した蛍光試薬はこれらの疾患の仕組みを明らかにする上で非常に有用な研究ツールとなることが期待されます。
本研究成果は、ドイツ科学雑誌「Angewandte Chemie International Edition」(5月6日オンライン版)に掲載されました。
また、蛍光試薬は五稜化学株式会社より「AcidiFluorTM ORANGE」シリーズとして販売が開始されています。
※詳細は![]() こちら[PDF: 359KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 359KB]をご覧下さい。
(2014/5/22)
シナプス刈り込みを制御する分子を明らかに
~逆行性シグナルの実体を解明~
統合失調症や自閉症の病態の根底には、神経回路の発達異常があると考えられています。
生後間もない脳には過剰な神経結合(シナプス)が存在しますが、発達の過程で不要なシナプスは除去されて、機能的な神経回路が完成します。
この過程は「シナプス刈り込み」と呼ばれ、機能的な神経回路が出来上がるために不可欠とされています。
しかし、シナプス刈り込みがどのような仕組みによって起こるかは完全には理解されておらず、特に逆行性シグナル伝達が関わる可能性が示唆されていましたが、その実体は長い間不明のままでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻神経生理学分野の上阪直史助教と狩野方伸教授らの研究グループは、発達期の小脳において、シナプス刈り込みは逆行性シグナルにより制御され、2つのセマフォリン分子Sema3AとSema7Aが逆行性シグナルとして働くことを発見しました。
研究グループはまず、マウスの小脳のプルキンエ細胞と登上線維間のシナプスの刈り込み時期に発現する分子を明らかにしました。
それらの分子の中で、逆行性シグナルとして働きうる分子を網羅的に解析した結果、Sema3A分子がシナプスを強化、維持し、Sema7A分子がシナプスを除去することが分かりました。
さらに、Sema3AとSema7Aは登上線維にあるそれぞれの受容体に直接働きかけて、シグナルを伝えることを明らかにし、シナプス刈り込みが逆行性シグナルにより制御され、そのシグナルの実体がSema3AとSema7Aによるものであることを証明しました。
自閉症や統合失調症といった精神疾患を発症したヒトの脳では、セマフォリン遺伝子やその受容体遺伝子に変異や発現異常が見られることが相次いで報告されています。
本研究の成果は、これらの精神疾患の早期診断や治療薬の開発につながる可能性があります。
本研究成果は、5月15日(木)にサイエンス誌のScience Expressウェブサイトに掲載されました。
なお、本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムの一環として実施されました。
また包括型脳科学研究推進支援ネットワークや科学研究費補助金などの助成を受けて行われました
※詳細は![]() こちら[PDF: 262KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 262KB]をご覧下さい。
(2014/5/16)
難治性スキルス胃がんの治療標的候補となる活性化遺伝子変異を同定
~がんのゲノムシーケンシングの成果~
東京医科歯科大学・難治疾患研究所・ゲノム病理学分野(石川俊平教授)と東京大学 先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス部門(油谷浩幸教授、垣内美和子大学院生)及び大学院医学系研究科 人体病理学・病理診断学分野(深山正久教授)らの研究グループは、難治性がんであるスキルス胃がん(びまん性胃がん)のゲノムシーケンシングを行い新規創薬の標的候補となるRHOA遺伝子の活性化変異を同定しました。
この研究は東京大学 医学部附属病院 胃・食道外科の協力を得て、文部科学省 新学術領域研究「システム的統合理解に基づくがんの先端的診断、治療、予防法の開発」、文部科学省の産学官連携プログラムである先端融合領域イノベーション創出拠点の形成プログラム「システム疾患生命科学による先端医療技術開発」等の支援のもとで行われたものです。
機能解析や構造解析は未来創薬研究所と共同で実施しました。
本研究成果は国際科学誌Nature Geneticsに2014年5月11日付オンライン版で発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 504KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 504KB]をご覧下さい。
(2014/5/13)
米国のスタチン服用者のカロリー及び脂質摂取量が過去10年間で増加
スタチンは血中LDLコレステロールを低下させて心血管疾患の発症を効果的に予防する脂質異常症の薬剤であり、米国では過去10年間で服用者が急速に増加し、成人の6人に1人が服用していると推定されています。
脂質異常症の治療の基本として食事療法や運動療法など生活習慣の改善があることはガイドラインに明記されていますが、食事療法がスタチン服用者において徹底されているかどうかの検証は十分に行われていません。
このたび、東京大学大学院医学系研究科の杉山雄大客員研究員(研究当時大学院生、現在国立国際医療研究センター病院フェロー)、小林廉毅教授、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のMartin F. Shapiro教授らの日米共同研究グループは、米国の政府統計であるNational Health and Nutrition Examination Surveyを用いて1999年から2010年までのスタチン服用者と非服用者の食事量を推計し、この12年間でスタチン服用者においてカロリー摂取量が1日あたり約190kcal、脂質摂取量が1日あたり約10g増加しているのに対し、スタチン非服用者では増加していないことを初めて明らかにしました。
スタチン服用者がスタチンのLDL-C降下作用に頼り食事療法を疎かにしている可能性があり、治療効果を上げるため、スタチン服用者に対する食事指導の奨励・強化が必要と考えられます。
なお、スタチン服用者は日本でも増えているため、日本人を対象にした同様の研究が計画されています。
本研究は、米国の医学雑誌『JAMA Internal Medicine (4月24日オンライン版)』に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF: 198KB]をご覧下さい。
こちら[PDF: 198KB]をご覧下さい。
(2014/5/7)
治験の段階にある抗がん剤が統合失調症モデル動物にも効果
~思春期のマウスで過剰なシナプス除去を予防~
統合失調症は思春期から成人にかけて100人に1人が発症し、幻聴や妄想、意欲低下、認知機能障害などのさまざまな精神神経症状により社会生活が障害される精神疾患です。
統合失調症の発症には遺伝因子が関与し、そして前頭野における神経細胞の接合部位(シナプス)が減少していることが報告されているものの、遺伝子の機能不全がどのように思春期の神経回路網形成に影響をあたえ、統合失調症への発症につながるのかは解明されていません。
東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター構造生理学部門の林(高木)助教らの研究グループは、マウスにおいて統合失調症の発症関連分子として確立されている遺伝子DISC1が機能不全に陥ると、思春期にシナプスが過剰に除去され、成体時にはシナプス密度が大きく減少することを見出しました。
PAK阻害剤であるFRAX486は、この過剰なシナプスの除去を予防し、統合失調症に関連様する症状の一つである感覚運動情報制御機能の障害も改善させました。
これまでの統合失調症の創薬はドーパミン遮断薬を中心とした開発が進められてきましたが、その効果は限定的でした。
PAK阻害剤は各種がんに対する治験がすでに進行しており、正常の細胞機能に対する影響が少ない安全性の高い薬剤であることが示されつつあります。
本研究は、「シナプスを保護する」という従来の統合失調症の治療戦略にない新たな観点により、特に早期介入による治療効果、ならびに既存の創薬の相乗効果の可能性を示唆し、今後の統合失調症の治療戦略に応用されることが期待されます。
本研究は、米国ジョンズホプキンス大学医学部統合失調症センター長の澤明教授、米国ベンチャー企業Afraxis, Incらによる共同研究グループの成果です。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 376KB]
リリース文書[PDF: 376KB]
(2014/4/7)
光に反応して目的の遺伝子をがんへ届ける
~三層構造高分子ミセルをベースに光応答性ナノマシンの開発に成功~
がん細胞などの標的細胞に特定の遺伝子を導入する手法は、現在の最先端医療開発・研究において非常に重要な技術です。
遺伝子導入には細胞に遺伝子を送達する仕組み(デリバリーシステム)が必要であり、これまでウイルスベクターや脂質または高分子から成る遺伝子導入試薬が広く利用され、その有用性が培養細胞や遺伝子の局所的な投与で明らかにされています。
しかし、がん治療や再生医療をはじめとする遺伝子治療では、生体内の狙った部位に遺伝子を導入する技術が不可欠である一方、上記のウイルスベクターや遺伝子導入試薬では実現が困難であり、その安全性にも懸念がありました。
今回、東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻(医学系研究科兼務)の片岡一則教授らの研究グループは、従来のデリバリーシステムを超越し、遺伝子導入の効率と選択性に優れた新規デリバリーシステムとして、三層構造の高分子ミセルをベースとした光応答性ナノマシンを構築しました。
このナノマシンを皮下に腫瘍のあるマウスの全身に投与し、固形がんに光を照射することで、固形がんへの光選択的遺伝子導入に世界で初めて成功しました。
本研究で開発したナノマシンは、ウイルスベクター等の従来の遺伝子導入技術と比較して安全性と選択性に優れ、全身投与が可能であることから、がんや動脈硬化などのさまざまな難治性疾患の遺伝子治療への応用が期待されます。
※詳細はリリース文書をご覧下さい。
![]() リリース文書[PDF: 224KB]
リリース文書[PDF: 224KB]
(2014/4/4)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報