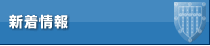広報・プレスリリース情報(2021年(令和3年))
日本人における持続可能な食事の実現には、全粒穀類の摂取量の増加と清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉の摂取量の削減が必要
~ 温室効果ガス排出、栄養素、食費、文化的受容性を考慮したモデル分析 ~
東京大学大学院医学系研究科の佐々木教授、杉本南大学院生(研究当時/現 同大学未来ビジョン研究センター 特任研究員)は,オランダ国Wageningen大学のvan’t Veer教授、オランダ国立公衆衛生環境研究所のTemme博士らとともに、日本人集団において、現在の食事よりも持続可能性が高い、最適化された食事のあり方(食品群の組み合わせ)を示しました。
食品の生産によって生じる温室効果ガス排出量は、世界全体の温室効果ガス排出量の1/3を占めると言われています。関連して生じる温室効果ガス排出量が最小になり、かつ、人々の健康を両立する食事および食システムへの変換は喫緊の課題です。欧米の先行研究では、主に数理最適化法を用いて、食事由来の温室効果ガス排出量が小さく、かつ栄養学的にも適切なものとなる、最適化された食品の摂取パターンを計算してきました。しかし、数理最適化法では、食品を単位として食品の摂取パターンを計算するため、非現実的な食品の組み合わせが生じる可能性があります。そこで、本研究では、過去に実施された、日本人成人369人を対象とした食事データに対して包絡分析法を応用し、栄養学的な食事の質の向上に加えて、食事の金銭的コストと食事に由来する温室効果ガスの排出量が最小になり、かつ文化的にも受容可能な食品の組み合わせを算出しました。
その結果、見いだされた組み合わせは、現在の食事と比べ、清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉、調味料類、砂糖・菓子類の摂取量が少なく、全粒穀類、乳製品、豆・種実類、果物類、鶏肉の摂取量が多いものとなっていました。
包絡分析法を用いたことで、栄養学的な食事の質の向上といった目標を達成しつつ、現在の食事により近い食品の組み合わせが示されています。本研究で示された食事のあり方は、地球の生態学的環境と人々の健康を両立する食システムの実現に向けた、最初のステップになり得ます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/3/23)
世界初、2型糖尿病患者に対し、食事調査に基づき個別化した栄養指導を従来の栄養指導と比較した優位性を実証
東京大学大学院医学系研究科の佐々木敏教授、大村有加客員研究員は、東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科の西村理明教授らとともに、日本人2型糖尿病患者を対象にBDHQを用いた個別化栄養指導を行い、従来臨床現場で行われている栄養指導と比較した血糖改善効果の優位性を明らかにしました。
2型糖尿病患者136人にBDHQを用いた食事調査を行い、個人の食事摂取状況に応じて個別化した栄養指導を提供する群(個別化指導群)と、従来現場で行われている、病院献立例の写真と食品交換表を用いた栄養指導を提供する群(従来型指導群)にランダムに割り付け、6ヶ月間で3回、栄養士による個人栄養指導を提供しました。
2種類の栄養指導方法の介入効果を完全に平等な条件下で比較検討した結果、個別化指導群の方が従来型指導群に比べてHbA1cを低下させる効果を認めました。「個別化」して栄養指導を提供するこの手法は、今後の糖尿病診療に大きく貢献する可能性があります。
本研究成果は、2022年3月22日に出版される「Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases」に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/3/22)
構造生理学部門 河西春郎教授が恩賜賞・日本学士院賞を受賞
この度、河西春郎教授(構造生理学部門、ニューロインテリジェンス国際研究機構)が、恩賜賞・日本学士院賞を授与されることが決定しました。 今回の受賞は、「大脳シナプスの形態可塑性法則の発見」に対するものです。
※ 受賞理由の詳細については日本学士院のホームページをご覧ください。
構造生理学部門 河西研究室のホームペ―ジ https://www.bm2.m.u-tokyo.ac.jp/
<今後の抱負・感想>
大脳のスパインシナプスの運動性やその法則性をご評価いただいたもので、大変光栄に思うと同時に、多くの共同研究者、東京大学や関係諸機関に深く感謝いたします。
これを励みに、シナプス運動性の脳機能における役割の解明を更に進められればと思います。
(2022/3/18)
リンパ腫における細胞外小胞を介した新規発がんメカニズムを発見
~ 脂質を軸とした新たな治療法の開発に期待 ~
JST戦略的創造研究推進事業およびAMED次世代がん事業などにおいて、東海大学 医学部の幸谷 愛 教授および東京大学 大学院医学系研究科の村上 誠 教授は、東海大学 大学院医学研究科の工藤 海 大学院生、東京大学 大学院医学系研究科の三木 寿美 特任研究員らとともに、リンパ腫の発生や悪性化における細胞外小胞(EV)の新規作動メカニズムを発見しました。
東海大学 幸谷グループでは、これまでにEpstein-Barrウイルス(EBV)陽性B細胞性悪性リンパ腫の発症におけるEVの役割を調査してきましたが、その作動メカニズムの全容は明らかになっていませんでした。一方、東京大学 村上グループでは、これまでに細胞外環境に存在するリン脂質分解酵素「分泌型ホスホリパーゼA2(sPLA2)」が関与する数多くの生命現象を明らかにしてきましたが、実際にsPLA2が細胞外で基質としているリン脂質の供給源は不明でした。
本研究では、悪性リンパ腫組織中の腫瘍随伴マクロファージ(TAM)から分泌されるsPLA2が腫瘍細胞由来EVのリン脂質を分解することを証明しました。さらに、この分解により「細胞への取り込まれやすさ」や「免疫抑制効果」などのEVの機能が飛躍的に向上し、さまざまな生命現象が誘導されることが分かりました。このとき、EVリン脂質の分解産物であるリゾリン脂質などが細胞にシグナルを伝達しているという、これまでのEV生物学にはない新規作動メカニズムを介することを発見しました。そして本研究グループはヒトにおけるリンパ腫発生を再現したモデルマウスを使って、sPLA2によるEV分解が腫瘍形成において必要不可欠であることを証明しました。また実際のヒト患者検体の解析からもsPLA2が腫瘍形成と悪性化に関わることを示しました。
一方で、本研究ではリンパ腫由来EVのみならず他のがん細胞由来EVもsPLA2により分解されることを証明し、sPLA2-EV軸は腫瘍形成において共通の現象であることを明らかにしました。今後はこのsPLA2-EV軸が新たな「免疫チェックポイント」として、がん治療のための新しい薬物標的となることが期待されます。また本研究で証明されたsPLA2によるEV機能の増強効果から、過去に幸谷グループで報告した「組織保護・抗炎症作用を持つEV」などのさまざまな種類のEVが持つ固有の能力をsPLA2が増強するのではないかという仮説の検証も現在行っており、今後は治療的応用への発展も期待されます(特許出願中)。
本研究は、東海大学 血液腫瘍内科の安藤 潔 教授、東海大学 病理診断学の中村 直哉 教授、Joaquim Carreras 講師、東北大学の井上 飛鳥 准教授、徳島大学の山本 圭 准教授、Massachusetts General Hospital/Harvard Medical Schoolの樋口 廣士 研究員、滋賀医科大学の森田 真也 教授、東京大学 大学院薬学系研究科の青木 淳賢 教授らを含む複数機関との共同研究によって得られました。
本研究成果は、2022年3月15日午前11時(米国東部時間)に米国科学誌「Cell Metabolism」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/3/17)
大規模な睡眠解析から成人の睡眠パターンを16に分類
~ 睡眠健診や睡眠医療への応用に期待 ~
近年、生活習慣の多様化に伴い、睡眠に不満・不安を覚える人が世界的に増えています。睡眠を簡便に測定し、1人1人の睡眠パターンを定量的に理解することは、ヘルスケアの分野だけでなく、睡眠障害の診断などの医療の観点からも非常に重要です。
JST戦略的創造研究推進事業において、東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田 泰己 教授(理化学研究所 生命機能科学研究センター 合成生物学研究チーム チームリーダー兼任)、香取 真知子 氏(修士課程2年(研究当時))、史 蕭逸 助教(理化学研究所 客員研究員兼任)らは、研究室で独自に開発した、腕の加速度から睡眠・覚醒状態を判別する機械学習アルゴリズム「ACCEL」を用いて、英国のUK Biobankにある約10万人の加速度データを睡眠データに変換し、それを詳細に解析しました。その結果、この10万人の睡眠が16種類のパターンに分類できることを見いだしました。
その中には、朝型や夜型と言った既知の睡眠パターンに加え、睡眠障害との関係が疑われる新しい睡眠パターンも含まれていたことから、今後、ウェアラブルデバイスなどの加速度センサーを用いた計測とACCELを用いた解析を進めていくことで、睡眠障害のより良い診断基準の提案や睡眠障害の自動診断方法の開発、さらには新しい治療法の開発につながることが期待されます。
本研究成果は、2022年3月14日(米国東部時間)に米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS」のオンライン版で公開されました
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/3/15)
体液に触れると瞬時に固化する合成ハイドロゲルで速やかな止血を実現
~ 安全かつ高性能な局所止血材や体液漏出防止材の開発に期待 ~
外科手術では出血の制御が極めて重要です。軽度な出血であれば、自然な血液凝固反応によって止血されますが、太い静脈や動脈からの出血に対しては止血剤を併用した圧迫止血が必要となります。しかし、既存の止血剤には、止血に長い時間を要する、もしくは、ヒト血液成分由来の感染症伝播が否定できないといった課題が残されており、医師・患者双方に負担となっています。東京大学医学部附属病院 血管外科の大片慎也 病院臨床医、保科克行 准教授、同大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻の鎌田宏幸 特任研究員(主任研究員)、酒井崇匡 教授らの研究グループは、新たに、体液と接触した際に速やかに自己固化する合成ハイドロゲルを設計しました。このハイドロゲルは、はじめは液体ですが、体液の一種である血液と接触すると瞬時に血液を巻き込んだ固化を起こし、止血に至ります。ラットの下大静脈大量出血モデルにおいては、1分間で安定した止血効果が得られました。今回開発した新規合成ハイドロゲルは、血液凝固反応とは独立した作用機序をもって速やかな止血に至るだけでなく、未知の感染症の伝播も否定でき、将来の医師・患者双方の精神的負担軽減に貢献できると考えられます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)産学連携医療イノベーション創出プログラム・セットアップスキーム(ACT-MS)(医療分野研究成果展開事業)の支援により行われ、3月3日に『Annals of Vascular Surgery』(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2022/3/7)
がん病理組織画像の特徴を数値化する人工知能技術の開発
東京大学 大学院医学系研究科 衛生学分野の河村大輔 助教、石川俊平 教授らの研究グループは、人体病理学・病理診断学分野の牛久哲男 教授、深山正久 教授(研究当時)、消化管外科学の瀬戸泰之 教授、東京大学医学部附属病院 免疫細胞治療学講座の垣見和宏 特任教授、日本大学医学部外科学系消化器外科学分野 山下裕玄 教授らのグループと共同で、人工知能技術の一つである深層ニューラルネットワークを用いて、がん病理組織画像の組織学的特徴を数値化する技術を開発しました。
通常、がんの診断は顕微鏡を用いて病理組織像を観察する病理診断により行われますが、基本的に個別の病理医の経験知に基づいています。組織像の客観的な記載や数値化は難しいため、多くの症例情報の集積、他の臨床データとの定量的な比較、類似症例の検索、といったデータとしての扱いが容易ではありませんでした。
本研究では、深層ニューラルネットワークを用いて組織画像からディープテクスチャと呼ばれる情報を抽出したところ、がんの病理組織像の特徴を表現するのに適していることを見いだしました。それは例えれば、絵画における「画風」に相当する情報です。この技術を用いることで、病理組織像の特徴が定量的データとして扱えるようになり、組織学的特徴に基づくがんの再分類や、過去の症例からの類似画像の検索、一部のがんの遺伝子変異の予測を含む様々なアプリケーションに応用可能になり、がん研究や医療が促進されることが期待されます。
本研究成果は、3月1日に米科学誌「Cell Reports」にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/3/2)
“スポーツ×生理”に特化した次世代型オンライン教材「1252 Playbook」を制作
~ Instagram で手軽に学べるスポーツと生理の次世代型オンライン教材を制作しました ~
東京大学医学部附属病院(所在地:東京都文京区、病院長:瀬戸康之 以下「東大病院」)女性診療科・産科は、一般社団法人スポーツを止めるな(所在地:東京都新宿区、代表理事:野澤武史 以下「スポーツを止めるな」)が発足させた1252プロジェクトと連携し、Instagram上で手軽に学べる“スポーツ×生理”に特化した次世代型オンライン教材「1252 Playbook」を制作しました。
東大病院女性診療科・産科は、女性アスリート特有の健康問題に対し、障害予防やコンディショニングの点から診療を行うため、女性アスリート外来の設置やコンディショニングガイドの発表、トップアスリートのモニター調査などに取り組んでいます。また、学生アスリートを支援するスポーツを止めるなの趣旨に賛同し、“スポーツ×生理”に関する問題について共有・発信をしていく「1252プロジェクト」を中心に連携しています。その活動の中で、女子学生アスリートには月経に関する具体的な相談先や正しい知識を得られる手段がないという課題が浮き彫りになりました。東大病院が持つ専門的な知見を女子学生アスリートにとってわかりやすい表現にし、Instagram上で正しい知識を手軽に学べる仕様にすることで、女子学生アスリートとその指導者、保護者の方々に活用していただき、女子学生が更にスポーツを楽しめる環境作りを目指します。
本教材は、東大病院女性診療科・産科がスポーツ庁委託事業 女性アスリートの育成・支援プロジェクト「女性アスリート支援プログラム」の一環で作成し、10代への普及啓発の観点からスポーツを止めるなと連携して取り組んでいます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2022/3/1)
認知症の病因「タウタンパク質」が脳から除去されるメカニズムを解明
~ 脳内のグリアリンパ系がタウを押し流すことを発見 ~
超高齢化を迎える現代社会において、認知症の克服は喫緊の課題です。タウは、アルツハイマー病をはじめとする様々な神経変性疾患で脳に蓄積して、神経細胞の死を招く、認知症の原因となるタンパク質です。しかしながらタウの蓄積を防止することにより神経細胞死を食い止める治療法は、これまでに開発されていませんでした。
東京大学大学院医学系研究科の石田 和久特任研究員、山田 薫助教、岩坪 威教授らの研究グループは、タウが脳内から除去される仕組みを明らかにすることが認知症の発症予防に繋がると考え、脳の細胞外での体液の流れに着目しました。研究チームは、マウスを用いた実験で脳内の老廃物を除去するグリアリンパ系(グリンパティックシステム)の仕組みによって、タウタンパク質が脳内から脳脊髄液に移動し、その後、頚部のリンパ節を通って脳の外へ除去されていること、またこの過程にアクアポリン4というタンパク質が関与していることを明らかにしました。さらにアクアポリン4を欠損し、脳からのタウの除去が低下しているマウスでは、神経細胞内のタウ蓄積が増加し、神経細胞死も助長されることがわかりました。本研究は慶應義塾大学医学部の安井 正人教授、阿部 陽一郎講師との共同研究として行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/28)
睡眠時の神経活動を作り出す数学的メカニズムの解明
東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田泰己教授(理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チーム チームリーダー兼任)、山田哲矢氏、史蕭逸助教(理化学研究所 客員研究員兼任)は、ホジキン・ハクスレーモデルをベースにした数理モデルを用いて、睡眠時に特定の神経細胞で観察される睡眠紡錘波発火パターンを制御する分子メカニズムと、その背後に潜む力学系理論を明らかにしました。
多数の神経細胞の集合的な活動がどのように制御されているのかを理解することは、脳の機能を理解する上で必要不可欠です。ヒトをはじめとする哺乳類の睡眠時には、特定の神経細胞集団において徐波発火パターンや睡眠紡錘波発火パターンなどの特徴的な発火活動が観察されます。これまでの本研究グループの数理モデルを用いた研究によって、徐波発火パターンの制御機構が明らかにされてきました。今回、本研究グループはもう一方の睡眠時に重要な神経細胞集団の発火活動である睡眠紡錘波発火パターンに着目しました。まず詳細な分子的・数学的解析が可能な睡眠紡錘波発火パターンの数理モデルを構築しました。続いて、数理モデルの大規模なシミュレーションと力学系における分岐現象の解析に基づいて、①遅延整流性カリウムチャネルの特性が睡眠紡錘波発火パターンの生成に重要な役割を果たすこと、および ②神経細胞膜を通過する内向き・外向き電流のバランスが睡眠紡錘波発火パターンの密度および細胞内カルシウム濃度を制御し得ることを明らかにしました。この結果は睡眠時に特徴的な発火パターンを制御する数学的なメカニズムを示しており、記憶の制御などの神経機能と睡眠との関係や、脳波活動の基礎となる神経細胞活動の制御機構の解明の一助となることが期待されます。
本研究は、米国の科学雑誌『iScience』(2月18日付け:日本時間2月19日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/22)
脳の神経活動を可視化する新規マウス系統を開発
~ 高感度・高速カルシウムセンサーによる神経活動の計測に成功 ~
複雑な脳機能を解明するためには、生きた動物の脳から、個々の神経細胞の活動を正確に計測する技術が必要不可欠です。京都大学大学院生命科学研究科 坂本雅行 特定准教授、東京大学大学院医学系研究科 井上昌俊 特任助教(研究当時、現:スタンフォード大学 博士研究員)、東京大学大学院医学系研究科 尾藤晴彦 教授らの共同研究グループは、高感度・高速カルシウムセンサーを安定して発現する遺伝子改変マウスの開発に成功しました。
近年、神経活動を可視化する方法として、蛍光カルシウムセンサーを用いた神経活動イメージング法が広く用いられています。本研究では、より正確な神経活動の計測を実現するため、高感度・高速カルシウムセンサー(G-CaMP9a)の開発と、この新規センサーを細胞種特異的に発現誘導可能な遺伝子改変マウス(G-CaMP9aノックインマウス)の作製をおこないました。2光子励起顕微鏡を用いた生体イメージングにより神経細胞の活動を観察したところ、このマウスは感覚刺激に対する神経細胞の応答をより正確に検出できることが明らかとなりました。作製したマウスは、カルシウムセンサーの発現レベルが安定して均一なため、複雑な高次脳機能を解明するための有用なリソースとなることが期待されます。
本成果は、2022年2月14日(現地時刻)に米国の国際学術誌「Cell Reports Methods」にオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/15)
世界初、「免罪符型」健康食品CMが「不健康な行動をしても良い」と誤った認識を誘発することを実証
健康食品は、乱れた食事や運動不足を簡単に解消する魔法の方法ではない。例えば、からあげ1つで約60kcalだが、その摂取を帳消しにする健康食品はない。
健康食品を不健康な行動をとるための免罪符として描く「免罪符型」の広告は、「健康食品を摂取すれば、不健康な行動をしてもよい、健康行動をしなくてよい」という誤った認識を視聴者にもたらす可能性がある。そこで、東京大学大学院医学系研究科の家れい奈大学院生、奥原剛准教授、木内貴弘教授らは、健康食品の「免罪符型」広告が、視聴者に及ぼす影響を評価することを目的としてランダム化比較研究を実施した。その結果、「免罪符型」の健康食品の動画広告の閲覧によって、視聴者の「健康食品を摂取すれば、不健康な行動をしてもよい、健康行動をしなくてよい」という認識が強まることが実証された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/14)
2万人規模、国内最大のオンラインコホート構築からアルツハイマー病超早期の研究と治療を目指す『J-TRC研究』が新規ステージに
~ アルツハイマー病・認知症の克服に向けて国際的な予防・治療薬治験との連携が本格始動へ ~
高齢社会の本格化とともに本邦でも認知症の予防・治療は重要課題となり、特にアルツハイマー病(AD)のメカニズムに即した治療法(疾患修飾療法)の実用化は焦眉の急となっています。近年注目を浴びているaducanumab等抗アミロイドβ抗体薬の、有症状期ADの治療におけるポテンシャルとその限界が治験結果から明らかになるにつれ、より早期の無症候段階「プレクリニカル期AD」における超早期治療が注目され、治験も開始されています。
J-TRC研究ではプレクリニカル期ADの方を、インターネットを介したウェブスタディへの登録を入口とし、アミロイドPET、血液バイオマーカー等を含むオンサイト研究において同定し、追跡研究を実施するとともに、希望者の治験参加を支援する「治験即応コホート」の構築を通じて、治療・予防薬開発の促進を目指しています。開始から3年を迎えたJ-TRC研究にはウェブスタディ7,540名、オンサイト研究333名の参加が得られ、オンサイト研究参加者のうちプレクリニカル又はプロドローマル期ADに相当するPET検査でのアミロイド上昇者の比率は25.5%でした。新規のバイオマーカーとして期待されている血漿Aβ42コンポジットスコアにより、PET結果をよく予測できることも実証されました。これらの成果に基づき、治験に即応できるコホートが構築され、希望される方への治験情報の提供も開始、一部の方はプレクリニカル期の抗アミロイドβ抗体薬治験に参加され始めています。今後、複数の薬剤の治験が展開される状況を迎える中で、J-TRCコホートのさらなる拡大により、ADの超早期治療が実現することが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/3)
日本人における未婚者の特性及び婚姻相手に求める要件について
~ 2015年出生動向基本調査の分析 ~
日本における未婚者の増加が課題となっている。しかしながら、「婚活市場」においてどのような需要と供給のミスマッチが存在するのかについては明らかになっていない。東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室は、結婚願望がある日本人未婚者の特性及びそのような人々が婚姻相手の要件として何を重視しているかを調べるために、国立社会保障・人口問題研究所が実施する2015年出生動向基本調査を用いて分析を行なった。その結果、日本の結婚市場では、18〜49歳の年齢層で、結婚の意思があるにもかかわらず未婚の人は女性で848万人、男性で983万人と男性の方が多かった。特に、非人工過密地域(男女比 1.31)および関東地方(東京都を含む)(男女比 1.23)では約60万人未婚男性が“余っている”状況であった。このように男女それぞれが婚姻相手に求める要件には、収入や年齢等で様々なミスマッチが見られることが明らかになった。分析結果は2022年2月3日午前4時(日本時間)に専門誌「Plos One」に掲載された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/3)
タンパク質の設計図を壊さないようにDNA切断を修復する新たな仕組みを発見
~ がんの発生を巧妙に抑制するメカニズムの一端を解明 ~
私たちの体のほとんどの細胞は、タンパク質の設計図としてコンパクトに折りたたまれたDNAを持っています。一つの細胞がもつDNAの長さは2メートルほどになると言われていますが、そのうちのほんの一部分しか設計図として利用されていません。設計図がRNAとして読み出されている部分は、細胞にとって非常に重要であるため、DNA切断などが起こった場合でも正確に修復して維持することが重要です。実際、設計図が壊れて変化してしまうと、大切なタンパク質が作られなくなったり、異常なタンパク質が作られたりすることで、がんなどの病気が発生してしまいます。設計図が頻繁に読み出されている部分、つまりRNAがたくさん存在する部分でDNA切断が起こると、RNAとDNAが対合することで、R-loopと呼ばれる構造が形成されることが知られていました。普段は、DNAは二本鎖で非常に安定に存在しますが、R-loop構造のように、DNAが一本鎖になる部分があると、DNAを切断するタンパク質がアクセスしやすくなってしまい、DNAを壊しやすくなってしまいます。従って、R-loop構造は非常に不安定な構造といえます。しかしながら、DNA切断を修復しなければならない状況にも関わらず、細胞がなぜこの不安定なR-loop構造の形成を許容し、またどのように巧妙に処理して正確なDNA切断の修復につなげているかはわかっていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の安原崇哲助教、加藤玲於奈大学院生、宮川清教授、マサチューセッツ総合病院のLee Zou教授、群馬大学の柴田淳史准教授らの国際共同研究グループは、タンパク質RAP80が、DNA修復中に形成された不安定なR-loop構造の崩壊を防ぐこと、さらにRAP80が機能しないと、不安定なR-loop構造の崩壊に伴ってタンパク質の設計図に異常が増えてしまうことを発見しました。RAP80によって保護されたR-loop構造は、BRCA1、Polθ、 LIG1/3を介してDNA切断を正確に修復することも明らかとなりました。今回明らかになったメカニズムは、タンパク質の設計図の異常を原因として生じるがんなどの疾患を防ぐために細胞が持っている防御機構の一端であることが示唆されます。
本研究成果は、米国科学雑誌『Cell Reports』の2022年2月1日 オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/2/2)
大学院医学系研究科 社会医学専攻 金森万里子さんが育志賞を受賞
この度、金森万里子さん(保健社会行動学分野)が令和3年度 日本学術振興会 育志賞を受賞されました。今回の受賞は、博士課程の研究テーマ「農村地域の自殺に関係する社会環境要因の解明と地域活動モデルの構築」に対するものです。
※ 詳細については日本学術振興会のホームページをご覧下さい。
金森万里子さんのホームページ http://mariko-kanamori.moo.jp/
保健社会行動学分野のホームペ―ジ http://webpark1166.sakura.ne.jp/wp/
(2022/1/26)
腸と皮膚の新たなクロストーク:
腸内細菌叢を変えて皮膚の健康に影響を及ぼす脂質分解酵素の発見
東京大学大学院医学系研究科の村上誠教授らの研究グループは、慶應義塾大学薬学部の有田誠教授、同先端生命科学研究所の曽我朋義教授、医薬基盤健康栄養研究所の國澤純プロジェクトリーダーらとの共同研究により、腸管内腔に分泌されるリン脂質分解酵素の一つであるIIA型分泌性ホスホリパーゼA2 (sPLA2-IIA)が、腸内細菌叢のバランスを変えることによって、皮膚がんや乾癬などの皮膚疾患に影響を及ぼすことを発見しました。これまで、sPLA2は発現している局所の組織微小環境中において固有の機能を発揮すると考えられてきましたが、本研究結果は、sPLA2の一つであるsPLA2-IIAが腸内細菌叢の調節を介して遠隔臓器に二次的変容を導くことを示しており、sPLA2の新しい動作原理を提示するものです。このことから、腸管のsPLA2-IIAを標的とした創薬は、皮膚疾患の新たな診断や治療に役立つ可能性が期待できます。
本研究成果は、2022年1月25日(米国東部標準時)に米国科学誌「JCI insight」のオンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/1/26)
腕の動きを元に、正確に睡眠覚醒状態を判定する方法ACCELを開発
東京大学大学院医学系研究科の上田泰己教授らの研究グループは、腕時計型のウェアラブルデバイス等を用いて計測することができる腕の動きの情報から、その人が眠っているのか、起きているのかを正確に判定する手法を発表しました。ACCEL(ACceleration-based Classification and Estimation of Long-term sleep?wake cyclesの略称)と命名されたこの手法は、加速度計を用いた腕の動きの測定と、睡眠覚醒状態を知るためのPSG測定を同時に行い、得られたデータを機械学習で解析することで開発されました。ACCELによる睡眠覚醒判定には、ウェアラブルデバイスで測定した腕の動きの加速度の変化を表す躍度(加速度の微分値であり、加加速度とも呼ばれます)のみを用います。ACCELを用いた睡眠判定精度は、90%以上の高い感度と80%以上の高い特異度を達成しています。既存の手法の多くは、睡眠判定の特異度が高くないという問題点がありましたが、ACCELは特にこの点を解決する新規手法として期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2022/1/20)
ビタミンCを脳に届ける運び屋を発見
~ 必須栄養素研究における長年の謎を解明 ~
ビタミンの中でもビタミンCは、誰もがその名を聞いたことのある有名な栄養素の一つです。生存に必須である一方、ヒトは体内でビタミンCを作ることができないため、この物質を食べものから摂取する必要があります。ところが、からだの隅々にビタミンCを行き渡らせる仕組みの全容は明らかになっていません。特に、脳はビタミンCを豊富に含む臓器でありながらバリア組織を形成する細胞によって血液と隔てられているため、血液からその細胞内に取り込んだビタミンCを脳側へと排出する分子機構が存在するはずですが、その分子実体は長年にわたって同定されていませんでした。
研究グループは、培養細胞や遺伝子欠損マウスを用いた実験などから、膜輸送体の一つであるSLC2A12トランスポーターが血液から脳へのビタミンC供給に重要な役割を果たすことを見いだし、「ビタミンC排出タンパク質:VCEP」と名付けました。これまで、ビタミンC輸送体については取り込み型しか知られていませんでしたが、この発見は、細胞内から細胞外への輸送を担う排出型輸送体を世界で初めて同定したものでもあり、生理学の発展にも貢献する重要な成果であると考えられます。
本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業などの支援によって行われたものであり、日本時間1月14日にCell Pressが発行する米国科学雑誌iScienceにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2022/1/14)
AIで医療画像と診療情報を統合
~ 高精度な疾患画像判別モデルを開発 ~
慢性肝炎、肝硬変患者に対する肝癌早期発見のため、最も広く用いられる画像検査は腹部超音波検査です。しかし、発見された腫瘤が治療の必要な悪性の腫瘤か、治療を行う必要のない良性の腫瘤であるかの質的な鑑別には造影剤を使用したCTやMRIなどを用いて血流の状態を診る血行動態的な評価が用いられます。腹部超音波検査で得られる超音波Bモード画像のみによる腫瘤の質的な診断が難しい理由は、通常の超音波検査を用いた画像は血行動態評価に比べて画像の客観的な定量化が困難なためです。
腹部超音波検査画像に客観的な定量化ができるようになれば、腹部超音波検査単独での質的な診断が可能になり、CTやMRI検査による被爆や医療費の削減に繋がる可能性があります。画像の定量化を行う方法として、近年注目されているのが深層学習などの人工知能(AI)技術です。
東京大学医学部附属病院 検査部の佐藤雅哉 講師、小林玉宜 臨床検査技師、矢冨裕 教授、消化器内科の中塚拓馬 助教、建石良介 講師、小池和彦 教授(研究当時)ら、および株式会社グルーヴノーツの田中孝 コンサルタントらのグループは、画像と数値など異なる種類のデータを同時に学習することが可能なマルチモーダル深層学習の技術を用いて超音波画像に診療情報を統合する新しい肝腫瘤の疾患画像判別モデルを開発しました。これまで、肝腫瘤の診断のために、肝臓の超音波画像にマルチモーダル深層学習によって他の情報を統合させたという報告は、なされていませんでした。本モデルでは、画像のみを用いた従来の人工知能 (AI)モデルに比べて飛躍的に診断能を向上させることが可能となりました。
マルチモーダル深層学習による画像と診療情報の統合は、医療のさまざまな分野にも応用が可能であり、他分野への応用も期待されます。
本研究結果は日本時間の2022年1月7日に学術誌 Journal of Gastroenterology and Hepatology にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2022/1/7)
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)に重要な腫瘍進展機構を新たに同定
~ “膵のう胞からの癌発生機序”に迫る研究成果 ~
IPMNは健診などで膵のう胞(液体が貯留した病変)として偶然見つかる膵臓癌のリスクとなる病変であり、近年患者数が増えています。IPMNが見つかっても手術以外の方法で癌化を予防する術は確立されておらず、IPMNの腫瘍進展プロセスの理解が必要とされていました。
そこで、東京大学医学部附属病院 消化器内科の加藤裕之 特任臨床医、立石敬介 講師、 小池和彦 名誉教授、藤城光弘 教授らの研究グループは、患者由来の生きたIPMN培養モデルを世界に先駆けて構築し、先進的なゲノム・エピゲノム解析を統合駆使することで、
(1)IPMNが進展する初期の段階から特有のエピゲノム制御機構が疾患を形成していること
(2)その責任分子としてMNX1・HNF1Bを同定し、IPMNの新たな治療標的となる可能性
を発見しました。
今回の研究結果・コンセプトにより、IPMN患者さんの予防医療・治療最適化に向けて研究が加速することが期待されます。
本研究成果は、米国科学誌『Gastroenterology』の本掲載に先立ち、2021年12月21日(米国東部標準時)にオンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/12/23)
血小板で新型コロナの重症化リスクを予測
COVID-19において、血栓症(特に微小血管血栓症)がCOVID-19の重症度や死亡率の重要な要因の一つであることが報告されてきましたが、その詳細は謎に包まれていました。その謎を解くために、東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授、東京大学大学院医学系研究科の矢冨裕教授、米国バージニア大学Gustavo Rohde教授が率いる共同研究グループは、東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)に入院したCOVID-19患者(110名)から採取した血液内の循環血小板凝集塊を、マイクロ流体チップ上で高速流体イメージングにより大規模撮影し、取得した循環血小板凝集塊の画像ビッグデータを解析しました。
その結果、驚くべきことに、全患者の約9割において、過剰な数の循環血小板凝集塊が存在することを世界で初めて発見しました。また、循環血小板凝集塊の出現頻度とCOVID-19患者の重症度、死亡率、呼吸状態、血管内皮機能障害の程度に強い相関があることを発見しました。本研究成果は、COVID-19における血栓症発症機序の解明、重症化リスクの予測、より良い抗血栓療法の探求・評価、後遺症の理解に資すると期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/12/10)
脳は記憶を力で刻む
~ シナプスの力と圧感覚による新しい伝達様式の発見 ~
大脳の興奮性シナプスの後部である樹状突起スパインは学習時に頭部体積を拡張する増大運動をして、自身の機能(グルタミン酸感受性)を増強します。東京大学大学院医学系研究科の河西春郎教授(同大学ニューロインテリジェンス国際研究機構・主任研究者)、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構のUCAR Hasan 特任助教らは、このスパイン増大運動の際に、軸索終末を力学的に押し、終末はこの力を感知して伝達物質放出を増強することを見いだしました。この作用は、ガラスピペットやショ糖による浸透圧で圧をかけることでも観察され、増強効果も20-30分続きました。この軸索の圧感覚から測ったスパイン増大力の大きさは0.5 kg/cm2と筋肉の張力並みでした。シナプスにおいては、電気が通る電気伝達か、化学物質をやりとりする化学伝達かのいずれかで情報は運ばれると言われてきましたが、今回の結果から、スパインの運動が軸索終末に感知され変換される、力学伝達という力学的様式もあることが明らかになりました。末梢神経の軸索終末の感覚受容機構は本年のノーベル医学生理学賞の対象となりましたが、今回の研究は中枢神経(脳)の軸索終末にも感覚受容機構があることを初めて示したものです。末梢とは機構も意義も異なり、脳では短期的な記憶を保持するのに使われている可能性があります。我々の運動能力には個人差があり、得意技が異なるように、脳のシナプスの運動にも個人差があり、頭の個性を決めているのかもしれません。スパインシナプスは精神疾患の原因となる多くの分子が関係するので、その運動性や圧感覚の調査により、我々の知能の起源に関する理解が深まり、精神疾患の診断・治療法が開拓されると期待されます。
本研究は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)、文部科学省科学研究費助成事業の支援を受けて国際科学誌『Nature(電子版)』に2021年11月24日付オンライン版で発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/11/25)
くびの脊髄損傷:24時間以内の緊急手術で麻痺の回復促進
群馬大学(群馬県前橋市)と東京大学(東京都文京区)を中心とする研究グループは、大学病院など全国43施設においてランダム化試験をおこない、非骨傷性頚髄損傷(骨折のない頚髄損傷)に対する早期手術の有効性を調査しました。その結果、24時間以内の早期手術は、待機的におこなう受傷2週以降の手術に比べ、手足に生じた麻痺の回復を早めることがわかりました。
本研究の成果は、非骨傷性頚髄損傷の治療指針の確立にむけた重要なステップになると思われます。
本研究成果は、日本時間2021年11月10日(水)公開の国際医学雑誌「JAMA Network Open」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/11/10)
生まれ順が遅い子どもが他者を助けやすい脳神経メカニズムを解明
東京大学 大学院医学系研究科の笠井清登教授、東京大学 国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構の岡田直大特任准教授、東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らのグループは、約3,000名の10歳児を対象としたコホート調査から、生まれ順が遅い子どもでは生まれ順が早い子どもと比べて、向社会性が高いことを示しました。また、その一部である約200名を対象とした磁気共鳴画像法(MRI)の研究により、遅い生まれ順と高い向社会性との関連を扁桃体の体積が媒介することや、扁桃体と前頭前野との機能的ネットワークの媒介効果に性差があることを示しました。生まれ順が思春期の脳発達に作用し、さらに社会性の発達に影響を与えることを明らかにした、初めての成果です。思春期は精神の発達に重要な時期であり、向社会性は心のしなやかさ(レジリエンス)と関係していることから、本研究結果は思春期における心の健康増進に貢献する可能性が期待されます。
本研究成果は、2021年11月8日午前10時(英国標準時)に英国科学誌「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されました。
本研究は、文部科学省科学研究費補助金や厚生労働科学研究費補助金、日本医療研究開発機構委託研究開発費などの支援を得て実施されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/11/9)
哺乳類の顔を作ったダイナミックな進化過程
~ 哺乳類の鼻は祖先の口先だった ~
哺乳類の顔には動く鼻があり、また上あごの骨格や神経の位置関係も爬虫類や両生類とは大きく異なります。こうした哺乳類特有の顔の進化は全くの謎でした。東京大学大学院医学系研究科の東山大毅特任研究員を中心とする研究チームは、筑波大学、東京大学大学院理学系研究科、テュービンゲン大学、理化学研究所のメンバーとともに、さまざまな動物の発生過程の比較や、遺伝子改変マウスを用いた分子発生学実験、さらに化石を使った古生物学的解析など多面的な手法を持ちいてこの問題に挑みました。その結果、これまで画一的と見なされてきた顔面の形成過程が、哺乳類において大幅に変更されていることが判明しました。爬虫類で上あごの先端部を作る発生原基は哺乳類では主に鼻を生じ、その代わり哺乳類では別の発生原基が上あごの先を作っています。骨格や神経など、顔の構造の位置関係はこの発生原基の系譜の差を反映しており、脊椎動物進化を通じて保存されてきたと考えられてきた上あごの先の骨「前上顎骨」も、哺乳類では進化の過程で別の骨に入れ替わっていたことが示唆されました。これらの結果は、哺乳類の進化研究の基盤となるとともに、顔面の解剖学的構造の位置関係やその発生についてのこれまでの教科書的知見を書き換えるものです。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/11/1)
大腸がんが免疫の攻撃から逃れる機序を解明
~ がん細胞の認識に関わる分子の異常による免疫回避を明らかに ~
国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:中釜斉、東京都中央区) 研究所 細胞情報学分野 河津正人ユニット長(現 千葉県がんセンター研究所部長)、間野博行分野長、腫瘍免疫分野 西川博嘉分野長らの研究グループは、東京大学医学部附属病院大腸・肛門外科 石原総一郎教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科 波江野洋特任准教授、国立国際医療研究センター ゲノム医科学プロジェクト 徳永勝士戸山プロジェクト長らと共同で、細胞が免疫の監視から逃れ、がん化する仕組みを解明し、免疫療法の治療効果予測に有用なバイオマーカーを同定するため、マイクロサテライト不安定性大腸がん等について、長いDNA配列を解読するロングリードシークエンサーを用いて免疫状態を詳しく調べました。
マイクロサテライト不安定性大腸がんは、一定程度で免疫チェックポイント阻害剤の有効性が確認されていますが、必ずしも全ての患者さんに効果が認められるわけではなく、有効性を予測する方法の確立が求められてきました。本研究においてがん細胞と免疫細胞が混在する腫瘍組織の全体像を解明し、免疫チェックポイント阻害薬の有効性の予測につながる成果が得られました。
本研究の結果、免疫細胞が、がん細胞を攻撃する際の目印とされるHLAクラスI遺伝子に多くの後天的変異が生じて機能を失っていることが明らかとなりました。さらに、数理モデルを用いた解析を行い、HLAクラスI以外の多くの遺伝子変異の蓄積によっても、がん細胞に対する免疫反応の効果が弱まることを示しました。本研究での免疫応答の解明により、今後の免疫療法の有効性予測や、効果的な治療戦略の開発の推進が期待されます。
本研究成果は、2021年10月20日(米国東部時間)に米科学誌「Gastroenterology」にオンライン掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/10/21)
子どもの8人に1人が医療サービスを必要とし、親もストレスを抱えやすい
東京大学大学院医学系研究科の笠井清登教授、安藤俊太郎准教授、東京大学相談支援研究開発センターの梶奈美子助教、東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センターの西田淳志センター長、国立成育医療研究センターの五十嵐隆理事長らのグループは、約4,000名の10歳児とその親を対象としたコホート調査から、一般的な子どもが必要とする水準以上の保健・医療サービスを必要とする子ども(Children with special health care needs (CSHCN))が日本において約12.5%存在し、そうした子どもをもつ親は不安・抑うつを抱えやすく、ソーシャルサポートによって軽減される可能性を示唆しました。
CSHCNは米国で提唱された概念で、米国の17歳までの小児の18.8%に存在する(2016/2017年調査)とされていましたが、偏りの少ない一般住民を対象としたコホート研究からその存在率を示した研究や、親の精神保健問題との関連やソーシャルサポートの媒介可能性を示した研究としては初めての成果です。
昨今、日本においても、医療的ケア児とその親の介護負担の問題がクローズアップされ、本年「医療的ケア児支援法」が成立したところです。CSHCNは医療的ケア児より幅広い概念ですが、こうした子どもたち自身や家族の介護負担に対する心理社会的な支援の拡充の必要性が望まれます。
本研究は、文部科学省科学研究費補助金、厚生労働科学研究費補助金などの補助を得て行われました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/10/13)
世界初・医師主導治験によって、リツキシマブが全身性強皮症に対する薬事承認を取得
東京大学医学部附属病院皮膚科の佐藤伸一教授、吉崎歩講師、江畑慧助教らの研究グループによる研究成果に基づいて、全身性強皮症(以下、強皮症)に対する新たな治療薬が厚生労働省より薬事承認されました。
強皮症は、全身に線維化病変を来す、膠原病に属する自己免疫疾患の一つです。病気の原因は不明ですが、佐藤伸一教授らは長年の研究によってB細胞が病態形成に重要な役割を果たしていることを見いだしていました。そして2017年11月から2019年11月にかけて行われた、多施設共同プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験によって、B細胞を除去する薬剤であるリツキシマブの強皮症に対する有効性が証明されました[Ebata S, Yoshizaki A, Sato S, et al. Lancet Rheum 3:e489-97,2021]。本治験は吉崎歩講師を治験調整医師・責任医師とする医師主導治験として実施されました。この結果をもとに、リツキシマブの製造販売元である全薬工業株式会社より医薬品の規制当局である厚生労働省へ承認申請がなされ、強皮症に対する新たな治療薬として、厚生労働省より2021年9月27日に承認され、保険適用されることとなりました。今回の承認は、公知申請以外で強皮症そのものに対する治療薬が承認を受けた、初めての事例となります。同時にこれは、新たな治療選択肢を難病である強皮症患者さんへ提示出来るようになったことを意味しています。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/10/12)
東京大学卓越教授の称号授与の決定
本研究科 宮園 浩平 教授に対して「卓越教授」の称号が授与されました。
宮園 浩平(みやぞの こうへい)大学院医学系研究科 教授
腫瘍生物学。がんの進展に密接に関与する生理活性タンパク質であるβ型腫瘍増殖因子(TGF-β)や骨形成因子(BMP)の信号伝達の研究を行い、この分野の創始期からの発展につながった。
また、がん研究の分野だけでなく循環器病学や骨・軟骨代謝など幅広い分野にも貢献した。
紫綬褒章、藤原賞、日本学士院賞等を受賞している。2017年より日本学士院会員。
卓越教授の称号は、本学現役教授のうち、専門分野において特に優れた業績を挙げ先導的な役割を果たしている者で、
①ノーベル賞の受賞者又は文化勲章の受章者
②ノーベル賞・文化勲章に準ずる賞の受賞又は業績を有する者として部局長が推薦した者
に対して付与することができることとしております。
(2021/10/1)
ドーパミン異常と学習・記憶の関係を表す計算モデルの開発に成功
~ 精神疾患・運動障害の原因解明に期待 ~
ドーパミンの情報伝達は、動物の学習・記憶に重要であると同時に、その異常は統合失調症をはじめとする様々な精神疾患や運動障害の原因となります。しかし、ドーパミンの情報伝達は非常に複雑で様々な要因が関わっているため、総合的理解は難しく、ドーパミンの情報伝達を説明できる計算モデルの開発が進んでいます。今回、自然科学研究機構・生理学研究所の浦久保秀俊特任助教および窪田芳之准教授らの研究グループは、ドーパミンの情報伝達におけるアクセルとブレーキのバランスの崩れが、学習・記憶に異常をもたらすことを計算モデルを用いて示しました。本研究は、東京大学大学院医学系研究科の河西春郎教授(東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構主任研究者)および柳下祥講師、京都大学大学院・情報学研究科の石井信教授(同 連携研究者)との共同研究であり、成果はPLoS Computational Biology誌(日本時間2021年10月1日午前3時解禁)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/10/1)
脳を参考としてヒトのような汎用人工知能を開発する方法論を標準化
人間の認知機能を脳全体の神経回路を参照しながら再現するソフトウェアの構築は、認知科学や神経科学などの人間科学や、人工知能やロボット工学などの工学的応用において高い価値があると考えられています。しかし、そうしたソフトウェアの設計基盤となる神経科学の知識は膨大かつ複雑であるため、特定の個人の能力によって設計することは困難です。さらに、脳科学の知見を認知機能に適切に反映させるためには、それに必要な解剖学的記述粒度を適切に揃える必要があります。東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻において、山川宏客員研究員は、そうしたソフトウェアを実装する際の仕様情報となる脳参照アーキテクチャ(BRA)データ形式と、それを用いた開発方法論を標準化しました。この方法論では、解剖学的構造を記述する粒度のガイドラインを示し、その構造記述に従って設計された計算機能の仮説をデータとして蓄積・共有するための方法論を提示しました。この方法論によってBRA形式のデータを蓄積・共有が進展すれば、脳型ソフトウェアの開発と活用が促進されると期待できます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/9/28)
クライオ電子顕微鏡により人工設計タンパク質ナノ粒子TIP60の立体構造を解明
~ さまざまな応用が期待される多孔性中空ナノ粒子構造 ~
信州大学繊維学部・バイオメディカル研究所の新井亮一准教授、慶應義塾大学理工学部の川上了史専任講師、宮本憲二教授、東京大学大学院医学系研究科の吉川雅英教授らの共同研究グループは、人工的に設計されたタンパク質ナノ粒子TIP60の詳細な立体構造をクライオ電子顕微鏡単粒子解析により解明することに成功しました。TIP60は、正三角形状の孔を20個持つ特徴的な正二十面体型60量体の多孔性中空ナノ粒子構造であることが明らかとなりました。今後、この特徴的な立体構造をもとにして部位特異的変異や化学修飾などにより、薬物を導入したナノカプセルとしての利用や新たなナノ材料の開発など、ナノバイオテクノロジー分野の発展や応用につながることが期待されます。
本研究成果は英国王立化学会学術雑誌Chemical Communicationsへの掲載に先立ち、同誌Webサイトにてオンライン速報版が9月4日に公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/9/16)
脳梗塞に対するAIMの新しい治療効果の発見
脳梗塞では、虚血による最初の脳神経細胞壊死に続く持続性の無菌性炎症の波及が脳の傷害を拡大し、脳梗塞患者の予後に大きく関与することが近年知られている。しかし、脳梗塞の治療法としては、超早期の血栓溶解療法を除くと、脳圧の低下を目的としたデキストランや濃グリセリン溶液の補液等の対症療法しかなく、前述の無菌性炎症を標的としたものを含め、効果的な治療法はほとんどない。
今回、東京大学大学院医学系研究科の宮﨑徹教授らのグループは、脳梗塞を発症させたマウスを用いた研究により、①脳梗塞発症に伴い、脳内のミクログリアや浸潤したマクロファージによってAIMが産生されること、そしてこれは、ヒトの脳梗塞患者の脳内でも同様であること、②AIMは、壊死した脳神経細胞や、無菌性炎症の原因となる、死細胞から放出されたDAMPsに結合し、マクロファージによるこれらの除去を亢進させること、③さらに一部のDAMPsはAIMの結合により炎症惹起能力が抑制(中和)されること、④こうした効果により、AIMは脳内での無菌性炎症を抑制し、脳梗塞後の生存率や神経症状を有意に改善させること、⑤梗塞後1日1回組換えAIMタンパク質を経静脈的に投与すると、梗塞後の予後を有意に改善させること、を明らかにした。
これらの発見により、AIMが、今まで効果的な治療法がほぼなかった脳梗塞に対する新しい治療法となりえることが期待され、今後も患者数が増加することが予測される脳梗塞による医療財政への負担を軽減させ得る可能性もあり、その社会的インパクトは大きいと考えられる。
なお、本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構革新的先端研究開発支援事業 インキュベートタイプ(LEAP)の一環として行われた。本研究成果は、2021年9月14日(米国東部時間)に「Cell Reports」オンライン版で公開された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/9/15)
クライオ電子顕微鏡によるヒト由来カルシウムポンプの構造決定
~ カルシウムポンプに必要なエネルギ―供給源ATPの新たな取り込み機構の解明 ~
細胞小器官の一つである小胞体は、カルシウムを取り込むことで細胞内カルシウムイオン濃度を適切に維持しています。SERCA2bは筋収縮の制御、神経伝達、アポトーシスの誘導、タンパク質の品質管理など、様々な生命現象において重要な役割をもつ細胞内カルシウムイオンの恒常性を保つ上で必須の小胞体膜局在カルシウムポンプですが、一部の反応中間状態の構造しか決定されていませんでした。
東北大学多元物質科学研究所の張 玉霞助教、渡部 聡助教、門倉 広准教授、稲葉 謙次教授(生命科学研究科、理学研究科化学専攻 兼担)、および東京大学大学院医学系研究科の包 明久助教、吉川 雅英教授らを中心とした共同研究グループは、SERCA2bの高分解能構造を、クライオ電子顕微鏡単粒子解析という技術を用いて決定しました。その結果、カルシウムポンプを駆動するのに必要なエネルギーの供給源であるATP分子をSERCA2bが取り込むための新たな機構を発見しました。
本研究成果は、2021年8月30日に欧州生命科学誌The EMBO Journalに掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/9/9)
B型肝炎ウイルスによる肝発癌機構を新たに同定
B型肝炎ウイルス(HBV)は、全世界で2億5千万人以上が持続感染し、HBV関連疾患により毎年約82万人が死亡しており、その克服は日本のみならず世界的な重要課題です。特に、死亡原因の多くを占めるのが肝癌ですが、既存のHBV治療薬では発癌をゼロにすることはできず、また そもそもの発癌機構も十分には解明されていませんでした。
そうした中、ウイルス蛋白HBxは宿主蛋白Smc5/6を分解することでウイルス複製を促進するという報告がなされました。本来、宿主蛋白Smc5/6は宿主DNAダメージ修復機構に重要な蛋白質であることから、東京大学医学部附属病院 消化器内科の關場一磨 特任臨床医(研究当時)、大塚基之 講師、小池和彦 教授(研究当時)らの研究グループは、「HBVが産生するウイルス蛋白HBxは宿主蛋白Smc5/6を分解することで、ウイルス複製を促進するだけでなく、宿主DNAダメージの修復阻害にも働いているのではないか」と考え検証を行いました。
実際に、ヒト検体やマウスモデル、HBx過剰発現細胞などを用いた検討で、宿主蛋白Smc5/6がウイルス蛋白HBxにより分解されると、宿主DNAダメージ修復能も低下することが分かりました。一般的にDNAダメージの蓄積は主要な発癌促進因子であり、研究グループの検証でも宿主蛋白Smc5/6が分解されている細胞で腫瘍形成能の亢進を認めました。さらに、ウイルス蛋白HBxの働きを抑制する化合物ニタゾキサニドをHBV感染細胞に投与すると、宿主蛋白Smc5/6の分解が阻害され、宿主DNAダメージ修復能が回復することが分かりました。
以上より、本研究は今まで明らかとなっていなかったHBV関連肝発癌の機序の一端を解明するとともに、「Smc5/6分解阻害薬による発癌抑止」という発癌予防の新たなコンセプトを提唱するものとなりました。本研究成果は、9月1日にJournal of Hepatology(オンライン版)にて発表されました。
なお、本研究は日本医療研究開発機構(AMED)肝炎等克服実用化研究事業の肝炎等克服緊急対策研究事業(研究開発課題名「近接依存性標識法を用いた HBV cccDNA維持に関わる宿主因子の網羅的同定と制御」研究代表者:關場一磨、「B型肝炎ウイルスRNAと相互作用する宿主因子の網羅的同定とその制御による病態制御法開発」・「慢性炎症を背景とした肝発癌の機序解明と肝癌高危険群の囲い込み法の開発」研究代表者:大塚基之)とB型肝炎創薬実用化等研究事業(研究開発課題名「新規メカニズムに基づくB型肝炎治療薬の探索」研究代表者:森屋恭爾)、および文部科学省科学研究費補助金などの支援により行われました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/9/1)
多くの施設で集めた複数疾患の脳画像ビッグデータを一般公開
~ 共通の脳回路マーカー開発促進で様々な精神疾患の診断・治療に貢献 ~
笠井清登教授(東京大学大学院医学系研究科/東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN))、田中沙織室長(ATR脳情報通信総合研究所 認知機構研究所 数理知能研究室)らの研究グループは、多施設で集めた複数精神疾患の数千人規模の脳画像データをオンライン上で一般公開しました。
近年、人工知能技術の発展と、ビッグデータ収集の環境整備により、様々な分野で人工知能が活躍しています。医療分野でも、脳のfMRI 画像に人工知能技術を適用することで、疾患の診断に役立てる試みが盛んになっています。一方で、この技術が実用化されるには、確かな再現性が不可欠になります。例えば単一施設で撮像された数十人程度のfMRI データに人工知能技術を適用して得られた結果は、他の施設では再現できません。さらに、異なる施設で集めたデータには、撮像方法や機種など施設による違いが含まれており、単に公開データを大量に集めて解析するだけでは、施設の影響のみを除くことができません。これらの問題を解決するには多施設において共通の撮像方法で複数疾患の患者から集めたビッグデータと、さらに一人の被験者が多施設で撮像したデータ(旅行被験者データ)が必要となります。しかし現状、これらを満たすfMRI 公開データセットは整備されていませんでした。
本研究では世界に先駆けて、多施設にて統一の撮像プロトコルで撮像した複数精神疾患のfMRI データ(データベース全体で14施設2414撮像、公開はそのうち最大1627撮像)および、旅行被験者データ(9名の被験者が12施設で合計143撮像)を合わせてデータベース化しオンライン上で公開しました。一般公開にあたり、同意を得ている被験者のデータのみを公開しています。さらに、脳画像からは顔の部分を削除するなど、個人情報保護に細心の注意を払い厳密に管理しています。また多くの研究者に広く使ってもらえるように、脳の領域間の活動の同期の強さを表す指標に処理したデータセット、画像データセットと、必要性と用途に応じて使用できる複数のデータセットを用意しました。
本成果は、多施設共通で使える精神疾患の脳回路マーカーの開発等に使用可能な公開データセットとして、精神疾患と発達障害の診断及び治療に貢献することが期待されます。
この研究成果は、8月30日の午前10時(英国時間)にScientific Data誌(Nature Springer)・オンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/8/31)
本邦における2型糖尿病患者に対して最初に投与される糖尿病薬に関する実態調査
~ 大規模データベースNDBを用いた解析 ~
国立研究開発法人 国立国際医療研究センターは、横浜市立大学、東京大学、虎の門病院の協力のもと、2型糖尿病患者に対して最初に投与される糖尿病薬についての全国規模の実態調査を実施しました。本研究により、DPP-4阻害薬が選択された患者が最も多く、ビグアナイド(BG)薬、SGLT2阻害薬がそれに続くこと、薬剤開始後1年間の総医療費はBG薬で治療を開始した患者で最も安いこと、DPP-4阻害薬およびBG薬の選択には一定の地域差、施設差があることが明らかとなりました。適正な糖尿病治療実現に向けての重要な基礎データとなると考えられます。本研究成果は、2021年8月23日(月)14時(JST)に国際科学誌「Journal of Diabetes Investigation」(オンライン)に掲 載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/8/24)
近年のオリンピック開催国では、開催前後で国民のスポーツ実践率に変化はなかった
~ 行動につなげる戦略的な取組みが必要 ~
オリンピックの開催・招致にあたっては、国民全体の身体活動とスポーツを促進し、健康増進に寄与するとともに、スポーツ、教育、都市、環境面等でのレガシー実現が期待されています。レガシーとは遺産とも訳される英語の「legacy」のことであり、オリンピックにおいては、その開催を契機に社会に生み出される持続的な影響のことを意味します。スポーツ、社会、環境、都市、経済など、様々な分野が含まれます。
東京大学大学院医学系研究科の鎌田真光講師は、シドニー大学のエイドリアン・ボウマン教授を中心とする国際共同研究グループの一員として、過去のオリンピックが開催国における国民のスポーツ実践や身体活動に与えた影響を検証しました。その結果、近年の大会では、国民や開催都市住民のスポーツ実践や身体活動の促進が、期待されるレガシーとして公式文書等で明言されるようになったものの、ほとんどの国もしくは都市において、オリンピックの開催前後で国民・住民のスポーツ実践率や身体活動量に変化がなかったことが明らかとなりました。人々のインターネット検索の傾向からは、国民の運動に対する「関心」については高まった可能性が示されており、今後は、意識だけでなく、国民のスポーツ実践や身体活動の普及といった「行動」の変容につなげるためのより戦略的な取り組みが必要と考えられます。
この研究成果は、英国の医学誌であるThe Lancet誌が、2012年ロンドン・オリンピックを契機にオリンピック開催年に発刊している身体活動特集号(Physical Activity Series)の掲載論文として発表されました。今回はThe Lancet誌で3回目の特集号発刊であり、オリンピックと直接関連する内容を扱う論文が特集号に掲載されるのは初めてとなります。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/7/26)
妊婦の不安 長期化するコロナ禍で変化
~ 気分障害、周囲からのサポートに関する支援が必要 ~
妊娠中の女性のメンタルヘルスの悪化は、胎児の発育や産後の育児に負の影響を与えることが知られており、予防と支援の重要性が指摘されている。しかし、コロナ禍の妊婦が、どの時期にどのような内容の不安やストレスを抱えていたのかについては分かっていなかった。
東京大学大学院医学系研究科の奥原剛准教授、調律子大学院生らの研究グループは、2020年1月1日~5月25日(第1回緊急事態宣言の解除が宣言された日)に日本最大のQ&AサイトであるYahoo!知恵袋に投稿された妊婦の質問1,000件の内容を週単位で分析し、妊婦の不安・ストレスの内容の移り変わりを国内の動きと照合した。その結果、妊婦は流行初期には感染についての不安を抱えていた一方、自粛期間が長期化するにつれて気分障害、周囲からのサポートについての不安が増えていったことが明らかになった。パンデミックが長期化し感染のフェーズが変化する中で、妊婦への支援内容も変化させていくことの重要性が示唆された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/7/16)
組織透明化手法と細胞周期観察蛍光プローブFucciを組み合わせ、がん転移並びに抗がん剤耐性メカニズムの解明に有用なイメージング手法を確立
組織透明化手法は神経研究分野で開発・応用がなされてきた手法ですが、近年がんの基礎研究でも応用される例が増えてきています。東京大学大学院医学系研究科 宮園浩平教授、高橋恵生助教(研究当時)、久保田晋平研究員(研究当時)のグループは、同研究科の上田泰己教授らのグループとともに、組織透明化手法CUBICのがん研究でのさまざま応用例を2017年に報告しました。本手法により、さまざまなマウスモデルでのがん転移を臓器のまま、1細胞解像度を有して3次元で観察できることがわかっています。本研究グループはこれまではがん転移そのものを捉えることに注力してきましたが、今回新たに細胞周期を観察する蛍光プローブFucciを組み合わせることで、がん転移の形や大きさのみならず、細胞周期のどこにあるかについても、高解像度かつ3次元で臓器のまま観察する系を立ち上げました。さまざまなマウスモデルでのがん転移を観察した結果、臓器間のみならず臓器内の原発巣や転移巣の間でも細胞周期パターンに違いがあることを見出しました。また、これらの手法を用いて抗がん剤の効果を観察した結果、抗がん剤の投与によりがん転移巣が特定の細胞周期で止まることが観察されました。本手法はがん転移の臓器指向性や抗がん剤耐性のメカニズム解析に活用されることが期待されます。
本研究は日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(19K16604, 20K16212, 15H05774, 20H00513)、文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御」(17H06326)などの支援を受けて行われました。本研究成果は「Cancer Science」オンライン版(7月8日付)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/7/8)
脳の全細胞を解析するクラウドシステムの開発
~ 日本発の全脳全細胞データ解析プラットフォーム ~
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター合成生物学研究チームの真野智之研修生(研究当時)、山田陸裕上級研究員、上田泰己チームリーダー、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学教室の史蕭逸助教らの共同研究グループは、全脳全細胞解析を可能にするプラットフォームであるクラウドシステム「CUBIC-Cloud」を開発しました。
本研究成果は、脳全体の遺伝子の働きやネットワーク構造などの膨大な3次元データをクラウド上で保管・解析し、データ駆動型の神経科学を推進するための基盤技術として、神経科学の発展に大きく貢献するものと期待できます。
CUBIC-Cloud は、組織透明化技術であるCUBICで得られた全脳全細胞データを取り込み、複数の脳画像の位置合わせ (レジストレーション) 、定量解析、可視化といった機能をグラフィカルユーザーインターフェースとともに提供します。全ての計算はクラウドで実行されるため、強力な計算機環境を持たない研究者でも使用可能です。また、CUBIC-Cloud で実行した解析結果はクラウドを通じて世界の研究者に共有・公開することができ、将来的には多数の全脳データを用いたデータマイニングの可能性を提供しています。
本研究は、科学雑誌『Cell Reports Methods』(6月21日付:日本時間6月22日)に掲載されました。またCUBIC-Cloud の利用にあたっては、https://cubic-cloud.com でユーザー登録を受け付けています。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/6/22)
上部尿路上皮がんの分子分類と新規分子診断
~ 尿中遺伝子変異の検出で高精度の診断が可能 ~
上部尿路上皮がんは腎盂や尿管の尿路上皮に発生する予後不良ながんであり、その希少さから遺伝学的な背景が十分に解明されていませんでした。また、上部尿路上皮がんは診断が困難なため治療の遅れにつながることがあり、新たな診断方法の開発が待たれていました。
この度、京都大学大学院医学研究科・腫瘍生物学講座 小川誠司 教授(兼:京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)主任研究者)、藤井陽一 同研究員(兼:同所属研究者)、東京大学大学院医学系研究科・泌尿器外科学分野 久米春喜 教授、および東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター 宮野悟 教授 (研究当時、現:東京医科歯科大学M&Dデータ科学 センター長)らを中心とする研究チームは、上部尿路上皮がんの腫瘍検体及び術前に採取した尿を用いて大規模なゲノム解析を行い、
(1) 上部尿路上皮がんは遺伝子変異に基づき、異なる生存率を示す5つの分子病型に分類できること、
(2) 術前の尿中にはがん組織と同一の遺伝子異常が認められ、上部尿路上皮がんの精度の高い診断が可能となること、を証明しました。
今回の研究結果により、上部尿路上皮がんの各病型のゲノム異常に基づく治療選択や、尿を用いた簡便かつ精度の高い診断が可能となり、治療成績の向上が期待されます。本研究成果は、米国の国際学術誌『Cancer Cell』にオンライン掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/6/16)
オートファジーが一次繊毛形成を促進するメカニズム
繊毛は、細胞表面から突出した細胞小器官で原生動物からヒトに至るまで真核生物に広く保存された細胞小器官です。そのうち一次繊毛は非運動性で、細胞外の環境を感知して細胞内に伝えるアンテナとして働き、胚発生、細胞分化、臓器形成などにおいて重要です。一次繊毛が形成されるときには、細胞内のダイナミックな変化を伴いますが、その詳細な仕組みは解明されていませんでした。今回、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、マクロオートファジー(以後、オートファジー)が一次繊毛の形成を促進していることを明らかにしました。
オートファジーとは、オートファゴソームが細胞質の一部を取り囲み、リソソーム(多種類の分解酵素を含む細胞小器官)と融合することで中身を分解する細胞内分解システムです。今回同グループは、オートファゴソームに結合するたんぱく質を網羅的に検索して、繊毛機能に関連することが示唆されていたNEK9を同定しました。さらに、NEK9は、一次繊毛形成の抑制因子であるMYH9と結合して、MYH9をオートファジー分解に導くアダプターとして機能することを見いだしました。NEK9がオートファゴソームに結合できないようにした細胞を作製したところ、MYH9は分解されず、一次繊毛の形成が顕著に抑制されました。また、同様の変異を導入したマウスでは、腎臓の近位尿細管細胞の一次繊毛形成が阻害され、細胞が腫大しました。以上のことから、NEK9を介したオートファジーによるMYH9の選択的分解は一次繊毛の形成に重要であると考えられました。
オートファジーによる繊毛形成制御は哺乳類などの陸上脊椎動物だけにみられるので、この機構が腎臓の陸上生活への適応に重要であった可能性が考えられます。また、本研究成果は、オートファジーの生理的意義や、繊毛形成の異常を伴う疾患の理解につながると考えられます。
本研究成果は、国際科学誌「Nature Communications」のオンライン版で公開されました。
本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/6/3)
皮膚硬化治療薬として世界初、医師主導治験により全身性強皮症に対するB細胞除去療法の有効性を証明
東京大学医学部附属病院皮膚科の佐藤伸一教授、吉崎歩講師、江畑慧助教らの研究グループは、全身性強皮症(以下、強皮症)に対する多施設共同医師主導治験(治験責任医師・調整医師 吉崎歩講師)を行い、リツキシマブの投与によるB細胞除去療法が強皮症の皮膚硬化に対して有効であることを世界に先駈けて証明しました。
強皮症は線維化病変を来す、膠原病に属する自己免疫疾患で、厚生労働省が定める指定難病に認定されています。線維化病変は皮膚をはじめ内臓を含む全身に生じ、特に肺に発生した線維化病変(肺線維症)は高頻度に生命を脅かします。原因は未だ不明ですが、免疫抑制薬が一定の効果を示すことから、病態には免疫異常が関与していることが予測されていました。今回の治験では、皮膚と肺に生じる線維化病変である皮膚硬化と肺線維症の改善を、それぞれ主要評価項目、副次評価項目とし、免疫を担当するB細胞を除去する薬剤「リツキシマブ」の効果を科学的に調べました。これまで皮膚硬化に対する有効性を証明できた薬剤は存在せず、今回の治験は世界で初めて皮膚硬化に対する薬効を証明したものとなります。
現在、リツキシマブの製造販売元から、PMDAへ承認申請が行われています。承認された後には強皮症に対する新しい治療選択肢が生まれ、福音となることが期待されます。
なお、本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「難治性疾患実用化研究事業」の支援と、リツキシマブの製造販売元である全薬工業株式会社の支援(治験費用の一部と治験薬の無償供与)を受け、東京大学医学部附属病院治験審査委員会の承認のもと実施されました。本治験の結果は、膠原病分野を代表する雑誌の一つである英国誌The Lancet Rheumatology誌(オンライン版:日本時間5月27日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/5/27)
肉眼では分かりにくい脳腫瘍に即時に「色をつける」局所投与型の手術用新規蛍光プローブの開発
東京大学大学院医学系研究科脳神経外科学の田中將太講師、北川陽介大学院生(研究当時)、齊藤延人教授および同大学院薬学系研究科薬品代謝化学・医学系研究科生体情報学の浦野泰照教授らの研究グループは、腫瘍細胞における酵素活性を利用する仕組みを応用することで手術中に脳腫瘍を蛍光標識できる(蛍光を発することで識別しやすくする)、局所投与型の蛍光プローブを開発しました。
脳腫瘍で最も多く見られる神経膠腫の治療では、手術によって腫瘍を摘出する際の取り残しをできる限り無くすことが極めて重要ですが、染み込むように発育する腫瘍のため肉眼では非腫瘍部分との判別が難しく、脳を闇雲に大きく取り除くこともできません。患者さんの術後の状態を悪くせずに腫瘍を最大限摘出するために、術中に蛍光プローブによる腫瘍の可視化することが有効です。現在、5-アミノレブリン酸(5-ALA)が唯一保険収載されている薬剤として使用されていますが、蛍光を示すまでに時間がかかるため術前内服が必要であり、手術終盤で蛍光が弱まりがちであるといった難点があります。そこで、開発済みであったHydroxymethyl Rhodamine Green (HMRG)を蛍光母核とした300種類以上のアミノペプチダーゼ型蛍光プローブライブラリーを用いて、がん部位イメージング法を応用した新しい蛍光プローブPR-HMRGを開発しました(国際特許出願済)。手術中いつでもその場で腫瘍に「色をつける」ことが可能となり、肉眼では判別困難な腫瘍を容易に認識できるため摘出度が向上し、神経膠腫治療の成績が改善することが期待されます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「橋渡し研究戦略的推進プログラム」(東京大学拠点、シーズA)「革新的がん医療実用化研究事業」、および文部科学省科学研究費助成事業「若手研究(B)」「基盤研究(C)」(15K19952、20K09365)の支援により行われ、日本時間5月24日に「Clinical Cancer Research, a journal of the American Association for Cancer Research」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/5/24)
分子生物学分野 水島昇教授が紫綬褒章を受章
このたび、医学部・大学院医学系研究科 分子細胞生物学専攻 分子生物学分野 水島昇教授が、2021年4月28日の褒章発令において、紫綬褒章を受章されました。
水島教授は、永年にわたって細胞生物学・生化学の教育と研究に従事され、斯学の発展に多大な貢献をしたことが評価されました。オートファジーの研究領域を細胞生物学から生理学・病態生理学へと発展させ、細胞が自分自身を大規模に分解するメカニズムとその生体内での役割の理解に大きく貢献しました。
水島教授の今回のご受章は、基礎学術への国際的な貢献と、分野をまたぐ複数の学術界への貢献を高く評価されたものです。研究の詳細については、水島研究室の下記ホームページをごらんください。
水島研究室HP:https://molbiolut.jp/
(2021/5/21)
ピロリ菌は遺伝性乳癌・卵巣癌と共通の機序で胃癌を引き起こす
~ 細菌癌蛋白質CagAによる癌抑制分子BRCA1の不活化 ~
ピロリ菌の胃への感染は胃癌発症の最大のリスク因子です。ピロリ菌から産出されるCagA蛋白質は胃上皮細胞に侵入後、胃上皮細胞内の蛋白質と結合することで癌化を促す細胞増殖などのシグナル伝達に異常をきたすことが知られていましたが、最終的にCagA非依存的な胃癌細胞が生み出される機構は不明でした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の畠山昌則教授、紙谷尚子講師らのグループは、同研究科石川俊平教授、牛久哲男教授らとの共同研究を通して、ピロリ菌CagAがゲノム安定性を司るBRCA1の機能を障害することで、胃上皮細胞の癌化に必要な遺伝子変異の蓄積を誘発することを明らかにしました。
BRCA1を作り出すBRCA1遺伝子はその不活化変異が遺伝性乳癌・卵巣癌を引き起こす癌抑制遺伝子であり、自らのBRCA1遺伝子が不活化変異を有していることを知った米国の有名女優が予防的な両側乳房・両側卵巣切除手術を行ったことで世界的にも大きな話題となりました。本研究は、ピロリ菌感染胃癌と遺伝性乳癌・卵巣癌との間に共通する発癌機構の存在を示したもので、これらの癌に応用できる革新的な予防法・治療法の確立に繋がることが期待されます。
本研究成果は、国際雑誌「Cell Host & Microbe」電子版(米国東部標準時間5月13日付)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/5/17)
新規ミオスタチン阻害薬である1価FSTL3-Fcの開発
~ 先行製剤の問題点を改善して骨格筋肥大や代謝改善の効果に期待 ~
これまで、ミオスタチンの機能を抑制することで骨格筋の肥大や筋力の増大を目指す、ミオスタチン阻害薬の開発が活発に行われてきました。臨床試験まで進み、実際の患者さんで骨格筋肥大効果が評価された製剤もありますが、効果が不十分であったり、副作用が明らかになったりしたため開発が中断され、現在までのところ臨床応用された製剤はありません。
今回、東京大学大学院医学系研究科の森川真大助教、小澤崇之博士課程大学院生(研究当時)、宮園浩平教授らの研究グループは、東京薬科大学生命科学部の伊東史子准教授、スウェーデン王立工科大学のPer-Åke Nygren(ペールオーケ・ニグレン)教授との国際共同研究で、新規ミオスタチン阻害薬として1価Follistatin-Like-3(FSTL3)-Fcを開発しました。研究グループは、標的と考えられる因子を過不足なく阻害しうる点からFSTL3に注目し、タンパク質工学の手法を活用して血中安定性を改善しました。さらに、マウスにおいて先行製剤と同等の骨格筋肥大効果があり、逆に先行製剤で問題となった副作用を認めないことを明らかにしました。有効でかつ副作用の可能性の低いミオスタチン阻害薬は、進行したがんで見られる悪液質や高齢社会で今後大きな問題となるサルコペニアなどの骨格筋萎縮や神経筋疾患の治療薬として有望と考えられます。また骨格筋の持つ代謝機能を改善することで、肥満や2型糖尿病の治療につながることも期待されます。
本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(15H05774、19K07683)、文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御」(17H06326)などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/5/17)
深層学習技術を応用した手術検討ソフトウェアでクラスⅡの医療機器の認証を取得
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が展開する「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業」における「術前と術中をつなぐスマート手術ガイドソフトウェアの開発」プロジェクトの支援を受けて、世界初となる手術計画の検討に特化したソフトウェア「GRID」(グリッド)を開発し、医療機器(クラスⅡ)の認証を取得しました。「GRID」は病気を診断することが目的ではなく、手術計画を検討することに特化し、深層学習技術などの画像処理技術を駆使して開発された世界初の手術検討ソフトウェアです。「GRID」には手術シミュレーションを効率よく検討するための多数の機能(自動位置合わせ機能、自動セグメンテーション機能などの自動処理や、組織の部分移動や削除機能などのバーチャルリアリティ操作)が搭載されています。「GRID」の使用によって、これまで医師の負担となっていた手術計画時の読影作業や医用画像処理の手間を大幅に効率化することが可能であり、手術計画の精度向上や、外科手術の安全性および技術向上などに資することが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/5/10)
長鎖シークエンサーを用いた日本人の遺伝的多様性と癌の体細胞変異の包括的解析
近年の次世代シークエンサーに代表される塩基配列決定技術の発展により、がんや遺伝性疾患の原因変異の探索が行われている。しかし、逆位や転座などの構造異常の検出は困難であり、ヒトの構造異常の全体像は未だ解明されていない。東京大学大学院医学系研究科の藤本明洋教授らは、長鎖シークエンサー(Oxford Nanopore)のデータから構造異常を検出する手法(CAMPHORソフトウエア)を開発した。それを用いて、日本人の遺伝的多様性(遺伝的な個人差)とがんの体細胞変異を対象とし構造異常を検出したところ、遺伝的多様性における挿入・欠失の特徴に関しては挿入の9割はトランスポゾン由来である一方、欠失にはそのような特徴がないことが明らかになった。さらに構造異常の切断点の詳細な解析から、構造異常の原因を推定した結果、短鎖次世代シークエンサーを用いた先行研究では検出されていない非相同組み替えにより生じた構造異常が発見された。
本研究で開発した手法は、遺伝性疾患の原因遺伝子探索やがんの変異解析に貢献すると考えられる。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/5/6)
免疫の個人差をつかさどる遺伝子多型の機能カタログを作成
~ 多様な免疫細胞ごとの違いと疾患による修飾が明らかに ~
免疫が病態に関わる疾患は自己免疫疾患や自己炎症性疾患など多様にあり、その多くは発症の原因が不明で、難病に分類されます。これまでゲノムワイド関連解析(GWAS)で疾患の発症と関わる多くの遺伝子多型が同定されてきました。しかし、その多型がどのように疾患発症に関わるかを解明するには、疾患と関わる細胞の遺伝子発現とゲノム配列を組み合わせた大規模なデータベースが必要でした。
この度、東京大学の太田峰人特任助教、藤尾圭志教授、理化学研究所の山本一彦センター長、中外製薬株式会社の角田浩行創薬基盤研究部長らの研究グループは、免疫疾患患者および健常人、計416例の末梢血(血管の中を流れる血液)から分取した28種類の免疫細胞9,852サンプルを解析し、過去の報告を大きく上回る規模の遺伝子発現データベースを構築しました。さらに、ゲノム配列との関連を解析し、これらの免疫細胞における遺伝子多型の機能についてのカタログを作成しました。このデータを既報のGWASデータと組み合わせて解析することで、さまざまな免疫疾患と関連する細胞種や遺伝子を明らかにしました。
今回作成したカタログは、免疫が関連する疾患・形質の原因解明に役立つものと考えられます。また、ゲノム機能のデータベースは、これまで欧米人主体に作成されてきましたが、アジア人とのゲノム構造の違いが課題となっていました。本研究により日本発のカタログを作成したことで、アジア人を対象としたゲノム研究の発展や、欧米人のデータとの統合解析によるゲノム機能の詳細な解明に役立つことが期待されます。
なお本研究は、中外製薬株式会社との共同研究費、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果展開事業 共創の場形成支援(センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業、免疫アレルギー疾患実用化研究事業の支援により行われ、日本時間4月30日に米国科学誌『Cell』(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/4/30)
脳全体に広がる聴覚応答の新たなネットワークを発見
ガンマオシレーションは、神経細胞が発する信号のひとつで、脳の情報処理基盤に関わると考えられてきました。特に、音を聞かせた時にみられる聴覚ガンマオシレーションは、中枢性聴覚疾患や精神疾患において低下していることが知られていましたが、単純な音に対する反応であるため、長年、聞くことに特化した脳部位(側頭葉の聴覚皮質)から発生すると考えられてきました。また、通常の研究で用いられる脳波計では、頭皮上から信号を検出するため、脳内発生源の全容を知ることは困難でした。
東京大学医学部附属病院精神神経科の多田真理子助教、笠井清登教授、脳神経外科の國井尚人助教(特任講師(病院))らの研究グループは、聴覚ガンマオシレーションが認知機能に関わる前頭葉や頭頂葉にまで広がる複雑なネットワークで発生することを明らかにしました。これは、難治性てんかんの手術治療前に、てんかんの発生源を正確に診断する目的で、脳表面に多数の電極を直接設置した患者さんのご協力により実現した研究です。疾患の影響を最小限にするために、てんかん発生源が異なる患者さんの計測データを組み合わせて解析を行いました。突然起こるてんかんの異常脳波を逃さず記録するため、患者さんは入院病棟で電極を留置したまま過ごします。この研究は同大学医学部倫理委員会で審査を受け、病棟で脳波記録中の方のうち、自由意志に基づく研究参加にご協力頂いた方を対象に行いました。
この結果は、統合失調症などの精神疾患で低下している聴覚ガンマオシレーションの発生メカニズムの理解につながり、将来の診断や治療の開発に役立つことが期待されます。
なお、本研究は、革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト「候補回路型・双方向トランスレーショナルリサーチによる脳予測性障害の回路・分子病態解明(領域代表者:小池進介)」による支援を受けて行われ、米国科学誌「Cerebral Cortex」(オンライン版:日本時間4月28日)に掲載されます。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/4/28)
従来の高血圧診断基準より低い血圧値から心不全や心房細動のリスクが上昇
~ 約200万例の国内疫学ビッグデータからの知見 ~
国内に約4300万人の患者が存在する高血圧は、脳卒中や心筋梗塞、狭心症など多くの循環器疾患の発症と関連することが知られています。一般的には、収縮期血圧が140mmHg以上あるいは拡張期血圧が90mmHg以上で高血圧と診断されますが、2017年に米国では、その基準値を引き下げ、収縮期血圧130mmHg以上あるいは拡張期血圧80mmHg以上の場合に高血圧と診断することを推奨しました。
この度、東京大学の小室一成教授、金子英弘特任講師、康永秀生教授、および、横浜市立大学の矢野裕一朗准教授らの研究グループは、心不全や心房細動の発症リスクが、収縮期血圧130mmHg以上あるいは拡張期血圧80mmHg以上という、従来考えられていた血圧値よりも低い段階から上昇する可能性を、200万症例以上が登録された大規模疫学データを用いて明らかにしました。本研究の成果は、心不全や心房細動など循環器疾患の予防を目的とした、最適な血圧コントロール方法の確立に大きく貢献することが期待されます。
本研究は、日本時間4月23日に米国科学誌Circulation(オンライン版:Published Ahead of Print)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/4/23)
眼の水晶体が透明になる仕組みの解明
~ 新たな細胞内分解システムの発見 ~
東京大学大学院医学系研究科の森下英晃助教(研究当時;現・同大学大学院研究科客員研究員/順天堂大学大学院医学研究科 講師)、水島昇教授らの研究グループは、眼の水晶体を透明にする仕組みとして、新たな細胞内分解システムを発見しました。
眼の水晶体の細胞の成熟過程では、核やミトコンドリアなどの細胞小器官が分解されることが100年以上前から知られています。しかし、その仕組みや意義はほとんど解明されていませんでした。一般の細胞では、細胞小器官は主としてオートファジーによって分解されますが、水晶体細胞ではオートファジーによらないことがわかっていました。
今回、本研究グループは、生きたままのゼブラフィッシュの水晶体で、細胞小器官が分解される様子を捉えることに成功しました。さらに、小胞体、ミトコンドリア、リソソームなどの細胞小器官が、サイトゾルに存在する脂質分解酵素(PLAATファミリー酵素)によって分解されることを明らかにしました。この新しい細胞小器官分解システムはマウスの水晶体にも備わっており、ゼブラフィッシュ、マウスのいずれでも水晶体の透明化に必要であることがわかりました。本研究成果は、水晶体細胞の分化のメカニズムを明らかにするとともに、細胞内分解システムの多様性の理解につながると考えられます。
本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)などの支援を受けて行われました。
本研究成果は、2021年4月14日(英国夏時間16時)に科学誌「Nature」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/4/21)
ベタインはキネシン分子モーターの機能低下による統合失調症様の症状を改善する
~ KIF3分子モーターはCRMP2タンパク質を輸送し、ベタインはCRMP2タンパク質のアクチン束化能を改善し神経細胞の形態を整える ~
統合失調症は、一般人口の約100人に1人の割合で発症する頻度の高い精神疾患であり、生涯にわたって生活の質が損なわれる可能性が高い疾患です。現在、統合失調症の治療薬は、薬効が不十分であること、また副作用に悩まされる患者が多くいることから、従来とは作用機序の異なる治療薬の開発が喫緊の課題となっています。統合失調症患者の血液中の代謝産物を網羅的に測定した結果、一部の患者で、健常者と比べてベタインの濃度が低下しているという研究成果が報告されています。そこで、東京大学大学院医学系研究科の廣川信隆特任教授(研究当時)、田中庸介講師、理化学研究所の吉川武男チームリーダー(研究当時)、福島県立医科大学の國井泰人准教授(研究当時)らの共同研究グループは、ベタインを補充することが統合失調症の治療に繋がると考え、モデル動物であるキネシン分子モーターKIF3遺伝子ヘテロ欠損マウスを用いた研究を行いました。本研究成果から、ベタインがこのマウスの統合失調症様の症状を改善するとともに、KIF3の輸送タンパク質であるCRMP2の有害なカルボニル化修飾を軽減することにより、CRMP2の輸送障害における神経細胞の形態異常を改善することで、症状を緩和させていることを明らかにしました。ベタインは既に承認されている薬剤であるため、現在、東京大学医学部附属病院精神神経科にて臨床研究を行っており、今後新規統合失調症治療薬としての承認が期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2021/4/14)
AIを用いた子宮鏡における子宮体癌自動診断システムの開発
子宮体癌は婦人科がんにおいて最も罹患数が多い疾患であり、国内外問わず、近年増加傾向にあります。早期であればホルモン治療によって子宮温存が可能ですが、進行期、再発症例であると難治性の事が多く、早期発見が重要となります。しかしながら、子宮体がん検診に関しては確立されたスクリーニング法が無いのが現状です。子宮鏡検査は腟を経由して子宮内腔をファイバースコープで観察する内視鏡検査であり、子宮体癌や、その前癌病変である子宮内膜増殖症の診断補助に使用することもあります。
このような背景のもと、東京大学の曾根献文講師、高橋優大学院生、大須賀穣教授ら、および、Predicthy合同会社の野田勝彦、吉田要らの研究グループは、子宮体がん検診の重要なデバイスとして子宮鏡検査を一般化することを目的とし、人工知能(AI)を用いた子宮鏡における子宮体癌自動診断システムの開発に成功しました。また通常、深層学習を用いた人工知能を学習させるには、膨大な症例数が必要ですが、本研究グループは、少ない症例数でも良好な正診率が得られる新たなアルゴリズムを開発しました。正常子宮内膜、子宮内膜ポリープなどの良性腫瘍、子宮体癌などの全177症例の子宮鏡画像をそれぞれ悪性グループと非悪性グループに分けて深層学習にて解析したところ、通常のアルゴリズムでは正診率が80%程度であるのに対して、今回独自に開発したアルゴリズムでは正診率が90%以上と少ない症例においても良好な結果が得られました。今後、本研究で開発されたアルゴリズムが子宮体がん検診法の確立に大きく貢献する事が期待されます。
本研究は内視鏡医学研究振興財団研究助成金の支援により行われ、日本時間4月1日に米国科学誌『PLOS ONE』に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2021/4/1)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報