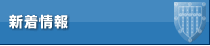広報・プレスリリース最新情報
食塩摂取量が多い食事とは?食べる状況と食品の特徴を解明
東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野の篠崎奈々助教、村上健太郎教授、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、日本人成人2,757人から得られた延べ6万食以上の食事データを用いて、食塩摂取量が多い食事の状況と食品の種類を明らかにしました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/30)
熱中症で死なせないために
エアコンを使いこなせない人を取り残さないように
熱中症は、エアコン(冷房)を使用すれば予防できます。しかし、エアコンを適切に使いこなせず、熱中症を引き起こして死亡する方が少なくありません。家族、コミュニティ、近隣での支えあいや目配りを行うことで、熱中症で亡くなる方を減らすことにつながるよう願い、この度、研究分析結果(中間報告)を発表します。
東京大学大学院医学系研究科の橋本英樹教授、東京都監察医務院の林紀乃院長、浦邉朱鞠監察医の共同研究では、2013-2023年の間に東京都23区において熱中症で亡くなった方々(1,447症例)の分析を行っています。熱中症を防ぐうえでエアコンの適切な使用が必要であるということは、ニュース・メディアでも取り上げられていますが、実際どのような事例があるか、どのような対応ができるのか、発表します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/20)
子宮腺筋症の黄体ホルモン療法の効果予測
~ 病態に応じた個別化治療による子宮腺筋症女性のQOL向上へ ~
東京大学大学院医学系研究科の平塚大輝(医学博士課程)、廣田泰教授、同大学医学部附属病院女性診療科・産科の松尾光徳助教らによる研究グループは、子宮腺筋症患者の子宮内黄体ホルモン放出システムによる治療効果と関連するMRI画像の特徴を解析し、子宮腺筋症の病変の位置や広がり方によって治療効果が異なり、病変が子宮筋層の内側にある場合と比較して、外側にある場合や筋層全層に及んだ場合に治療効果が得られにくいことを明らかにしました。これは、子宮腺筋症の病変の位置や広がり方を評価することによって、黄体ホルモン療法の効果を予測できることを示唆しています。
子宮腺筋症は生殖年齢女性の20~30%に見られ、月経痛、過多月経などの月経随伴症状や不妊症・不育症・妊娠合併症をきたし女性のQOLを著しく損なう良性疾患です。本成果により子宮腺筋症の位置や広がりの評価に基づいて適切な治療法選択ができるようになり、子宮腺筋症女性のQOL向上に繋がるものと期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/6/14)
「睡眠学習」が生じる条件を理論的に予測
~ 特定の神経活動量と学習則がシナプス結合を強化 ~
JST戦略的創造研究推進事業ERATOにおいて、東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田 泰己 教授(理化学研究所 生命機能科学研究センター 合成生物学研究チーム チームリーダー兼任(当時)、久留米大学 特別招聘教授 兼任)、大出 晃士 講師、大阪大学 大学院医学系研究科 博士課程 木下 福章さん(当時)と久留米大学 分子生命科学研究所 山田 陸裕 准教授らは、睡眠時の大脳皮質における神経シナプス結合の強さがシナプス学習則と睡眠時の神経活動量に依存して変化することを示し、「睡眠学習」が生じ得る条件を理論的に予測できることを明らかにしました。
大脳皮質では、多数の神経細胞がシナプスと呼ばれる接合部を介して情報をやり取りしています。各シナプスのつながりの強さは神経細胞の活動状況に応じて変化し、これが学習や記憶の基盤になると考えられています。これらの活動のパターンとシナプスのつながりの変化の関係にはいくつかの決まりがあり、「シナプス学習則」と呼ばれています。睡眠は学習や記憶にとって重要であることが知られていますが、睡眠時にシナプス結合がどのように変化するのかについては解明されていない部分が多く残されていました。
そこで本研究グループは、多くの種類の神経細胞がつながった神経ネットワークの活動をコンピューターシミュレーションにより再現し、覚醒状態や睡眠状態で観察される神経活動が生じている時のシナプス結合の変化を調べました。その結果、特定の神経活動量とシナプス学習則が組み合わさることで、睡眠時に大脳皮質のシナプス結合が強まることが分かりました。これにより、睡眠中でもシナプス結合の強化が起こる条件が明らかとなり、「睡眠学習」が生じ得る条件を予測することが可能になりました。
今後、この予測を基に、睡眠と学習・記憶の関連性についてより深い理解が進むことが期待されます。また、神経精神疾患のような睡眠障害を伴う脳疾患のメカニズム解明にもつながる可能性があります。
本研究成果は、2025年6月12日(現地時間)に米国学術誌「PLOS Biology」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/13)
新たな希少がん分類を策定
~ 実臨床に即した分類の活用により希少がん対策の推進を期待
日本のがん発生の約2割が希少がんに該当する実態も確認 ~
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の力武諒子助教、東尚弘教授は、国立がん研究センター希少がんセンターと共同して、がんが発生する臓器と組織型で希少がんを分類する、新しい希少がん分類「New Classification of Rare Cancers(NCRC)」を策定しました。 また、この希少がん分類で、日本のがん罹患を網羅する全国がん登録データを解析したところ、2016年から2019年に日本で診断されたがんの約2割が希少がんであることが明らかになりました。また、これまで用いられてきた欧州の希少がん分類では含まれなかった希少がんも特定されました。
希少がんは、厚生労働省の希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書(2015年8月)において、「概ね罹患率人口10万人当たり6例未満、数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい」がん種と定義され、分類は欧州で開発されたRARECARE分類を参考とすることになっています。しかし、RARECARE分類は、病気の性質や日本での発生頻度とのずれがあることや最新の分類ではないことなどから、日本の実臨床に即した希少がん分類の開発が必要とされていました。
新たに策定した希少がん分類は、年間発生数が人口10万人あたり6例未満であることを基準に、がんが発生することが少ない臓器31部位のがんと、がんの発生が多い臓器であるが発生が少ない特定の組織型のがん364種を希少がんに分類しました。
どのがんが希少がんかを明確にすることは、希少がんの実態把握や政策の推進に不可欠であり、本希少がん分類の活用により、日本の希少がん対策が進むことが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/10)
膵癌のリスク層別化を実現する新たな視点~脂肪膵とIPMN併存癌~
~ MRIを活用した観察研究 ~
東京大学医学部附属病院 消化器内科の大山博生 助教、浜田毅 助教、藤城光弘 教授らによる研究グループは、脂肪膵を有する患者がIPMN由来癌ではなくIPMN併存癌を発症するリスクが高いことを明らかにしました。
IPMNは膵癌の高リスク群であり、IPMN由来癌とIPMN併存癌が同程度の頻度で発生することが知られています。一方で近年、脂肪膵が膵癌のリスク因子であることが認識されてきています。本研究では330ものIPMN症例について、MRI画像(T1強調画像)を用いて脂肪膵の程度を定量的に測定することで、IPMNの長期経過観察開始当初から脂肪膵を認める場合にIPMN併存癌に罹患しやすく、高度な脂肪膵の患者ほどIPMN併存癌に罹患するリスクが高くなることを世界で初めて報告しました。先行研究と比較して、IPMN由来癌とIPMN併存癌の発生機序の違いに迫る点、脂肪膵と通常型膵癌の発生との因果関係を明確にした点で新規性があり、この研究成果は今後膵癌のリスク層別化や早期発見に役立つことが期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/6/4)
吸入麻酔薬はなぜ効くのか?作用メカニズムの一端を解明
~ 標的分子の1つとして1型リアノジン受容体を特定 ~
JST 戦略的創造研究推進事業 ERATOにおいて、東京大学 大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学分野の上田 泰己 教授(久留米大学 特別招聘教授 兼任)、金谷 啓之 医学博士課程大学院生、桑島 謙 特任研究員(研究当時、現 同大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 助教)、大出 晃士 講師らの研究グループは、カルシウム放出チャネルである1型リアノジン受容体(RyR1)が、吸入麻酔薬の標的分子として全身麻酔の導入に関与していることを見いだしました。
吸入麻酔薬の麻酔作用は約180年前に発見されて以来、外科手術の全身麻酔などに用いられてきましたが、どのようにして麻酔作用を発揮するのかは、いまだ完全に解明されていません。これまでの研究から、吸入麻酔薬が複数のたんぱく質に作用して麻酔効果を発揮することが分かっていましたが、未知の標的分子の存在も示唆されていました。
一方、通常と異なるRyR1を持つ(RyR1の変異)患者は、吸入麻酔薬によってまれに引き起こされることがある悪性高熱症の発症リスクが高いことが知られていましたが、吸入麻酔薬とRyR1との直接的な分子間相互作用は明確に示されておらず、麻酔作用との関連も分かっていませんでした。
本研究グループはまず、イソフルランをはじめとする吸入麻酔薬がRyR1を活性化して小胞体からのカルシウム放出を促すことを確認しました。次に、イソフルランによる活性化に重要なRyR1のアミノ酸残基を特定することに成功し、イソフルランの結合部位を推定しました。また、イソフルランに反応しないRyR1変異体を発現する遺伝子改変マウス(ノックインマウス)を作製してイソフルランを投与したところ、正常なマウスに比べ、部分的に麻酔への感受性が低下することが確認できました。
さらに、化合物スクリーニングによってイソフルランの推定結合部位に作用する新しい化合物を特定することに成功し、その化合物が実際にマウス個体で鎮静作用に近い効果があることを見いだしました。これらの結果は、RyR1がイソフルランの標的分子の1つとして麻酔作用に関与することを示唆しています。
本成果は、全身麻酔に用いられる吸入麻酔薬の分子メカニズムの一端を明らかにするものです。これまでの研究では、哺乳類においてRyR1と麻酔作用の関連は示されておらず、新しい知見となります。麻酔薬が作用する仕組みをより詳細に理解することで、より優れた麻酔薬や投与方法の開発につながる可能性が期待されます。
本研究は、筑波大学 医学医療系の広川 貴次 教授、順天堂大学 医学部の大久保 洋平 准教授、村山 尚 准教授、日本大学 医学部の飯野 正光 上席研究員らと共同で行われました。
本研究成果は、2025年6月3日午後2時(米国東部夏時間)に米国科学誌「PLOS Biology」オンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/6/4)
慢性子宮内膜炎の新たな治療の可能性を発見!
~ 魚に含まれるEPAが妊娠を助ける鍵に ~
不妊や流産を繰り返す原因の一つとされる「慢性子宮内膜炎」。この病気の背景に、脂質代謝の異常が深く関わっていることを、日本医科大学 松田繁 助教、桑原慶充 准教授、東京科学大学 大石由美子 教授、東京大学 村上誠 教授、千葉大学 眞鍋一郎 教授らの共同研究グループが明らかにしました。さらに、魚油に多く含まれるω(オメガ)3系脂肪酸「エイコサペンタエン酸(EPA)」を食事として補うことで、この病気の改善や流産の防止が期待できることも示されました。この研究は、慢性子宮内膜炎に対する新しい治療法を提案するだけでなく、妊娠を考える女性が日常的に取り組める「プレコンセプションケア(妊娠準備のための健康管理)」の重要性を示すものです。研究成果は2025年6月に「Frontiers in Immunology」誌に掲載されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/30)
山本一彦名誉教授が瑞宝中綬章を受章
山本先生は、リウマチ学および臨床免疫学の分野において、ヒトを対象とした研究を長年にわたり推進されてきました。独自の手法による自己抗体の認識エピトープの同定、抗原特異的T細胞による免疫応答の証明に加え、既知の制御性T細胞とは異なる、IL-10産生を特徴とする新たな制御性T細胞サブセットを明らかにされ、自己免疫疾患における免疫応答および免疫制御機構の解明に多大な貢献をなされました。
さらに、ヒトゲノム情報に基づいて疾患感受性遺伝子を評価する手法を確立され、関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患に関連する多数の感受性遺伝子を同定されました。これにより、遺伝的素因の解明にとどまらず、これらの遺伝子が病態形成や治療戦略において果たす重要な役割を明確にされました。中でも、関節リウマチの感受性遺伝子としてPADI4を同定されたことは、抗シトルリン化蛋白抗体という最も特異性の高い自己抗体の標的抗原形成に深く関与する発見であり、特筆すべき成果です。また、ヒト体内の複雑な免疫系の解明を目指して、機能ゲノム学という新たな解析体系を構築され、多くの疾患に関与する免疫経路を明らかにされたことは、今後のヒト免疫学の発展に大きく寄与する業績として高く評価されています。
平成9年から平成29年まで東京大学医学系研究科アレルギー・リウマチ内科教授を務められた後、理化学研究所生命医科学研究センター長として5年間にわたり卓越したリーダーシップを発揮されました。学会活動においても、日本リウマチ学会およびアジア太平洋リウマチ学会連合の理事長を歴任されるなど、国際的にもご活躍されました。
これらの優れた業績に対し、日本リウマチ学会賞、日本チバガイギーリウマチ賞、エルウィン・フォン・ベルツ賞(アレルギー疾患および自己免疫疾患の研究に対して)、日本医師会医学賞、高峰記念第一三共賞、日本免疫学会ヒト免疫研究賞、Carol Nachman Award、欧州リウマチ学会賞、紫綬褒章など、数多くの栄誉ある賞が贈られています。
さらに、これらの一連の研究の中で、山本先生が大学院生の頃よりご指導された多くの後進が、現在では国内有力大学の教授として活躍しており、日本のみならず世界におけるリウマチ学および免疫学の発展に大きく貢献しておられます。
このたびのご受章を心よりお慶び申し上げますとともに、今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
(医学部附属病院 藤尾圭志)
(2025/5/20)
辻省次名誉教授が瑞宝中綬章を受章
令和7年春の叙勲において、本学名誉教授ならびに国際医療福祉大学特任教授の辻省次先生が、長年にわたる学術および医療への顕著なご貢献により、瑞宝中綬章をご受章されました。
先生は、神経内科学およびゲノム医科学の分野において卓越した業績を重ねられ、特に神経難病の病態機序の解明と治療法の開発において、極めて多大なご功績を残してこられました。その研究成果は国際的にも高く評価されており、平成23年には紫綬褒章を受章され,平成27年には世界神経学会より,Medal for Scientific Achievement in Neurology を受賞されています。
神経内科学の対象となる疾患には、治療可能なものもある一方で、有効な治療法が確立していない進行性難病もなお数多く存在します。こうした難治性疾患の原因や病態を明らかにし、治療法を見出すことは、神経内科学における喫緊かつ重要な課題であり、臨床脳神経医学研究の最前線をなすテーマの一つです。
先生は、ゲノム医科学的手法を駆使し、神経難病の病因遺伝子の発見と病態解明を力強く推進され、本分野における世界的な研究リーダーとして、学術の発展に大きく寄与されてきました。これらの先駆的な成果は、神経内科学のみならず、脳神経科学やゲノム医科学を含む広範な医学領域において極めて高く評価されています。
具体的には、歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)、脊髄小脳失調症2型(SCA2)、眼球運動失行と低アルブミン血症を伴う早発型失調症(EAOH)、常染色体劣性脳小血管病(CARASIL)など、数多くの単一遺伝性疾患において、病因遺伝子を世界に先駆けて同定されました。さらに、良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん(BAFME)、神経核内封入体病(NIID)、眼咽頭遠位型ミオパチー(OPDM)などの原因遺伝子も明らかにされ、分子病態の解明においても大きな貢献を果たされました。家族性および孤発性の多系統萎縮症やパーキンソン病において、疾患の原因またはリスクとなるrare variantを同定し、研究領域を切り拓かれました。さらに、多系統萎縮症に対する還元型コエンザイムQ10の臨床治験や、成人期大脳型副腎白質ジストロフィーへの造血幹細胞移植療法の実施など、神経難病に対する革新的な治療法の開発にも尽力されておられます。
このたびの瑞宝中綬章のご受章は、先生の長年にわたる先駆的かつ継続的な研究成果と、臨床医学への献身的なご尽力に対する極めて高い評価の証と存じます。
謹んでお祝い申し上げるとともに、今後ますますのご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(大学院医学系研究科・医学部 佐竹 渉)
(2025/5/20)
高校生が困った時に友人に助けを求めやすいかは、仲間を積極的に助ける学級の雰囲気と関連
東京大学医学部附属病院精神神経科の森島遼届出研究員(兼:帝京平成大学健康メディカル学部心理学科講師)、笠井清登教授(国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)、同大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻教育心理学講座の宇佐美慧准教授らの研究グループは、関東圏の中学生・高校生21,845人のデータを分析し、向社会性(積極的に他者を助ける行動や考え)の高い学級に所属している高校生は友人への援助希求行動(困ったときに他者に助けを求める行動)をとりやすいことを見出し、高校生の援助希求行動が学級の向社会性と関連することを明らかにしました。これまで、思春期の向社会性が援助希求行動と関連するという報告では、それが個人ごとの向社会性にもとづくものか、学級など所属集団の向社会性の影響を受けたものかの検討は行われていませんでした。そこで本研究では、向社会性を学級全体の平均と、各生徒の学級平均からの差(偏差スコア)に分けて検討し、学級全体の向社会性と個人ごとの向社会性のいずれもが援助希求行動と関連することを初めて明らかにしました。本研究の知見から、学校現場における他者と助け合う学級の雰囲気作りが、他者に助けを求めやすい環境作りにつながり、虐めや自殺への対策のひとつとなると期待されます。
なお、本研究は米国医学雑誌「JAMA Network Open」(オンライン版:米国中部夏時間5月15日)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/5/16)
三毛猫の毛色を決める遺伝子をついに発見
~ 60年間の謎だった三毛猫の毛色の仕組みを解明 ~
三毛猫やサビ猫はメスばかりであること、オレンジ/黒の毛色を決める「オレンジ遺伝子」がX染色体上にあることは120年以上前から知られていました。1961年、メスの細胞では一対のX染色体の片方がランダムに選ばれて不活性化されるという仮説が提唱され、三毛猫やサビ猫の模様はこの仮説と合致する例として広く受け入れられてきました。しかし、それから60年以上経った今日まで、オレンジ遺伝子の正体やその働きについては明らかになっていませんでした。
九州大学生体防御医学研究所(研究当時)の佐々木裕之特別主幹教授(現:高等研究院)、同大学大学院歯学研究院の松田美穂准教授、国立遺伝学研究所の藤英博特命准教授、中村保一教授、国際基督教大学の歐陽允健助教、東京大学の鵜木元香准教授、アニコム先進医療研究所株式会社の松本悠貴研究員(麻布大学特任准教授兼任)および、近畿大学農学部の佐渡敬教授らの研究グループは、オレンジ遺伝子の正体が「ARHGAP36」であることを突き止めました。
本研究グループは、福岡市内の様々な毛色を持つ18匹の猫のDNAを解析し、オレンジ毛を持つ猫のX染色体にはARHGAP36遺伝子内に約5,000塩基の欠失があることを見つけました。さらに50匹以上の猫を調べ、海外のデータも参照したところ、この欠失の有無とオレンジ毛の有無が完全に一致していました。この欠失領域には、動物種を超えて高度に保存された配列が含まれ、この配列がARHGAP36の発現を制御している可能性が強く示唆されました。次に、オレンジ毛が生えた皮膚での遺伝子発現を調べたところ、欠失によってARHGAP36の発現が上昇し、その結果としてメラニン合成遺伝子群が抑えられ、黒色のユーメラニンからオレンジ色のフェオメラニンへと合成の切り替えが起きることが示唆されました。さらに、遺伝子の発現を抑制するDNAメチル化の状態を調べたところ、ARHGAP36はX染色体の不活性化に伴って高度にメチル化されることが分かりました。これらの結果から、オレンジ遺伝子の正体はARHGAP36であり、60年前に提唱された通り、この遺伝子の不活性化がオレンジ/黒の斑の形成に関与することが明らかになりました。
本研究成果は、⽶国の雑誌「Current Biology」に2025年5月16日(金)午前0時(日本時間)に掲載されました。なお、同雑誌の同じ号にはStanford大学のGregory Barsh教授らの類似の論文が掲載されており、日米の独立した研究がほぼ同時に同じ結論に到達しました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/16)
抗血小板薬の効果を“見る”時代へ
冠動脈疾患患者において、血栓は重要な役割を果たし、血小板凝集を抑制する抗血小板薬は冠動脈疾患管理に必須の薬剤です。しかし、生体内における血小板凝集の程度を直接評価することは、これまでの検査方法では困難でした。
東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授、東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)検査部の矢冨裕教授(研究当時)・蔵野信教授、同循環器内科の武田憲彦教授らによる共同研究チームは、東大病院に入院し心臓カテーテル検査・治療を受けた冠動脈疾患患者(207名)から採取した血液内の循環血小板凝集塊を、マイクロ流体チップ上で高速流体イメージングにより大規模撮影し、取得した循環血小板凝集塊の画像ビッグデータをAIを使って解析しました。
その結果、冠動脈疾患患者では健常者と比較して血小板凝集が亢進し、特に急性冠症候群で顕著でした。また、血小板凝集塊の出現頻度は抗血小板薬の数が増えるほど低下していました。さらに、冠動脈疾患は動脈の疾患であるにも関わらず、血小板凝集の程度は静脈血と動脈血のいずれの検体においても良好な相関を認めることを発見しました。本研究結果は、冠動脈疾患のスクリーニング及び抗血小板療法の個別化、最適化、非侵襲モニタリングに貢献することが期待されます。
本研究成果は、日本時間2025年5月15日(18時)にNature Communicationsのオンライン版で公開されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/5/16)
時間栄養学の視点からみた食行動
~ 食事の質および肥満との関連 ~
東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、20~69歳の日本人1047人を対象として、時間栄養学からみた食行動を幅広く調査し、食事摂取時刻や頻度といった時間栄養学的食行動と食事の質および肥満との関連は、時間栄養学的行動をどのような方法で調べるかによって大きく異なることを明らかにしました。本研究は、時間栄養学的行動と食事の質および肥満との関連を、異なる二つの調査法(質問票法と日記法)を用いて検討した世界で初めての研究です。本研究の成果は、世界で急速に進む時間栄養学分野において、調査方法を慎重に吟味することの必要性を改めて強調する貴重な科学的根拠となることが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/13)
日本人集団におけるアイソフォームの発現量に影響する遺伝的多様性の同定
東京大学大学院医学系研究科の名倉祐哉大学院生(研究当時)、藤本明洋教授らによる研究グループは、アイソフォームの発現量と関連する遺伝的多様性を明らかにしました。
本研究では、ロングリードシークエンス技術を用いて健康な日本人67人のB細胞のアイソフォームを解析し、アイソフォームに関するeQTL(ieQTL; isoform eQTL)を同定しました。その結果、17,119個のieQTLが発見され、その70.6%は遺伝子レベルの解析では検出されませんでした。ieQTLの特徴を調べたところ、ieQTLはスプライシングに関係している部位や、特定のヒストン修飾(H3K36me3、H3K4me1、H3K4me3、H3K79me2など)に多いことが分かりました。実験的検証により遺伝子から離れた遺伝的多様性がアイソフォームの発現量に影響すること、従来の知見では重要と考えられなかった遺伝的多様性がスプライシングに関与することが確認されました。また、先行研究で発見された疾患リスクに影響する遺伝的多様性との重なりを調べたところ、遺伝子のeQTLと比較して、ieQTLは疾患リスクに関わる遺伝的多様性の数が多いことが明らかになりました。これらの結果は、人類遺伝学研究におけるアイソフォームの解析の重要性を示唆しています。
本研究では、アイソフォームを区別し、発現量に影響する遺伝的多様性(eQTL)を検出し、多くの新規eQTLを同定しました。本研究は新たな疾患関連遺伝子の同定に寄与すると考えられます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/5/9)
呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患の遺伝的背景の多様性を解析
~ 東アジア系集団と欧州系集団では、両疾患が逆方向の遺伝的相関を示す ~
大阪大学大学院医学系研究科の山本悠司さん(博士課程)(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学)、白井雄也 助教(遺伝統計学/呼吸器・免疫内科学)、岡田随象 教授(遺伝統計学/東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームリーダー)、東京大学 大学院医学系研究科の山内敏正 教授、門脇孝 東京大学名誉教授(虎の門病院 院長)らの共同研究グループは、喘息などの3種類の呼吸器・免疫疾患と、関節リウマチ、脂質異常症などの7種類の心血管代謝疾患、およびこれらに関連する特徴や性質を対象に、遺伝的関連を調査しました。
その結果、呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患の遺伝的リスクの関係が東アジア系集団と欧州系集団で異なることを発見しました。また、これらの疾患で遺伝的リスクが逆方向に関連する生物学的パスウェイを発見し、メタボロームやプロテオームなどとの統合解析により、遺伝的リスクとの関連が異なるバイオマーカーを発見しました。
本研究成果によって呼吸器・免疫疾患と心血管代謝疾患を合併するメカニズムの理解が進み、将来的にこれらの疾患の予防や個別化医療へ貢献することが期待されます。
この成果は、2025年4月28日(月)18時(日本時間)に英国科学雑誌Nature Communicationsにオンライン掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/30)
時間栄養学のための簡易評価ツール(Chrono-Nutrition Behavior Questionnaire; CNBQ)
~ 11日間食事日記との比較による妥当性研究 ~
東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏東京大学名誉教授らによる研究グループは、時間栄養に関する幅広い行動を簡易的に評価することを目的とした「Chrono-Nutrition Behavior Questionnaire; CNBQ」が、11日間にわたって収集された食事日記との比較において、十分な妥当性を有することを明らかにしました。CNBQは、時間栄養に着目した研究で必要とされる、さまざまな食行動や睡眠行動を十分な妥当性をもって測定できる、世界初の簡易ツールです。CNBQは、時間栄養に関する大規模な観察研究や介入試験で広く活用され、食に関する政策立案に不可欠である信頼できる科学的根拠の構築に大きく寄与することが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/25)
家庭で心不全を早期発見するAIシステムを開発
~ 心不全重症度の新たな指標を構築 ~
東京大学大学院医学系研究科先進循環器病学の荷見映理子特任研究員、藤生克仁特任教授らの研究グループは、SIMPLEX QUANTUM株式会社と共同で、人工知能(AI)を活用した新しい心不全の早期検出システムを開発しました。
本システムは、単一誘導心電図データのみから、心不全の重症度を高精度(91.6%)で分類できることを実証しました。これにより、従来、植込み型心臓電気デバイス(CIED)に依存していた心不全の在宅モニタリングが、スマートウォッチを含む携帯型心電計で計測できる単一誘導心電図データのみを用いてできるようになり、心不全の進行を早期に検出することが可能になりました。さらに、AIによる独自の「HF(Heart failure)インデックス」を開発し、心不全の重症度を数値化する新たな指標を確立しました。
このようなアプローチによる心不全のリアルタイム評価システムの報告はこれまでになく、心不全管理のより良い医療を提示するものです。本システムの導入により、心不全患者さんは自宅で簡便に病状をモニタリングできるようになるため、再入院のリスク低減や早期の治療介入につながります。さらに、遠隔医療の発展や、心不全管理の効率化や患者さんの生活の質向上にも寄与することが期待されます。本研究成果は、日本時間4月24日に循環器領域の国際的な学術誌 「International Journal of Cardiology」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/25)
肝臓由来のタンパク質「アクチビンB」が糖代謝を制御する新たな仕組みを発見
~ 糖尿病のすべての病態を改善できる治療薬開発への期待 ~
糖尿病は我が国のみならず全世界的に有病者が増加しており、血管合併症のみならずがんや老年症候群の要因ともなることが明らかになってきており、深刻な公衆衛生課題となっています。こうした中、国立健康危機管理研究機構(JIHS)糖尿病研究センターの植木浩二郎センター長および分子糖尿病医学研究部の小林直樹上級研究員らのグループは、東京大学大学院医学系研究科の山内敏正教授、門脇孝東京大学名誉教授やドイツ・ライプツィヒ大学Matthias Blüher教授らとの国際共同研究により、肝臓由来のタンパク質「Activin B」が糖代謝を改善する新たな仕組みを発見しました。Activin Bは、肝臓でFGF21の産生を促進しインスリン感受性を高める一方で、肝臓のグルカゴンに対する反応性(グルカゴン感受性)を低下させることで、血糖を改善するしくみを持つことが明らかになりました。また、肥満に伴いこの作用を阻害するタンパク質であるFSTL3が増加することも示され、糖尿病の新たな治療標的としての可能性が期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/24)
寄付講座設立による臓器移植体制の充実と次世代育成
~ 東大病院内に「次世代臓器移植開発推進講座」を開設 ~
東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)の脳死下臓器移植の受け入れ数は国内最多となっています。一方、増加する国内の脳死ドナーに対応するための人材育成、体制・設備の整備が急務です。そこで、移植を受けられた患者さんが設立した一般社団法人N28からの寄附をもとに「次世代臓器移植開発推進講座」を2025年4月1日に東大病院内に開設しました(協力講座:大学院医学系研究科 呼吸器外科学)。
本講座では、肺移植だけでなく、他臓器の移植や麻酔科、集中治療分野など、臓器移植に関わる多岐にわたる分野で、高度な専門知識と技術を持つ人材を育成します。これにより、これまで海外でしか学べなかった最先端の臓器移植に関する教育を国内で実現し、日本の臓器移植医療の国際的なレベル向上を目指します。また患者管理の効率化を図るための情報管理システムの研究開発を加速させ、より安全で質の高い臓器移植を実現するための基盤を構築します。
また本講座と関連して、臓器移植を優先して実施する高規格手術室の増設や、臓器移植患者を優先して受け入れるICUの増設など、臓器移植に必要な医療環境の整備を計画しています。
本講座の設置は、日本の臓器移植医療における大きな転換点となることが期待されます。当院は、この寄付講座を起点として、臓器移植に関する臨床、研究、教育の基幹施設としての「東大モデル」を構築し、日本の臓器移植医療を次のステージへと導いていきます。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/23)
メタボリックシンドロームの基準値を外れる肥満・内臓脂肪蓄積・脂質異常症と慢性腎臓病の関連
~ 大規模職域健診を受診した約30万人のデータ解析結果 ~
東京大学大学院医学系研究科の吉田 唯助教、松山 裕教授らの研究グループは、国内大規模職域健康診断実施団体である公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターの308,174名の約3年分のデータを解析し、追跡開始時点(ベースライン)のウェスト径、HDLコレステロール・中性脂肪値がメタボリックシンドロームの基準から外れている場合、及びBMI≧25kg/m²の場合に、将来尿蛋白が発生するリスクが高いことを明らかにしました。また、HDLコレステロール値が低いと、その後の腎機能低下と関連していることが分かりました。
本結果は、血糖・血圧のみでなく、肥満・脂質異常症・内臓脂肪蓄積が独立して慢性腎臓病の発症・進行と関連していることを示唆し、該当者の早期の発見・介入により慢性腎臓病の予防・進行の抑制に役立つことが期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/16)
認知機能が低下した高齢運転者は同乗者がいると事故を起こしにくい
高齢運転者による交通事故を防ぐため、運転免許更新時の高齢者講習や認知機能検査が長年行われ、近年では先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の普及が図られています。本研究では、高齢運転者について、同乗者がいると事故を起こすリスクが低いという海外での知見や、同乗者を要する条件付き免許を採用している国があることに注目し、認知機能が低下した運転者においても、同乗者がいると事故を起こすリスクは低いという仮説をたて、これを検証しました。
2014年から2017年までに認知機能検査を受検し運転免許を更新した75歳以上の免許保有者のうち、免許更新後3年間に車両相互事故に遭った運転者を第1当事者(過失の重い方)と無過失の第2当事者に分けて、事故時の同乗者の有無を、認知機能検査の結果ごと(認知症の恐れがある人、認知機能低下の恐れがある人、いずれの恐れもない人の3群)に男女別で比較しました。
分析の結果、認知機能の程度にかかわらず、男女とも、第1当事者より第2当事者の方が同乗者を伴っているケースが多いことが分かりました。一方、二者間で事故の発生に寄与しうる要因(年齢、過去の事故経験、事故時の時間帯・天候・場所)に大きな違いは見られませんでした。
この結果は、認知機能検査で認知症や認知機能低下の恐れがあると判定された高齢運転者でも、同乗者がいれば、車両相互事故で第1当事者になりにくい可能性を示唆しています。因果関係を示すものではありませんが、高齢運転者の安全運転に同乗者が重要な役割を果たしているのかもしれません。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/15)
ニチバン、東京大学に「社会連携講座」を開設
~ 「世界から難治性創傷をなくす」ために、「次世代創傷ケアの開発」を目指す ~
ニチバン株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:高津敏明、以下「ニチバン」)は、国立大学法人東京大学(東京都文京区、総長:藤井輝夫、以下「東京大学」)において2025年4月1日より大学院医学系研究科に産学連携の社会連携講座「次世代創傷ケア開発学」を開設いたしました。本講座は5年間の期間を通じて次世代創傷ケア技術の開発と人材養成、並びに研究成果を看護教育に反映させることで患者の創傷治癒プロセスを加速させ、社会課題の解決を目指します。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/8)
尿酸輸送体GLUT9の立体構造を解明
~ 腎臓で尿酸値を協調的に調節 ~
横浜市立大学大学院生命医科学研究科の松下大輝さん(研究当時博士前期課程1年)、西澤知宏教授、李勇燦助教らの研究グループは、東京大学医学部附属病院の高田龍平教授、防衛医科大学校の松尾洋孝教授、豊田優講師(学内准教授)らとの共同研究により、体内で尿酸値の制御に関わる尿酸輸送体GLUT9の、尿酸が結合しているときの構造と結合していないときの構造をクライオ電子顕微鏡単粒子解析により明らかにし、それを基に行った機能解析から尿酸認識機構を解明しました。GLUT9を分子標的とする新たな尿酸降下薬の創製につながる重要な成果であると考えられます。
本研究には、本研究成果は、Cell Pressが発行する米国科学誌「Cell Reports」のオンライン版に先行公開されました(2025年4月5日)。
※詳細は東大病院HP掲載のリリース文書[PDF]をご覧ください。
(2025/4/8)
『行動するか?しないか?』は、高次運動野へ入力する二つの脳内経路の相反する信号によって決定される
~ To act or not to act の脳回路を解明 ~
東京大学大学院医学系研究科の吉田恵梨子大学院生(当時)、近藤将史助教、松崎政紀教授(理化学研究所脳神経科学研究センター脳機能動態学連携研究チームチームリーダー、東京大学大学院理学系研究科教授 兼担)、中江健特任准教授(当時、自然科学研究機構生命創成探索センター)、石井信教授(京都大学大学院情報学研究科)、小林憲太准教授(自然科学研究機構生理学研究所)らによる研究グループは、行動するかしないかを決定する大脳皮質回路機構を解明しました。マウスを用いた神経活動の計測・操作と、行動履歴と神経活動の数理解析によって、行動するかしないかに関する相反する信号が大脳皮質内と皮質下から高次運動野(M2)へ入力され、M2の神経細胞がこれらの信号を統合することで、行動開始信号が生成されるかどうかが決まることがわかりました。自律的なより良い行動を促す(行動変容)手法の開発や、行動決定異常に関わる疾患の理解への貢献が期待されます。
本研究成果は、米国のシュプリンガー・ネイチャー社(Springer Nature)が発行する学術雑誌『Nature Communications(ネイチャー・コミュニケーションズ)』のオンライン版に 2025年4月4日(英国夏時間)に公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2025/4/4)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報