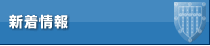広報・プレスリリース情報(2018年(平成30年))
オートファジー遺伝子の縮小進化
~ ATG12結合系の共有結合から非共有結合への進化 ~
たんぱく質がその機能を発揮するためには、さまざまな分子の共有結合による修飾を受けることがあります。その一つがたんぱく質同士の共有結合で、たんぱく質のユビキチン化などで広く見られます。細胞内の主要分解系として知られるオートファジーにおいて重要な役割を司るオートファゴソームという膜構造体は、多数のATGたんぱく質群によって作られますが、そのなかのATG12とATG5も共有結合によって連結して働いています。これは酵母や動植物などを含む、すべての生物で共通であると考えられてきました。
今回、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、中国農業科学院ハルビン獣医研究所のHonglin Jia(ホンリン・ジア)准教授、京都大学大学院農学研究科の阪井康能教授、微生物化学研究会の野田展生部長、長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科の北潔教授らのグループと共同で、マラリア原虫やトキソプラズマのような寄生虫や一部の酵母では、ATG12とATG5が非共有結合による複合体として機能していることを発見しました。本研究成果は、高度に保存されているオートファジー遺伝子も進化の過程で大きく変化していることを示すとともに、結合が強い共有結合性のたんぱく質複合体の一部が、結合が弱い非共有結合性のたんぱく質複合体へと縮小進化し得ることを示しました。
本研究は科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究(ERATO)「細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」(研究総括:水島昇)および日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)の計画研究「オートファジーの生理・病態生理学的意義とその分子基盤」として行われました。
本研究成果は、「Nature Structural and Molecular Biology」(英国時間3月25日:オンライン版)へ掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/3/26)
介護士の頑固な腰痛
~ 心身のストレス反応と腰を大事にする行動が強く関係 ~
介護施設で働く介護士の仕事に支障をきたす腰痛が長引く要因は、心身のストレス反応を示唆する身体愁訴(例えばめまい、肩こり、目の疲れ、動機息切れ、胃腸の不調、食欲低下、睡眠障害など)が多いこと、腰痛を過度にかばう思考であることが、東京大学医学部附属病院22世紀医療センター 松平浩特任教授、岡敬之特任准教授、吉本隆彦特任研究員らの研究チームによる大規模な観察研究からわかりました。これは、石川産業保健総合支援センターの小山善子所長の協力のもと、石川県内にある95の介護施設に勤務する介護士1,704名のデータ分析より得られた結果です。
介護施設の需要が高まる一方で、介護士の腰痛による休業件数は増え続けています。さらに腰痛は、労働生産性に大きく影響を与える原因であることも明らかになってきており、その対策は早急に検討すべき重要な課題です。厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」では、作業中の腰にかかる過度の負担を減らすための対策、例えばリフトを積極的に活用することや日頃の体操の習慣化などが推奨されています。このような従来の対策に、本研究で明らになったリスク要因を加味した教育・対策を標準化することによって、社会問題となっている介護士の慢性腰痛が減少し、労働生産性が向上することが期待されます。
なお、本研究は厚生労働省労災疾病臨床研究事業補助金により実施され、日本時間3月21日にJournal of Pain Researchにて掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/3/25)
脳のネットワークを視る新しい技術
~ シナプスの表面形状をナノスケールで解析することに成功 ~
東京大学大学院医学系研究科の柏木助教、岡部教授らの研究グループは、超解像顕微鏡の手法の一つである構造化照明法を用いて、神経細胞のつなぎ目であるシナプスの形態、特に樹状突起スパイン(スパイン)と呼ばれる構造の表面形状をナノスケールで解析する技術を開発しました。スパインは記憶・学習の基盤とされているシナプス可塑性によってその形態が変化します。そのためスパインの形状を、技術的に困難な電子顕微鏡を使わずに、光学顕微鏡で効率よく解析する技術が求められています。しかし、これまでは光学顕微鏡の解像度が低いためにこのような解析は実現できませんでした。今回の技術開発により、構造化照明法を用いて電子顕微鏡で得たデータとほぼ同等のスパイン形状データを1000個以上のスパインから取得し、数理科学的な手法を用いて自動的に解析することが可能となりました。精神疾患などの脳の疾患ではスパインの数や形に変化が生じる例も報告されており、精神疾患の薬物スクリーニングの手法としても今回開発された技術の応用が期待されます。
本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)「生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出(研究総括:山本 雅)」の一環として行われました。
また、本研究成果は、「Nature Communications」3月20日オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/3/20)
大学院医学系研究科 高柳広教授が日本学士院賞を受賞
この度、高柳広教授(病因・病理学専攻免疫学分野)が平成30年度の日本学士院賞を受賞されました。今回の受賞は、「骨の研究と免疫学の融合を目指すOsteoimmunologyの研究」に対するものです。
※ 受賞理由の詳細については日本学士院のホームページをご覧ください。
免疫学分野高柳研究室のホームペ―ジ http://www.osteoimmunology.com/
(2019/3/14)
糖尿病診療の質は向上したか?
~ 並存症治療の質は向上、網膜症・腎症の検査実施率が課題 ~
糖尿病性腎症、糖尿病網膜症はそれぞれ、透析導入原因の第1位、失明原因の第3位と言われており、糖尿病診療においては合併症発症・進展予防、合併症が発症した場合の早期診断・早期治療が重要です。わが国の糖尿病患者において適切な検査や処方が行われている割合の近年の推移は分かっていませんでした。国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センターの杉山雄大室長と東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の田中宏和(大学院生)ら共同研究チームは、健康保険組合のレセプト(診療報酬請求明細書)データベースを用いることにより、薬物治療中の糖尿病患者において糖尿病治療ガイド(日本糖尿病学会編著)等で推奨されている検査や薬の処方を受けている割合を糖尿病診療の質を示す指標として算出し、その経年変化(2007〜2015年度)を分析しました。
研究の結果、3ヶ月に1度以上の頻度で医療機関を受診し糖尿病治療薬の処方を受けていた糖尿病患者において、翌年度に1回以上のHbA1c検査、血中脂質検査を実施した割合は高く、それぞれ約95%、約85%でした。また、『高血圧治療薬を処方されている糖尿病患者がACE阻害薬またはARBの処方を受けている割合』と『脂質異常症を並存している糖尿病患者がスタチンの処方を受けている割合』は上昇傾向にありました。
一方で、糖尿病治療ガイド等で推奨される年1回以上の糖尿病網膜症の検査を受けている糖尿病患者の割合は約40%にとどまり、この実施率は近年上昇していませんでした。また、糖尿病性腎症の検査である尿アルブミン検査の実施率は上昇傾向にあるものの2015年度においてもわずか24%であり、糖尿病網膜症・腎症の検査実施率に課題があることが明らかになりました。これらの点については、糖尿病治療ガイド等で推奨されている適正な検査のさらなる普及が望まれます。本研究ではインスリンの処方の有無や医療施設の規模で層別化した解析を行っており、これらの結果が糖尿病診療の質の向上のための基礎資料として今後活用されることが期待されます。本研究は国際糖尿病連合が発行する” Diabetes Research and Clinical Practice”の3月号に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/3/8)
深層ニューラルネットワークに脳細胞の活動を写し取る
近年、人工知能の分野で、深層ニューラルネットワークは大きな進展を遂げ、人間に近い性能で物体の認識を行うことができるようになってきています。一方、人間とは明らかに異なった認識をしてしまう例も報告されています。今後、人工知能がさまざまな分野、特に自動運転や医療診断など人命に関わりうる領域に活用されるにあたって、私たち人間を含む動物がどのように目で見た視覚情報を処理しているのかを解明することは重要と思われます。さらに、視覚野の情報処理の原理を取り入れることで、より人間などの動物と似たように振る舞う人工知能ができる可能性があります。
東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 統合生理学分野・東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構の浮田 純平大学院生、大木 研一教授の研究チームは、目で見た画像に対する視覚野の神経細胞の活動を深層ニューラルネットワークモデルに写し取ることで、神経細胞の活動をコンピュータで詳細に解析する手法を開発しました。本手法をマウス一次視覚野の神経細胞の解析に適用し、各神経細胞がどのような画像に対して最も強く反応するかを仮説フリーかつ網羅的に可視化することができました。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」、文部科学省科学研究費助成事業などの支援を受けて行われました。本研究の成果はScientific Reports誌(3月7日付けオンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/3/7)
皆保険制度の国で在住外国人に健康格差の懸念
~ 富裕層対象の医療政策導入で悪化の恐れ日本人医師グループが英医学誌で注意を促す ~
日本の在住外国人には医療格差があります。困窮している外国人が、医療保険がないことを理由に、病気になっても窓口で受け付けてもらえなかったり、高額な医療費を請求されるなどの問題も起きています。言葉や制度の壁を乗り越える適切な支援がなければ事態はより深刻化すると日本人医師グループが英医学誌ランセットで注意喚起しました。
在住外国人の診療や研究に携わってきた沢田貴志港町診療所所長、安川康介医師、東京大学の神馬征峰教授(国際保健学専攻)、橋本英樹教授(公共健康医学専攻)らの研究グループは、2月28日発行のランセット(The Lancet)の論評(Correspondence)で「外国人就労拡大政策を進めているにもかかわらず、日本の在住外国人に対する医療は他のOECD諸国より大きく遅れている。富裕層の旅行者を前提とした医療サービスの充実では在住外国人の健康問題が置き去りにされ、公平なサービスで健康を守ってきた日本の医療が損われる。」と警告しました。概要は以下の通りです。
1)誰でもいつでも必要な医療が受けられる日本の医療は世界的にも高く評価されている。その一方で、在住外国人は言葉や医療保険制度の障壁などにより健康格差にさらされている。
2)2010年の統計調査でも、在住外国人は日本人よりも糖尿病や腎不全の死亡率が高いなどの課題が示されている。
3)言葉の壁のある外国人に対する医療通訳は適切な医療のために不可欠である。しかし、米国などと違い、日本では住民のための安価な医療通訳制度が未整備である。東京オリンピックに向けて外国人患者への医療提供サービスの整備を進められているものの、施策の対象は観光客や富裕層などが中心。
4)一部の難民申請者や在留資格をなくした外国人労働者などは医療を保証する制度からこぼれてしまっており、こうした外国人が受付で身分証を厳しくチェックされ受診を拒否されることが生じている。かつては困窮層の外国人患者を受け入れてきた公的病院の中にも、無保険者に高額な医療費を請求したり、早期の退院を迫るなどの事例も出ている。
5)現在日本には250万人を超える外国人が暮らしている。外国人就労拡大政策によりこの数字はさらに増える見込みであり、日本で暮らす外国人に生じている医療格差に配慮した制度設計が急務である。
※The Lancet Correspondence Volume 393, ISSUE 10174, P873-874, March 02, 2019
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30215-6/fulltext
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/3/1)
肥満を制御する酵素を発見
肥満は糖尿病(インスリン抵抗性糖尿病)、高血圧、脂質異常症など、多くの生活習慣病の原因となることから、肥満の予防や解消は急務の課題となっています。日本の糖尿病有病者数は約1,000万人と推計されていますが[平成28年「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)]、特に、肥満が原因となってインスリンが効かなくなり、血糖値が下がらないインスリン抵抗性糖尿病の患者数は、増加の一途をたどっています。しかし、肥満は複雑に制御されていることから、肥満のメカニズムを解明し、新たな抗肥満薬の開発につながる「肥満調節分子」の発見が期待されています。肥満では、体の組織に脂質が蓄積するだけでなく、脂質自体が、直接、肥満や生活習慣病の病態の進展に関わることが知られています。脂質の一つであるプロスタグランジンD2(PGD2)とPGD2のL型合成酵素(L-PGDS)が脂肪細胞に蓄積した脂肪の分解の抑制に関わることが発見されています(Biochem. Biophys. Res. Commun. 490: 393, 2017)。
そこで、東京大学、大阪薬科大学、第一薬科大学、筑波大学の研究グループは、肥満制御におけるPGD2のはたらきを調べるため、脂肪細胞でL-PGDSを作ることができないマウスを作製し、肥満におけるL-PGDSのはたらきを解析しました。正常なマウスと脂肪細胞でL-PGDSを作ることができないマウスに11週間、高脂肪食を与えて肥満にさせたところ、脂肪細胞でL-PGDSを作ることができないマウスでは、正常なマウスと比べて体重増加が20%以上減少し、内臓や皮下の脂肪量も減少していました。さらに、糖尿病の指標となるインスリン感受性も改善されていることが分かりました。今回の成果は肥満を調節する新たな酵素の発見であり、この酵素の活性を調節する化合物が抗肥満薬につながることが期待されます。本研究は、日本時間2月13日英国科学誌『Scientific Reports』(オンライン版)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/2/14)
日本人集団の2型糖尿病に関わる新たな遺伝子領域を発見
2型糖尿病は脳卒中・心筋梗塞・腎不全・がんなど、万病の危険性を高める重大な病気であり、日本国内で1,000万人、世界中で4億人以上が2型糖尿病と言われています。2型糖尿病のかかりやすさは、遺伝と環境の両方によって影響されますが、日本人集団における2型糖尿病の遺伝の理解は不十分でした。東京大学大学院医学系研究科の門脇 孝特任教授、山内敏正教授、理化学研究所 生命医科学研究センターの堀越桃子チームリーダー、鎌谷洋一郎チームリーダー、大阪大学大学院医学系研究科 岡田随象教授、鈴木 顕助教らの研究グループは、20万人規模の日本人集団の遺伝情報を用いた大規模ゲノムワイド関連解析(GWAS)を行い、2型糖尿病の危険性を高める遺伝子領域を新たに28箇所同定しました。また、2型糖尿病治療薬の標的分子であるGLP-1受容体のミスセンス変異が2型糖尿病の危険性と関わることを見出しました。このミスセンス変異は薬剤投与後のインスリン分泌を増加させるため、薬の効き方を予測する指標に応用できる可能性があります。2型糖尿病の遺伝において、膵臓のβ細胞が日本人集団と欧米人集団に共通して重要である一方、インスリン分泌を調節する経路など日本人集団においてより大きな影響を有する分子生物学的パスウェイを見出しました。これらの結果は2型糖尿病の遺伝要因の理解を深めるとともに、将来的には糖尿病の発症予測・発症前予防に応用できる可能性があります。
本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のゲノム医療実現推進プラットフォーム事業「先端ゲノム研究開発」(GRIFIN)領域における研究開発課題「糖尿病の遺伝・環境因子の包括的解析から日本発次世代型精密医療を実現するプロジェクト」(研究開発代表者:門脇 孝)、「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」の「糖尿病・メタボリックシンドローム関連疾患の個別化医療実現」(研究開発代表者:門脇 孝)の一環で行われました。その成果は日本時間2019年2月5日に米国科学雑誌 Nature Genetics オンライン版に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/2/5)
人工知能で脳波からてんかん発作を自動検出
東京大学先端科学技術研究センターの高橋宏知准教授、自治医科大学脳神経外科の川合謙介教授、情報通信研究機構脳情報通信融合研究センターの篠崎隆志研究員らの研究グループは、脳波からてんかん発作を自動検出できる人工知能の開発に成功しました。脳の一部が異常で過剰な活動を起こすと、突然痙攣を生じたり、意識を失ったりする「てんかん発作」を起こします。てんかんの診断には、脳波検査が欠かせません。これらの診断は、てんかん専門医の専門知識と経験に加え、膨大な検査データの精査に長時間を要する大変な作業でした。このような診断の負担軽減のためにも、脳波からてんかん発作を自動検出できる手法が強く求められていました。
本研究では、脳波データを脳波計の画面に出力されるような画像に変換し、これらの無数の画像を人工知能に学習させることを試みました。そのような試みの動機は、てんかん専門医が脳波を精査するとき、脳波を時系列データとして数理的に解析しているわけではなく、自らの経験に基づいて、脳波計の画像の特徴から「視覚的に」判断していると考えたことにあります。本研究では、ビデオ脳波モニタリング検査を実施した24名から得た合計1124.3時間の脳波データを解析対象にしました。これらの検査データから作成した脳波画像を深層畳み込みニューラルネットワークに学習させたところ、市販のソフトウエアにおける既存手法を大きく上回りました。今後、さまざまな脳波データを集積すれば、専門的な知識と経験を備えたてんかん専門医に勝るとも劣らないてんかん発作を検出できる人工知能の開発の可能性が示されました。将来的には、てんかん専門医が不足する地域でも、本手法により専門的な脳波診断を提供できるようになると期待されます。また、時系列データを画像に変換したうえで画像認識技術を適用する手法は、てんかん発作以外の脳波診断や生体信号解析をはじめ、さまざまな用途への応用が考えられます。本研究成果は、2019年1月22日付でAccepted Manuscripts 版が「NeuroImage: Clinical」に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/2/1)
思春期早期における向社会性の発達に脳帯状回の神経代謝と機能的ネットワークが関連することを発見
ヒトの向社会的な行動は「他者の利益となるような自発的な行動」と定義されており、小児期に出現し思春期に成熟します。これまでに、思春期の社会認知に前部帯状回が関連することが示されていました。しかし、思春期早期における向社会性の、神経伝達物質や脳機能的ネットワークとの関連は、明らかではありませんでした。東京大学医学部附属病院精神神経科の岡田直大助教、笠井清登教授らの研究グループは、一般人口集団から抽出した大規模な思春期早期の被験者グループを対象とし、磁気共鳴画像法(MRI)を用いた研究により、前部帯状回のγ‐アミノ酪酸(GABA)の濃度が低いと向社会性が高く、前部帯状回と後部帯状回との機能的ネットワークが強いと向社会性が高いことを、新たに見出しました。「ポピュレーション・ニューロサイエンス(Population Neuroscience)」研究による今回の成果は、思春期早期における向社会性の発達に、脳神経の代謝動態や機能的ネットワークが関連することを見出しており、ヒトの主体価値の発展に関する理解を深めるものと期待されます。本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」や文部科学省科学研究費補助金などの支援により行われ、日本時間1月24日に英国科学誌『Scientific Reports』(オンライン版)にて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/1/25)
エストロゲンが骨細胞のSema3Aを介して骨の恒常性を維持するしくみを解明
~ 閉経後骨粗鬆症の新たな治療法の開発に期待 ~
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学分野の中島友紀教授と林幹人助教らの研究グループは、東京大学大学院医学系研究科免疫学分野の高柳広教授、同研究科骨免疫学寄付講座、同研究科整形外科学分野の田中栄教授、同研究科ロコモ予防学寄付講座の研究グループとの共同研究で、閉経後骨粗鬆症や加齢での骨量減少の原因が骨細胞でのSema3A発現低下によることを突き止めました。この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)「メカノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及び医療技術の創出(研究開発総括:曽我部正博)」における研究開発課題「骨恒常性を司る骨細胞のメカノ・カスケードの解明」(研究開発代表者:中島友紀)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業 さきがけ「生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御(研究総括:春日雅人)」における研究開発課題「運動器の動的恒常性を司るロコモ・サーキットの解明」(研究者:中島友紀)、文部科学省科学研究費補助金、セコム科学技術振興財団、武田科学振興財団等の支援のもとで行われたもので、その研究成果は、国際科学誌「Cell Metabolism」に、2019年1月17日午前11時(米国東部時間)にオンライン版で発表されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2019/1/18)
B型肝炎ウイルスの治療薬候補「ペボネジスタット」を新たに同定
B型肝炎ウイルス感染者は世界中で20億人、そのうち持続感染者は2.57億人、さらに年間90万人がB型肝炎ウイルス関連疾患で死亡しています。B型肝炎の克服は日本国内のみならず世界的な重要課題です。B型肝炎の長期予後改善のために、ウイルスタンパクであるHBs抗原の陰性化「Functional cure」が治療目標として掲げられていますが、既存のB型肝炎治療薬では達成困難であり、新薬の登場が切望されています。そうした中、ウイルスタンパクHBxによる、宿主ユビキチン・プロテアソーム系を介した宿主タンパクSmc5/6の分解がもたらすウイルスの複製促進機構が明らかとなり、新たな治療標的として注目されていました。
そこで、東京大学医学部附属病院 消化器内科の關場一磨 大学院生、大塚基之 講師、小池和彦 教授らの研究グループは、Smc5/6タンパクが宿主ユビキチン・プロテアソーム系によって分解されること、また、このユビキチン化にはネディレーションによるユビキチン化酵素の活性化が必要なことに注目し、ネディレーション阻害薬であるペボネジスタット(Pevonedistat)がB型肝炎の新規治療薬となり得ると考えました。そして実際に、ペボネジスタットはネディレーションを阻害することによって、Smc5/6タンパクの分解を阻害して機能を回復し、ウイルスRNAをはじめとしたウイルス産物量を強力に抑えるという、既存のB型肝炎治療薬には無い効果を有することを、初代ヒト肝細胞を用いた検討などで明らかにしました。ペボネジスタットは白血病領域を中心とした悪性腫瘍の治療薬として開発が進められており、今後早期のB型肝炎治療薬への応用が期待されます。 本研究成果は、米国肝臓病学会誌『Hepatology』に掲載されるのに先立ち、米国東部時間12月26日にオンライン版にて公開されました。なお、本研究は日本医療研究開発機構(AMED)肝炎等克服実用化研究事業の肝炎等克服緊急対策研究事業(研究開発課題名「B型肝炎ウイルスRNAと相互作用する宿主因子の網羅的同定とその制御による病態制御法開発」研究代表者:大塚基之)および文部科学省科学研究費補助金などの支援により行われました。※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/1/17)
世界で最も精巧な頭部3次元CGデータを開発
~ 脳神経外科医の解剖学的知識を可視化 ~
東京大学医学部附属病院脳神経外科の齊藤延人教授と金太一助教らの研究グループは、最先端のコンピュータグラフィックス技術を用い、ヒトの頭部の解剖学的構造を精巧に再現した3次元コンピュータグラフィックス(3DCG)モデルを開発し、この度その無償提供を開始しました。
本3DCGモデルは、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の「バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命」(プログラム・マネージャー:原田 香奈子)の研究の一環として開発されたもので、バイオニックヒューマノイドの基礎設計図となっています。
人体の高精細な3DCG作成には、高度なCG技術と医学的知識、そして高い開発費を要するため、その開発は困難でした。本研究グループは、最先端のコンピュータグラフィックス技術と脳神経外科医の知見を集約し、医療の現場に必要な解剖情報を3DCGとして作製しました。
今回開発した頭部3DCGモデルは1,000パーツ以上におよび、世界で最も精巧なものです。この度専用のホームページ(https://brain-3dcg.org)を開設し、全てのパーツを無償で提供しています。
ダウンロードした3DCGモデルは、非商用で、かつ研究もしくは教育用途であれば自由に使用できます。本3DCGパーツは、いくつもの研究機関で開発に利用されるなど、その拡張性は高く、さまざまな分野で活躍することが見込まれます。世界最高レベルの精巧な頭部3DCGを普及させることによって、医療や教育、研究開発など広い分野への貢献が期待されます。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/1/17)
緑内障手術練習用の眼球モデルを開発
~ ヒトの強膜の感触を忠実に再現 ~
名古屋大学未来社会創造機構の新井史人教授、同大学大学院工学研究科の小俣誠二特任助教の研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の相原一教授の研究グループ、同大学大学院工学系研究科の光石衛教授の研究グループ、三井化学株式会社との共同研究により、人間そっくりな眼科手術シミュレータに搭載可能な緑内障手術練習用眼球モデルを開発しました。本研究は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導するImPACTプログラム「バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命」(プログラム・マネージャー:原田香奈子)の一環として実施されたものです。
近年、医学教育の効率化や難手術の効果的訓練が求められており、以前より当研究グループは、精巧な手術シミュレータを開発してきました。一方、緑内障手術では、眼圧を下げるために白目にあたる強膜の薄切りと縫合が多く施術されていますが、練習用の眼球モデルが十分に開発されておらず、医師が基礎学習や術前訓練を十分に行うことができませんでした。
本研究では、上記の課題を踏まえ、緑内障手術に必要な強膜構造を形成することにより、緑内障手術における強膜の薄切りと縫合に対応した中空構造の眼球モデルを開発することに成功しました。これにより、従来は行うことのできなかった手技訓練が可能になりました。
この研究成果は、2019年1月11日の公開シンポジウム「バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命」、2月1~3日の「第42回日本眼科手術学会学術総会」で展示公開するほか、3月27~30日(豪州)の「World Glaucoma Congress 2019」にて学術発表します。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/1/17)
微細手術に適用可能な低侵襲手術支援ロボットの開発
~ 「バイオニックヒューマノイド」活用により世界最高水準のロボットを実現 ~
東京大学大学院工学系研究科光石衛教授らの研究グループは、大学・企業・病院との共同研究により、脳神経外科などにおける微細手術への適用を可能とする低侵襲手術支援ロボット「スマートアーム」を開発しました。
近年医療現場に導入されている低侵襲手術支援ロボットは、腹部を主な対象としていますが、さらにさまざまな手術への普及が期待されています。しかしながら体内の狭所・深部において非常に繊細で高度な手術を行うには、個別技術の小型化や高性能化に加えて、手術ロボットシステムとしていかに要素技術を統合するかが大きな課題でした。
本研究グループは、大学・企業・病院との共同研究により開発した要素技術を統合し、産業用ロボットアームをベースとした双腕の手術支援ロボット「スマートアーム」を開発しました。スマートアームの研究開発は、バイオニックヒューマノイドの脳神経外科手術用モデル「バイオニック・ブレイン」を活用することで、脳神経外科医からのフィードバックを受けながら医工連携研究として実施しました。このバイオニック・ブレインを用いることで、経鼻内視鏡手術における硬膜縫合を実現できる性能も確認しました。これは手術ロボットとして世界最高水準の性能です。この研究成果により、高度で困難な手術へのロボット手術適用の可能性が大きく広がります。
本研究成果は、平成31年1月11日(金)に東京大学伊藤国際学術研究センターで開催される公開シンポジウムにおいて、研究報告を行うとともに実機や関連技術の展示を行います。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2019/1/17)
大腸がんの新しい発症メカニズムを解明
大腸がんは、大腸の中にある少数の幹細胞に特定の遺伝子異常が蓄積することで発生するものと考えられていました。しかし幹細胞以外の細胞ががん化しうるかどうかや、もしそうであればどのようなメカニズムでそうした細胞ががんに変化していくかについては分かっていませんでした。今回、東京大学医学部附属病院消化器内科の早河翼助教、坪井真代医師、小池和彦教授らは、特定の内分泌系前駆細胞ががんの起源となりうること、またその過程でNotch経路とYAP経路ががん細胞化に重要であることを明らかにしました。本研究グループはマウスモデルを用いて、内分泌系前駆細胞の中でNotch経路が活性化すると幹細胞のような働きを持つようになり、さらに大腸がん発生にかかわる重要な遺伝子であるApc遺伝子の変異を生じさせることでがんのもととなることを示しました。また、潰瘍性大腸炎の患者さんでみられるような炎症発がんの発生過程においては、この細胞の中のYAP経路が重要な役割を果たすことを明らかにしました。今回の新しい発見により、これまで分かっていなかった多様な大腸がんの発生メカニズムが明らかになるとともに、内分泌系前駆細胞やNotch・YAP経路を標的とした新規大腸がん治療の開発につながることが期待されます。
これらの研究成果は、米科学誌『Gastroenterology』に掲載されるのに先立ち、米国東部時間11月15日にオンライン版にて公開されました。なお本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端開発支援事業(PRIME)の支援を得て東京大学とコロンビア大学の共同で行われました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/11/21)
健常高齢者の2割を占める「前臨床期アルツハイマー病」は、一見正常だが、学習効果が乏しいことが特徴
アルツハイマー病の病理変化が生じているが、臨床症状の見られない「プレクリニカルAD」は、アルツハイマー病の根本治療薬による予防的な治療の対象として注目されています。しかし、日本人におけるプレクリニカルADの特徴は十分知られていませんでした。今回、東京大学大学院医学系研究科の井原涼子特任助教、岩坪威教授らの研究グループは、日本人を対象にしたJ-ADNI研究により得られたデータを用いて、60~84歳の認知機能正常高齢者の22.6%がプレクリニカルADに相当することを示しました。プレクリニカルADの被験者の認知機能は正常範囲にありますが、ミニメンタル検査や論理的記憶検査などの基本的な認知機能検査を半年~1年ごとに反復して行うと、学習効果の喪失という形で異常が検出されることを示しました。また、プレクリニカルADの中でもより進行した病期では、遂行機能課題においても学習効果の喪失が検出される傾向がありました。これらの特徴は、認知機能の低下のない高齢者の中からプレクリニカルADの人を選択する場合に、あるいはプレクリニカルADにおける認知機能障害の進行を精密に評価する際に重要と考えられます。
本研究は、新潟大学脳研究所・池内健教授、桑野良三前教授との共同研究により行われました。
本研究成果は、Alzheimer's and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 11月19日(月)(米国東部標準時間)オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/11/19)
肥満における慢性炎症の新規発症メカニズムの解明
肥満に伴う糖尿病や脂質異常症などの代謝異常の原因として、脂肪組織における抗炎症作用を有するM2aマクロファージの活性低下による慢性炎症が注目されておりますが、なぜ肥満でM2aマクロファージ活性が減弱しているのか、その分子機構は不明でした。東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座 特任教授 門脇孝、医学部附属病院 病態栄養治療部 部長 窪田直人、理化学研究所 生命医科学研究センター 粘膜システム研究チーム 上級研究員 窪田哲也らは、肥満・インスリン抵抗性に伴う高インスリン血症が、マクロファージのインスリン受容体を介してインスリン受容体基質-2(Irs2)の発現を低下させ、その結果Irs2を介したIL-4によるM2 aマクロファージ活性化が減弱し、慢性炎症が惹起されることを発見しました。肥満に伴う慢性炎症の新しい分子機構の解明により、肥満を解消せずとも糖尿病や脂質異常症等、肥満関連代謝疾患を改善できる新たな治療薬の開発につながることが期待されます。
本研究成果は、日本時間11月19日に英国の科学雑誌Nature Communicationsにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/11/20)
卵子提供、代理懐胎など第三者を介する生殖補助医療と出自を知る権利に対する国内の意識調査について
東京大学医学部附属病院 女性外科の平田哲也講師、大須賀穣教授らは、「第三者を介する生殖補助医療」「出自を知る権利」に対する国内の意識調査をWebアンケートで行いました。第三者が関わる生殖補助医療に関する課題に向き合う法整備、ルール作りが行われていない現状を踏まえ、今後の法制化の可能性も視野に入れて意識調査を行いました。
「第三者を介する生殖補助医療」や「出自を知る権利」に対する意識は、肯定的な意見が否定的な意見を上回っていますが、その差は性別、年齢、不妊経験の有無などに影響を受けていることもわかりました。一方で、ほとんどすべての質問において30%以上の人が「わからない」と答えていることから、社会的合意を得るためには、これらの問題の知識を提供し、議論を活発化させる必要があると考えられます。本研究成果は、これらの結果も踏まえて、早期の第三者が関わる生殖補助医療に関する課題に向き合う早期の法整備やルール作りにつながることが期待されます。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「成育疾患克服等総合研究事業」の「生殖補助医療により出生した児の長期予後と技術の標準化に関する研究(研究開発代表者:苛原稔)」及び「生殖補助医療の技術の標準化と出生児の安全性に関する研究(研究開発代表者:苛原稔)」により実施され、日本時間11月1日に米国の科学雑誌PLOS ONEにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/11/5)
シングルセル解析と機械学習により心不全において心筋細胞が肥大化・不全化するメカニズム(心筋リモデリング機構)を解明
心不全はがんと並び世界中で多くの患者の命を脅かしています。心臓に高血圧や大動脈弁狭窄症のような血行力学的負荷がかかると、代償的に心臓は肥大してポンプ機能を維持しようとしますが、慢性的な負荷は壁運動低下・心拡大を引き起こし、心不全を発症します。その過程で心筋細胞の肥大化と不全化が中心的な役割を担っていると考えられていますが、その詳細な分子メカニズムは明らかでなく、心不全の分子病態を把握・治療する有効な手法は存在しません。
東京大学医学部附属病院 循環器内科の小室一成教授、野村征太郎特任助教、先端科学技術研究センターの油谷浩幸教授らは、心不全モデルマウスおよび心不全患者の心臓から心筋細胞を単離した後、細胞集団ではなく個々の細胞を解析できるシングルセル解析によりトランスクリプトーム(全遺伝子発現情報)を取得し、機械学習により世界で初めて心筋細胞リモデリング(環境に合わせて細胞の性質が変わること)の過程における分子プロファイルの挙動を明らかにしました。
その結果、心筋細胞の肥大化にはミトコンドリア生合成の活性化が重要であること、肥大心筋細胞は代償性心筋細胞と不全心筋細胞へと分岐すること、不全心筋細胞への誘導にはがん抑制遺伝子であるp53の活性化による代謝・形態リモデリングが重要であることを明らかにしました。さらに、心筋遺伝子の発現応答はマウスとヒトで極めて良く保存されていることを確認し、心不全に特徴的な遺伝子の発現パターンから患者の予後を予測し病態を層別化できることを実証しました。これらの成果は、心臓疾患の詳細な病態解明に役立つだけでなく、個々の心不全患者の臨床像と連結した分子病態の理解に直結し、循環器疾患における精密医療の実現に貢献するものと期待されます。
本研究は日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業「心筋メカノバイオロジー機構の解明による心不全治療法の開発(研究代表者:小室一成)」、日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究A「心不全発症における心筋細胞不均一性の意義(研究代表者:小室一成)」、日本循環器学会 基礎研究助成「心臓細胞分子アトラスによる心臓疾患の病態解明および精密医療の実現(研究代表者:野村征太郎)」等の支援により行われ、日本時間10月30日に英国の科学雑誌Nature Communicationsにて発表されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/10/31)
人工知能による小腸粘膜傷害の診断
~ AIを活用したカプセル内視鏡画像診断支援システムの開発 ~
このたび、東京大学医学部附属病院(病院長:齊藤延人、所在地:東京都文京区)消化器内科の青木智則医師(大学院生)、山田篤生助教、小池和彦教授らのグループと株式会社AIメディカルサービス(CEO:多田智裕、所在地:東京都豊島区)は共同で、人工知能(AI)を活用し、小腸カプセル内視鏡画像の中から粘膜傷害(びらん・潰瘍)を高精度で自動検出する内視鏡画像診断支援システムを開発しました。
薬や炎症による粘膜傷害は、胃や大腸だけでなく小腸にも起こります。小腸はカプセル型の内視鏡を用いて見ることができ、粘膜傷害は最も高頻度な異常です。しかし、1患者あたり6万枚程度の内視鏡画像を30~120分かけて読影するのは、読影者にとって大きな負担であり病変が見逃されることも危惧されます。病変自動検出システムがあれば、これらを軽減できる可能性があります。
本研究グループは最先端のAI技術であるニューラルネットワークを用いたディープラーニングを活用し、小腸のびらん・潰瘍が写った5,360枚の内視鏡画像をAIに学習させ、病変検出力の検証をしました。その結果、検証用の内視鏡画像10,440枚から、びらん・潰瘍を91%の精度で正診することができました。また、10,440枚の画像の解析に要した時間は233秒であり、解析速度は人間の能力をはるかに超えるものでした。さらに、本システムは熟練した内視鏡医が発見できなかった病変も見つけることができ、病変見逃しの防止につながる可能性も示しました。
これまで、AIを活用したカプセル内視鏡診断支援システムは確立されていません。今後さらに、検出精度の向上や粘膜傷害以外の病変の検出といった応用を進め、小腸病変検出を支援するカプセル内視鏡診断支援システムの実用化を目指します。
本研究成果は、米国内視鏡医学雑誌『Gastrointestinal Endoscopy』オンライン版(2018年10月25日付)に掲載されました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/10/29)
新規作用機序に基づくB型肝炎ウイルス治療薬候補を同定
B型肝炎は、全世界で2億5千万人以上が罹患し毎年約90万人が死亡しているとされており、その克服は世界的な重要課題とされています。B型肝炎の長期予後改善のための治療目標はウイルスタンパクであるHBs抗原の陰性化(Functional cure)ですが、既存のB型肝炎治療薬では達成困難であり、新規治療法の登場が強く望まれています。そうした中、ウイルスタンパクHBxと宿主タンパクDDB1との結合を端緒とするウイルス複製の制御機構が徐々に明らかとなり、新しい治療標的として注目されてきました。東京大学医学部附属病院 消化器内科の關場一磨 大学院生、大塚基之 講師、小池和彦 教授らの研究グループは、相補型スプリットルシフェラーゼアッセイ技術を応用し、HBxとDDB1との結合阻害剤を簡便に探索できるスクリーニング系を構築し、それによってニタゾキサニドをB型肝炎治療候補薬剤として同定しました。さらに、ニタゾキサニドはHBxとDDB1結合を阻害することによって、ウイルスRNAをはじめとしたウイルス産物量を有意に抑えるという、既存B型肝炎治療薬には無い効果を有することを、初代ヒト肝細胞を用いた検討などで明らかにしました。ニタゾキサニドは原虫による腸炎の治療薬として米国食品医薬局(FDA)で既に認可されている薬剤であり、今後のB型肝炎治療薬への転用(ドラッグリポジショニング)が期待されます。本研究成果は、米国東部夏時間10月24日にCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology(オンライン版)にて発表されました。なお、本研究は日本医療研究開発機構(AMED)肝炎等克服実用化研究事業の肝炎等克服緊急対策研究事業(研究開発課題名「B型肝炎ウイルスRNAと相互作用する宿主因子の網羅的同定とその制御による病態制御法開発」研究代表者:大塚基之)および文部科学省科学研究費補助金などの支援により行われました。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/10/26)
IgM五量体の真の姿と、疾患制御タンパク質AIMとの結合様式の発見
IgM抗体は、血中で5つの抗体単体が五量体を形成して存在する、ユニークな抗体である。過去50年間以上、IgM五量体は桜の花びらのような正五角形をしていると信じられており、実際そのように教科書に記載されてきた。IgM五量体は、多彩な免疫学的な働きと共に、一方で、さまざまな疾患を制御する血中タンパク質AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage)の血中におけるキャリアーとして機能していることが知られている。AIMは腎疾患を始めとする多くの疾患を抑制する血中タンパク質であるが、正常時にはIgM五量体に結合し不活性化しており、疾患が発症するとAIMは解離し活性化して、疾患の治癒を促進する。しかし、これまでAIMがどのような様式でIgM五量体に結合しているのか分かっていなかった。
東京大学大学院医学系研究科の宮﨑徹教授らの研究グループは、IgM五量体は正五角形ではなく、一ヵ所大きなギャップを持った、歪な五角形をしており、そのギャップにAIMが嵌まり込むように結合していることを明らかにした。
本研究では、AMED創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)の支援により、東京大学大学院医学系研究科の吉川雅英教授の協力を得て、負染色したAIMと結合・非結合状態のIgM五量体分子の2D構造を、最新の電子顕微鏡により観察することに成功した。その結果、IgM五量体の構造が、過去のどの研究結果よりも鮮明な像として捕らえられ、従来考えられていたものとは異なる真の構造と、AIMとの結合様式を明らかにすることができた。
本研究成果は、これまで50年以上免疫学の教科書に誤って記載されていたIgM五量体の構造を覆す成果である。現在、本研究グループを中心に、AIMをIgM五量体から解離させ活性化することにより、腎疾患を始めとするさまざまな疾患を対象とした創薬開発が進められているが、本研究によるAIMとIgM五量体との結合様式の解明は、そのような新規創薬開発に大きく貢献することが期待される。
本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)の研究開発領域「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」(研究開発総括:永井 良三)における研究課題「生体内の異物・不要物排除機構の解明とその制御による疾患治療」(研究代表者 宮崎徹)、文部科学省科学研究費補助金基盤研究(S)の一環で行われた。
本研究成果は、2018年10月10日(米国東部夏時間)に「Science Advances」オンライン版で公開された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/10/12)
がん遺伝子パネル検査「Todai OncoPanel」の臨床性能試験を先進医療で開始
がん研究の進歩により、がんの病態に関わる多くの遺伝子異常が発見されていますが、たとえその異常を標的とする治療が存在したとしても、1回の検査で1遺伝子を調べるこれまでの検査では、解析対象がん種も限られていることもあり、高い精度でその治療が有効であるという情報を提供することが困難でした。このような課題を克服するために、1回の検査で数多くの遺伝子を網羅的に解析することを可能とするがん遺伝子パネル検査が近年相次いで開発されていますが、中でもTodai OncoPanel(東京大学が独自に開発したがん遺伝子パネル検査)は、DNAのみならずRNAも解析すること、各々450以上の遺伝子を解析する点において、解析対象の範囲が極めて広いことが大きな特徴です。そこで、東京大学医学部附属病院は、標準治療がない、標準治療が終了している、もしくは終了が見込まれる患者を対象として、このパネルが治療の選択においてどの程度有用であるかを検証することを目的として、先進医療B「遺伝子パネル検査(Todai OncoPanel)」を、本研究連携医療機関とともに実施します。
※詳細は東大病院HP掲載の ![]() リリース文書[PDF]をご覧ください。
リリース文書[PDF]をご覧ください。
(2018/10/9)
遺伝情報を正確に守るための新たなDNA修復メカニズムを発見
~ ヒトの体が持つ「がんにならないようにする」仕組みの一端が明らかに! ~
私たちの体の中にあるほとんどの細胞は、それぞれ一つずつ細胞核を持っていて、その細胞核の中にはDNAが折りたたまれて入っています。一つの細胞核に入っている全てのDNAを繋ぎ合わせると、全長2メートルになると言われていますが、実はそのうちのほんの一部分しか「遺伝子」として利用されていません。タンパク質を合成するために遺伝情報が頻繁に読み出される領域は細胞にとって非常に重要であるため、もしその領域でDNAが切断された場合には、他の部位に比べ正確に修復することが必要と考えられてきました。しかしながら、重要な遺伝情報が記録された領域のDNAが切断された時、細胞がどのようにして広大なゲノムから重要な部分を探し出しているのか、さらにはどのようにして正確に修復しようとするのかについては、ほとんど分かっていませんでした。
今回、東京大学大学院医学系研究科の安原崇哲助教、加藤玲於奈大学院生、宮川清教授、群馬大学大学院医学系研究科の柴田淳史研究講師らの研究グループは、重要な遺伝情報を含む領域にゲノム損傷が生じると、周辺にR-loop構造と呼ばれる、DNAとRNAからなる特殊な構造が形成されること、さらにタンパク質Rad52がこの構造を認識することが、その部位のゲノム損傷を正確に修復するきっかけとなることを発見しました。広大なゲノムの中で、その領域の重要性を認識し、正確な修復経路を誘導するために、R-loop構造はいわば、目印として利用されていることが判明しました。さらに、このメカニズムがうまく機能しない場合には、不正確なDNA修復によって生じるゲノム異常が顕著に増加することも分かりました。今回明らかになったメカニズムは、ゲノム異常を原因として生じるがんなどの疾患を防ぐために細胞が保持している防御機構の一つであることが示唆されます。
本研究成果は、米国科学雑誌『Cell』の2018年10月4日号(2018年9月20日オンライン版(米国東部夏時間))に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/21)
リークカリウムチャネルの睡眠時間制御への関与を発見
東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻薬理学専攻 システムズ薬理学分野の上田泰己教授(理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チーム チームリーダー兼任、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 主任研究者兼任)、吉田健祐学生(研究当時:医学部6年生)、史蕭逸助教(理化学研究所 客員研究員兼任)らの研究グループは、ホジキン・ハクスレーモデルをベースにした数理モデルと網羅的遺伝子ノックアウト技術(トリプルCRISPR法)・非侵襲で並列化可能な睡眠測定法(SSS法)を用いて、リークカリウムチャネルが睡眠時間の制御において重要な役割を果たすことを示しました。
ヒトをはじめとする哺乳類で睡眠時間がどのように制御されているかはよくわかっていません。睡眠中、特に徐波睡眠中は特徴的な大脳皮質の神経細胞の発火パターン(徐波発火パターン)が観察されます。これまで本研究グループの研究によって、徐波発火パターン形成と睡眠時間の制御は一部の制御機構を共有している可能性が示唆されています。今回、本研究グループはまず、神経細胞の数理モデルを用いた徐波発火パターン形成機構の解析を行い、リークカリウムチャネルが徐波発火パターンの形成に重要な役割を果たしている可能性を明らかにしました。その後トリプルCRISPR法とSSS法を組み合わせることで、リークカリウムチャネルがカルシウム依存的な過分極と協調的に徐波発火パターン形成に寄与している可能性を明らかにし、リークカリウムチャネルファミリーに含まれる遺伝子の網羅的ノックアウト実験から、Kcnk9が睡眠時間制御に重要な役割を果たすことを明らかにしました。この結果は、徐波発火パターン形成・睡眠時間制御におけるリークカリウムチャネルの役割を示すとともに、二つの現象の裏には共通する制御機構がある可能性を再度強調するものであり、睡眠時間の制御機構の解明に大きく貢献すると期待できます。
本研究は、米国の科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America』(9月17日付け:日本時間9月18日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/18)
眼科手技を模擬した眼科手術シミュレータの開発
~ マイクロフックを用いた緑内障手術用眼球モデルの開発に成功 ~
名古屋大学大学院工学研究科の新井史人教授、小俣誠二特任助教の研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の相原一教授の研究グループと東京大学大学院工学系研究科の光石衛教授の研究グループとの共同研究により、科学技術振興機構(JST)の原田香奈子(はらだかなこ)ImPACTプログラム・マネージャーのプログラムの研究成果として、人間そっくりな眼科手術シミュレータに搭載可能な緑内障手術用眼球モデルを、この度、開発しました。近年、医学教育の効率化や難手術の効果的訓練が求められており、我々は、以前より精巧な手術シミュレータを開発してきました。一方、より侵襲性の低い緑内障手術用の治療器具が開発されているにもかかわらず、練習用の模擬眼球が十分に開発されておらず、医師が基礎学習や術前訓練を十分に行うことができませんでした。本研究では、上記の課題を踏まえ、緑内障手術に必要な前眼部構造を形成することにより、近年の低侵襲緑内障手術に対応した眼科手術シミュレータを開発することに成功しました。これにより、従来では行うことのできなかった手技訓練を行うことが可能になりました。
この研究は、平成27年度から始まった内閣府ImPACTプロジェクト「バイオニックヒューマノイドが拓く新産業革命」の支援の下で行われたものです。
(2018/9/18)
分子モーターたんぱく質KIF26Aによる痛みの体感短縮機構の解明
我々のあらゆる細胞の中には、微小管の線維に沿って細胞の中心と周縁を結ぶ物質輸送のシステムが張りめぐらされ、45種類以上のキネシン分子モーターが、さまざまな種類の積荷複合体を秩序だって輸送している。一方、それぞれの細胞の状態は「細胞内シグナル伝達」によってグローバルに規定されている。また細胞内のカルシウムを速やかに排出して神経細胞の興奮を収束させる「細胞膜カルシウムポンプ」は、活性型FAKによるリン酸化によってその機能が阻害される。これまで分子モーターは「シグナル伝達」の手足となるものと信じられてきたが、ここ数年の本グループの研究により、分子モーターがシグナル伝達分子を運び分けることによって、細胞内シグナルをさまざまに制御していることが明らかになりつつある。
東京大学大学院医学系研究科 寄付講座 分子構造・動態・病態学の廣川信隆特任教授、細胞構築学分野の田中庸介講師、分子構造・動態・病態学の王力特任研究員(研究当時)らは今回、KIF26A分子モーターがFAKを末梢感覚ニューロンの深部の微小管につなぎとめることで細胞外基質からインテグリンを介したFAKの活性化を阻害し、神経細胞からのカルシウムの排出を促進して、末梢神経細胞の興奮を早く鎮静化させる作用を明らかにした。まずKif26a遺伝子欠損マウスは、ごく軽く尾をつまんだだけで数分間にわたって疼痛反応が遷延していた。そこで末梢感覚ニューロンの性質を調べると、カプサイシンあるいは電気刺激によってニューロンが一度興奮すると、その刺激を取り去っても数分間にわたり細胞内カルシウム上昇が続き、痛みが遷延していくことがわかった。一方、超解像度顕微鏡の観察により、KIF26AがFAKを微小管につなぎとめており、KIF26AがないとFAKが微小管から外れて細胞周辺部に出てきてしまうことがわかった。このことによってノックアウトマウスではFAKが細胞膜直下のインテグリン・SFK複合体に結合しやすくなり、FAKシグナル伝達が異常に活性化された結果としてPMCAによる細胞内からのカルシウム排出が妨げられていたことがわかった。このカルシウム排出と疼痛の遷延は両方とも、SFK阻害剤であるPP2を投与することで、細胞レベルでも個体レベルでも実際に治療できることがわかった。
本研究はKIF26A分子モーターによる細胞内シグナル伝達の新しい制御機構を発見したものであり、これらの成果により遷延性の疼痛、がん等の新規治療法の開発に道を開くものである。
本研究の成果はCell Reports(米国東部夏時間9月11日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/12)
パーキンソン病 病因タンパク質LRRK2の関わる新規ストレス応答機構の発見
パーキンソン病は主に高齢者に発症し、運動の障害をきたす代表的な神経変性疾患ですが、αシヌクレインなどの病因タンパク質が特定の神経細胞に蓄積し、細胞死に至る原因は明らかになっていません。パーキンソン病の一部には遺伝性を示す例があり、代表的な病因遺伝子の1つとしてLRRK2が知られています。従ってLRRK2の生体における機能を明らかにすることは、パーキンソン病の発症の仕組みを解明する鍵になると考えられます。今回、東京大学大学院医学系研究科の江口智也大学院生(研究当時)、桑原知樹特任助教、岩坪威教授、医学部の櫻井まりあ研究生らの研究グループは、LRRK2が細胞内のタンパク質などの分解に関わる小器官であるリソソームに対するストレスに応答して、その恒常性を維持する働きを持つことを発見しました。その仕組みとして、LRRK2がストレスを受けて肥大化したリソソームの膜上に移行し、Rabと呼ばれるタンパク質群をリン酸化して膜上にとどめることにより、過積載状態になったリソソームの形態や機能を調節することを示しました。この発見は、リソソームがストレスに応答する新たな機構を提唱するものであると同時に、病因タンパク質の細胞内での分解障害や細胞外への放出などの、パーキンソン病の病態メカニズムの理解と治療法の開発にもつながるものと期待されます。
なお、本研究は順天堂大学医学部・神経生物学・形態学・小池正人教授、東北大学大学院生命科学研究科・膜輸送機構解析分野・福田光則教授、大阪大学大学院医学系研究科・細胞生物学・原田彰宏教授との共同研究で行われました。
本研究成果は、米国科学アカデミー紀要 オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/11)
骨芽細胞のRANKLが骨形成を促進する創薬標的になることを発見
~ 骨粗鬆症の新規治療薬開発に繋がる可能性も ~
骨細胞に発現するRANKLは、破骨細胞に発現するRANKを刺激し、破骨細胞の成熟と骨吸収(老朽化した骨の除去)の促進を行うリガンド分子として知られ、RANKLに対する中和抗体は骨吸収を抑制する骨粗鬆症治療薬として臨床応用されています。一方、骨芽細胞に発現するRANKLに関しては、これまでその生理機能が不明瞭のままとなっていました。今回、東京大学医学部附属病院の本間雅講師らを中心とし、東京医科歯科大学など5大学による共同研究グループは、骨芽細胞に発現するRANKLが、破骨細胞から膜小胞の形で放出されるRANKを認識する受容体として機能しており、骨芽細胞分化の促進および骨形成の上昇に寄与していることを、RANKL遺伝子の点変異マウスを用いた解析などから明らかにしました。骨芽細胞に発現するRANKLは、骨形成を促進するための創薬標的になり得ると考えられ、骨粗鬆症新規治療薬の開発に繋がるものと期待されます。
本研究成果は、日本時間9月6日にNatureにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/9/7)
予防医学センターと臨床研究支援センターP1 ユニットが機能を強化し新たなスタート
この度、東京大学医学部附属病院の予防医学センターと臨床研究支援センター P1(Phase1)ユニット(以下、P1ユニット)が、今年1月に開院した新しい入院棟Bの15階(予防医学センター)、12階(P1ユニット)に移転し、9月3日より新たなスタートを切りました。予防医学センターでは、先制医療を推進し受診者枠を大幅に増やすとともに、全基本検査と可能な限りのオプション検査を1フロア内に集約することで、人間ドックのために過ごす豊かな時間をスムーズに提供できるようになりました。P1ユニットでは、ベッド数が1病室13床から、4病室30床(15床室が1室、5床室が3室)となり、複数試験の同時期実施や、患者対象試験、少人数から大人数までの多様な試験への柔軟な対応が可能となりました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/9/4)
離れた脳領域の神経活動の大規模同時計測に成功
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻生理学講座細胞分子生理学分野の寺田晋一郎特任研究員、松崎政紀教授、自然科学研究機構生理学研究所の小林憲太准教授、埼玉大学の中井淳一教授、大倉正道准教授らの共同研究チームは、顕微鏡の観察位置を高速に移動させる小型光学装置を開発することで、マウス大脳皮質の異なった領野よりほぼ同時かつ大規模な神経細胞活動の計測に成功しました。
脳の複雑な情報処理機構を明らかにするため、近年日・米・欧において脳機能の統合的理解を目指すプロジェクトがそれぞれ進行中ですが、詳細な脳活動の計測手法の開発はプロジェクト遂行において重要な位置づけにされています。本研究成果は、複数の領野における神経活動計測を簡便な機構によって実現するものであり、今後幅広く脳機能研究において用いられ、分野の発展に貢献することが期待されます。
本研究は、日本学術振興会特別研究員奨励費、文部科学省科学研究費助成事業、JST CREST『脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御技術の創出』及び日本医療研究開発機構(AMED)『革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト』の一環として行われました。
本研究の成果はNature Communications誌(9月3日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/4)
運動学習における「課題の成功率」と「運動の安定性」
~ 視床から運動野への2種類のシグナルを発見 ~
東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 生理学講座 細胞分子生理学分野の田中康代特任助教、田中康裕助教、松崎政紀教授らのグループは、自然科学研究機構 生理学研究所 大脳神経回路研究部門の川口泰雄教授との共同研究により、光子顕微鏡によるカルシウムイメージング法を用いてマウス大脳皮質運動野に投射する視床皮質軸索のシナプス前部(ブトン)の神経活動を計測しました。マウスが新しい道具を使って運動課題を学習する際の計測を通して、視床から運動野へ送られるシグナルが2種類あり、互いに異なる時間変化(ダイナミクス)を示すことを明らかにしました。これら2種類のシグナルは「運動課題の成功率」あるいは「運動の安定性」と、それぞれ関連していました。また、シグナルは大脳皮質のどの部位に入力するかによってダイナミクスが異なり、それぞれが大脳基底核あるいは小脳に強い影響を受けることがわかりました。その一方で、どちらのシグナルを作り出すにも大脳基底核と小脳の両方の活動が必要であることも見出されました。本研究成果は、脳領域間ネットワークの視点から運動学習や運動制御のメカニズムを解明するという点で非常に重要であり、運動疾患の病態理解に貢献すると期待されます。
本研究は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)、文部科学省科学研究費助成事業、日本医療研究開発機構(AMED)、コニカミノルタ科学技術振興財団、武田科学振興財団の支援を受けて行われ、成果は雑誌Neuron(ニューロン)の電子速報版に日本時間2018年8月31日に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/9/3)
世界初のIntelligent Image-Activated Cell Sorterを開発
~ 細胞画像の深層学習により高速細胞選抜を実現 ~
ImPACTプログラム「セレンディピティの計画的創出」の合田圭介プログラムマネージャー(東京大学理学系研究科化学専攻教授)が率いる研究グループは、細胞の高速イメージングと深層学習を用いた画像解析で細胞を高速に識別し、その解析結果に応じて所望の細胞を分取する基盤技術「Intelligent Image-Activated Cell Sorter」の開発に世界で初めて成功しました。さらに本技術を用いて、微生物や血液細胞をその形状や内部構造を指標として分取する原理実証を行い、本技術の有用性や汎用性が確認されました。この快挙は、超高速蛍光イメージング技術、10ギガビットイーサーネットによる高速データ処理システム 、マイクロ流体技術を活用した高速分取技術や細胞制御技術など、複数分野にまたがる異分野融合での大規模な共同研究によって達成されました。本研究成果は、2018年8月27日(米国時間)に米科学誌「Cell」のオンライン版で公開されました。
本研究は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議の革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のうち、合田圭介プログラムマネージャーの研究開発プログラム「セレンディピティの計画的創出」で実施されました。
詳細は理学系研究科ホームぺージ プレスリリースをご覧下さい。
【発表者】
合田 圭介(科学技術振興機構 プログラムマネージャー/理学系研究科化学専攻 教授)
新田 尚(科学技術振興機構 プログラムマネージャー補佐/理学系研究科化学専攻 客員研究員)
上村 想太郎(理学系研究科生物科学専攻 教授)
矢冨 裕(医学系研究科内科学専攻/医学部附属病院検査部 教授)
(2018/8/29)
レム睡眠に必須な遺伝子を発見
~ 睡眠はどこまで削れるか ~
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター合成生物学研究チームの上田泰己チームリーダー(東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学教授)、丹羽康貴基礎科学特別研究員(研究当時)、神田元紀研究員、山田陸裕上級研究員らの国際共同研究グループは、レム睡眠に必須なニつの遺伝子を発見し、レム睡眠がほぼなくなっても生存するマウスの作製に初めて成功しました。
本研究成果は、レム睡眠の誘導や睡眠覚醒における神経伝達物質アセチルコリンの役割の理解と、その異常により引き起こされる睡眠障害の病態解明や治療法の開発に貢献すると期待できます。
レム睡眠は、身体は寝ているのに脳は起きているという、覚醒とノンレム睡眠の中間の状態と考えられています。アセチルコリンはレム睡眠を誘導する分子として知られていますが、本当にレム睡眠に不可欠なものであるかはこれまで不明でした。今回、国際共同研究グループは、脳・神経系49部位のマイクロアレイによる網羅的遺伝子解析、新しいマウス遺伝学ツール「tTR」の開発、トリプルCRISPR法などの個体レベルの遺伝学的手法を駆使することで、アセチルコリンの受容体遺伝子であるChrm1とChrm3が睡眠量の制御に重要な働きをしていることを明らかにしました。特に、その両方の遺伝子を同時に欠失させたマウスでは、レム睡眠がほとんど検出されないことを発見しました。
本研究は、米国のオンライン科学雑誌『Cell Reports』(8月28日付け:日本時間8月29日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/29)
分子モータータンパク質KIF1Bβによるニューロンの生存・再生機構の解明
われわれのあらゆる細胞の中には、微小管の線維に沿って細胞の中心と周縁を結ぶ物質輸送のシステムが張りめぐらされ、45種類以上のキネシン分子モーターが、さまざまな種類の積荷複合体を秩序だって輸送している。ことに神経細胞(ニューロン)は軸索という長い突起を持つが、軸索の中ではほとんどタンパク質は合成されないので、その中で必要な物質は分子モーターによる「軸索輸送」によって供給されている。一方、それぞれの細胞の状態は「細胞内シグナル伝達」によってグローバルに規定されており、ことに細胞表面に提示されている「レセプター型チロシンキナーゼ」と呼ばれる受容体群は、おのおのの受容体に特異的な成長因子群(growth factors)を結合して細胞内のMAPK/PI3Kカスケード等の「シグナル伝達」のトリガーとなり、これが細胞の生存や再生を促進する。これらのシグナル伝達が十分でないと細胞は死んでしまうが、一部のがんにおいては、逆にこれらのシグナル伝達が異常に亢進したために細胞の増殖が止まらなくなっている。これまで分子モーターは「シグナル伝達」の手足となり細胞機能を直接的に調節する分子群と信じられてきたが、ここ数年の本研究グループの研究により、分子モーターが逆に、レセプター型チロシンキナーゼ等のシグナル伝達分子を細胞内の必要な位置に配置していくことが明らかとなってきており、細胞内シグナル伝達を空間的時間的に調節する新しいパラダイムとして脚光を浴びている。
東京大学大学院医学系研究科 寄付講座 分子構造・動態・病態学の廣川信隆特任教授、細胞構築学分野の田中庸介講師、分子構造・動態・病態学の徐方特任研究員(研究当時)らは今回、KIF1Bβ分子モーターがレセプター型チロシンキナーゼの一つIGF1Rを軸索輸送し、IGFシグナル伝達を通してニューロンの生存や再生に必須な役割を果たしていることを発見した。研究チームはマウスにおける実験的なKif1b遺伝子欠損ならびに、神経難病であるシャルコー・マリー・トゥース病の患者家系におけるKIF1Bβタンパク質の新しい遺伝的変異によってIGF1Rの軸索輸送が低下し、IGFシグナル伝達によるニューロンの軸索伸長過程と生存が障害を受けていたことから、KIF1Bβのニューロンの生存・再生における重要性を裏付ける証拠を得た。
この研究は、分子モーターによる細胞内シグナル伝達の新しい動的制御機構を同定するとともに、IGFシグナル伝達が関与する種々の神経難病、アルツハイマー病、パーキンソン病、がん等の新規治療法の開発に道を開くものである。
本研究成果は、Journal of Cell Biology 8月20日オンライン版(米国東部夏時間)に掲載された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/24)
歯科医による口腔ケアが癌手術後の肺炎発症率と死亡率を減少
癌手術直後は体力が低下し、一時的に肺炎などにかかりやすくなります。肺炎が重症化すると死に至ることもあります。術後肺炎の発症の原因の一つとして、口腔内や咽頭に常在する細菌を含む唾液を気管内に誤嚥してしまうことがあります。歯科医が手術前に口腔ケアを実施することにより、口腔内の清潔を保ち、唾液中の細菌量を減らすことにより、術後肺炎の発症を低減できる可能性が、理論的には示唆されてきました。しかし、大規模な臨床データを用いてその効果を実証した研究はこれまでありませんでした。
東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教室の石丸美穂(博士課程大学院生)、康永秀生(教授)らの研究グループは、厚生労働省のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を用いて、歯科医による手術前口腔ケアが癌手術後患者の術後肺炎発症率や死亡率を減少させることを明らかにしました。
2012年から2015年の間に頭頸部、食道、胃、結腸直腸、肺、または肝臓癌の切除手術を受けた50万9,179人の患者のうち、8万1,632人(16.0%)が歯科医による術前口腔ケアを受けていました。歯科医による術前口腔ケアを受けなかった患者群と比較して、歯科医による術前口腔ケアを受けた患者群では、術後肺炎の発症率が3.8%から3.3%に低下し、手術後30日以内の死亡率は0.42%から0.30%に低下していました。
本研究成果は、実際の医療現場における歯科医による術前口腔ケアの有用性について、医療従事者・患者の双方にとって重要な情報の一つとなることが期待されます。
本研究は、厚生労働科学研究費補助金(厚生科研費)、科学研究費助成事業の助成のもとに行われ、研究の成果は英国の国際学術誌であるBritish Journal of Surgery誌(2018年8月8日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/24)
水溶性化合物による組織透明化の化学
~ 包括的ケミカルプロファイリングに基づく化学的原理の体系化 ~
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター合成生物学チームの上田泰己チームリーダー(東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学教授)、新潟大学脳研究所システム脳病態学分野の田井中一貴特任教授、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻システムズ薬理学の村上達哉日本学術振興会特別研究員らの共同研究グループは、水溶性化合物を用いた組織透明化の化学的原理の体系化に向けて、求められる透明化パラメータ(脱脂・脱色・屈折率調整・脱灰)の包括的なプロファイリングに基づいた合理的手法を開発しました。
本研究成果により、ヒト臓器全細胞解析に向けて、従来の偶発的発見に依存した透明化試薬の開発戦略から、化学的原理に基づく合理的な開発戦略へのパラダイムシフトが期待できます。
今回、共同研究グループは、それぞれのパラメータに対して約1,600種類の水溶性化合物の「包括的なケミカルプロファイリング」を実施しました。その結果、①脱脂には塩を含まないオクタノール/水分配係数(logP)の高いアミン(脂溶性アミンおよびアミノアルコールなど)が効果的であること、②脱色にはN-アルキルイミダゾールが効果的であること、③屈折率調整には芳香族アミドが効果的であること、④脱灰にはリン酸カルシウムのリン酸イオンのプロトン化(水素付加)が重要であることを見いだしました。さらに、各パラメータにおいて最適化されたケミカルカクテルを統合した一連の新しい「CUBIC」プロトコール(手順)を開発することで、マウスの各種臓器および骨を含むマウス全身、ヒト組織を含む大きな霊長類サンプルの高度な透明化に成功しました。
本研究は、米国の科学雑誌『Cell Reports』オンライン版(8月21日付け:日本時間8月22日)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/22)
パーキンソン病の新たな治療薬候補を同定
~ 悪性黒色腫の薬dabrafenibの新たな可能性 ~
パーキンソン病は、世界で最も多い運動症状を呈する脳の病気であり、進行を抑制する根本的な治療法がまだ見つかっていない神経難病です。今回、東京大学大学院医学系研究科神経内科学の戸田達史教授らは、悪性黒色腫に対する薬として承認されているダブラフェニブが、パーキンソン病の進行を抑制する可能性を持つことを見出しました。戸田教授らは、大阪大学の岡田随象教授が開発した薬剤データベースなどを利用した解析を用いて、パーキンソン病の治療薬候補を同定しました。そのうちの1つであるダブラフェニブが、培養細胞やマウスのパーキンソン病モデルにおいて実際に神経保護効果を示すことを世界で初めて証明しました。この成果により、パーキンソン病の進行を抑制する研究が進むことが期待されます。また、この薬剤スクリーニング手法は、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症などの他の神経難病のみならず、糖尿病や高血圧症といった様々な疾患で有用な可能性があります。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/8/17)
ヒト全遺伝子を対象とした網羅的探索による新規オートファジー遺伝子の発見
~ 効率的なゲノム編集技術 CRISPR(クリスパー)法を用いたスクリーニング ~
マクロオートファジー(以後、オートファジー)は、オートファゴソームという膜構造体によって担われる細胞内分解システムです。細胞質の一部がオートファゴソームによって取り囲まれ、リソソームと融合することで分解されます。オートファゴソーム形成は数多くのオートファジー関連遺伝子が必要です。今回、東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授らの研究グループは、同研究科の間野博行教授(現国立がん研究センター研究所)と同大学院理学系研究科の濡木理教授らのグループと共同で、ヒト全遺伝子を対象としたオートファジー関連遺伝子の網羅的スクリーニングを実施し新たなオートファジー関連遺伝子TMEM41Bを発見しました。TMEM41Bを欠損させた細胞ではオートファゴソームの形成がほぼ全く起こりませんでした。また、TMEM41Bは出芽酵母には存在しないため、本発見を契機として哺乳類オートファジーの分子機構がさらに明らかにされることも期待されます。
本研究は国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業ERATO「水島細胞内分解ダイナミクスプロジェクト」及び日本学術振興会 新学術領域研究「オートファジーの集学的研究」(領域代表:水島昇)の計画研究「オートファジーの生理・病態生理学的意義とその分子基盤」として行われました。
本研究成果は、「「The Journal of Cell Biology」8月9日(米国東部夏時間)オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/14)
ミクログリアが小脳神経回路の生後発達に不可欠であることを発見
~ 精神・神経疾患の病態の理解と治療方法の解明に期待 ~
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 橋本浩一教授、中山寿子元助教(現 東京女子医科大学助教)、森本千恵元大学院生、新潟大学脳研究所モデル動物開発分野 阿部 学准教授、同研究所 﨑村建司フェロー、東京大学大学院医学系研究科神経細胞生物学 飯田 忠恒特任助教、岡部 繁男教授らの研究グループは、脳の免疫細胞であるミクログリアが、小脳皮質の神経回路の生後発達に重要な働きをすることを明らかにしました。
これまでミクログリアは、神経回路が形作られる過程において、脳の働きに必要ないシナプスをマクロファージのように貪食して取り除くことにより、機能的に必要な神経回路の精緻化に関わることが報告されていました。しかし本研究の解析の結果、小脳皮質においてミクログリアは貪食ではなく、神経細胞との相互作用を介して神経回路の精緻化に関わる、という新しい知見を発見しました。
今回の解析は、ミクログリアの機能破綻が病態の一端を担うと考えられている神経変性疾患や自閉症、統合失調症などの精神疾患の病態理解や治療方法の解明に新たな切り口を与えると期待されます。
本研究は、科学研究費補助金、脳科学研究戦略推進プログラムのサポートを受けて実施され、研究成果は、イギリス時間の2018年7月19日英国科学誌「Nature Communications」オンライン版に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/8/2)
軽度認知障害における認知機能低下の加速因子を同定
J-ADNI研究では、234名のものわすれを主体とする軽度認知障害の被験者の認知機能を、最長3年間追跡しました。そのなかで、認知機能の低下に関与する要素を様々な角度から検討し、性差、教育歴がその進行に対して影響をもつことを見いだしました。女性の軽度認知障害被験者の認知機能は男性に比べて速く悪化しました。教育年数の長い男性の被験者では悪化は緩徐でした。軽度認知障害の背景にはアルツハイマー病以外の疾患も含まれますが、J-ADNI研究で女性が早く悪化する原因は、アルツハイマー病の方が多く含まれていたためではありませんでした。女性の軽度認知障害の方が悪化し易い要因として、慢性腎臓病のグレードが高いことが見出されました。その理由として、長年の高血圧や動脈硬化によって脳の小血管の障害を来たすことが、認知機能障害の進行に関係することを想定しました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/7/17)
学校給食が野菜・果物摂取量の格差を9.9%・3.4%縮小
東京大学大学院医学系研究科 健康教育・社会学分野 近藤尚己准教授らは、首都圏に住む小学生(4都市)719人を対象に、家庭の社会経済状況と子どもの野菜・果物摂取量の関連を分析しました。その結果、家庭の社会経済状況によって野菜摂取量と果物摂取量に違いがあることが明らかになりました。しかし、学校給食からの野菜・果物摂取量には差が見られませんでした。このことから、児童全員を対象とした日本の学校給食制度が、家庭の社会経済状況の違いによる野菜・果物摂取量格差を縮小する可能性が示唆されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/7/13)
分子モーターたんぱく質KIF21Bによる恐怖記憶の制御機構の解明
恐怖の記憶消去の異常は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに重要な役割を演じているが、そのメカニズムはほとんど明らかになっていなかった。
東京大学大学院医学系研究科分子構造・動態・病態学講座の廣川信隆特任教授、細胞構築学分野の田中庸介講師、分子構造・動態・病態学講座の森川桃特任研究員らは、KIF21B分子モーターがシナプスの構造を制御するRac1タンパク質の制御分子ELMO1複合体をダイナミックに輸送してRac1タンパク質の「活性サイクル」を終結させ、シナプス伝達効率の「長期抑圧」を通して恐怖記憶が消去されることを解明した。 本研究チームがKif21b遺伝子を欠損したノックアウトマウスを開発したところ、Rac1タンパク質の活性化が長く持続し、場所につながる恐怖の記憶がほとんど消去できないPTSD様の症状を示した。 そこで、このノックアウトマウスにELMO1複合体の阻害剤CPYPPを投与してみると、野生型マウスとまったく同じように恐怖記憶を消去できるようになった。 この研究により、キネシン分子モーターのかかわるシナプス可塑性の新しい分子機構が解明されたことは、記憶の書き換え障害が関与するPTSD等の難治性精神疾患の治療に道を開くものである。
本研究成果は、「Cell Reports」で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/6/27)
がん細胞のDNA修復能力を規定する新しい因子の発見
DNA修復能力の異常はがんの代表的な特徴ですが、どのようなメカニズムでその異常が引き起こされるかについては、まだ十分に明らかになっていません。
このたび、東京大学大学院医学系研究科の細谷紀子講師と宮川清教授らの研究グループは、生殖細胞関連タンパク質SYCE2が、体細胞でDNAが存在する細胞核内の環境を変化させることにより細胞のDNA修復能力を増加させることを発見しました。 SYCE2は生殖において大切なはたらきをする一方、正常体細胞では殆ど存在しませんが、がん細胞では増えることが多く、いわゆる「がん精巣抗原」と呼ばれることになります。 今回、そのがんにおけるはたらきを初めて示したことになり、今後このような現象を狙った新しいがん治療の開発が期待されます。
本研究成果は、EMBO、Rockefeller University、Cold Spring Harbor Laboratoryにより創刊された生命科学系オープンアクセス学術誌「Life Science Alliance」に2018年6月22日に掲載されました。 なお、本研究は、文部科学省新学術領域研究「動的クロマチン構造と機能」、日本学術振興会科学研究費補助金などの支援を受けて行われました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/6/25)
ゼブラフィッシュのべん毛の構造解析から軸糸ダイニン構築メカニズムの一端を解明
~ 繊毛・べん毛の解析手法として新たな脊椎動物モデルを開発 ~
JST 戦略的創造研究推進事業において、東京大学 大学院医学系研究科の吉川 雅英 教授と同大学院理学系研究科の武田 洋幸 教授らは、遺伝子操作を行ったゼブラフィッシュの精子べん毛について、はじめてクライオ電子顕微鏡法を用いた微細構造解析を行い、軸糸ダイニン構築メカニズムの一端を明らかにしました。
繊毛、べん毛は単細胞生物から我々ヒトまで共通して存在する細胞小器官であり、精子の運動や、気管粘膜についたゴミの除去など、ヒトでも重要な役割を持っています。 従来、繊毛、べん毛の構造解析にはクラミドモナスなどの単細胞生物や、ウニなどの無脊椎動物が主に利用されてきました。 しかし、ヒトの繊毛、べん毛疾患(繊毛病)との関連から、よりヒトと遺伝子機能の共通性が高い、脊椎動物のモデル生物の開発も求められていました。
本研究グループは、実験動物としてすでに広く利用されている小型魚類ゼブラフィッシュに着目しました。ゼブラフィッシュはCRISPR/Cas9を用いた遺伝子操作技術が確立されており、また精子の採集が容易であるという点で、繊毛、べん毛の脊椎動物モデルとして優れた特徴を有しています。
本研究では、繊毛病の原因遺伝子であるKTU、PIH1D3と、そのたんぱく質ファミリー遺伝子(PIH1D1、PIH1D2)についてゼブラフィッシュの変異体を作製し、クライオ電子顕微鏡法を用いて精子べん毛の微細構造を解析しました。 その結果、変異体では繊毛、鞭毛のモーター分子である軸糸ダイニンの構築ができなくなり、精子の運動に異常が生じることを明らかにしました。
本研究から、新たにPIH1D1、PIH1D2の2つの遺伝子が、その機能とともに繊毛病の原因遺伝子として示唆されました。 脊椎動物モデルを使用した本成果は、繊毛病が生じるメカニズムを解明する上で、今後の研究に役立つ知見になると期待されます。
本研究成果は、2018年6月19日(英国時間)に国際科学誌「eLife」のオンライン版で公開されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/6/19)
胚が子宮内膜に浸潤する着床のメカニズムを解明
~ 胚浸潤を可能にする子宮内膜の低酸素誘導因子HIF2αの作用 ~
着床障害は生殖医療の大きな課題となっていますが、有効な診断・治療法は確立していません。 着床は、子宮内に入ってきた胚が子宮内膜と接着する過程(胚接着)と、その後に胚が子宮内膜に入り込む過程(胚浸潤)を経て成立します。 着床の成立にはこれらの過程において子宮と胚の精妙な相互作用が必須と考えられてきましたが、その仕組みの詳細はこれまでわかっていませんでした。 東京大学医学部附属病院の廣田泰講師らは、遺伝子改変マウスを用いた研究を行い、低酸素で誘導される転写因子である低酸素誘導因子(HIF)が子宮内膜で作用して胚浸潤の過程を調節していること、子宮内膜間質のHIFが重要な働きを持っており、子宮内膜管腔上皮をはがして子宮内膜間質を露出させ胚が子宮内膜間質に入り込みやすくすると同時に、子宮内膜間質が胚とじかに接することによって胚が生存できるよう働きかけていることを明らかにしました。 この結果、子宮というブラックボックスのなかで起こる着床の仕組みが解明され、着床障害による不妊の一因が明らかとなりました。 今後ヒト子宮内膜におけるHIFの作用を検討することで、今回の研究が着床障害の新規診断・治療法の開発につながっていくことが期待されます。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/6/19)
CTやMRIなどの医用画像を誰でも簡単に見ることができるモバイルアプリを無料リリース
東京大学医学部附属病院脳神経外科(教授:齊藤延人)の金太一助教の研究グループは、スマートフォンやタブレットコンピュータでCTやMRI、レントゲンX線検査など医用画像を手軽に閲覧できるアプリケーションを開発しました。
医用画像は一般の方には馴染みの薄いものです。自分自身の画像であってもじっくり見る機会もツールもありません。また、医師や医療従事者、医学生、研究者であっても、画像を見るためには難解な操作を要するソフトウェアを使用しなければなりません。しかし本アプリによって、これまで敷居の高かった医用画像情報が広く社会に行きわたり、一般の方の医学的知識の啓発や医用情報の正確な共有化、および医用研究開発の促進が期待されます。また、どこでも簡単に閲覧できることによって、遠隔医療、災害地や医療過疎地での医療の質の向上につながることが期待されます。
本アプリは2018年6月12日に株式会社Kompathから無料でリリースされます(2018年6月12日時点ではiPhoneおよびiPadにのみ対応しており、その他のスマートフォンやタブレットコンピュータには対応していません)。データの取り込みはiTunes経由で簡単に行えます。
なお、本研究成果は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)「研究開発成果実装支援プログラム」 プロジェクト名「医師の高度な画像診断を支援するプログラムの実装」による成果の一部です。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/6/12)
日本の給食が肥満を減らす
我が国は、思春期の肥満率が低いことが知られています。 低い肥満率の理由の1つとして、給食が挙げられてきました。 これは、日本の小中学校の給食では、適切な栄養基準のもとで提供された同じ食事をその学校の全員が食べているからです。 しかし、それを支持するエビデンスはありませんでした。
東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学の宮脇敦士(博士課程大学院生)、李廷秀(特任准教授)、小林廉毅(教授)のグループは、まず、政府統計の公開データから、「2006年から2015年の都道府県(以下、県)レベルの給食実施率」、および「県レベルの栄養状態の指標(過体重・肥満・やせの生徒の割合、平均身長、平均体重)」を性・年齢別に抽出しました。 解析方法としては、パネルデータ分析の手法を用い、前年の栄養状態の指標、県・年齢・観測年などを考慮した上で、前年の県レベルの給食実施率と翌年の栄養状態の指標の関連を調べました。
解析の結果、県レベルの給食実施率が10%増加すると、翌年の過体重の男子の割合は0.37%(95%信頼区間 0.18-0.56)、肥満の男子の割合は0.23%(同 0.10-0.37)低下していました。 一方で、女子については、過体重・肥満を減らす傾向が見られたものの、統計学的に有意な結果ではありませんでした。 また、やせの割合や県レベルの平均体重、平均身長については、統計学的に有意な効果は認められませんでした。
本研究の結果から、学校給食プログラムを介した、適切な栄養基準に基づいた食事の提供は、思春期の肥満を減らす有効な施策の1つであると示唆されました。 本研究成果は英国の国際学術誌「Journal of Public Health」(2018年6月5日オンライン版)に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/6/7)
マルファン症候群の原因遺伝子FBN1の変異型が大動脈瘤・解離症の進展に及ぼす影響について
マルファン症候群は、全身の結合組織の働きが体質的に変化しているために、大動脈(大動脈瘤や大動脈解離)や骨格(高身長・細く長い指・漏斗胸・側弯など)、眼(水晶体(レンズ)がずれる)、肺(気胸)などの多臓器に障害が発生する遺伝性疾患(常染色体優性遺伝)です。 マルファン症候群の患者の約90%以上でフィブリリン1(FBN1)遺伝子に変異があり、幼少期から大動脈の拡大(大動脈瘤)は年齢とともに進行しており、急性大動脈解離を発症すると生命予後や生活の質は著しく低下します。 そのため、大動脈瘤の進展速度を予測して対応することは、患者・家族にとって大変有益と考えられます。
東京大学医学部附属病院循環器内科の武田憲文助教(特任講師(病院))、小室一成教授、小児科の犬塚亮講師らは、日本人患者でのフィブリリン1の遺伝子型(種類)と主要な大血管障害(Stanford A型急性大動脈解離、大動脈基部置換術および関連死)の発症時期に関する実態調査を行い、比較的簡便な方法で、遺伝子異常を早発型(HI群とDN-CD群)と遅発型(DN-nonCD群)とに分類できることを明らかにしました。 本研究は、ゲノム情報などの個々人の違いを考慮して予防や治療を行う医療(プレシジョン医療)の推進に向けた成果であり、一生涯に渡って患者・家族が抱く強い不安や悩みを和らげるための情報を提供するのみならず、本症の治療法開発や病態生理の解明にも繋がる研究への発展が期待されます。
本研究は日本医療研究開発機構(AMED)難治性疾患実用化研究事業「マルファン症候群における長期多系統障害増悪機構の解明と新規薬物療法開発に向けた研究(研究代表者:武田憲文)」の支援により行われました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/6/4)
バストサイズや月経痛など女性特有の体質と関連の強い遺伝子領域を新たに発見!
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座 大須賀穣教授ら、株式会社スタージェン 鎌谷直之らのグループは、株式会社エムティーアイの子会社である株式会社エバージーンの遺伝子解析サービスのプラットフォームを利用し、エムティーアイが運営する『ルナルナ』ユーザーの女性ボランティアの協力により得た11,348人の遺伝情報を用い、22の女性特異的な体質に関して、大規模なゲノムワイド関連解析を行いました。
11,348人、約54万SNPの遺伝子情報と体質に関するWEBアンケートの結果を用いて、GWASを行い、バストサイズや月経痛など女性特有の体質と関連の強い遺伝子領域をそれぞれ発見しました。
今後は本研究にて得られた結果をもとに、さらなる研究を進め遺伝因子および環境因子の全貌が明らかになることで、個人の体質に合わせた月経中の痛みや発熱などの改善への取り組みが可能となり、また、女性特有の体質とそれに関連する疾患との関係性が明らかになることで、一人ひとりに合った情報やアドバイス、疾患予防法の選択が可能になることが期待されます。
本研究成果は、日本時間5月31日にScientific Reportsにて発表されました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/6/1)
8Kスーパーハイビジョンカメラによって生きたマウスの脳活動を大規模に計測することに成功
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻生理学講座細胞分子生理学分野の松崎政紀教授、吉田恵梨子大学院生、寺田晋一郎研究員、自然科学研究機構生理学研究所の小林憲太准教授、埼玉大学の中井淳一教授、大倉正道准教授らの共同研究チームは、従来のハイビジョンの16倍に当たる3300万画素を持つ8Kスーパーハイビジョンカメラを世界で初めて脳神経活動の計測に用いることで、運動中のマウス大脳皮質から、軸索終末とよばれる神経細胞の一部における活動を大規模に計測する事に成功しました。
脳の複雑な情報処理機構を明らかにするため、近年日・米・欧において脳機能の統合的理解を目指すプロジェクトがそれぞれ進行中ですが、詳細な脳活動の計測手法の開発はプロジェクト遂行において重要な位置づけにされています。 本研究成果は、脳内における微細構造からの脳活動計測の新たなる方向性を示したものであり、今後、脳全体の活動の計測に向けたさらなる発展に繋がります。 神経細胞の活動や細胞内の分子動態といった生命現象の高精細かつ高速な記録により、様々な疾患の理解とその治療法開発に貢献することが期待されます。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)『革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト』(平成27年度より文部科学省から移管)の一環として行われ、研究の成果はScientific Reports誌に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/5/29)
日本人におけるレアバリアントの心筋梗塞発症への関与を解明
~ コレステロール値・発症年齢に大きく寄与する遺伝子変化 ~
東京大学大学院医学系研究科 循環器内科の森田啓行講師と小室一成教授、東京大学大学院医学系研究科 医学博士課程/理化学研究所生命医科学研究センター 研修生(研究当時) の田島知幸、理化学研究所生命医科学研究センター 循環器疾患研究チームの伊藤薫チームリーダーと基盤技術開発研究チームの桃沢幸秀チームリーダーは、大規模ヒトゲノム研究を行い、日本人における心筋梗塞発症と強く関係する遺伝子変化を明らかにしました。
心筋梗塞と関係するSNP(一塩基多型)に関してはこれまでにも多くの報告がありますが、それらが単独で臨床所見に与える影響は小さく臨床的有用性は未だ明らかになっていません。今回発見された遺伝要因は、SNPよりも頻度は低いもののインパクトはより大きな遺伝子変化「レアバリアント」(一般人口の5%未満に分布)です。
2つの脂質関連遺伝子LDLRおよびPCSK9に起こるこの遺伝子変化は単独で血液中のLDLコレステロール値を規定し、心筋梗塞発症リスク、さらには心筋梗塞発症年齢にも影響を及ぼします。脂質異常症と関連するLDLRおよびPCSK9のレアバリアントを有する個人を血中脂質上昇前の早期に割り出すことにより、特にその個人を対象に積極的脂質降下療法を開始し将来の心筋梗塞発症を抑えることが可能となります。今回の知見は、近未来のゲノムガイド精密医療開発に大いに貢献すると考えられます。
本研究成果は、日本時間5月25日にScientific Reportsにて発表されました。なお本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)オーダーメイド医療の実現プログラム「疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の高度化」(研究代表者:久保 充明 理化学研究所統合生命医科学研究センター・副センター長)等の支援を受けて行われました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/5/28)
霊長類の大脳皮質で運動課題中の多細胞活動を2光子カルシウムイメージングで長期間・同時計測することに成功
東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻生理学講座細胞分子生理学分野の松崎政紀教授、蝦名鉄平助教、正水芳人助教、川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科の彦坂和雄教授、自治医科大学分子病態治療研究センター遺伝子治療研究部の水上浩明教授、自然科学研究機構生理学研究所生体システム研究部門の南部篤教授、実験動物中央研究所マーモセット研究部の佐々木えりか部長、理化学研究所脳神経科学研究センター高次脳機能分子解析チームの山森哲雄チームリーダーらの研究チームは、霊長類コモン・マーモセットのための手を使って道具を操作する運動課題用装置と課題の訓練方法を開発し、2光子顕微鏡という脳の比較的深い層まで生きたまま“見る”ことができる顕微鏡で運動中のマーモセット大脳皮質から運動に関連した神経細胞の活動を計測する事に成功しました。
マーモセットはヒトと似た生体機能を持っており、遺伝子改変動物を含む疾患モデルの開発が積極的に進められています。今回の開発によって、認知や行動などヒトの高次脳機能の神経ネットワーク基盤の理解が大きく進展すると考えられます。
本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)『革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト』(平成27年度より文部科学省から移管)の研究開発課題「脳科学研究に有用性の高い遺伝子改変マーモセットラインの創出と普及」として行われました。本研究の成果は5月14日にNature Communications誌に掲載されました。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/5/15)
反復配列RNAの異常発現が膵癌発生を促進するメカニズムをマウスで確認
膵癌は抗癌治療の発展した現在においても予後不良であり、難治癌の代表的存在として知られています。この発癌の過程において、単純な塩基配列の繰り返しで構成される「反復配列RNA」と呼ばれるタンパク質情報を持たないRNA(ノンコーディングRNA)が、癌になる前段階から異常に発現していることが明らかになってきました。
東京大学医学部附属病院 消化器内科の岸川孝弘(留学中)、大塚基之 講師、小池和彦 教授らの研究グループは、以前、マウスの膵臓の良性腫瘍から樹立した細胞を用いて研究を行い、これまで機能を持たないと考えられてきた反復配列RNAの一種であるMajSAT RNAと呼ばれる「サテライト配列由来のRNA」がYBX1というタンパク質と結合すると、YBX1のもつDNAダメージ修復機能を阻害して、突然変異の蓄積を促進、細胞を癌化させることを見出しました(Kishikawa et al. Nat Commun 2016;7:13006)。
今回は、新たにMajSAT RNAを恒常的に発現するマウスを作製し、このマウスで膵臓に炎症を惹起したところ、膵組織内のDNAダメージが増え、さらに膵特異的Kras遺伝子変異マウスとの交配で膵臓の前癌病態の形成が促進されることを確認しました。これらの結果は、以前に、細胞レベルの検討で見いだした、反復配列RNAが「細胞内変異原」として機能し、発癌プロセスを進める重大な働きをしていることを生体でも確認したことになり、発癌機序の解明、発癌予防という観点からも重要な成果であるといえます。
本研究成果は、日本時間5月10日にMolecular Cancer Research(Online First)にて発表されます。なお、本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)次世代がん医療創生研究事業「次世代の診断・治療・予防法の創生をめざした膵がん特異的リピートRNAの新規探索と応用」、「血中反復配列RNAの高感度測定による癌の早期診断と囲い込み法の開発」および文部科学省科学研究費補助金等の支援により行われました。
![]() リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
リリース文書[PDF](東大病院HP掲載)
(2018/5/11)
J-ADNI研究によりアルツハイマー病早期段階(軽度認知障害)の進行過程を解明
高齢化とともに本邦で急増しているアルツハイマー病(AD)の根本治療薬開発は急務です。 今後の予防・治療の対象として重要な軽度認知障害(MCI)などの早期段階を、画像診断やバイオマーカーを用いて精密に評価するAlzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative(ADNI)研究が米国で進み、本邦でもJ-ADNI研究が推進されてきました。 J-ADNI研究の主任研究者を務める東京大学大学院医学系研究科の岩坪威教授らのチームは、今回J-ADNIの全結果を詳細に解析し、アミロイドPET画像法などの最新技術によって診断された、ADを原因とするMCIについて、その症状や進行速度などの特徴が米国ADNIのMCIに極めて類似していることを明らかにしました。 J-ADNI研究では全国で総数537例、うちMCI 234例が3年間にわたり追跡され、今回米国ADNIチームと共同でデータの比較解析が行われました。 MCIからADへの進行過程の自然経過に日本人と欧米人で高い共通性が示され、AD根本治療薬の治験においても、認知症期よりもまだ進行のスピードが遅いMCIなどの早期段階で、治療薬の効果を精密に評価できる技術が確立しました。 これにより本邦のADの予防・治療薬開発が加速されるものと期待されます。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/5/10)
B型肝炎ワクチンの効果に影響を与える
~ HLA-DRB1-DQB1ハプロタイプとBTNL2遺伝子」 ~
世界の180カ国以上でB型肝炎ウイルス(HBV)に対してB型肝炎ワクチン(HBワクチン)接種が行われている。
HBワクチンの1つであるビームゲンはHBVの遺伝子型C由来であり、日本で主に使用されてきた。
しかしビームゲン接種者のうち、約10%はその中和抗体であるHBs抗体を十分に獲得できないという問題があった。
国立国際医療研究センターを研究代表施設とする多施設共同研究において、成人日本人1,193例を対象としたゲノムワイドSNPタイピングを実施し、ワクチン低反応群(107例)、ワクチン中反応群(351例)、ワクチン高反応群(735例)の3群に分けてゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施した。
ワクチン低反応群と高反応群を比較した結果、HLA class III領域に存在するBTNL2遺伝子が有意な関連を示した。
一方で、3群を比較すると、HLA class II領域に存在するDRB1-DQB1遺伝子とDPB1遺伝子がそれぞれワクチン応答性に関連することを明らかにした。
次に、ゲノムワイドSNPタイピングデータを用いてHLA imputationを実施し、HLAアリルおよびハプロタイプとHBワクチン効果の関連を詳細に解析した。
HLAアリルおよびハプロタイプの頻度をHBワクチン低反応群とB型慢性肝炎患者群で比較した結果、HBワクチン応答性に特異的に関わるDRB1-DQB1ハプロタイプが存在することを見出した。
さらにHBワクチン高反応群と健常対照群について同様の比較をした結果、HLA class II遺伝子(DR-DQ、DP)はワクチン高反応に有意な関連を示さなかった。
ワクチン高反応群と低反応群のGWASでBTNL2遺伝子が検出されたことから、BTNL2遺伝子はワクチン高反応に関連すると考えられる。
本研究により特定のHLA-DR-DQ分子によるHBs抗原の認識(ワクチン低反応)、およびBTNL2分子によるT細胞やB細胞の活性制御(ワクチン高反応)がHBワクチンの効果に重要な役割を果たすことが明らかとなった。
本研究の成果をもとに国際共同研究を進めることで、ユニバーサルワクチネーションが行われている日本やその他の国において、HBワクチンの適正かつ効率的な使用方法の確立が期待できる。
本研究成果は、米国日時3月14日にHepatology(オンライン版)に掲載された。
※詳細は![]() こちら[PDF]をご覧下さい。
こちら[PDF]をご覧下さい。
(2018/4/5)









 ホーム
ホーム 一般向け情報
一般向け情報 学内向け情報
学内向け情報 広報・プレス情報
広報・プレス情報